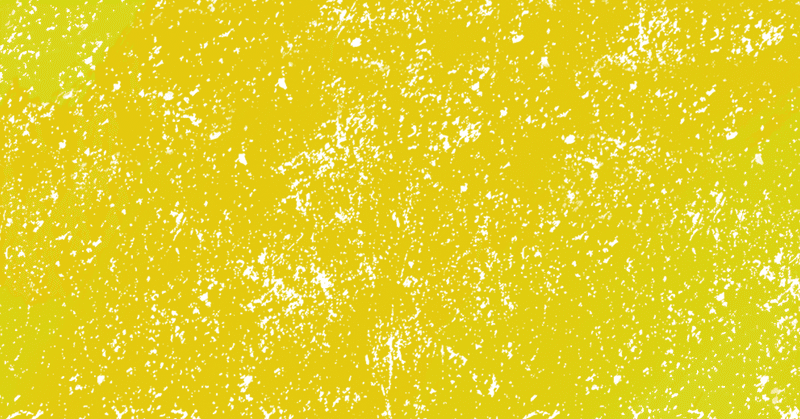
『動物園』(超短編小説)
「さて、みなさんを動物に例えると何ですか? じゃ、右の人からね」
面接官をしている中間管理職風の垂れ目男は、にやつきながら半分お遊びのような調子で3つ目の質問をした。それを聞いた4人の就活生たちは少ない時間の中で必死に考える。
「私は自分をアリだと思いました。なにごともコツコツとやるタイプで、以前大学のゼミで・・・」
一番右の黒縁眼鏡の男は、優等生っぽい顔をしているかと思っていたが、受け答えも優等生の模範解答みたいだ。全くつまらない。
「私はゾウガメだと思います。その根拠としては体が大きいこと、あとは、顔も亀っぽいとよく言われます」
二番目のプロレスラーみたいにデカい男は、見た目からは想像のつかない高い声で真面目に答えていた。面白くはないが、顔は確かにスーパーマリオに出てくるノコノコに似ている。
「私を動物に例えるなら女王蜂です。私は中学時代は生徒会長、高校時代は合唱部の部長、大学生の今はチアリーディングのキャプテンとしてみんなを引っ張っています。自分はリーダーとして動くのが得意なので女王蜂です」
三番目の意識高い系の女子は、スラスラと慣れた口調で話した。表情と声に自信がみなぎっていた。苦手なタイプだ。
あっという間に、自分の順番がまわってきた。一番最後だから考える時間があって有利なのだが、まともに答える気はさらさらなかった。そもそも、この質問の意図は何だ。いずれにせよ、くだらない質問だ。
「私は人間です。以上」
そう答えると、にやにやしていた垂れ目男の表情が一瞬で変わった。垂れ目男は「社会人をなめるな」と威嚇するような感じで口を動かした。
「きみは・・・、えーっと、◎◎大学の高橋君か。高橋君、君のは、質問の答えになってないよ。社会に出てそんな態度じゃ通用しない。わかる?」
「・・・わかりません」
「ん?わからない??高橋君は例え話がわからないんだ」
「いえ。この質問の意図です。この質問をすることによって私たちの何がわかるんですか?」
「えっ、それは・・・」
「では逆に質問します。あなたを動物に例えると何ですか?」
「きみ、自分の立場をわかってるの?」
「答えられないなら私が代わりに答えましょう。あなたはショウジョウバエです」
「きみ、失礼だよ!」
「失礼なのはどちらですか?私たち学生をバカにしてるんですか。上から目線で適当な質問して。必死にエントリーシートを書いて提出しましたが、ちゃんと見てるんですか?初対面の私たちのことを本当に知りたいと思うなら、そのエントリーシートに書かれてある志望動機とか自己PRとか、一人ひとりのパーソナルな部分を掘り下げて聞くべきではないですか。こちらは御社のことをちゃんと調べてきましたけど。なぜ“入れてあげる”的な態度なんですか。そもそも集団面接っていうのも、こちらに対して失礼ですよね。御社が3社目の面接ですが、どの会社もまともに就活生個人の情報を見てないし、社会人ってそんないい加減なものなんですか」
まくし立てると、その場はシーンと静まりかえった。垂れ目男は、何かを言い返したいけれど何も言い返せなくて苦虫を食いつぶしたような顔をしていた。
「あなたたちは不採用です」
私は面接官たちに向かってそう言って、一人立ち上がって面接会場の外に出て行った。
当初は真面目に面接を受けようと思っていた。しかし、垂れ目男の「君たちの未来の運命、にぎっちゃってるよ〜」的なふざけた態度に、その気は失せてしまった。
面接会場を飛び出した私は、同フロアのエレベーターホールにいた。今日も時間の無駄だったなと落胆しながら、矛盾だらけの日本式就職活動システムに対して憤りを感じながら、ボタンを押してエレベーターを待つ。
「あの〜すみません!高橋さん、でしたよね」
誰かが声をかけてきたので振り向くと、さきほど一緒に面接を受けていた女王蜂だった。
「高橋さん、すごかったです」
「ああ〜、さっきはごめんなさい。自分、取り乱しちゃいました。っていうか面接まだ終わってないんじゃ?」
すると女王蜂は顔をクシャッとさせてこう言った。
「私も勢いで出てきちゃいました!さっきの面接官の顔見ました?怒りに悔しさを滲ませたバカ面。思い出しただけで笑えてきます。私、正直スカッとしました」
「でしょ?(笑)」
「今からちょっと一緒にランチでも行きません?午後の面接まで時間あるので」
超高層ビルのエレベーターから見る東京の景色は、ジオラマみたいに安っぽく見えた。
(了)
読んでもらえるだけで幸せ。スキしてくれたらもっと幸せ。
