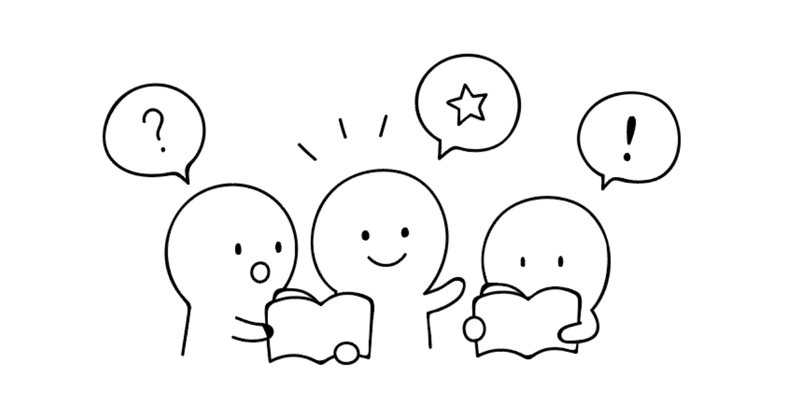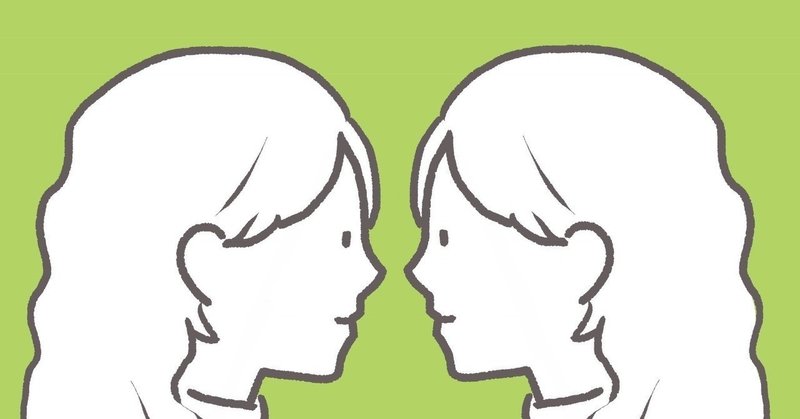- 運営しているクリエイター
2019年6月の記事一覧
インデックスファンドを上回るリターンを目指す、という理由でアクティブファンドを選ぶのは不毛だと思う。(個人の感想です)
こんなツイートを見かけました。
アクティブファンドの「目的」という話であれば、「インデックスを超える成果を目指す」ということになるかと思いますが、
確かにアクティブファンドの目論見書等を見ると、ベンチマークを設けているファンドは、そのベンチマークを上回ることを目指すと表明しているはずです。ただ、ベンチマークになっているインデックスを上回る、とすると、そのファンドマネジャーは株価(「価格
投資教育を受けるのが若ければ若いほど、早ければ早いほど、良いたった一つの理由
#COMEMO #NIKKEI
投資教育はなるべく早いうちに受けておくべきだと私も思います。その理由はたった一つです。(というような書き方、表現は好きではないのですが笑)
株式投資による資産形成は「時間」がモノを言うからです。
元本 x 時間 x 利回り
自分の投資した元本になるだけ長い時間を与えてあげることが非常に大事なことはこの掛け算をご覧になればお分かりになると思います。
ここ最近
『コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ』9周年!!! #k2k2
『コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ』というイベントの幹事役を務めています。このイベントは、投資信託等で時間をかけて資産形成に取り組む=コツコツ投資家の、情報交換、懇親の場として始まりました。
幹事は、『投資信託事情』の編集兼発行人である島田知保さん、ファイナンシャル・ジャーナリストの竹川美奈子さん、そして私の3人です。
第1回は2010年6月、東京・六本木でセットしました。以来、原則、毎月第
つみたて投資(コツコツ投資)を長く続けるために、「不安」を「希望」に替えましょう! #k2k2 #つみたてNISA #iDeCo
先日、金融庁から発表された報告ー金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」ー、それに反応したマスメディアの報道をきっかけに「2,000万円」という数字が特にクローズアップされています。
この数字を見て「不安」を感じ、「何か」行動しなければ、と考え始めた方もいらっしゃることと思います。その「不安」は理解できますし、「何か始めなければ」という意思はごく当たり前のこと
株式投資が大衆化するための教育
まろさんのブログ。
https://pixy10.org/archives/post-6504.html
これをヒントに、私の感想を。
中学・高校の社会科 とくに大学受験では歴史(日本史・世界史)が重視され、
政治・経済の科目もあるが一段下に位置づけられているように感じる。
確かに。私も日本史・世界史で大学受験しました。遥か昔のことですが。
自身の受けた教育を振り返ると、学校で学ぶ歴
ノートの毎日更新に挑戦する理由: #コツコツ投資 の入口を知ってもらいたいから
ノートを毎日更新していると、褒められます。
「つぶやき」だったせいか、連続更新を褒めてくれるメッセージは一瞬で消えてしまいスクリーンショットを撮れませんでしたが、43日連続の更新だそうです。
私は"rennyの備忘録"というブログも運営しており、こちらもほぼ毎日更新。2017年2月以来、毎月、記事数>日数となっています。
ブログもnoteも毎日更新というのは苦ではないのですが(noteの場合
現実を直視しない、目を逸らすことが、長い目で見て、最大の「リスクテイク」
#COMEMO #NIKKEI
昨日のニュース。これには唖然とさせられました、、、
金融庁のWebサイトに載せられている資料です。
今回出された報告の主題は「高齢社会における資産形成・管理」で、公的年金と資産形成との関係にフォーカスしていたせいか、この2年前の資料で、いの一番に載せられたデータ、グラフは、報告書にありませんでした。
金融庁のつみたてNISAの普及活動を通じて、このグラフがず
今年1月2日以降に20歳になった人たちは、#つみたてNISA が18年分しか使えない仕様になっています。
最初にお断りしておきます。私には、16歳(2003年生)、12歳(2007年生)の息子がいます。ですから、これから述べることは"ポジショントーク"なのかもしれません。その点、ご容赦ください。
今、巷で注目されている、報告書(まだ金融庁のサイトには「ありました」。そのうち「なくなる」かもしれないのでダウンロードしておきました)のおかげで、俄かに注目を浴びた(えっ!?浴びていない?)、きっと浴びてい
【投資は“よりよい明日”のための手段】 #コモンズ投信
#コモンズ投信 さんのメルマガ、最新号のタイトルが
投資は“よりよい明日”のための手段
でした。
その本文から、です。
“老後資産2000万円(が必要)”と試算した金融庁の報告書が、年金制度への不安を煽るものとして報告書そのものがなかったものにされ、かつ“投資は足りない年金の穴埋めのためにしなければならないもの”と受け止められているとしたらそれはとても残念に思います。将来が不安だか
「株式投資とはオーナーシップ」が常識になった時、社会は劇的にステキになっている…鍵を握るのは投信の月次レポート
昨日放送されたこの番組を視聴しました。
奥野一成さんについてはこちらのノートをご覧ください。
奥野一成さんが番組内で強調されていた言葉で一番印象的だったのは
"オーナーシップ"
奥野さんのインタビューや日々の活動の紹介から"オーナーシップ"とは何ぞや、ということが表現されているように感じました。
私の"オーナーシップ"の解釈です。
価値を生みだし続ける会社を探し出して、その株式を所有、
資産形成、何か始めなきゃ!と考えているアナタにぜひご覧いただきたい!
「投資」は資産形成のための選択肢として真っ先に挙がるものの1つだろう。事実、我々日本人は投資を「金稼ぎ」の道具として見る傾向が強い。「金融」はお金を右から左に動かすだけの仕事といわれることもあるが、果たしてそうなのだろうか。農林中金バリューインベストメンツ 常務取締役CIO 奥野一成は「長期投資」を通じて投資の本質がどういうものかを熱く語る。
https://kenja.jp/10478_201
"人生100年時代の資産形成"で「置き去りにされている」文脈があると思う。
「老後2000万円」の報告書の騒動から"人生100年時代の資産形成"について関心が高まっているようです。ただ、その様子を見るにつけ、強い違和感を抱いてしまうのです。違和感の最大の理由は、今現在の大人たちが感じる自分が老いたタイミングでの経済的不安に、あまりに意識が向き過ぎているということです。確かに、不透明な部分が多く不安になるのは致し方ありません。しかし、余りに身勝手なのではないか、とも感じます
もっとみる年金型保険、貯蓄型保険って果たして「自分ごと」の資産形成でしょうか?
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45773130W9A600C1EE9000/
#COMEMO #NIKKEI
金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」をきっかけに、資産形成についての関心が高まっているようです。
その流れで先般「年金型保険、貯蓄型保険」への関心が高まっているらしい、とSNSで目にしました。
金融
株式投資に対するイメージって変化するものなのだろうか?
SNSを見ていて思わずツイート。
「株式投資=ギャンブル」という捉え方で凝り固まっている人って、まだまだとても多いんだろうなあ、と感じたからのツイートです。
で、素朴な疑問。
株式投資に対するイメージって変化することってあるんだろうか。
変化するとしたら、何がきっかけになるんだろうか。
私の場合。
こんな風に出逢っていたせいか、ネガティブなイメージを持つことはありませんでした。
株式