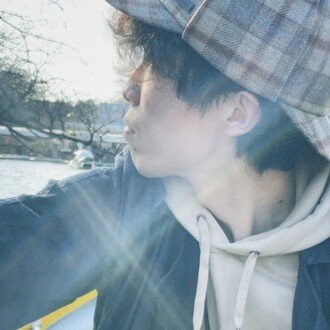Mr.Childrenの音楽を聴いていると、どうしてこんなに共感性の高い歌詞を書けてしまえるのだろうと考えたくなってしまうんです。
Mr.Childrenが、国民的なロックバンドになり得たのにはさまざまな要素があるけれど、まず絶対に、絶大な歌詞の力についてを語らないわけにはいかないと思うのです。
J・D・サリンジャーの小説『ライ麦畑でつかまえて』はその共感性の高さから、多くの若者が「この小説のモデルは自分に違いない!」と錯覚したといいます。
Mr.Childrenの歌詞は、自分がモデルになっていると錯覚するようなものではありません。それは歌詞と小説という「容器」の性質の違いであるかもしれませんけれど。というよりは、自分の言いたいことが代弁されていたり、自分がもやもやとしていたことが言語化されていてスッキリするという感覚があって、桜井さんの歌詞に触れるといつも心が安まるんですよね。こういう感覚を多くの人に持たせることができるからすごい!
このことについて、インタビュー中でこんなふうに語られています。
大衆性があるかどうかっていうことだと思うんです。自信があるときは、『中学生の子が聴いても、同年代のおじさん、おばさんが聴いても、これ感動しちゃうよ』って思えるんです。でも、自信がないときに『大衆性はどうなんだろうな』ってなったら、『これは俺のコンピューターの中に眠らせておこうかな』みたいなときもあります
ここでは大衆性という言葉が使われていますが、ひと口に大衆性と言ってもいろいろあるわけです。麻婆豆腐に四川風と広東風があるのと同様に。カレーにインドカレーと欧風カレーがあるのと同様に。大衆性も、大きく分けて2種類があると思うんです。
全体の平均値をとって作為的につくりあげられる大衆性
自己を深部まで掘り下げてみることで発見される大衆性
①の大衆性のもとでつくられたコンテンツは、なんとなく共感することはできるけれど、心をえぐられるような体験にはならないことが多いです。
心をえぐられないということは記憶に残りづらいということ。記憶に残りづらければ、繰り返し聴いたり観たりされづらくなります。
あと、僕は、個人的には、平均値をとったコンテンツからは「だいたいみんなこんな感じのこと悩んでいますよね?」みたいなわかってる風な感じに、嫌気が差してしまうことが、多々あります。
Mr.Childrenの歌詞にはややもすると「綺麗事…?」と感じてしまうような歌詞もあるのですが、そう感じさせない説得力には、歌詞の大衆性が①ではなく、②(自己を深部まで掘り下げてみることで発見される大衆性)だからだと思います。
実際、この言葉は僕が勝手に考えたものではなく、1994年のシングル〈innocent world〉を振り返って当時のプロデューサー=小林武史が言っていた内容——桜井には自己の深部を歌詞にしていく能力が具わっていた、というような内容だったと思う——を参考にしたものです。
僕はこの言葉を聞いたときに、ひとりひとりの人間を遺伝子情報にすると、99.99%が同じで、差異はたった0.01%しかない、という話を思い出しました。
現代を生きるわたしたちは、良くも悪くも、他人との違いばかりに注目しがちですが、わたしたちには差異よりも共通点のほうが多くあるのだということを忘れてはいけないような気がするのです。
だからMr.Childrenの音楽は、人々の心の深いところで響くのでしょう。自己の深部を掘り下げて、そこで見つけたものに共通性があるかどうか精査し、何重にもふるいにかけられ、厳選された言葉であるために、人々を惹きつけるのでしょう。
今日も最後まで読んでくださってありがとうございます。 これからもていねいに書きますので、 またあそびに来てくださいね。