
569.本当はね、売れる本ってね、売れない本かもしれないんだよ~
【お馬鹿なcoucouさんの自主出版論㉘】
1.売れる本と、売れない本
本はね、「売れる本」と「売れない本」がある、そんなことは誰でも知っているよね~
だけれど、「売れない本」って、無限に存在していることを知っている?
そう、それも知っているよね~
ここでね、【お馬鹿なcoucouさんの自主出版論】もいよいよ、最終に近づいてきたので、「売れる本と、売れない本」をテーマでまとめたんだ~
でもね、その「売れない本」を出している出版社さんたちは、決して売れないなんて思ってもいない、信じていないんだ~
そりゃあ、売れなかったら、という不安はたくさん抱えているけれど、常に「今度は売れる」という期待を抱きながら本を発行し続けている。
そうだよね~
創業何十年、プロの経営者さんがいて、スタッフさんがたくさんいる。
さらに有能な編集者さんや営業さんの方々がいるんだもの。
過去の体験や、経験、修羅場をくぐり抜け、様々な市場分析、リサーチをして本を発行し続けているんだもの~
そう、儲からないわけがないし、売れないわけがない…。
でも、それでも売れない~
現実は、返品の山々~
毎月返品の山を見るたびに恐ろしくなる~
そして、また配本の繰り返し。
まるで本の在庫倉庫業と化す…。
みんな、知っている本の量を~
1冊当たり約200頁とすると、本の厚みは1.5~2㎝ある。
それが10冊束で15㎝から20㎝。100冊で150㎝から200㎝、1000冊で1500㎝から2000㎝となる。
これが、5,000冊、10,000冊、30,000冊が積み重なったらどのくらいの高さになるんだろう?
また、本を1年間に10冊から20冊発行し続けている出版社さんたちは、数年で倉庫が満杯になってしまう怖れがある。
自費出版さんで3,000冊以上製作している会社があるけれど、一体、その在庫をどうしているんだろうね?作者が保管するっていったって限界がある…。
だから、お馬鹿なcoucouさんはね、在庫を持たない、在庫リスクのない出版方法を言い続けているんだ。そして、常に再販を繰り返せばいい~
だけどもわかっちゃいるけれど、それができない出版社体質も理解できる~
だって、それじゃあ儲からないもんね…。
じゃあ、どうするの?
誰も答えられないけれど、結論は、売れる本を出して儲けることだよね。
そんなことは経営者であれば誰にでもわかる答えだよね。誰もが、この苦境に対して、売り上げを上げて利益を出すことだけに奔走し続けている…。
だけどね、それも解決じゃあないよ~
問題は、出版社の固定経費、人件費、返済金、その他にある。
coucouさんの仲間の出版社さんたちは、みんな「ひとりぼっち出版社」、それでも数人のスタッフさんで本を作り続けて、大きな儲けはないけれど、みんなが生活する最低分は確保している。
これが本来の出版社の姿だったように思える。
今は、何でも大きくしすぎて小回りが利かない。小さな利益の積み重ねが大きな儲けにつながるのだけれど、そんな面倒なことは嫌なんだよね~
そう、夢よもう一度~
10,000部~100,000部を目指す、いや、1,000,000部売ればさらに儲かるし、今までの赤字分などすべて取り返せるという、千三つと言われる一獲千金の不動産屋と化した気がする。
だけどね、これからの時代はね、小さな会社の方が有利になる世の中~
ひとりぽっち経営者の方が結果的に利益体質となる気がする、coucouさんなんだ~

2.売れる本ってね、売れない本かもしれない
coucouさんはね、無目的で本屋さんに行く時が多いんだ。
もちろん、好きなコーナーは当然チェックするけどね。
ただ、週刊誌、月刊誌、旅行雑誌、単行本、新刊コーナーなどでタイトルや文字は確かに目に入るけれど、あまりにも多すぎる言葉の氾濫の中で、手に触れたいという本が少なくなった気がする。
ただ、素晴らしい装丁専門のデザイナーさんたちが力を込めた力作なんだろうけれど、心に残らないと思うのはcoucouさんだけなのかなあ~
反面、漫画や、絵本の世界、子供雑誌などはまるでアート作品のようにそれぞれの独自性を発揮してるように見える~
それは、やはりイラストや漫画の訴求力が強いのだと思う。
そう、文字よりも絵の表現が強い気がする。
そう、心に残るよね~
タバコのピースのデサインをしたレイモンド・ローウィは「売れなければデザインを変えろ!」と唱えた。そう、まさに本の命は興味を持ってもらい手に触れて、開いてもらうことから始まる。
どんなに素晴らしい本でも、興味がなければ誰も読んでくれないんだもの~
そして、もうひとつ、みんな同じような表現、色使い、似たような装丁~
これって、coucouさんにはわからないけれど、今どきの流行なのかなあ~
完成されたデザイン、美しいデザインって目立たないよね。たとえ、下手であっても、未完成な絵であっても、バランスが悪くても、その方が心に残る気がする。これはね、あくまでも比喩なんだけど、子どもたちに本の表紙デザインをしてもらった方が目立つかもしれない…。
そして、どの出版社も「売れる本」づくりをしているためか、柳の下にドジョウ百匹の精神を持って、千三つの世界で勝負を繰り返している。
でもね、時代が逆行しているのかもしれないけれど、本当の売れる本って、今、売れている本のことではなくて、「売れない本」「売れそうにない本」が、もしかすると売れる本かもしれない。
だってね、みんな売れる本はこうなんだという思い込みと、固定観念、「思考の盲点」にはまりすぎて、見えなくなっている気がするからなんだ~
(専門家になればなるほど見えなくなる、思考の盲点)
みんなと同じような本ではなくて、みんなと違う本、独自性の強い見せ方と、内容が一体化しないと、何時まで経ってもその本を誰も開いてくれない恐ろしさが残る…。
だからね、「売れない本」を考えて見ない…。

3.パレートの法則
パレートの法則って知っている~
う~ん~
ある意味、業界用語なのかな~
この法則はね、イタリアの経済学者ビルフレッド・パレート(1848~1923)が1880年代の欧州の経済統計から「個人の所得額」と「その所得額以上の所得を得ている人の数」との間に見出した法則なんだ。
え~
それが本と、何が関係あるの?
そんな人もいると思うけれど、まさに関係のある、言葉を変えた「千三つ」のリアルな考え方なんだ。
千三つという言葉はね、千のうち、三つ当たればいい、というような不動産屋さんがよく使っていた言葉。
このパレートの法則はね、「80:20の法則」ともいわれ、「売上げの8割は2割の社員に依存する」といった傾向を経済統計からパレートさんが考えたものなんだ。集団の報酬や評価が一部の構成員に集中するという経験則から来ている。
だからといって、統計学だからね、「80:20」の数値に絶対的な意味があるわけじゃあない。集団の報酬や評価の集中傾向を端的に表すただの統計にすぎない。
こんな逸話もある。
園芸家でもあったパレートが、エンドウ豆の80%が20%のサヤから収穫されたことに着想を得たという逸話がある。
簡単に要約すると、
いつも着ている服の8割は、持っている服のうち、お気に入りの2割しかない…
自分の部屋で過ごす時間の8割は、部屋全体のスペースのうち2割の場所にいつもいる。
働きアリは、よく働く2割のアリが8割の食料を集めてくるという。
また、働きアリの中でも、働いているアリが8割、サボっているアリが2割と言われている。
これって、人間の世界も似ているよね。
80人が働いていても、本当に頑張って働いている人って、20人くらいしかいない。これは組織が小さければ別だけど、働きさんが増えれば増えるほどサボる働きさんも増えてくるのとおんなじだね。
こんな、逆のパレードの法則もあるみたい~
例えば、ネットの世界ではロングテール手法というものがあるという。
リアル店舗では売れている主要上位20%の商品が全体80%の売上を占めていると言われていたけれど、ネットでは陳列の物理的限界がないため、あまり売れていない商品80%が売れている20%の売上を越えてしまう現象が起こるという話もあった。
さらに、このパレートの法則を簡単にいえば、売れる点数は少なくとも、それがたくさん集まることによって、売上が上がる場合もある、という。スーパーなんてそうだよね。たくさんの種類を置くことで「80:20の法則」となる。
これは、何かの記事に掲載されていてメモを取ったものです~
出典先がわからないけれど、創作性のない単なる事実なのでこのメモを掲載。でも、もし失礼があればお詫び申し上げます。
ビジネスは、売上の8割は全顧客の2割が生み出している。
商品の売上・利益の8割は、全商品銘柄のうちの2割で生み出している。
売上の8割は、全従業員のうちの2割で生み出している。
成果の8割は、費やした時間全体のうちの2割の時間で生み出されている。
住民税の8割は、全住民のうち2割の富裕層が担っている。
プログラムの処理にかかる時間の80%はコード全体の20%の部分が占める。
人生の8割は、費やした時間全体のうちの2割の時間で生み出されている。

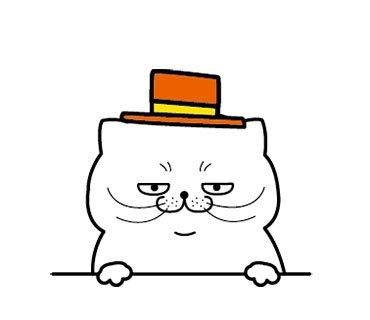
coucouさんです~
みなさん、ごきげんよう~
毎回、ここまで読んでいただいている、
みんなには心から感謝申し上げます~
出版社さんはね、本を売ることが儲け~儲からなければ本は発行できないし、働きさんたちにも給料を支払わなければならない…。
別に出版社さんだけじゃあないよ、みんな567後遺症で苦しんでいる。
こんなにも簡単に日本って壊れちゃうことがよくわかったよね~
戦争だって、簡単に影響を受けてしまうのだから対岸の炎だなんて眺めてられないよね。
でも出版社さんは口を揃えて言う言葉がある。
それはね「いい本だからって売れるわけじゃあない…」っていう。
え?
いい本と、売れる本は違うの?
誰もが、そう思う~
だけど、売れる本ってなに?と質問すると、最終的には答えられない。
そう、簡単ではないよね~
でも、売れる本ってどこまでのことをいうの?
やり方によっては、500冊だって、1,000冊だって、充分な利益があるよ~
それで儲けだって出せるはずなんだけれど、出版社の維持費があまりにも大きすぎる。
人権費だってそうだよね、支払うのに限界も来ている。
だけどね、世の中にはひとりぼっち経営者はたくさんいる。
別に出版社さんたちだけではないよ。
カメラマンさん、デザイナーさん、ライターさん、翻訳者でフリーで活動している人もたくさんいる。
このnoteの世界にもたくさんのライターさんがいる。
どうして、こんなに宝物が転がっているのに利用しないのだろうね~
coucouさんにしてみれば不思議なこと~
ライターさんたちの仕事は雇われている編集スタッフさんよりも厳しく生きている。だって、安定した給料などないし、一つの仕事に対して報酬を頂いている。雇われている編集の人たちよりもハングリーなのは間違いないよね~だって、必死なんだもの~
coucouさんはね、外の世界の厳しさや世間をよく見ている、会社内にいる人たちよりも、ものの見方がまったく違うことがわかる。
だって、ハングリーな人ほど、固定観念が少ないんだもの~
567後遺症の中小企業や自営業者さんや会社経営者さんたち、
見直すのはまだ遅くない。
会社で働いている人たちも、遅くない。
定年を迎えた人だって、遅くない。
70代だって、80代だって遅くない~
もっと、もっと、自由に生きるのが567後の新しい世界なんだよ~
noteの世界の20パーセントの人たちが、世の中を動かすんだよ~
ここまで、読んでくれて、ありがとう~
とってもうれしい~
また、あしたね~
今日も素敵な佳き一日でありますように、みなさまへ。
coucouさんのホームページだよ~みんな、みてね~
Production / copyright©NPО japan copyright coucou associationphotograph©NPО japan copyright association Hiroaki
Character design©NPО japan copyright association Hikaru
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
