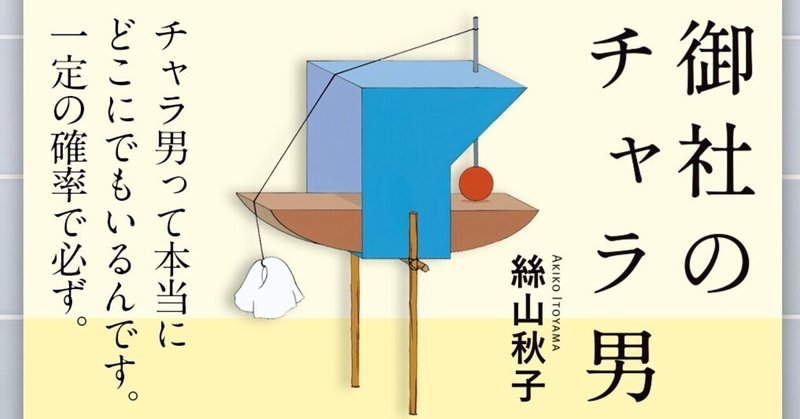
絲山秋子『御社のチャラ男』 : チャラ男をめぐる〈会社というディストピア〉
書評:絲山秋子『御社のチャラ男』(講談社)
勘違いしてはいけないのが、本作は、「チャラ男」を批判的に「笑いものにした」小説ではない、という点である。
そうではなく、本作は、どこの会社にもいた「チャラ男」的な社員の存在が許容されなくなり、ギスギスした職場環境が当たり前になってきた「会社」社会を、「チャラ男」を狂言回しとして、多視点で描いた小説なのだ。
さて、いまさらと思われる方がおられるかも知れないが、私がごく最近知って驚いた言葉に「勤怠管理」というのがある。テレビのコマーシャルで「勤怠管理ソフト」の宣伝がなされていて、この「勤怠管理」という言葉が、そのまま使われているのだ。
私がこの言葉を聞いて、すぐに連想したのは、ジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984年』だった。
『市民は常に「テレスクリーン」と呼ばれる双方向テレビジョン、さらには町なかに仕掛けられたマイクによって屋内・屋外を問わず、ほぼすべての行動が当局によって監視されている。』
(Wikipedia「1984年 (小説)」より)
このように紹介されるのが『1984年』のディストピアだが、その会社版が「勤怠管理ソフト」ではないのかと、そう思ってゾッとしたのである。
今はどうかよく知らないし、職場によっても色々なのだろうが、昔の外回りの営業社員と言えば、社用車で得意先回りに出ると、出先で適当に休憩を取っていた。食事は無論だが、時には目立たない場所に車を駐めて、昼寝をしたりもしたものだ。つまり、建前上「8時間労働」と言っても、否応なく残業を強いられるその一方で、このように自分なりに工夫して「抜くときは抜く」という調整をしていたからこそ、過労死することもなく仕事を続けることができたのである。
ところが、ここに「勤怠管理ソフト」なるものが導入され、営業社員はそれぞれGPSを持たされて、ずっと「勤怠管理ソフト」に監視されるとしたら、これはまさに職場版『1984年』ではないかと、私は考えたのだ。
それにしても、こんな恐ろしい言葉を、よくも当たり前のようにテレビコマーシャルで使うものだと疑問に思い、この言葉は、私が知らなかっただけで、世間ではすでにそこまで当たり前になっているのかと疑って、ネット検索してみると、案の定「勤怠管理とは?いまさら聞けない人事・総務の基礎知識」などという記事を発見し、読んでみると『正しい勤怠管理は適正な賃金の支払いにつながるだけではなく、過剰労働の早期発見や防止効果が生まれ、従業員の健康維持やひいては法令遵守にも結び付くのです。』などと書いてあるのだが、文字どおりの「勤めを怠ける者を管理する(サボらさないための監視管理)」のためだとは、一言も書いてはいない。
だからこそ逆に、この「勤怠管理」の本来の目的が「勤めを怠ける者を管理(サボらさないための監視管理)」するところにあるのだという事実を、私はひしひしと感じたのである。
そして、このような語感しか持たない「勤怠管理ソフト」が、当たり前のようにテレビコマーシャルとして流されている、現代の日本社会における会社環境において、社長との姻戚関係のコネによって横滑りで部長に就任した、見栄えと講釈だけの「チャラ男」部長が、部下たちからどのように見られているのかを描いたのが、本作である。
当然「チャラ男」は、好人物とは評価されない。
少なからぬ読者も「こんなやつ会社にいるよね」と共感はするが、すくなくともその共感が「チャラ男」に向けられることはない。「こんなやつ、いなければいいのに、どこにでもいるんだよね」というのが、多くの読者の感じるところなのである。
たしかに、こんなやつはどこの職場にもいるだろう。ましてそれが上司であれば「あんな役立たず、消えてしまえばいいのに」と思うのは、部下たる者の、当然の思いでもあろう。
しかし「こんな役立たずはいらない」という批判は、そういう批判をする部下たち自身に対しても向けられ得る、という可能性を考慮する者は、ほぼいない。
いくら自分では「それなりに頑張っている」つもりでも、他人から見れば「あいつはなあ…」ということになりがちなのは、「チャラ男」の場合とまったく同様なのだ。自分では「当たり前」のつもりが、価値観を異にする他人には「当たり前」には見えず、単に「変なこだわりのある困った奴」としか映らない。そしてそうした「狭量な同僚間の相互監視」もあって、職場はどんどんギスギスしたものになっていく。
それが、昨今の会社における職場環境なのではないだろうか。
ひと昔前の会社には、たしかに「困った人」も大勢いた。「チャラ男」ではなくても、端的に「仕事をしない人」がいた。そこまでいかなくても「何をしているのかよくわからない人」も少なからずいた。そして、そういう人の存在を、部下たちは陰口することで憂さ晴らしをしながら仕事を続け、いずれは自分もそうした地位について「楽をしたいものだ」などと考えたりもした。
しかし、今では、そういう「楽な立場」というのは、ごく一部の上層部に限られ、管理職の多くもまた、部下からの監視の下、露骨に楽をすることが出来なくなってきたのではないだろうか。なにしろ、このネット社会である。そんなことをしていると、いつ自分のことを(匿名の部下によって)晒されるかわからないし、その場合に、会社が守ってくれるという保証はない。だから、現場幹部の方も、緊張を強いられ、「俺もこんなに頑張っているのだから、おまえらだって、もっと頑張れよ。仕事をするために、会社に来ているんだろうが」となって、相互監視の網はますます強化されていく。
本書における語り手たちの、それぞれの意見は、「チャラ男」自身のそれも含めて、それなりに「もっともらしい」ものであり、特に問題があるようには見えない。なのに、お互いの意見は、相矛盾する現実を映し出す。これは、なぜなのか。
それはたぶん、誰もが「主観的」だからだ。「主観的」に世界を見て、世界を解釈し、それを描いたものだからこそ、そこには「矛盾」はない。その自己完結性において破綻はないのだが、しかし、それは所詮「自己完結的な自己満足」でしかない。そこには「他者の視点への配慮=世界を総体的に眺める姿勢」が決定的に欠けているのだ。
そして「他者の視点」とは、「自己の視点」の拡張ではない。自分に都合の良いように「他者を解釈する」のは、それが否定的なものであれ、肯定的なものであれ、いずれにしろ「自己の視点」でしかない。つまり「チャラ男」を好意的に評価する場合もまた、本作の登場人物の場合、「自己の都合による」好意的解釈の域を出ないのである。
しかし「他者」とは、本来の意味においては「理解し得ない他人」である。つまり、「他者理解」とは「理解できないけれど、その存在を容認しよう」ということにしかならないのだ。だが、これが容易なことでないのもまた、明らかであろう。
こうして、私たちの「会社」は、相互監視の網をますます強化し狭め、「チャラ男」や「何をしているのかわからない人」の存在をどんどんと排除していく。
それを見て「ざまあ見ろ」と、密かに喝采の声をあげる部下も少なくないだろう。
しかし、自分ではそれなりに一生懸命に仕事をしているつもりでも、勤怠管理ソフトは、あなたの「気持ち」や「つもり」などには配慮してくれないし、それぞれに必死に働いている同僚や上司の目にも、あなたの「努力」は可視化されていないかも知れない。
その結果、他者にとっての「チャラ男」や「何をしているのかわからない人」でしかないあなた自身も、当然のことながら、いずれは会社に居場所を失うことになるのである。
本書が描くのは、「チャラ男」の居場所を認めない職場の、「滅菌された地獄」という「会社の今後」なのかも知れない。
初出:2020年2月28日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
・
・
