
ハッピーエンド作成中 《全編》
プロローグ
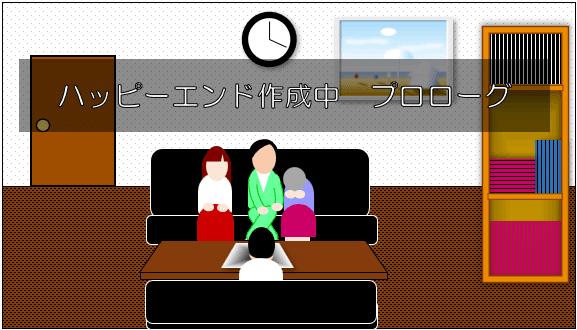
「ハッピーエンドなんてものはありはしない。何故なら人は皆死ぬんだから」
これは夫が結婚する前に付き合っていた時に言っていた言葉だ。ちょっと哲学とか文学を齧った人間ならすぐに言いそうな物言いだけど皮肉屋の夫も例に漏れずこんな事をよく言っていた。私は絵に描いたようなこの皮肉屋が面白くって何故か付き合うようになりそして結婚したけど、結婚してから夫はだんだんそういう事を言わなくなった。私はその夫を見てたぶん彼は目の前の現実を見て自分の考えの幼さに気づいて恥ずかしくなったのだろう、やっぱり結婚って人を変えるな、あの皮肉屋の夫さえも変わるんだからなんて思っていた。
だから今、昔とまるっきり同じ言葉を、よりにもよってこんな時に、聞かされるとは思わなかった。ベッドで横になっている夫は突然の言葉に驚く私を無表情で見ていた。
「いや、ハッピーエンドだけじゃないな」と夫はベッドの脇の椅子で呆然としている私に向かって話を続けた。
「全てに終わりなんてものは存在しないんだな。そもそも死なんてのものは有機物が無機物に変わる現象に過ぎないし、無機物はいつまでも、たとえ粉々に砕かれて塵同然になっても、そこにあり続けるものなんだから。我々有機体なんてのはただの無機物からたまたま出た余剰だよ。顔に出来たニキビ程度のものに過ぎないんだよ。寿命だってDNAで生まれて死ぬまでのおおよその時間をプログラミングされているロボットと大して変わらない存在なんだよ。そんな連中がハッピーエンドだの、バッドエンドだの自分のくだらない尺度で勝手に物事の終わりを決めるなんて傲慢だと思うね。とにかく今はっきりと見えるのはそのニキビの中のミクロの細胞程度でしかない俺が近々死ぬっていう現実だけだ」
「いや、悪かった」と私があからさまに動揺しているのを見たのか夫が急に謝ってきた。「単に宇宙の定理について講釈を垂れて見ただけだ。大体まだ死ぬって決まったわけじゃないしな。とにかくこれからどうするかを考えねえと。とにかく今はすぐにガン保険下ろして生活の足しにしないと」
学生の頃だったらこういう物言いによくそんな暇な事考えられるねぇ、なんて茶々を入れただろう。だけど今はそんな心の余裕なんてまったくなかった。夫が末期の癌であるという事実を知った今となっては、夫の皮肉はあまりにも重すぎて、私の心が崩れてしまわないように笑みを浮かべて取り繕うのが精一杯だった。
昨日、夫は私と彼の母親と一緒に、夏の日差しが照りつけ、クーラーのせいで寒くさえ感じる部屋の中で、自分がステージ4のガンだと告げられた。一週間前に夫が腹痛が酷いと言って病院に駆け込んで薬をもらっても全く効かず、それでレントゲン検査を受けたら腸閉塞が発覚して、さらに検査を重ねた結果ガンだとわかった。ここまで進んでは手術も抗がん剤も放射能治療も無理。医者の言うことでは夫は長く持って一年、早ければ半年も持たないということだった。がん告知を受けた瞬間、夫の母親は号泣して医者に何か治る方法はないのかと必死に食ってかかっていた。私はショックでたまらず何度も夫を見て反応を確かめたが、当の夫は表情を変えずになんとなくそんな気がしていたと納得した表情をしていて、案外事態を冷静に受け入れているように見えた。
夫とともに医者の癌告知を聞いた後で、私とお母さんは別室に呼び出され看護師の方から真っ先に行わなくてはいけない人工肛門の手術のことやそれと入院や緩和ケアなんかの事についての話を聞かされた。看護師はその時に夫交えてもう一度話すが自宅療養の事も考えて欲しいとも言った。そのほかに入院費や重体になった際の対応なんかについても詳しく説明してくれたが、私は混乱していて看護師の言うことにただはいはいと頷くことしか出来なかった。お母さんは意外に気丈で、時折涙を見せながらも私の代わりに色々と看護師に質問や要望を伝えていた。彼女はただショックのあまり何もできない私に向かって私は一回経験してるから慣れているからいつでも相談してと私に言ってくれた。
その後再び今度は夫を交えて私たちは改めて看護師さんの説明を聞いた。私は自宅療養を望んだが、夫はお前には仕事がある。俺はお前の負担だけにはなりたくないと頑として入院すると言って聞かなかった。
「大体素人のお前に看護なんて出来ないだろうが。お前はキッチリしている風に見えるけどいざって時に絶対役に立たないんだから。それだったらプロの看護師の方に付いていて貰った方がずっと安心できるんだよ」
私はこの夫の言葉に今の自分を顧みて全くそうだとしかいえなかった。
入院が決まるとすぐ夫は救急病棟から個室に移動させられた。これがどういう事をさすのか家族をガンでなくした方なら大体わかるだろう。私はベッドに乗せられて個室へと運ばれてゆく夫について行く間、自分が何を思っているか夫に気取られないように必死に笑顔で取り繕った。だけどお母さんには耐えきれなかったみたいでもう歩いている間ずっとため息をついていた。そうして私はお母さんと一緒にベッドの上の夫とそれを押して運ぶ看護師について入院する個室のある階の妙に静まり返った廊下を歩いていた時、たまたま開いていた病室で完全に骨と皮だけになっている患者を見てギョッとした。夫もいずれああなるのであろうか。
病室に着くとまず私はお母さんにも手を貸してもらって備え付けの棚に夫の荷物を入れた。一旦それが落ち着くと看護師は夫や私たちに向かってベッドの調整と呼び出しベルの説明をはじめた。続いて看護師は百円入れると三時間テレビが観れる事を紹介したけど普段テレビ等観ない夫は全く興味なさそうに聞いていた。看護師が入院の説明を終えて病室から出て行くと、夫が私に向かってこれから持ってきて欲しいものはリスト化してお前のスマホに送ると伝えてきた。彼に言わせるとわざわざ口で伝えるよりその方が手間がかからないということだ。その後私たちは軽い雑談をして、その後私とお母さんが帰る事を伝えた時、夫は私とお母さんに向かってこう言った。
「まあ、心配するな。自分の体は自分が一番よくわかっている。すぐに死ぬわけじゃないんだからまだ時間はあるさ」
夕方に病院を出て、駅にお母さんを送っている途中で彼女は夫が高校生の時に亡くなった彼のお父さんについて話してくれた。お母さんの話によると夫のガンはおそらくお父さんからの遺伝じゃないかということらしい。お父さんも夫と同じガンでしかもガンが発見された時すでに末期だったそうだ。ガンは遺伝するというからそれは本当かもしれないと私は思った。お母さんが言うには夫と私たちが知り合いになる前に亡くなったお父さんは性格がそっくりだったそうだ。皮肉めいたところとか、物知りぶるとか、とにかくプライドの高さが度を超しているとかそんなところがよく似ているらしい。私はお母さんが共通点としてあげる所夫に思い当たるので思わず笑ってしまったが、次のお母さんの次の言葉を聞いたら胸が苦しくなった。
「全く病気まで似なくてもいいのにねぇ」
だけどお母さんはいけないいけないこんな事言ったらあの子に怒られると首を振り泣きながら笑って自分と私を励ますように続けて言った。
「とにかく今はあの子ができるだけ長く生きられるか祈りましょ。こんな所で泣いてたって仕方がない。一番辛いのはあの子なんだし、そのあの子が今生きようと必死になって頑張ってるんだから」
私は病室で夫が言った言葉を思い浮かべお母さんと同じ事を思いそうですねと相槌を打った。
今日夫が私に向かって言ったあのあまりに今更な戯言はそんな私たちの希望と願望を徹底的に嘲笑うようなものだった。私はその後夫に別れを告げて病院から自宅のマンションに戻り、それからずっと部屋で夫が病室で言った言葉を考えていた。ハッピーエンドなんてない。そもそも終わりなんてものはない。寿命なんてのはDNAで生まれた時から決まっている。学生時代から延々と聞かされたこんな皮肉は夫が健康なときだったら軽くあしらってやり過ごしていた。だが今となっては夫の言葉は皮肉でなくて事実そのものとなってしまった。夫はあの時自分の言葉に私がショックを受けている事に気づいてすぐ誤魔化した。あの発言は皮肉とはいえ半分ぐらいは本音だったのかもしれない。「ほら、やっぱり自分の考えは正したかった。ハッピーエンドなんてありえない。命なんて惑星全体からしたらニキビ程度のもの」ステージ4のガンだと知った時彼は昔の自分の発言を思い出して心の中でこう例の皮肉めいた笑みを浮かべて苦笑したのだろうか。私は部屋の中のいつもそこに夫が座っている椅子を見ながら夫の身になってそんな事を考えた。こうして夫のいない空間に佇んでいると、その日がきた時の事が思い浮かんできて思わず震えた。彼が死んだら私はどうすればいいのだろう。
夫からのメール

翌日仕事のお昼休憩の時にスマホを開けたらにいきなり夫からのメールの通知があった。私は早速使ってきたなと思ってすぐにスマホを開けてメールを確認した。夫が持ってきて欲しいと頼んできたのは全て私と思い出の物たちだった。メールには思いついた順か無造作にリストが並べられ、この中から持てるだけのものを持ってきて欲しいと書いてあった。それから夫は行を開けてこんな事を書いていた。
『もう家には戻れないだろうからせめてコイツらを近くに置いてずっと眺めていたい』
これを読んで私は思わずスマホに向かってバカヤロウと叫んでしまった。私は自分の声の大きさに驚いて我に帰り口を塞いで無理矢理閉じて恐る恐る周りを見た。近くにいた人たちがびっくりした顔で私を見ていた。今日は本当に公園で食べて正解だった。会社の食堂だったら大変なことになっていた。夫がこんな私を見たら思いっきり笑うだろう。そう考えるとますます夫に対して腹が立ってくる。一昨日は前向きなことを言ってたくせに、昨日はあれで、今日でこれか。今頃はどうせまた死は有機物から無機物に変わる現象に過ぎないとか一人でブツブツ言ってるんだろう。私は夫への怒りと悲しみで混乱してとても働く気になれず結局早退してしまった。
早退して家に帰ると、私はすぐにリストの思い出の物たちからとりあえず手持ちで持っていけるだけのものをバッグに詰め込んだ。それが終わるとリビングでテレビを観たり、スマホをいじったり、しばらく寝たり、ぼぉ〜としたりとにかく夫の見舞いにいくまでの時間を潰した。勿論すぐにでも見舞いには行けた。だけど行ったら行ったでどうせ夫は会社はどうしたんだとか聞いてくるに違いないし、それで早退したと答えて彼に余計な気を使わせる事が嫌だったし、早退した事を彼に揶揄われるのも嫌だった。
病室に入った私をベッドに寝ている夫は待ってましたとばかりに手を振って迎えた。私はその夫を見て存外元気そうなので拍子抜けしてしまった。それで私は夫に色々持ってきたと言って持ってきた思い出の物たちを見せたら夫はお前はさすがよくわかってるなとすごく喜んで、私が明日他のやつも持ってこようかと聞くと、夫はとりあえずこれでいい、またなんか欲しくなったらメール寄越すからと答えて、それから軽く深呼吸するとこれで安心して治療に専念できると言って笑った。そんな夫を見て私は「なんだ結構元気じゃん。メール読んだら今にも死にそうなこと書いているから心配したよ」と苛立ち紛れに皮肉を言ったけど、その途端夫は真面目な顔で私を見たのでまずいと思って口をぎゅっと閉じた。だが、夫はすぐに笑顔に戻って私にこう言った。
「考えすぎんだよお前は!俺が死ぬって時にあんな短文ですませるかよ。俺はちゃんと俺が死んだ後お前が何をすべきかきちんと、バカなお前にもわかるように書くに決まってるだろうが」
とここで夫は話を一旦止めて再び真面目な顔に戻って話を続けた。
「だけどさ、俺がメールで書いたことは本当に思ってることなんだ。俺は今の自分の状況を総合的に見てるんだよ。俺の前には二つの坂道があって一つは死ぬ道で、もう一つは奇跡的に助かる道だ。俺はその坂道のどっちにも転んでも大丈夫なようにとにかく最善の方法を取りたいんだ。だから俺はお前にコイツらを持ってこいって書いたんだよ。こうしてコイツらを手元に置いておいたらどっちの覚悟もできるんだ。ひょっとした案外長く生きられるんじゃないかとか、でもやっぱりすぐ死ぬかもしれないからそれまでの時間をコイツらを見て我が身を振り返っておくとかさ。いい考えだろ?言ってみれば一石二鳥だよな」
そう言って話しを終えると夫はいつものように鼻で笑った。私は夫がとにかく全てを諦めたわけではないんだと安心してそういう心構えが必要なのよと説教混じりに励ましたけど同時に夫は私を安心させるためにあえてこんな演技してるんじゃないかとも思った。
二人はそれからしばらく互いに黙ってすっかり日が暮れた空を見ていた。そうしてずっと空を見ていたらふいに夫が土曜日の手術の事を聞いてきた。
「あのさ、今度の土曜日に手術あるだろ?お前それみんなに言ってねえよな。人工肛門の手術なんてみっともねえから誰にも知られたくないんだよ。だからあんまり人来てほしくないんだ」
「ねえ、お医者さんにも言われたでしょ?そういう偏見はよくないって。特にあなたは当事者なんだから自分を卑下したりするなって」
「うるせえな、みっともないというのは俺の勝手だろ?みっともねえものはみっともねえんだよ。それはともかくとしてさ……お前わかるだろ?こんな一時間もかからない手術にさ、みんなが生死を決する大手術みたいに大袈裟な顔して心配される俺の気持ちが。特にお袋だよ!あのババア俺がガンだって分かったらやたらピーピー泣きやがって!どうしてああも弱くなったかね。親父が死んだ時は全然平気だったのに。やっぱ年かね」
「またそんなこと言ってホント良くないよ。お母さんだってあなたの事を大切に思ってるんだから」
「それは勿論わかるよだけどさ……」とここで夫は言葉を詰まらせた。それから天井を見上げてまた続けた。
「お前も俺が愁嘆場が嫌いだって事わかるだろ?とにかく人に目の前で泣かれるのは嫌なんだよ。まぁお袋にはあんまり言えないけどさ」
私はその夫の言葉に彼とお母さんの強い絆を感じた。なんだかんだ言っても彼とお母さんはお父さんを亡くしてからずっと二人きりで暮らしてきたのだ。
「そうだよね。あなたホントにそういうの嫌いだよね。ドラマとか映画ホント大嫌いだもんね」
私は夫を和ませようと軽口を言った。すると夫は笑って「確かに俺はドラマとか映画とか小説とかあんなフィクションは全部大嫌いだ。あんなものに感動するやつは全員バカだぐらいに思っている」と返してきた。私はその夫の言葉に一緒に笑ったけど、それと同時に心の中でこう夫に話しかけていた。でもあなたそうブツクサ文句言いながらドラマとか映画とか一緒に全部観てくれたよね。あそこが悪いここが悪いなんて私の見落としてたシーン挙げるぐらい真剣に観てくれていたよね。それはきっと私に対するあなたの照れ隠しの優しさなんだよね。
そうしてひとしきり話した後で私は夫に向かって「じゃあ今日は帰るね。明日また来るからそれまでになんか欲しい物とかあったらメールして」と言ってから帰り支度を始めた。すると夫は私を呼び止めて言った。
「昼間にメール送って悪かったな。今度からちゃんと就業時間の後にするよ。あのさ……お前今日会社早退しただろ?それって俺のメールが原因だよな」
私は慌てて早退なんかしてない。ちゃんと定時まで働いたと嘘をついた。しかし夫は呆れたように私を見て言ってきた。
「おい、下手な嘘つくんじゃねえよ!俺たち何年付き合ってると思ってるんだよ!お前のことなんかすぐにわかるんだよ!」
手術の日の出来事

手術の付き添いには私とお母さんとその弟のおじさんだけ呼んだ。これは私が夫に言われた通り見舞いは控えてくれと頼んだからだ。このおじさんというのは私と夫がお母さんの弟さんで私たちもよくお世話になっている人だった。いかにも堅物といった感じの人だが、喋ってもやっぱり堅物な人だった。おじさんはお母さんのうちの近くに家族で住んでいて、いつも一人で暮らしているお母さんを気にかけていた。
当日私と病院の入り口でお母さんとおじさんを迎えると早速二人を病室に連れて言った。そしてベッドで待機している夫に二人を会わせたけど、おじさんは少し動揺したのか言葉を詰まらせてしまった。お母さんは夫に駆け寄って興奮して声を震わせながら腕を取って何度も頑張るのよ!負けちゃダメよと励ました。夫はお母さんに対しておじさんがいるからか文句を言う事ができずただうざそうな目で睨んでいるだけだった。やがて看護師が手術の用意が出来たので移動すると言ってベッドを運び出した。私たちも後から手術室へと向かった。
手術室の前でお母さんは辛いと言って泣き出してしまった。おじさんはそんなお母さんを一番辛いのは本人なんだからと言って嗜めていた。おじさんは話の最中に私の方を向いて彼女だって辛いのに耐えてるじゃないかと言っていた。私はお母さんに対して何も声がかけられない事が辛かった。お母さんは自分よりも遥かに辛い思いを味わっているのだ。夫のがん宣告のショックで足元がまだふらついているような私には彼女にかけられる言葉などありはしない。やがてドアが開いて先生が手術が成功した事を告げた。だがその顔は決して明るいものではなかった。
それからすぐに夫がベッドに乗せられて私たちの元に運ばれてきた。夫は手術前に比べると急にグッと老け込んでいるように見えた。お母さんはその夫を泣きながら呼び、看護師に息子さんは大丈夫だからと嗜められた。おじさんはそのお母さんと夫を何ともいえないような顔で見ていた。その時向こう側から看護師がやって来て私に話しかけてきた。先生が話したい事があるので落ち着いたら面談室まで来て欲しいとの事だった。私はお母さんとおじさんにその事を伝え寝ている夫に後ろ髪を引かれながら面談室へと向かった。
先生にお辞儀をして面談室から出た瞬間大きなため息が出た。面談で先生は私にこんな事を言っていた。手術の前に簡単な検査をしたが、それがあまり良くなかったとのことだ。ガンは思ったより早く進行しているらしい。先生は来週にまた正式な検査をするが結果はあまり変わらいだろうとも言っていた。この予想されていたとはいえこうして改めてハッキリと事実を聞かされて精神的にかなりきた。私はもう夫が戻っているであろう病室へと向かっていたけど、もう足元がふらついてなんだか底なし沼を歩いているような気分になった。
病室のドアを少し開くと夫はやはり病室に戻っていてさっきと同じようにベッドでぐっすりと寝ていた。その夫の脇にお母さんが座っていて、無表情のまま目と口を開いて必至に夫の腕をさすっている。私はそれを見て入ってはいけないものを感じて立ち止まった。そこにおじさんがやって来て私に向かって手術が成功したことを自分の親戚の人間や彼と私の父親に連絡した事を伝えてくれた。私はおじさんに感謝して申し訳ないと礼を言ったけど、その時おじさんを見たら彼もお母さんの姿に動揺したのか目を剥いてベッドの母子をみていた。
「あの、しばらく休憩コーナーで待ってないか?」とおじさんは私に声をかけてきたので私は頷いて一緒に休憩コーナーへと向かい、二人で空いていたテーブルに座った。おじさんは自販機でジュースでも買うから何がいい?と聞いてきたが、私は別に喉が乾いていなかったので結構ですと断った。
おじさんは私の父が能天気によかったよかったこれですぐに退院だな明日あたり早速見舞いに夫の好きなメロンでも持って行くかなどと言っていた事を話してきた。私はそれを聞いて顔が真っ赤になった。うちの両親は能天気な人たちで相手に気を使うとかそんなことに無頓着な人たちなのだ。私がおじさんに申し訳ないと謝ると、おじさんは大丈夫と言って私にまだ両親に夫の病気を話していないのかと聞いてきた。私がためらいがちに頷くとおじさんは続けてこう言った。
「あの、あまりに急な出来事であなたもどう周りに伝えればいいのかわからないのだろうが、こういう事は早めに伝えておいた方がいい。出ないとあらぬ誤解が生じていらぬ揉め事を起こしかねないから」
それからおじさんは私に生活はどうなっているのかと聞いてきたので、私は今のところは特に問題はないと答えた。実際に今の所特に何も問題はなかった。私は今も普段通り働いているし、夫の今月分の給料も振り込まれる予定だし、夫のがん保険も来月に降りる予定だし、生活費も特に足りないわけではないし、とにかく表目的には生活に支障は出ていなかった。あくまでも表面的にはだが。おじさんは私の話を聞いてなるほどと言って頷き、何かあったらいつでも連絡してくれと自分が使用しているLINEのIDを教えてくれた。
それからおじさんはお母さんのことについていろいろ話してくれた。お母さんはしっかりした意志の強い人で子供の頃はいじめっ子からおじさんを守ってくれていたらしい。その性格は大人になっても変わらず兄さん、つまり夫の父親だ、が亡くなった時も涙一つ見せず気丈に振る舞っていたそうだ。
「だからあの姉さんがあんな簡単に泣くなんて僕は悲しいんだよ。だけどこうも思うんだ。涙ってのは人間の感情の最後の防御線じゃないかって。昔のまだ若かった姉さんは気だけで不幸を乗り越えられたんだと思う。だけど年取った姉さんにはもうそんな事は無理なんだ。今の姉さんはもう泣く事でしか自分を守れなくなっちまったんだな。それでもダメだったら姉さんは……」
おじさんはそこまで言うと続けてさっき私と一緒に病室で見たお母さんについて話し始めたが、おじさんはもう姉であるお母さんのことに夢中になるあまり私が何者であるかすっかり忘れてしまったようだった。
「あなたも見ただろ?病室で姉さんが惚けたような顔で必死に息子の腕を摩っているのを。あれ多分手術室から運ばれてきた息子を見て兄さんのこと思い出してショックを受けたからだよ。兄さんも病院で人工肛門の手術受けた時あんな風だったんだ。これからの姉さんを思うとゾッとするよ。彼女は今最愛の夫に続いて最愛の息子まで同じ病気で失おうとしている。姉さんはそうなったらどうなるんだろう。泣くことさえ出来なくてただあの惚けた顔で息子を見送るのだろうか。だがそれから姉さんはどうすればいい?人は自分の愛する全てを失った後はどうやって生きていけば良いのだ」
「わかりません!」
私はおじさんの言葉に耐えられなくて思わず声を荒らげてしまった。思った以上に声が大きかったようで休憩コーナーに座っていた患者さんがみんな私たちの方を向いていた。おじさんはしまったとばかりに口を押さえてそれから長々とバカげた事を話してしまったと深く頭を下げてきて、私もただの相槌をするつもりだったのに声を荒げてしまって申し訳ないと慌てて謝ったが、それでも二人の間に出来た気まずい雰囲気は取れなかった。
※※
その翌週私は先生から夫の検査結果を聞かされた。やはり予想以上に悪いらしい。思った以上に進行が早く確実に一年は持たないだろうという事だった。
インディアン・サマー その1
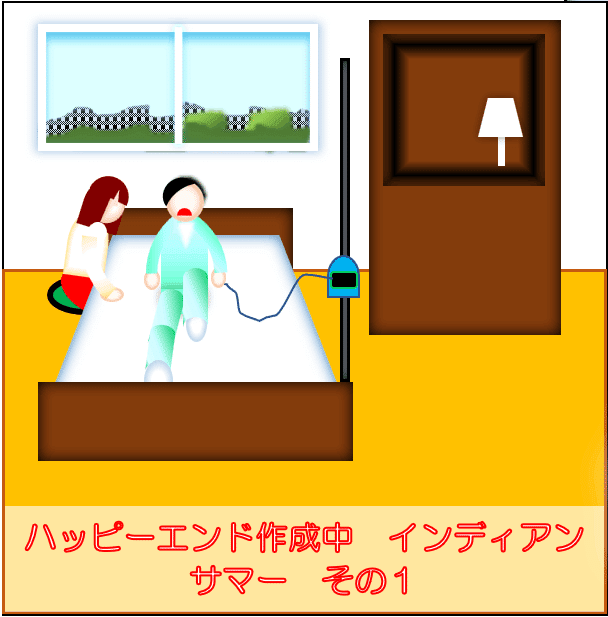
夫が手術を終えて本格的に入院生活に入ると今まで慌しかったのが嘘のように平穏になった。私の生活は夫が入院してからずっと同じだった。アラームが鳴ると隣に誰もいないベッドで一人起きそして朝食を食べる。それから気分によってはお弁当を作ってオフィスの休憩室や近くの公園で食べる。お弁当じゃない時は近くのお店で食べる。仕事が終わったら真っ直ぐに夫のところに見舞いに行った。病室に見舞いに行くと夫がいつもコイツらとか言っている私たちの思い出の品たちが迎えてくれた。私はそれをみるたびに何故か自宅に帰ってきたような気がした。そうして見舞いから帰ると夕食を作り食べた後はメールやLINEなんかで友達や同僚たちと寝るまでの時間を潰す日々の繰り返しだった。慣れれば恐ろしいぐらい何にも変わらない、ただ緩慢な時間が流れるだけのそんな毎日の中で時折このまま時がこの時が永遠に続きそうなほどの錯覚さえ覚えてしまっていた。これは私にとって一種のインディアン・サマーだった。しかしそれは冬が来るまでの、いや多分すでに来ている冬をごまかすために、私が心の中で無理矢理拵えた人工的な晴天だった。
その間にも夫は医者の検査結果通りに日々弱ってゆき、ついこの間まで普通に立って歩いていたのに今では杖で体を支えないと歩くのにも一苦労するような状態になっていた。そんな夫を見て長くはないかもと目の前が真っ暗になったこともある。家で夫のいない暮らしに慣れている自分に気づきゾッとしたこともある。だけどこの恐ろしく単調な毎日の繰り返しは私にこのまま時が続けばいいなんて能天気な願望に耽るだけの心の余裕だけは与えてくれた。
私たちはよく病室にある私たちの思い出の品、夫のいわゆるコイツラを見ながらよく思い出話に花を咲かせた。とはいっても夫は自分ではなにも語らずもっぱら私に喋らすのだ。夫はその私の話に嘘だろとかバカだなお前はとか言っていちいち茶々を入れてくる。私がそれに対して人にばっかり喋らせないであなたもなんか喋りなさいよと文句を言うと、その度に夫は俺は記憶力が悪いからお前みたいにいちいち物事を覚えていねえんだよと誤魔化して逃げた。
そんなある日のこと、夫が見舞いの最中には何も言わなかったくせに、その後私が家に帰ってる最中に突然メールで次から見舞いは三日に一回にしてくれと言ってきた。いきなりの要望に私がなんでと一言入れて返信すると、夫はすぐに長々しくいろんな理由を述べて返してきた。曰く、俺にも一人になりたい時がある。看護師たちが自分たちを揶揄い半分でチラチラ見てくるのがいやだ。などと理由を書いていて、それから弁明かなんだか分からないが、別にお前がうざくなったわけじゃないとか。看護師の女性に惚れたわけじゃないとかそんな私が思うであろう事を自分で勝手に邪推してこんなどうでもいい余計な弁明を長々と書いていた。私は読んでいて本当に相変わらず余計な気を回すなと思った。
夫はいつもこうだ。何か私に疑わしいと思わせるようなそんなシュチュエーションになると決まってその事について嘘をついて誤魔化してると勘繰らせてしまうほどに長々と、こちらが全く思ってさえいないことまで、今のような感じで長々と弁明してくるのだ。全くなんてバカなんだろう。いつもいつもどうでもいいことばかり気を遣って勘違いも甚だしい。私は呆れ果ててもう何も言う気になれずただ簡潔に『メール読みました。仰る通り次からは見舞いは三日に一度にしますから』と書いてとりあえず送っておいた。
病院で看護師さんから夫についてのいろんな話を聞かされた。まず夫の失敗談だ。一昨日夫はストーマ袋の中の便を誤ってこぼして部屋中に撒き散らしてしまったそうだ。看護師さんが入ると夫は普段はあり得ないぐらいもの凄く落ち込んでいて看護師さんが最初のうちは慣れないから仕方がありませんよと慰めても、ただ申し訳ありませんと謝って項垂れるばかりだったそうだ。しかしその翌日である。看護師さんが検温のために病室に入ると夫は昨日迷惑をかけたお詫びのつもりか、なんと自ら拭きもので床を拭いているではないか。看護師さんは慌てて止めたけど、夫は昨日のお詫びと言って聞かずしばらく拭き続けたらしい。多分看護師さんは夫に対して相当困ったであろう。私は彼女に深く頭を下げて謝った。
これも夫の悪いところというかなんといっていいかわからないけど、一種の完璧主義的なところから出た行動だ。夫は普段から私や他の人たちに自分がどうしたらよりよく見られるかを気にして振る舞っていた。行動でも人格的にも相手より上の人間だと思われたかったのだ。だからその自分かよりによって便をこぼしてしまうような大失敗をした事が耐えられず、その恥の埋め合わせをするためにわざわざ雑巾拭きをしだしたのだ。全くといっていいかなんというか私は夫のこの頑固なまでのプライドの高さに呆れてしまった。全く日頃自分で人間ほど不完全なものはいないとか偉そうに言っておきながらどうして自分はそれを認められないのだろうか。
次に話してくれたのがだいぶ前に夫が診察の際に先生に対して自分の体はこれからどうなってゆくのかと尋ねた時の事だ。夫はすでに私と一緒に検索結果を教えられていたが、夫はさらに詳しく病状を知りたかっということだ。先生は夫の精神状態を心配して躊躇ったようだったけど、夫がどうしても知りたいと頼んで来たので先生も決心して診察の後で特別に時間を設けてくれて夫に病状の経過について話したそうだ。
「旦那さん、何も言わずに先生の説明にずっと耳を聞いていたんです。多分ご自身にとってお辛い事も知ったと思うんですけど。あの人顔色ひとつ変えないで最後まで聞いてらしてそれで説明が終わったら笑顔で先生にありがとうございます。これで覚悟が出来ましたって深く頭を下げて。私ね、今までいろんな患者さん見てきたけどあそこまでお強い人見た事ないですよ。あんな辛い話を聞かされても全然いつもと変わらないんですから」
私は看護師さんの言葉を聞いてため息をついた。夫が病状の事を全て知りたがったの彼の性格を知っている私にはよく分かる。彼は自分の病状の全てを知ってそして自分がどうすべきか考えたかったんだと思う。何事にもまず事態を完全に把握してから判断をする。夫はそういう人間だった。だけど全く、全くどうしてこの人は無理してカッコつけたがるんだろう。夫は強いんじゃなくて他人に弱音を見せたくないだけだ。私にはそれがよくわかる。だって私は彼が完璧に振る舞おうとして無惨に失敗しているところをいつも見ているから。そして自分の失敗を取り繕うとしてさらに取り返しのつかないほど傷口を広げているのをいつも見ているから。全くあなたはなんでこんな時までカッコつけるのよ。そんなに我慢したって辛くなるだけなのに。だんだん目頭が熱くなって目に手を目に持っていこうとした時看護師さんが心配そうな顔で私に声をかけてきた。私はハッとして我に返り顔を上げて大丈夫ですと答えた。
その後夫の病室に行った。ドアを開けて病室に入った時、床がやたらピカピカしているのが目についたので、私はベッドから体を起こしていた夫に向かって「今日も床磨いたの?」と思わず聞いてしまった。口にした瞬間マズイと頭が真っ白になったけど、もう後の祭りだった。ベッドの夫は真っ赤な顔で目を剥いて私を睨みつけていた。私は冷たい汗を背中に感じながら「だ、誰でも失敗はあるし」と慌てて夫を和ませようとしたけど完全に逆効果だった。完全にキレてしまった夫は「うるさい、今すぐ帰れ!」と私を怒鳴りつけると思いっきりふて寝してしまった。
インディアン・サマー その2

お母さんは相変わらず見舞いに来ていた。手術の翌日の日曜日に見舞いに来たお母さんは昨日の憔悴ぶりが嘘のようにすっかり元気になって、部屋を見回して私達の思い出の品たち、夫がいつもコイツラを言っているものを見つけて、あれ?いつの間にかお部屋が華やかになってと言って私と夫を囃し立てた。それから夫に向かってちゃんとご飯食べてるの?とか、お医者さまの言う事ちゃんと聞いてるの?とか立て続けに尋ねて夫に文句を言われていた。お母さんは月曜日からパートに復帰するらしい。私はそんなお母さんを見てとりあえず一安心した。ただおじさんを誘ったけど断られたという話を聞いて心が痛んだ。おじさんはまだあの時のことを気にしているのだろうか。
お母さんは見舞いに来るたびに夫に対してあれこれとお小言を言って、その度に夫から文句を言われていたけど私はそんな二人のいつもと変わらぬ光景を見てなんか嬉しくなった。
そうしてお母さんが見舞いにきていた時、夫がふいにお母さんに向かってお父さんの最期の事を喋り出した。私は夫の話に少し身構えたが、お母さんは全然平気なようで時折相槌を打って息子の話に耳を傾けていた。
「おふくろ。やっぱりオヤジの最期って立派だったよな。今こんな体になってあらためて思うよ。あれほどプライドが高くてウザいだけだったオヤジが、死ぬってわかった途端急に人が変わったみてえに落ち着きやがって、騒ぎもせず泣きもせずただ目の前の現実を受け入れて死んだんだ。俺はそんなオヤジを見て死ってのはここまで人を変えるのかと思ったね。全てに未練がなくなって自分や周りを客観的に見ることが出来るようになったのか、あるいは最期に父親らしいところを見せようとしたのか、それはわからない。だけどあの時のオヤジの姿は今もハッキリと思い出せる」
私は父親の事を語る夫と、「そうね」と何度も息子の話に頷いて相槌を打つお母さんを見て手術の日に見た二人の姿を思い出して居づらくなった。私は肉親の死というものに一回もあった事がない。私は父母ともに長寿の家系らしく祖父母のお父さんお母さんまで健在だ。一年前に曽祖父のお兄さんが亡くなったけどこれが私が今まで体験した唯一の血縁の死だ。そんな私がここで一緒に聞いていていいのだろうかと思った。
「俺、最後の最期で初めてオヤジを尊敬したよ。死という事実にどうやって向き合うか。俺はオヤジからそれを学んだんだ。死というのはただの事実でしかない。だけどその事実に真正面から向き合う事で人はあそこまで偉大になれるんだってさ。まだ先だけど俺もその時が来たあんな風に死ねたらいいなって思うよ」
夫がここまで言い終えた時お母さんは相槌を打ちながら涙ぐんでいた。私は夫の話を聞きながら彼がその死生観も含めてお父さんからかなりの影響を受けているんじゃないかと考えた。ひょっとしたら彼の皮肉な部分もお父さんの死を見たからなのかもしれないと思った。彼はお父さんのように立派に死ぬつもりなのだろう。だけど……まだその時じゃないよ。まだそんなこと考えなくていいんだよ。あなたそうやって先走って考えていつも失敗ばかりしているじゃない。私はずっと心の中でそう夫に訴えかけていた。
病院を出た時お母さんがお家に行っていい?と聞いてきた。私は勿論と答えた。私と夫の住んでいる家はごく平凡な賃貸マンションだ。いずれ郊外にでも一戸建てやマンションを購入するつもりだったけどそれも夢物語に終わりそうだ。家に着いてお母さんを中に入れてリビングに連れて行こうとした時、お母さんが夫の書斎の前で止まってここに入れてもらっていいかと聞いてきた。私は躊躇いがちに大丈夫だと答えて早速ドアを開けたけど、お母さんは部屋を見るなり顔をしかめた。
部屋はお母さんが顔をしかめたように見事なまでに乱雑な状態だった。本などが床に置きっぱなしになっていて、広げたまま置かれている本もたくさんあった。チラシの類も同じように散らばっていてとても足を踏み入れられる状態ではなかった。夫は片付けがまるで出来ないタイプで、たまらず私が片付けをするとものすごく怒るのだ。いつかそのせいで一晩中互いに罵り合うほどの大喧嘩になった事がある。私はそれに懲りてそれからはもう夫が出張とかで家をあけるときでも部屋の整理はせず、ただあからさまにゴミとわかるものだけ捨てることにしていた。
「……すみません。散らかってて」
と私がいいかけるとお母さんは笑って私を制した。
「あなたが謝ることじゃないわよ。どうせあの子でしょ。……はぁ、相変わらずね。大人になってもこんなに散らかして。昔からあの子整理整頓が出来ないのよ。それでこっちが片付けろって言うとガミガミ怒るしねえ~」
お母さんの言葉に私も釣られて笑った。
「なんだか懐かしいわ。あの子家でもこんな風だったのよ」
それからお母さんはしばらく夫の部屋を見つめていたけど、ふいにこう呟いた。
「あなた、ずっとこのままにしてるのね」
お母さんの突然の問いに心臓がビクんとした。彼女は続けて私に尋ねてきた。
「ねぇ、あなたあの子に帰ってきて欲しい?」
「出来れば帰ってきて欲しいという思いはあります」
「だけどねぇ、あの子頑固者だからねぇ。うちの旦那とまるで同じで……」
と、ここでお母さんは突然話を切って私に言った。
「ああ、いつまでも部屋覗いてちゃあの子に怒られれちゃうわ!もう行きましょ!」
それから私たちは夫の書斎のドアを閉めてリビングに行った。お母さんはまだ私に話したい事があるみたいで私の顔をチラチラと見ていた。
「あの、さっきあの子が言ってた事なんだけどね」とリビングでお母さんがお茶を一口飲んでから私に話しかけてきた。「あれ、あの子がいつも私に話していることだから気にしないでほしいのよ。あの子は昔から何かというと死ぬ時の旦那が立派だったとか言ってねえ。自分もあんな風に死にたいとかよく言ってるのよ」
「全然平気ですよ。むしろ私お父さんの事は夫から全く聞かされてなかったから、知ることが出来て良かったです。あの人のお父さんってすごい立派な人だったんだなって」
私がそう言うとお母さんは急に笑い出した。
「実はね……あの人が立派そうに振る舞ってたのってあの子の前だけなの。私と二人きりの時はずっと愚痴ばかり言ってたの。いっそこっから飛び降りたらこの苦痛から開放されるのにとか、お前にはこの苦痛はわからんだろうとか、まあそんな事を死ぬまでずっと延々と言ってたわ。賢人ぶってたのはあの子の前だけ。多分死ぬ前に父親としての威厳を見せたかったのよ。全く呆れるわ。どうしようもないええカッコしいで」
お母さんはそう話すと深いため息をついた。私は夫の顔を思い浮かべて複雑な気持ちになった。するとまたお母さんが私に顔を近づけて言った。
「ねえ、今言ったことあの子に絶対に言っちゃだめよ。あの子ああ見えてすごく純粋な子だから、本当の事知ったら、自分の全てが否定されたってぐらい傷つくと思うの。自分が見た父親の最後が今のあの子の心の支えになっているんだから」
「わかってます。絶対あの人には黙ってます」
「ありがとう」
お母さんはそう言ってにこやかに微笑んだ。私はそんなお母さんを見て本当に強い人だと思った。今までずっとお母さんの一面しか見ていなかったんだと思う。やっぱり最愛の人を亡くしてからずっと一人で息子を世話してきたんだから。そんな人が弱いはずはないんだ。お母さんはお茶を飲み切ってから黙ったまま私をみていた。私がどうしたのかと聞くとお母さんはごめんなさいねと謝ってから私に言った。
「やっぱりあなたがあの子の奥さんになってくれて良かったわ」
私はこの突然のお母さんの言葉に動揺して何も言えずにいるとお母さんは続けて話した。
「私ね、あの子があなたを連れてきた時あなたを見て、案外あっさりとあの子も自分に合う子を見つけてきたなって思ったの。だって私実はあの子ずっと結婚できないんじゃないかって思ってたものねぇ、わかるでしょ?あの子の性格見れば」
私はお母さんの話に思わず笑ってしまった。確かにそうだ。冷静に考えればあんな捻くれ者でプライドばかり高い人間と結婚しようなんて考える人間なんてまずいないだろう。あんな人間と間違って結婚したとしても二年もしないうちに離婚裁判になるのがオチだ。私だって出会って最初のうちは結婚どころか付き合うことさえ考えていなかった。だけどこうして付き合い結婚して二十代を丸ごと彼と共に過ごしてきたのだから人間なんてわかったものじゃない。
「多分あの子絶対あなたに感謝しているはずだわ。あの子ああいう性格だから友達もあまりいなかったし、女性とだってあまりいいお付き合い出来ていなかったと思うの。だけどあなたはそのあの子が唯一心を許せる人なのよ。だってあなたはあの子の洒落ではすまない皮肉でも全く動じないでしょ?」
「慣れてますから。学生時代から延々と聞かされていた事だし」
お母さんは私の返事を聞いて深く頷いた。そしてしばらくしてからこう呟いた。
「あなたがそういう子で助かったって今ホントに思うの。あなたも知ってるようにあの子目の前で泣かれるのを本当に嫌がるでしょ?それどころかそういうそぶりさえ見せるのさえ我慢が出来ない子でしょ?あなたはそんなあの子に対してずっと普通に接してくれてるんだもの。今の私には全く出来ないわ。本当は旦那の時から全然できていなかったんだけど……」
「それって多分私があの人と一緒で感情出すのが苦手だからですよ。だから普通に接しているように見られるです。だってあの人がガンの末期状態だって聞かされた時混乱してお母さんの手助けがなかったら何も対応出来なかったじゃないですか。私はあの人がいつも言っているように、しっかりしてそうに見えるけど肝心な時に何もできない人間なんですよ。今もこの現実にどう対応していいかわからなくて毎日自問自答して本当なら答えのないはずの答えに無理矢理解答をつけてそれでどうにか自分を安心させているんです」
「だけどあなたはそんな思いを抱えながらもあの子に普通に接してくれてるでしょ。それが私にとって、何より今のあの子にとっては助かるの。あの子はあんな子だから他人には絶対に怖がっているところなんて見せないけど実は毎晩夢でうなされるぐらいの恐怖を味わっていると思うの。そんなあの子にたいしてあなたはいつも通りにお話や冗談なんかをしてくれてるじゃない?あの子にとってはそれだけで救いになっている思うの。あと、あなたは今あの子が自分の事を肝心な時に役に立たないって言ってたって喋ったわよね。それってあの子の照れ隠しでしょ。本当はあの子はずっとあなたを頼りにしているのよ。あの子一度私に言った事があるの。ほら、あの時よ」
お母さんがあの時と言ったのは私が夫の子供を流産した時の事だ。あの時は本当に落ち込んで生きる気力さえなかった。赤ちゃんを産むことが出来なかった自分に対する苛立ちと、赤ちゃんの父親になるはずだった夫への申し訳なさで毎日が辛かった。夫はそんな私を見て凄く動揺してまるで挙動不審みたいに家中をあちこち歩き回っていた。私はあの皮肉屋でプライドの高い夫の夫そんな姿を見るのが耐えられす、とりあえず立ち直ったふりをして彼に接していたらいつの間にか本当に気力を取り戻していたとう話だ。その事を今お母さんは話していた。
「あの時はあの子珍しく私に電話かけてきて相談してきたのよ『アイツがあそこまで落ち込んでるの初めて見たよ。お袋は女だからわかんだろ?だから教えてくれよ。俺はこれからアイツにどう接すればいいんだよ。考えても考えてもわからねえよ』でもそんな事相談されたって私には流産の経験なんてないからわからないでしょ。だから私しばらく放っておくしかないってアドバイスにもならないアドバイスしたのよ。私もしなんかあったらって心配しながらあの子の報告待ってたんだけど。それから何日もしないうちにあの子から電話がかかってきたじゃない。私悪いことが起きてなきゃいいけどって電話とったらあの子明るい声であの子が元気になったって言うじゃない。そしてこう言ったの。『俺、アイツをずっといざって言う時に役に立たないポンコツ人間だって思ってたけど全然違ったよ。アイツやっぱり強えよ。ちゃんと自分で立ち直ってるんだから』私もあの時あの子とおんなじこと思ったわ。そして今もっと強くそう思うの」
私はお母さんから夫が私を強い人間だと言っていた事を聞かされてなんだか恥ずかしくなった。夫は私を褒めることなど滅多にない。ついてだけど私も夫を褒めることは滅多にない。夫は私には絶対に言わない事をどうしてお母さんだけには言うのだろう。私にはいつも捻くれたことを言っているくせに。ポンコツのアイツにしては頑張ったなとか、あのポンコツもやれば出来るんだなとかそんなセリフの方が彼には似合っているのだ。そもそも夫はあの件を全く誤解している。私はただ夫が私を心配しすぎておかしくなっているのを見てられなかっただけだ。それで無理して立ち直ったふりをしていただけだ。立ち直ったのはただの結果にすぎない。それを強いだなんて誤解にもほどがある。だけど今はその言葉を支えに夫に向き合っていくしかなかった。
ふと手の甲に暖かいものが被さっている気がして私は我に返った。いつの間にかお母さんが私の手を握っていた。お母さんは手を強く握って私に言った。
「あなたは強いのよ。そのあなたの強さがあの子に生きる力を与えてくれていると思うの。もう私だけじゃあの子を支えきれないわ。きっとあの子を迷惑がらせるだけだもの。だからお願い、私と一緒にあなたもあの子を最期まで見守っててあげて」
お母さんはもう私が必死に見まいと避けているこれからの事を考えている。お母さんはやっぱり私なんかより全然強い人なんだ。お父さんに続いて一人息子まで失おうとしているのにちゃんと前を向いて現実を受け入れようとしているんだから。私はお母さんの同じようにお母さんのシワだらけになった手のひらを力を込めて握りしめた。その手には今までの苦難を乗り越えてきた人の力強さが込められていた。私はお母さんに向かって自分を鼓舞するようにハッキリと答えた。
「ええ、あの人が最期まで笑顔でいられるようにしっかり見守ります。それが私のあの人へに出来る唯一のことだから」
インディアン・サマー その3

夫とは入院してから何度か病院の敷地内にある庭に行った。医者も夫の外出を勧めていたからだ。この日も夫は看護師に向かっていい天気だから外行ってきますと言い、私にも今から散歩に行くから部屋の外で待ってろ言って体を気遣うようにゆっくりと立ち上がった。私はその夫の動作を見てるといつも悲しくなる。あんなにシャキシャキ動く人がこんなにもゆっくりとしか動けないなんて。夫は看護師が差し出した杖をもらうと私に向かって準備がもういくぞと言ってきた。
看護師は夫と私をエレベーターのそばまで案内し下に降りるエレベーターが来て、私たちが乗り込むとではお気をつけてと手を振って見送った。夫はエレベーターに乗った途端に杖を私に差し出してお前が持ってろと言い出した。杖なしで大丈夫だという。私が危ないよと言うと夫は骨折しているわけでもないのになんで危ないんだと言い返してきた。私はまた始まったと呆れ、これ以上説得しても無駄だと思い手を出して彼から杖を受け取った。
エレベーターが一階に着いたので私たちは庭に行こうと出入り口まで歩いていたらやっぱり夫が手すりに手をついてぜえぜえいいだした。だから言わんこっちゃないと私が音楽に杖を差し出すと彼は怒ったように窓に写っている庭を指指して「あそこの木の下の空いてるベンチで待ってろ。俺もすぐに行くから絶対に場所取られんじゃねえぞ」と言ってきた。私もうめんどくさくなってわかったと頷いてそのまま出入り口へと向かった。
出入り口で私は後ろからやってきた若い夫婦とぶつかりそうになった。私たちは互いに頭を下げてごめんなさいと謝った。若い夫婦は共に私と同じぐらいの年頃で奥さんはお腹を膨らませていた。夫婦は私に頭を下げながら病院を出て行った。私は薄暗い病院の出入り口から眩しい明かりをうけて歩いている二人を見て思わず手をぎゅっと握った。私達だってああなれたかもしれないのに。ああなるべきだったのに。夫婦に続いて中年の夫婦が出てきて、それとすれ違いに老年の夫婦が入ってきた。そんな散々見慣れたはずの光景は今の私にとってはただの当てつけでしかなかった。あの人たちは私と夫が絶対に手に入れることの出来ない時間を持っている。私たちがもうじき失うであろう幸福な時間を。
私は夫に言われた通りベンチに座って夫と待っていた。夫は周りの柱とか木に手をついてゆっくりとこちらに向かってくる。その姿は健康だった頃の彼からは想像できないぐらい弱々しいものだった。夫が精神まで弱々しくなっていたらまだこの状態に納得がいく。だけど夫の精神は驚くほど変わっていなかったので、彼がこんな状況に陥っているのはやっぱり不条理としかいえないものだった。
夫がぜいぜい息を吐きながらベンチにやってきた。彼は崩れ落ちるようにベンチに座るなり思いっきり息を吐いて「まさか歩くだけでこんなに苦労するとは思わなかった」と言った。私は夫に看護師さんのいうように杖つかないからそんなに疲れるのよ、無理しないで杖ぐらいつきなさいよと注意したけど、彼は俺はまだ杖なんかついて歩く年じゃないとか口答えしてきた。全くどこまで見栄っ張りなのか。お前は毎日看護師がいる時は自分から杖を取ってるじゃないか。全くあっちこっちに良いところを見せてもしょうがないでしょうに。私はこの相変わらずの見栄っ張りぶりに本当に呆れ果てた。
ベンチに座った夫はそのまましばらく無言で晴天の空を見ていた。彼は昔から時折そうやって空を見ていた。私はそんな彼をみるたびにきっと小難しい事を考えているんだろうって思っていた。じゃあ今は何を考えているんだろう。今の彼には考えなくてはいけない事が多すぎるはずだ。だけど私には……
「こうやってポカンと空見上げるのもいいよな」と突然夫が話しかけてきた。私は珍しく頬を緩ませてこちらを見ている夫に「そうだよね」と相槌を打ってそれから少し勇気を出して「今、なに考えていたの?」と聞いた。すると夫は笑って答えた。
「別に何も考えてねえよ。ただホントに外っていいなって思っただけだよ。こうやって体が弱ってきて、思い通りに動かなくなってみるとさ。ホントに外気に触れることのありがたみがわかってきたよ」
「あなたがそんな事素直に言うなんて珍しいね」
「バカ、俺はいつだって素直じゃないか。素直すぎるから他人といつも余計な軋轢を起こしているんだろうが!」
「ああ……そうだね」
私は相変わらず夫の言葉に笑い、夫もまた笑った。
それから私たちは黙って空を見ていた。そうしていたらふいに夫がこの間売った車の事を謝ってきた。
「車のこと悪かったな。俺がこんな事になったせいで」
私は夫の謝罪に動揺して慌てて夫に「そんなのいいから全然!」と言った。すると夫はにこやかに微笑んでこう言った。
「お前、昔から旅行好きだったよな。大学時代からよく海外旅行とかしてたよな。ほら、新婚旅行で海外に行った時すごいはしゃいでてさ。この病室に飾ってある新婚旅行の写真なんか全部お前のじゃないか」
「そうだよね。あなた全く周りの景色に興味なかったよね。一人ポツンとなにもしないで立ってたし。結局買い物も食事も全部私に任せっきりだっだじゃん」
「だから最初に言っただろ?俺は旅行が下手なんだって。別に海外なんか行ったって新たな発見なんかあるわけないだろ?テレビや動画で散々見たような景色なんか見たって、違う国の違う制度の元に生きている俺たちと多少形が違うだけのホモサピエンスなんか見たって面白いわけないだろうが。……それに旅行は別に退屈じゃなかったよ。だってはしゃいでいるお前を見ているだけで楽しかったからな」
「なに?はしゃいでいる私かバカみたいでおかしかったって言いたいのあなた?」
「そうじゃねえよ。お前って妙に鈍感なとこあるよな」
「えっ?」
夫は私に向かって呆れたようにため息をつくと黙って私を見てこう言った。
「お前、暇んなったらどっか旅行いけよ。最近全然旅行してなかっただろ?」
この夫の言葉を聞いた途端いきなり風景が影に覆われたような気がした。太陽も、庭の芝も、シルクスクリーンのようなもので覆われてしまって息さえ出来ないほど胸が苦しくなった。だけど私はそれを振り切って笑顔を作って夫に答えた。
「じゃあ、当分暇にならないよね。だってこれからもあなたの面倒見なきゃいけないじゃん!」
「はは、まあそうだよな。まだその時じゃない。だけどさいつか暇が出来た時にさ……」
「わかってるよ!」
私の口調の強さに夫は黙りこんだ。私は夫にそれ以上喋って欲しくなかった。たとえエンディングまで近づいているのだとしてもそれを認めたくなかった。出来るなら、出来れば永遠にこのインディアン・サマーが続いて欲しい。それが今の私のせめてもの願いだった。
※※
私たちのインディアン・サマーは思わぬ形で突然の終わりを告げた。全く何がきっかけでどうなるかなんて本当にわからないものだ。夫が入院して三ヶ月ぐらい経ったある日彼の会社の上長が退職届を受け取りに来た。夫が会社で親しくしていた同僚や先輩はよくきていたけどこの上長は初めてだった。私はわざわざご足労いただいてありがとうございますと深く頭を下げて上長を迎えいれて夫を引き合わせた。
上長は夫から出された退職届を受け取ると残念だと口にしてそれから仕事の引き継ぎはすでに済ましてあるから安心にしろと夫に声をかけた。それから上長と夫はしばらく会社の近況やらプライベートな事について会話していたけど夫はこう言ったら怒るだろうが以外にもコミュ力があり上長によく話を合わせていた。そうして上長は私にお見舞いの品を渡して病室を退出したが、そのすぐ後だった。突然壁から上長がバカでかい声で誰かと電話している声が聞こえてきたのだ。上長は電話相手にこう言っていた。
「おい、今病院行ってきたぞ。いや、ありゃひでぇもんだ。もう死相が出てるなんてもんじゃない。まるで別人、てかありゃもうミイラだよ。見舞いに行くんだったら早く行った方がいい。でなきゃいつ死ぬかわからないからな。だけど見てもあまり気分は良くないから注意しろよ」
上長の電話は終わったらしく、彼の去ってゆく足音だけが鳴り響いた。上長の足音が聞こえなくなった時突然夫がけたたましく笑い出した。
「ハハハ!おかしいよな!俺やお前やこの病院の連中なんかより部外者の職場以外になんの交流もないアイツが一番俺の病状を理解してるんだぜ!ミイラ状態だってよ!全くその通りだ!」
夫のけたたましい笑いと共に私たちのインディアン・サマーは一瞬にして消えてしまった。今、二人の前にあるのはただ映写機もスクリーンもなくなったただ冷たい壁だけがそこにある、そんな何もない映画館のような、当たり前で残酷な現実だけだった。
人生のエンディング
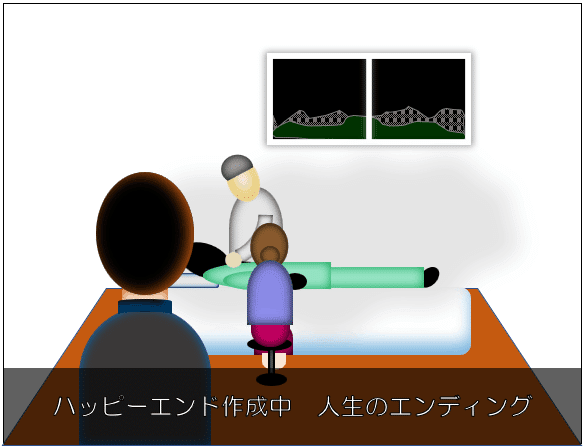
上長との一件を境に夫の病状は急速に悪化した。常時点滴をつけるようになり、歩く事さえままならない状態になってしまった。とはいえ別に上長のあの言葉だけが彼の病状を悪化させたわけではないと思う。全てはタイミングだった。私がインディアン・サマーなんて能天気なことを思っている間に夫の病状は著しく悪化していた。それがあの上長の電話で全てが呼び起こされてしまったのだ。私は急激に弱ってしまった夫を見て自分たちが新しい段階に来てしまった事を認めざるを得なかった。もう自分たち夫婦に戻り道はなく、ただただ強制的に進むしかなかった。
しかしそんな状態でも私の生活は変わらなかった。相変わらず病院は三日に一回だったし、普段通り会社に行き、普段通りご飯を食べた。それは夫が強くそう言っていたからだ。夫は私に全部これまで通りにするように言い、それから彼はお前にはお前の生活がある、とにかく今までの生活は変えられたくないんだよ。医者も言ってるようにまだ本当の危険は来ていないんだ。なのに今お前に毎日病院に来られると不安になるんだよと言った。夫がここまで自分の不安を語るのは珍しかった。私は夫の要望を聞き入れてこれまで通りにすることにした。
夫は少なくとも表面的には大きく変わってはいなかった。体力は根こそぎ奪われ、声の張りは著しく衰えても、夫はいつもの夫であった。私が来ると相変わらずの態度で迎え、これからは一生プーだなと笑いにもならない冗談を言い、私がいい加減にしろと嗜めると、へへへといつもの皮肉混じりの笑いで応じるそんな彼であった。病院の生活が退屈でしょうがないと愚痴をたれ、それから満足に動けないから却っていろんな事を考えられるなと微笑んだ。なんだか独身時代に戻ったような気がするとも言っていた。その時私が何考えてたのと聞いたら、夫はそれは秘密だといつもの皮肉混じりの笑みを浮かべながら答えていた。
私はそんな夫を見て彼がかなり無理をしているように見えた。時折こわばる笑みを浮かべて普段どおり振る舞おうとする彼が痛々しく思えた。やはり死ぬ前のお父さんの姿を意識して演技しているのだろうか。私は夫にお母さんが話していたようにあなたのお父さんは決して完璧だったわけじゃない。あなたと同じように見栄っ張りな人間なんだと伝えてあげたかった。
看護師さんもまた夫のことを心配していた。私に向かってあの人は我慢しすぎた。変に我慢して却って病状を悪化させたら元も子もない。だから不満があるなら我慢しないでこちらにハッキリ言ってと伝えて欲しいと話してきた。
だから私はその看護師の口を借りて夫にあんまり我慢しないで不満があったらハッキリ言えと言ったのだ。夫はそれを聞くと私の顔をじっと見て言った。
「じゃあホントに思った事正直に言えばいいの?例えば看護師にこのババアいきなり布団に手を突っ込むなとか、お前にもいつも薄っぺらな笑顔浮かべて部屋ん中入ってくんな見え見えなんだよこのバカ!とか言わせたいわけ?お前だってここに来る度に嫌だなぁとか、また痩せちゃってとか俺のこと思っているんだろ?そんな本音を出したって陰惨になるだけじゃん。俺はそんなバカなことはしたくない。相手を思えばこそ隠したい本音もあるんだよ。相手を絶対に傷つけたくないからさ……。それに、今そんなことしたらそれが俺の最後の姿として記憶されてしまう……」
夫はそこまで言うと突然「な〜んてな!ただの一般論だよ!」と言って笑い出し、それから「びっくりした?びっくりした?」繰り返し私を囃し立てた。そして真顔になって私に「そういうことだから看護師には不満なんかないから大丈夫とでも言っとけ。それからついでに言っとくけどお前も余計な心配するな」と言った。
私は夫が今の言葉を看護師さんじゃなくて私自身に対して言っているのだと分かりすぎるぐらいわかっていた。私は夫に向かって「じゃあ看護師さんにはそう言っとくね。私もあなたの言いたいことはわかったから」と答えた。
お母さんは不思議なくらいいつも通りだった。みるみるうちに衰えてゆく夫を目の当たりにしてもそうだった。彼女は見舞いに来る度に夫に小言を言い、その度に夫に文句を言われていた。秋の深まった日の夕暮れだった。夫の見舞いを終えてお母さんと一緒に病院の入り口を出た所で突然お母さんが話しかけてきた。
「たぶんもうすぐよねあの子。あなた覚悟出来てる?」
「全く出来てません」
「そうよね、出来るはずないわよね」
出来るはずなどなかった。確かに夫がいなくなること、そしていなくなった後の世界はなんとなく想像は出来る。だけど実際に彼はまだこの世界にいるしこうしてちゃんと生きて私と話しているんだから。彼のいなくなった後の世界などまだ無料体験さえしていないんだから。
季節はいつの間にか冬に入ろうとしていた。夫の体は時を経るごとにますます弱くなっていった。見舞いに行ってもずっと寝ていることがたびたびあった。起きている時でもぼぉ〜っとしていることが多くなり、私が何度か呼びかけてやっと気づく時さえあった。そんな夫を度に見る暗いものが頭をよぎった。
家の中で一人でいる事にはもうすっかり慣れてしまった。あの夫の無駄に慌ただしい朝食も、汚い食べ方も、風呂が沸いていないとわめく大きい声もなんだか遠い昔の出来事のように思える。だけどもうじきそれは現実のものになる。あの書斎の床に乱雑に散らかった本たちの所有者は、無駄に可愛いくまのイラストのコーヒーカップの所有者は、そして学生時代からずっと付き合って結婚してここでずっと一緒に暮らしてきた夫は、もうすぐこの世界から消え去ろうとしている。その後私はどうなるのか。人生のおおよそ三分の一を失ってそれからの時間をどうやって過ごせばいいのか。夫はお母さんに私は強い人間だよと言ったそうだ。だけどそれは誤解でしかない。あなたは私という人間を誰よりも知っているはずなのにどうしてそんな誤解をするの。私はあなたがいつも言っているようにいざとなったら何もできないポンコツじゃない。今だってこうしとあなたに対して何も出来ないまま、ただ打ちひしがれているだけなのに。
いつものように見舞いに言って夫の話し相手をしていたら彼が突然私の親族の事を聞いてきた。前にも触れたように私の家系は父母とも長寿の人ばかりだ。私がいきなりどうしたの?と聞き返すと夫は別にと言ってこの間亡くなった曾祖父のお兄さんいくつだったっけ?と聞いてきた。私が百五歳だと答えると夫はびっくりし、そして感慨深げな表情で「人生って長いな」と呟いた。
この頃夫はよく自分の事をいろいろ話すようになった。夫はあまり自分の事を話す人ではなかったのでこの変化に私は驚いた。彼は私に向かって自分という人間がやっぱり世間からズレている事、だけどそれでも自分という人間は変えられないという事をエピソードを交えて語っていたけど、そんな話をひたすら語り続ける夫を見て、私は彼が自分の人生の整理をしているように思えて悲しくなった。おい、勝手に先にいくなよ。まだそんな時じゃないよ。お医者さんだってまだ緊急を要する事態じゃないって言ってだじゃんと言ってやりたかった。だけどそれはあくまで私の現状に縋りつきたい甘えでしかなかった。夫は差し迫って時間の中で必死に自分にできる事をしていたのだから。
暦が冬を知らせてもまだ気温は暖かかった。コート無しでもまだ余裕で外を歩けた。だけどいずれ本格的に冬がきたら全てをもう身を守るものなしではいられない。コートは勿論、ストーブやエアコンも必要だ。そして……。
私はクリスマスが近づくにつれだんだん華やかになってゆく街並みを見ながら自分たちと世間の間に線が引かれていると感じた。目の前を横切っているカップルたちは一人立ちすくむ私を置いて先へと進んでゆく。そして私と夫がもう手に入れることの出来なくなった幸福を甘受するのだ。だけどそんなカップルたちも結局は、最後まで添い遂げたとしても私たちのように別れが待っているはず。だって人生にはハッピーエンドなんかないんだから。ここで私はハッとして我に返った。これじゃまるでいつかの夫みたいじゃない。他人を妬むのはよくないと自分を戒めて足早に病院へと向かった。
夫は私が来るとゆっくりと腕を上げて迎えた。もう夫はほとんど寝たきり状態だった。この頃はスマホでメールを打つのも一苦労らしく、いつも短くてすまないと謝っていた。今日もメールの事について触れ、「なんだか断片的になってすまない。手指に力が入んないんだよ」と謝ってきた。私は言いたい事は大体わかるから大丈夫だと彼には言っといたけど、それ以上踏み込む事はしなかった。これ以上慰めたり同情なんかしたら夫のプライドが傷つくからだ。夫は「お前なんかに憐れまれるようじゃ終わりだ」と笑って私に言い、それから自分の痩せ切って骨と皮が剥き出しになった手首を見て「これじゃまるで死ぬ寸前のオヤジだ」苦笑いし、それから真顔で私に尋ねた。
「そういえばお前にうちのオヤジのことちゃんと話したことなかったよな」
「うん、確かに。だけど病院でお母さんとお父さんのこと話しているのは聞いたよ」
「たしかにそうだな」夫はそう言うと、「何故か最近オヤジのことが思い浮ぶんだ。こうしておんなじ立場になったからなんだろうけど、でも嫌なもんだな。少しオヤジの事話していいか?」
「いいよ」と私は答えた。すると夫はありがとうと言って早速話しはじめた。
「オヤジと俺はずっと反りが合わなかったんだ。オヤジと合わねえわって思ったのが中学に入ったときぐらいかな。ほら、大体人間ってその頃から自我が目覚めて親に反抗して悪さするだろ?だけど俺はこの通り真面目な人間だし、親に対して特に反抗するとか悪さすることはなかった。だけどその頃からオヤジとのコミュニケーションはギクシャクするようになったんだ。オヤジは何故か妙に高圧的になっていったし、俺は俺でオヤジに対して言い返すから何故か毎日口喧嘩になってな。結局オヤジが病気で倒れるまでそんな調子だった。今あの時の事を振り返って考えると多分プライドの高いオヤジは自分が俺にナメられてると思って、自分が保護者であることと、俺がただの扶養社に過ぎないって事を態度で俺に知らしめようとしたんだな。まあ、俺がオヤジをナメていた、いやはっきり言ってバカにしていたのは事実なんだけど」
ここで夫は少しむせって水が欲しいと言ってきたので、私は吸い飲みを夫の口元に差し出した。夫は吸い飲みに口をつけて少し水を飲んでから続けて喋りだした。
「だけど、そんな親父がさ。病気を境にすっかり変わっちまった。なんで変わったのかはよくわからねえ。年をとったとはいえまだ五十前だったしな」
ここからは私の聞いたお父さんの話だった。夫は末期の病に侵されて後は死を待つだけになったお父さんの覚悟を決めた態度について心から尊敬の念を込めて語った。彼は自分に手を差し伸べて母をささえてやってくれと頼み込むお父さんを見て思わず泣きそうになったことまで話した。それから夫はお父さんが危篤だと病院から連絡を受けてお母さんと一緒に駆けつけた事を話した。
「駆けつけた時はもう完全に意識がなくなっていた。でもまだ心電図は動いていたし、一応生きてはいたんだ。おふくろはオヤジに向かって自分と俺が来ていることを言って呼びかけていた。だけど突然心電図は止まった。つまりオヤジは死んだんだ。ベッドのオヤジはいつの間にかただのミイラの置物になってたよ。おふくろはだんだん冷たくなっていく手を握りしめながらまださっきまでオヤジだったミイラに呼びかけてた。それから医者と看護師がミイラの脈とったり、ミイラの目にライト当ててそれからご臨終ですってさ。唖然とするぐらいあっさりだった。俺はエンゼルケアして貰う前のオヤジの顔今も覚えてる。はっきり言ってとても安らかな死を迎えたって言えるような顔じゃなかった。顔をこわばらせていかにも怯えきった表情してさ。生きている時あれだけ厳粛に死を受け入れていたオヤジだけど、意識のそこの底ではやっぱり死から逃げていたんだ。まあ人間だって動物なんだから当たり前だけど。俺はそんな光景を見て死ってのは今まで育んできたものをいきなりぶった切ってしまうただの現実なんだってわかったよ。オヤジは自分の手を握りしめているおふくろや、その隣で見ている俺たちの前でただのミイラになった。決して宗教なんてインチキなものが言っているようにあの世じゃなくて、ただの無機物にだ」
夫はここで一旦喋るのをやめ、そしてまたこう言った。
「そして、俺は一人取り残されて呆然としているおふくろを見て思ったんだ。ハッピーエンドなんてありはしないんだって」
久しぶりに夫の口から例のセリフを聞いて体中がゾワっとするのを感じた。夫はさらにこう続けた。
「今こんな状態になって、やっぱり俺の考えは正しかったんだって思うよ。ハッピーエンドなんてありはしない。人がそれまでの人生で何を成し遂げようが、どんなに幸せな人生を送ってようが死はそれらを断ち切って全てを無に帰してしまうんだから」
私がなんとなく思っていた夫のこの特殊な死生観がやはりお父さんの死による影響で生まれたものであることがこうして証明されたわけだ。だけど当然ながら全く嬉しくはなかった。夫はまだ喋り続けている。
「死は無なんだから当然来世を説く宗教なんてデタラメでしかない。宗教ってのはどれも死という避けることのできない現実に怯える人間の恐怖に付け込んで銭儲けしている詐欺集団だ」
もうやめてよ。そんな御託昔耳にタコが出来るほど聞かされてうんざりしていたのに、今更なんでそんなこと話し出すのよ。
「人生って飛行機みたいだよな。まるで幼虫が成虫になるように大人になって飛ぶんだ。で、飛行中にいろんな経験を積んだりしてしばらくの間人生というものを飛んでゆく。だけどいつかは地上に降りて自分の本質に帰るんだな。そうやって今自分の人生を振り返ると、結局俺は俺自身でしかなかった。虚しいけどやっぱりこれが現実なんだ」
あなたはそれが自分の本質だっていうの?いつもハッピーはありはしないとか皮肉ぶってる人間があなたなの?じゃあ結婚してからのあなたは猫だか犬だかそれともぬいぐるみでもかぶってたわけ?仕方がねえなあとか愚痴言っていろんなことに付き合ってくれたあなたはなんだったの?お前のために車買ってやる。その次は家だとか言ってはしゃいでいたのはなんだったの?私が流産した時あれだけ心配してくれたじゃない?そのほかにも沢山あるあんなことやこんなことをあなたは飛行機とやらに乗っている間スチュワーデスみたいにこなしていただけだとでもいうの。お願いだからもうそんなくだらないご高説はやめてよ。今そんな事聞かされてもつまらないよ。しかし夫は話しをやめず最後にダメ押しのように私に対してこう言った。
「お前、俺が死んだらどうするんだ?」
「そんなことわかるわけないでしょ!」
カッとなって思わず声を張り上げてしまった。自分でも驚くほどだった。だけど私には自分が抑えられなかった。
「大体今更なんなのよ!ハッピーエンドなんてありはしないとか、死は無機物へと変わるだけだとか、自分の本質だとか、何が今あなたそんな御託述べてる余裕なんかあるの?あのさ、あなたのハッピーエンドなんてありはしない。死は無だなんてのはただの一般論でしかないんだよ。確かにどんな人生を送ろうが、人は死ぬし別れなくちゃいけないよ。だけどそれでも人は自分の人生を全うしようと、相手に思いを伝えようと最期まで生きようとするんじゃない!人生のエンディングを決めるのは他人じゃなくて自分じゃない!あなたのお父さんだってそうやって最期まで自分の人生を生きぬいてその想いをお母さんにしっかり託したんだから。だけどあなたは何?今更ハッピーエンドなんてありはしないとか、死は無だとか言い出してさ。結局あなたはただ死ぬのが怖いだけでしょ?死ぬのが怖いからそんな観念的な言葉遊びに逃げてるだけなんでしょ?そんなことやめてさ、もう正直になろうよ。相手を傷つけたくないとかそんな事どうでもいいから、全部自分の思いを吐き出しなよ。私に対しても言いたいこと山ほどあるでしょ!」
とここまで言った時、誰かが私に声をかけているのに気づいてハッとして話を止めた。看護師さんがそこにいた。彼女は私に向かって何かあったのかと聞いてきた。私は慌てて申し訳有りませんでしたと謝った。すると看護師さんは他の患者さんのご迷惑にもなりますから出来るだけ声を抑えて話すように注意し、そして部屋から去っていった。
私は冷静になって自分がカッとしたあまり夫に対して自分がとんでもないバカな事を言っていた事を気づいて恐ろしくなった。なんでこんなバカな事言いだしたんだろう。偉そうに夫を頭ごなしに怒鳴ったりして!一番苦しんでいるのは夫なのに、その彼が私に苦しい胸の内を打ち明けてくれたのに、なぜその夫の言う事を全否定するような事を言ったのか。私は恐る恐る夫の顔を見た。夫は平静な顔で特に怒っているようにもショックを受けているようにも見えなかった。
「ゴメン、いきなり変なこと言って」
「俺のほうこそいきなり訳のわからない話ししてゴメン。最近自分の感情が整理できなくてな」
「それでもゴメン」
夫は突然笑い出して互いに謝っていたらキリがないからやめようぜと言い出した。私も夫に安心して釣られて笑った。
「お前にマジギレすると怖えよな。流石に俺もビビったよ。だけどお前の言っている事は正直言ってかなり胸に刺さった。たしかに自分の人生がハッピーエンドかどうかなんて決めるのは人じゃなくて俺自身でしかないわな」
「偉そうなこと言ってホントごめんね。さっき私自分でも訳わからないこと喋ってたからあんまり気にしないで」
「また謝るのかよ。お前は全然悪くねえだろうが」
そう言って夫は声を上げて笑った。そして笑いが収まるとしみじみとした表情で私を見て呟いた。
「お前ってやっぱり強えな」
※※
このことがあってから夫の口数がグッと少なくなった。とはいっても私の話にはよく反応してくれたし、彼からも話しかけてはきたし、そこはいつもと変わらなかった。ただ時折黙り込み病室に飾ってあるかれのいういわゆるコイツら、つまり私たち夫婦の思い出の品をずっと見ている事があった。そんな彼に時折私は何考えてるのって聞いた。夫の回答はいつも違っていた。単純に写真を取った日の事を思い出していたと言ったり、近々ある検査の事を考えていたと言ったり、ただ見ていただけだと言ったりしていた。だけど彼が真面目な顔でお前の言っていた人生のエンディングについて考えているといった時私は驚いて思わず聞き返した。
「なんだよ。そんなに驚くことはないだろ?お前自分で言ったんだぜ。人生のエンディングを決めるのは他人じゃなくて自分だって。自分の言ったこともう忘れたのかよ」
「い、いや、あれさ。ちょっと感情が高ぶったせいでおかしくなってたからさ」
「ったくしょうがねえなあ。俺はあの言葉を聞いてお前を尊敬すらしたんだぜ。なのにそれから何日もしないうちにこれかよ。でもまあいいや。俺はもうとっくにエンディングを考えなきゃいけない時期に来てるんだから……悪いな」
「大丈夫だよ。全然」
別の日に夫と話していた時突然私に自分以外の男と付き合ったことはあるかと聞いてきた。私は何いきなり素っ頓狂なこと聞いてくるんだと驚いて思わず声を上げた。夫は今まで私の男関係について一度も聞いた事はなかった。なのになんで今突然こんな事を聞いてくるんだろう。私が黙っていると夫は私を見ていいから答えろ、別に今さらどうこう言う気なんかねえんだからと言ってさらに回答を迫ってきた。私はこりゃ夫の顔からこりゃ絶対に引き下がらないぞと感じて正直に四人いたと答えてやった。すると夫はほぉ〜んとか言って続けてこう聞いてきた。
「じゃあお前さ、その付き合ってた男の誰かと結婚しようとか思わなかったのか?」
「あるわけないじゃん。こうしてあなたと結婚していることが全ての答えでしょ?」
「でもお前には他の男と結婚する可能性はあったんだ。そいつらの誰かとそうなる可能性はあったんだ。俺との結婚を決めたのだってそれはお前の選択肢の一つに過ぎないんだよ。それがよかったのか悪かったのか俺にはわからないけどさ」
「あのちょっとさ。さっきから何言ってるの?今更昔のことでヤキモチ妬いたとか言うのはなしだからね」
私がこう言うと夫は軽くため息をついてまた喋り出した。
「今更昔の男なんかにヤキモチ妬くかよ。ただ人生ってそういう選択によって大きく変わるんだってことを言いたかっただけだ。俺たちがこうして一緒にいるのもその選択の結果なんだよ。お前が俺という人間を選択しなかったら俺たちは今はただの他人だったはずだ。何故なら未来は……」
「不確定性のものでしょ!あなた昔いつも言ってたよね。現在も未来も不確定性のもの。過去は確かに確定性のあるものに見えるけど、しかし記憶とは容易に作り変えることのできるからこれも信用がならない。結局自分たちがいるこの世界は不確定性で曖昧なものなんだって。あのさ、いい加減にしてよ。この間みたいにまた私を怒らせたいの?」
「怒ったか?」
夫はそう言うとイタズラっぽく笑った。私はその顔がなんかムカついてきたから逆にこいつの女性関係を問いただしてやった。
「さっきから私にばっかり話させるけど自分はどうなのよ。あなたも昔の女のこと話しなさいよ。あなただって付き合っていた女はいるだろうし、さっきのご高説に従えば、あなただって私以外の誰かと結婚する選択肢があったんでしょ?さあ言いなさいよ」
「いや、俺お前と付き合うまで女と付き合ったことなかったからお前しか選択肢がなかったよ」
「えっ……?」
まさかこんな答えが返ってくるとは思わなかったので私は唖然として言葉が出なかった。あの……冗談でしょ?
「なんだ。お前疑ってるのか?俺はホントのこと言ってるんだぞ?俺は女と付き合ったのはお前が初めてなんだ」
私は込み上げてくる笑いとこそばゆさに耐えるのが精一杯だった。確かに夫と付き合いだしてからあまり女性と付き合った経験ないんだろうなって場面はたびたびあった。だけどまさか私が初めてだったなんておかしな話だ。あれだけ人に沢山ご高説を語っていた彼を私が大人にしていたとは。私はとうとう耐えきれずに吹き出してしまった。夫は不思議そうな顔で私を咎めた。
「お前、何笑ってるんだ。俺のどこがおかしいんだ?」
夫はそれからしばらく窓を見ていた。彼は窓の向こうの冬の快晴の空を見ながら時折いい天気だなとか呟いた。夫はあと何回空を見ることが出来るのだろうか。私たちはもう最終コーナーに近づきつつある事をひしひしと感じていた。ゆっくりと、だけど別れの時は確実に近づいていた。
「あのさ」と夫が突然話しかけてきた。私はなに?と聞き返した。
「なんか最近無性に自分の人生について考えるんだ。子供の頃からお前と結婚して今まで生きてきた時間をさ。俺の人生なんて夜の大半の人間と同じようにたわいないものだけど、別に考えた所で意味なんかないけど、それでもこうして考えてしまう。これって終わりに近づいているってことなんだろうな。だからこうして次から次へといろんな思い出が浮かんでくるんだ」
ここで夫は重いため息を漏らした。しばらく黙ってから彼はこう言った。
「もう人生のエンディングを決める時が来たんだろうな。そしてその後のことも……」
私は夫の口を塞ぐように彼のその痩せ切ったカサカサした腕に手を置いた。そして彼の目を見て言った。
「あの、一人で勝手に考えて先に行ったりしないでよね。私もあなたと一緒にいるんだから。私はずっとあなたを見守っているんだから。何かあったら絶対私に言ってね。絶対、絶対だよ」
最期のメッセージ
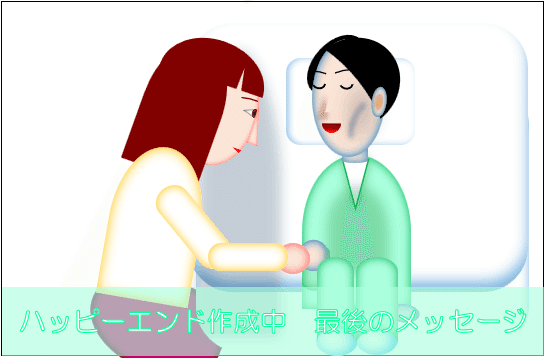
仕事が終わって帰宅しようと会社のビルから出た時突然スマホが鳴った。私はなんとなく夫からだと思ってすぐにスマホを取り出した。通知画面を見たらやっぱり夫だった。だけどこんなに早く送ってくるなんて珍しい。いつもだったら私が家に着く頃にメールを送ってくるのに。私は妙な胸騒ぎがしてスマホを開いてメールを読んだ。
「今からすぐ来れるか?お前に話したい事がある』
いつもよりもさらに短いメールだった。夫が自分から私を呼ぶのは初めてだ。昨日見舞いに行ったばかりだというのになぜだろう。あの三日ルールにうるさい夫があえてそれを破ってまで話したい事ってなんなのか。この間言っていた事と関係があるのだろうか。いや、あえてこうして私を呼び出したって事はもっとハッキリと……。急に体が冷えてきた。多分そうなんだ。アイツのことだから絶対にそうなんだ。
正直に言って病院までの足取りは重かった。病院に近づくにつれ手足が震えてきた。だけどちゃんと聞いてやらなくちゃいけない。病院に入ると真っ直ぐエレベーターへと向かった。夕方だったので人は少なかったが、そのせいで自分の靴音が異様に澄み切って聞こえた。
夫の病室のある階でエレベーターは開いた。だけど私にはドアから出る勇気がなかった。そうしてしばらくためらっていると私を押し出すようにブザーが鳴り出した。私は慌ててエレベーターから出て夫の病室に向かった。その途中でいつも夫の看護をしてくれている看護師さんとすれ違った。彼女は私を見ると笑顔で挨拶してきたけれど、その時の態度から昨日から夫に特に変化はないと見てとって少し安心した。そしてとうとう夫の病室のそばにきた。ここまできたらもう逃げられない。私は深呼吸をして病室に入った。
夫はいつものように手を上げて挨拶をして来た。私は挨拶を返すと出来るだけ平静を装って「メール読んできたんだけど話したいことってなんなの?」と彼に聞いた。すると彼は布団の下を指差して言った。
「これ、受け取れよ」
布団に乗っていたのは遺言状と書かれた封筒だった。私は見た瞬間やはりと思った。だけど自分でも不思議なくらい動揺しなかった。
「用って私にこれ渡すため?」
「ああそうだ」と夫は言い、続けて喋り出した。
「こういうのっていつ渡したらいいかわかんねえけど、まぁ渡さなきゃいけないもんなんだろうし、とにかく受け取れってくれよ。そこにはまぁ、俺が死んだ後にお前がすべき事を調べて書くだけ書いたつもりだ。まぁ、俺たちには財産らしい財産はねえからそんなに苦労することもねえんだろうけど一応な」
夫はそう言って軽く笑って見せる。私は封筒いっぱいに書かれた彼特有の異様に右上がりの癖のある字を見て、この遺書が最近書いたものじゃないと思った。
「これっていつ書いたの?」
「あの人工肛門の手術の後ぐらいかな。もうだいぶ経ってるから書いた日にちなんて覚えてねえや」
私は夫がそんな前から遺書を書いていた事に驚いた。そうだとしたら一体彼はこれをどこに隠していたんだろう。彼によく探し物を頼まれて引き出しの中は全て見ていたはずなのに。
「そんな前から書いてたんだ。全然気づかなかったよ」
「当たり前だバカ。すぐにバレるところにこんなもの置いておかねえよ。あの、読むんだったら今ここで読んでもいいぞ。何事も早め早めが肝心だからな」
「読まないよ。こんなの今読むものじゃないでしょ?大体今読んでももしかしたら書いた事自体無駄なるかもしれないじゃん」
「なんだよそのふざけた態度は。お前は俺が渾身の力込めて書いた遺書をバカにするのか。ったくまさか俺の遺書に対してそんな態度取られると思わなかったよ。俺は遺書見たお前が深刻な顔して「なにこれ?」って体を震わせるところを想像してたんだよ。もしかしたら流石のお前も泣き出すんじゃねえかと思ってな。なのにお前遺書見ても全然平気じゃねえか。なんか調子狂っちまったよ」
ホントに夫の言うとおり私は彼の出した遺書を自分でもおかしなぐらい平然と受け入れていた。これはやはり私自身が知らず知らずのうちに夫の間近に迫る死という現実を受けいれ始めたせいなのだろうか。それは自分でも理解できないことだ。ただ私が今すべきことはこうしていつものように彼の話し相手をすることだという事はハッキリとわかっていた。本当にただそれだけだった。医者でも神様でもない私が彼に対してしてあげられる事は。
「まぁとりあえず遺書は渡した」としばらくしてから夫が口を開いた。「だけどさ、ぶっちゃけるけど遺書なんていつでも出せんだよ。なんなら死んだ後だって別にいいんだから。実は今日お前を呼んだのはその遺書に書ききれなかった事を言うためなんだ」
私は夫の言葉を聞いて夫を見た。
「書ききれなかった事って?」
「いや、遺書書いたの大分前だろ?書き終わった時はさ、これで言いたい事や伝えたい事は大体書いたと思った。バカなお前が読んでわかりやすいようにわかりやすく簡潔に書いたつもりだった。だけどさ、書き終わった途端に書き忘れていた事が次から次へと浮かんでくんだよ。俺はまた書き直そうとしたんだけどさ、今度は文章が纏まらなくなっちまった。書きたいことを全部書いたらとても文章にならない。大体そんなことをお前に伝えてどうするんだって事も書こうとしていた。だけどさ、そうやって書き直ししようと考えてるうちにこの手は完全に使い物にならなくなっちまった。頭はまだまともだから考える事は出来る。だから俺今までお前に何を伝えようかずっと考えていたんだ。正直に言って俺は人に物を伝えるためだけにこれほど考えた事はなかった。いつもだったらすぐに言葉がでてくるのにさ」
夫はそこで一旦口を閉じた。どうやら疲れてきたようだ。私は夫に水は?と聞いたけど、彼は今はいらないと断ってきた。彼はもう私に話す事だけに集中していた。
「そうやって考えに考えてようやく言いたい事が纏まったのが今日なんだ。本当にいろんな事を考えた。今まで自分自身についてここまで考えた事はなかった。前にお前の言っていた人生のエンディングについても考えた。まぁ、こう言っちゃなんだけど俺自身の人生のエンディングをいくら考えても答えなんて出てこなかった。それは単純に今答えを出すときじゃないからかもしれない。多分俺の心のどっかでまだ死にたくねえって気持ちが残っているからかもしれない。もう少し経って完全に諦めがつかないと人生のエンディングなんて見えないのかもしれない。だけど実は自分のことなんてどうでもいいんだよ。自分が何を考えようがどうせ俺はほっといても死ぬだけの存在なんだから。それより大事なのはお前のことだ。正直に言うよ、俺は自分のことなんかよりずっとお前の事ばかり考えていた。お前に何を伝えたらいいかただそればっかり考えてた。今日はそれをお前に伝えたくて呼んだんだ。さっき俺、頭はまだ大丈夫だって言ったけど、ハッキリ言っちゃえば頭だって日が経つごとにバカになってるし、何よりこの口と声はこうして喋っている間もだんだん衰えて来ている。多分もう少ししたら俺は完全に息をするだけの人間になるだろう。だから今日俺の話を聞いて欲しいんだ。明日になったら俺は話そうとした事を覚えていないかもしれないから。頼むよ」
こんなに必死な表情で私に懇願する夫は初めて見た。そしてそこまでして私に伝えたい事ってなんだろうかと思った。だけど彼が何を話そうが私は一語一句ちゃんと聞いてあげなければならない。何故ならこれが本当に夫の最期の言葉になるかもしれないからだ。私は彼に向かってゆっくりと頷いた。夫は私が頷いたのを見てホッとしたのか軽く笑って喋る前に少し水を飲ませてくれと頼んできた。夫は私が口元に吸い飲みを寄せると勢いよく飲んだ。そしてもう大丈夫だと言って軽く深呼吸してから喋り始めた。
「こうやっていざ喋ろうとするとどっから話していいかわからなくなるな。でもいいや。最後なんだから思いついたままの事を全部喋らせてもらうよ。とにかく俺は今死のうとしている。これはただの事実であり現実であるからどうしようもない。受け入れようが受け入れまいが絶対に来るもんなんだから今更ジタバタしても意味がない。まぁ、正直に言えば死ぬのは怖いよ。毎日睡魔が襲ってくる度に死ぬんじゃないかって震え上がるよ。だけど死ってやつはそんな俺の気持ちを無視してやってくる現実でしかない。死んだら文字通り俺はただの骨になるだけだ。お前もよくわかってるように俺は宗教も来世も信じない。勿論幽霊なんてのも信じない。よく死んだ親とか友人が枕元かどっかに出てきたなんて話す奴がいるけどそれは欠乏感を埋める脳の作用でしかない。お前はこんな事俺から散々聞かされてうんざりするだろうけど、結局はそうなんだ。だからもしお前の枕元なんかに俺の幽霊を見たとしたらそれは脳の作用だと思ってくれ。とにかく俺は死んだら二度とお前の前には現れない。俺はお前の枕元で会いに来たよなんて言わないし、寂しいよなんて泣かないし、一緒においでなんてお前を誘わないから。そもそも俺は死んだ時点でこの世界から消滅しているんだから。まぁ、いきなり去っていくなんてお前には申し訳ないとは思っている」
「いや、申し訳ないなんて」と私は言いかけたが、夫は厳しい顔で私を制した。
「お願いだから俺が話している時には黙って聞いていてほしい。でないと俺自分の話そうと思っている事忘れちゃうから。さっきも言ったように俺の記憶力はかなりあやふやになっててちょっとした事で飛んでいっちゃうんだ。わかったか?」
「わかったよ。出来るだけ黙っているようにするから」
「悪いな」
夫はそう笑顔で言って話を続けた。
「えっ〜と、とにかく申し訳ないとは思っているってことだ。俺も出来たら最終目的地まで飛んでいきたいとは思っていた。だけど事故っちまったんだからしょうがない。俺は途中で降りる、いや降ろされる。だけどお前は最後まで乗っていてくれよな。俺と一緒に飛び降りるなんて絶対バカなことするなよな。まぁ、お前に限って絶対にそんなことはしないだろうけど。今から言う事は遺言というより、お前のこれからの人生へのちょっとしたアドバイス的なもの。いや、ただのメッセージだよ。俺が勝手にお前の将来を考えたもんだから別に聞き流してもいいし、忘れてもいい。別にこれを守れなんて強制はしないよ。大体これを守れなんて言ったって俺はすでにいないんだし。守る意味なんて何もないよ。あのな、俺これから凄い事言うからさっきも言ったように黙って聞いていて欲しい。止められたら俺二度と喋れなくなるから。いいか?」
「うん、わかった」
私が頷くと夫は安心したように微笑んだ。そして深く深呼吸をして言った。
「正直に言って俺自身は今死んでも別に構わないと思っている。何故なら人生ってのは長短じゃなくて濃淡だからな。長くて薄い人生より、短くて濃い人生の方がずっといい。それに俺はお前を失うことなく死ねる。こんなこと言うととんでもないエゴイストだと思うだろうけどそれが俺の正直な気持ちだ。だけど俺はやっぱりここに残していくお前の将来が心配なんだよ。それだけが心残りなんだよ。俺はオヤジに死なれた後お袋が一人きりでずっと暮らしてきたのを知ってる。お袋はまだいいよ、オヤジがなくなった時、もう四十後半だったんだから。だけどお前はまだ若いんだよ。それにお前の家系は両親ともに長命だって話じゃないか。お前もきっと長生きする。ということはこれからうんざりするほど長い時間がお前を待ってるんだ。だかもし、お前が将来俺以外の人間を好きになったとしたらさ、俺のことは遠慮なく忘れろ」
「えっ?」
夫の信じがたい言葉に思わず声が出てしまった。
「いや、もし好きな人間が出来たとしたらだよ。別に死んだら俺を忘れろなんて言ってるわけじゃない。だけど将来もしそういう人間が出来たとして俺の存在が足枷になるのなら忘れてしまえばいいって言ってるんだ。俺は新婚旅行でやたらはしゃぐお前を見ているのが、楽しかった。旅行に言った時先に歩いて行っちゃうお前が好きだった。そんなお前が俺のせいでどこにも行けず何も選べなくなるなんて耐えられないんだよ。結婚したって人間なんだから当然二人が一人になるわけじゃない。あくまで互いに一人の人間として相手とどうやって関係を築いていくか考えてゆくものだろ?たとえ子供がいたとしてもそれは変わらないよ。子供だって成長していずれ自分の人生を生きてゆく。これってただのエゴかもしれないけど、人生ってのはやっぱり自分のためにあるんだよ。俺の人生はあくまで俺のものだし、お前の人生はあくまでお前自身のものだ。だから俺はお前と立場が逆で、他に好きな女が出来たとしたら、俺は絶対にお前を忘れてそいつと付き合うよ。だってそれが俺の人生だからな。俺は死んだら消えるだけだし、何も残さない。勿論幽霊になって現れることなんて絶対にない。せめてお前やお袋の記憶に残るだけだ。だから俺に遠慮なんてするな。お前はこんな捻くれ者でどうしようもない俺とずっと同乗してくれたんだから。お前は俺が生きている間最高の時間をくれた。それだけで充分だ。だからこれからは今まで出来なかったいろんな事しろよ。車でドライブしたり、海外行ったり、誰かと恋したり……あっ言っとくけど別に強制はしないからな。とにかく自分の人生を最後まで生き抜けよ」
そこで夫は一旦話を止め、そして最後にこう言った。
「照れ臭くて言おうかどうか迷ったけど、やっぱり最後に言っとかなきゃな。ここまで俺の人生に同乗してくれてありがとう。俺とのフライトはもう少しで終わるけどもうしばらく付き合ってくれよ。それからしつこいようだけどあらためて言うよ。お前の人生はお前が選べよ。そして最後まで生きてハッピーエンドだって言えるような人生を送ってくれ」
こうして夫の話は終わった。私は彼の言葉を聞いて怒りと悲しさと愛しさとこそばゆさと感謝が入り混じった感情を覚えてどうしようもなくなっていた。ベッドの夫はそんな私の気持ちをそ知らぬ顔でただ自分が話し切った事に満足しきった顔で目を閉じていた。その自分に酔いきった顔を見て私はますます腹が立った。ああ!この男は相変わらず頓珍漢な事を言って!私の将来なんかどうでもいいでしょ!そんなの私が勝手に決める事じゃない!ひょっとしてあなたずっとそれ考えてた?あの時庭で私に暇が出来たら旅行しろよとか言った時も、ここでお父さんのこと話した時私に自分が死んだらどうすんだって言った時も、あなたずっと今言った事を考えてた?そういうのを余計なおせっかいというのよ!全くあなたって人は捻くれてるくせにいつも自分より人の事ばかり考えているんだから!それより自分はどうなのよ!あなたには時間がないんだから自分の事をちゃんと考えてよ!私は目を閉じてとにかく自分の感情を整理しようとした。あなたへの私の想い痛いほどわかるよ。あなた自身だって本当はこんな事言いたくないはずだよね。でもあなたは言わざるを得ないんだよね。それはきっと私が大事だからなんだよね。いいよ、わかったよ。あなたの想い受け止めてあげる。私は再び目を開けて夫を見てただこう言った。
「あなたの言いたいことよくわかった。考えとくよ」
「ありがとう」
夫はそう言うと、彼は緊張から解き放たれたのかリラックスした表情になり私に話しすぎて疲れたらもう寝たいと言った。私は「わかった。じゃあもうじきしたら私帰るね」と答えて彼の布団を首まであげてそれからしばらく眠りにつく夫を見ていた。
いまさらのこと
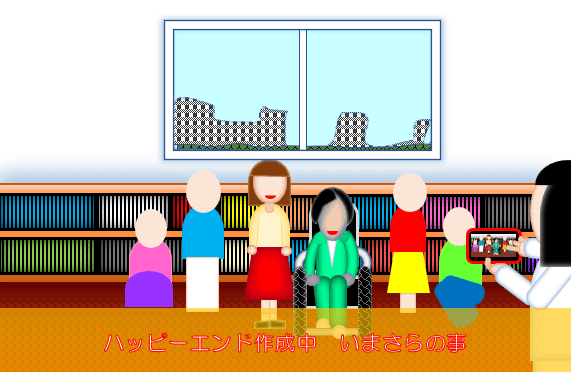
ありがたいことにこれが夫との最後の会話になるなんてことはなかった。夫はまだ充分に話す事が出来た。ある時彼は私とお母さんを目の前にして自分には葬式も墓もいらないと言い出した。自分が死んだらその辺に埋めてくれ、いやその辺に捨ててくれ。宗教なんてのは馬鹿げているし、大体葬式も墓もバカみたいに金がかかる。死なんてのは現象にすぎないんだからそんなものにご大層な葬式や立派な墓なんて作るのは非効率でバカげたものだということだ。私はこれを聞いてまた始まったかと呆れ果てたけど、お母さんはそれどころではなくて本気で息子を叱りつけた。
「なんですって?仏さまがバカげている?あなたこんな時に罰当たりなこと言うんじゃないわよ!そんな人は閻魔さまに舌抜かれるわよ!葬式もいやだ、お墓もいやだ。野晒しでいい。そんなこと言ってあなた成仏できなかったらどうするのよ!三途の川渡れなくて幽霊になってこっちにやっぱり葬式とお墓作ってくださいって泣きついてきても知りませんからね!」
「だからそれが迷信って言うんだよ。お袋だって宗教がどれほど世界に争乱をもたらしたかわかってるだろ?マルクスが言うように宗教ってのは民衆のアヘンなんだよ。宗教ってのは人の知性の発展を阻害する原始的なだな……」
「ああ!やかましい!あなた小難しいこと言って逃げるんじゃないわよ!」
「お袋こそ話から逃げるな!いいか?三途の川だの幽霊だの天国だの地獄だのそんなものは古代の為政者が民衆を縛るためにでっち上げた代物でしかないんだよ。アンタも大学までいってるんだからそれぐらいわかるだろ!」
「ああ!アンタって子は!」
夫とお母さんは性格がよく似ていると思うが、一番よく似ているのは二人とも嘘がつけないと言うところだ。おまけに夫は勘がいいから人の嘘をすぐ見破る人間だ。だからこんな風に互いの主張をぶつけ合う事になってしまう。しかもこの二人絶対に主張を譲らないのだ。
「なぁ、お前も俺の言ってることわかるだろ?大学の時散々俺話したろ?宗教なんてバカバカしいもんだって」
「わからない」
夫が私を味方にしようとして振ってきたのに気づいたから思いっきり突き放してやった。夫はびっくりした顔で目を剥いて私を見ている。このバカ。少しはお母さんの気持ちも考えなさいよ。夫は目を剥いて私を見て、お母さんは味方を得たと感じたのかホッとした顔をしていた。
「確かにさ、大学の頃はあなたの主張に納得してた部分もあったけど、こうしてさ、大人になってみれば宗教って意外に生活と切り離せないものだってわかって来たからさ。宗教によって慰められる人たちだって居るわけだし、どこかで神様が見ていることを支えに生きている人もいる。そういう人たちがいるのにあなたみたいに宗教をバッサリと切り捨てられないよ。それにあなただって毎年初詣に行ってたし、クリスマスだって祝ったし、私の亡くなった曽祖父のお兄さんに香典出してくれたじゃん。決してあなただって宗教と無関係に生きているわけじゃないのよ。だからお母さんの話をちゃんと聞きなさいよ」
夫は私の話を呆気に取られた顔で聞いていた。恐らく完全に寝耳に水の話だっただろう。まさか私がこんな話をするなんて思ってすらいなかったのだ。彼は慌てた顔で私たちに向かって「とにかく俺は葬式も墓もゴメンだ!」と言ってその場で思いっきりふて寝してしまった。そんな息子にお母さんは呆れ果てて「あなた私どころか自分の奥さんの言うことにさえ耳を貸さないの!私明日また来るからそれまでにもう一度じっくり自分の事考えておきなさい!」と言って病室から出て行ってしまった。私は慌て呼び止めようとお母さんを追っかけたら、お母さんは私は大丈夫だからあの子についていてあげてと言ってそのまま帰って行った。
お母さんを見送ってから病室に戻ると夫が起きていた。私がお母さん今帰ったからと伝えると夫はお袋大丈夫だったかと聞き、それから暗い顔でさっきは言い過ぎたなと呟いた。
「やっぱりあそこまで言うんじゃなかったな。俺は最後の最期でお袋を傷つけちまった。このまま俺が死んだらお袋にとってこれが最期の俺の姿になっちまう」
そんなに心配するならお母さんにあそこまで言わなきゃいいのに。夫は俯いて俺はバカだと自分を責めていた。だから私は彼を慰めようと声をかけた。
「大丈夫だよ。お母さんだってあなたの性格ぐらいわかってるはずじゃない?大体そんなに申し訳ないと思ってるなら葬式もお墓も全部認めたら?それがお母さんを安心させる一番の方法じゃない」
「いや、それは絶対に出来ない。それは俺の主義に反する」
全くこの男はどこまでも強情っぱりなんだから。ではと考えて少し厳しめに言ってやった。
「でもさ、あなたはそう言うけど、死んだらあなたにそんなこと言う権利なんてないんだよ。この間あなた言ったじゃん。自分は死んだらだから自分に遠慮するなって」
「それは別の話だろうが!」
「同じ話だよ。それもこれも全部同じだよ。とにかくあなたは自分が死んだ後に私たちが何をしようとも抗議する権利なんてないし、しようとしても出来ないんだよ。だってあなたはその頃にはただの骨でしかなくなるんだから」
「カッ!いつからそんな論破キャラになったんだよお前は。とにかく俺は葬式も墓もイヤなんだよ。……だけどなんだろうな。俺どうしてこんなに冷静に先のこと話せんだろ?先には死しかないのにさ」
夫の言っている事は私にも当てはまった。あれほど怖がっていた彼の死を今間近に控えて自分がこんなにも冷静でいられるのが不思議だった。夫はもうすく私たちの元から消えるそれなのにどうしてなのだろうか。もしかしたらこの間彼が私に託したメッセージが知らないうちに私に覚悟を決めさせたのかもしれない。だけど今はただこの人と最後まで旅を続けよう。一分一秒を噛み締めるように歩んで行けばまだ時間はたくさんあるんだから。私は目のチューブがすっかり増えてしまった夫を見てそんなことを考えた。
「ところで、ホントのところお前は俺の処理についてどう考えてるんだ?お袋に気を使わなくていいからお前の気持ちを正直に聞かせてくれよ」
「正直に言って未来のことなんて何にも考えてないよ。今は今のことを考えるのが精一杯だよ。だけどあえていうならさ、お葬式はしたいかな。だってそうしないとキチンとお別れ出来ないでしょ?」
「チッ、なんも考えてねえんじゃ話にならねえじゃねえか。まぁ、いいや、さっきどうせお前が言ったように、お前とお袋がどうしようが俺には何も言う権利なんてねえんだから」
「それってお葬式もお墓も全部許すってこと?」
「違う!断じて違う!俺は絶対にそんな事認めん!」
そう言うと夫は突然笑い出した。笑いながらさっきから何言ってるんだ俺はと言った。私もそんな夫がおかしくて笑った。笑った後で彼にこう言った。
「あのさ、先のことは後で後にして、今はとにかくこの時間をどう生きるか考えない?大体あなたの人生はまだ終わってないのよ」
彼は私に向かってそうだなと頷いて言った。
「まだ人生の総括もやってないからな。まだ俺にはいろいろ考えなきゃ行けないことがあるんだよ」
※※
これまで全く話してなかったけれど、夫が病で倒れてから彼の友達や、それから彼が会社で仲良くしていた同僚の人たちが度々彼の見舞いに来ていた。まだ夫が末期の癌だって聞かされていなかった時、友達たちは彼に向かって意外に元気そうじゃないかなんて言っていたものだ。だけど友達たちは夫の命が残り少ないとわかると、みんなして来るようになった。夫は一様に驚いて自分を見ている友人たちに自分の体を指差しながら「ひでえだろ。これ死にかけの体なんだぜ」とからかった。全く悪趣味だけどいかにも夫らしい言葉だ。彼の性格をよく知っている友人たちは「お前全く変わってないなぁ」と言って苦笑していた。
その光景はまるで同窓会だった。まず大学時代の私の親友でもあった子たち。彼ら彼女たちは私をすごく心配してくれた。私の知らなかった夫の小中時代の親友。その中にはわざわざ海外から夫を見舞いに来てくれた人もいる。会社で仲良くしていた同僚の人たちも来ていた。後輩らしき男性は夫が使っていた万年筆を持ってきてくれた。その万年筆は夫が無くしたと大騒ぎしていたものだった。私は夫のためにこんなにも多くの人たちが見舞いに来てくれているのが嬉しくなった。
そんなある日夫は突然見舞いに来ていた友達たちに向かって一緒に記念を撮りたいと言い出した。私はこの夫の言葉にすこし驚いた。夫は自分を写真に撮られるのがあまり好きではなかったからだ。ましてや今のような状態の自分を写真に撮らせるなんて。だけど私はこうも考えた。だからこそ彼は敢えて自分を写真に撮らせるのかもしれない。夫の心中は残念ながら私にはわからないが多分そういうことなんだろう。私は夫にここで撮るの?と聞いた。すると彼はゆっくり病室を見回して流石に狭いなと呟いた。それから少ししてから「じゃあ休憩ルームで撮ろう」と言ってきた。私は他の患者さんの迷惑にならないか不安だったけどやっぱりダメだと言う事は出来なかった。もしかしたらこれが夫と友達たちとの最後の別れになるかもしれない。それを考えたら止めるなんて出来ない。私は看護師さんの所へ行って休憩ルームで写真を撮りたいが大丈夫か聞いた。看護師さんはしばらく考えて静かに撮影をすることと、何枚も撮影をしない事を条件に撮影を許可してくれた。看護師さんはそのまま私と一緒に病室に来てくれて夫を車椅子に乗せてくれた。
夫と一緒に皆で休憩ルームまで歩いていた時誰かが妙に静かだなとつぶやいた。私は思わずヒヤッとし、周りの人も、言った当人も慌てて口を塞ぐ中、夫は脳天気な顔で「ああ……この個室エリアなんだけど今は俺の他に寝たきりの爺さんしかいないからな」とかすれた声で言った。それから続けて「他は二週間ぐらい前に一人死んで……もうひとりは自宅療養で家に帰ったみたい。……でもまあそのうち誰か入って来るんじゃないか?」と喋りだしたがそこで夫の車いすを押していた看護師さんが彼に注意した。夫はバツの悪そうな顔をしたが、私達にとってはそれどころではなかった。だけどこれが夫なのだ。彼はこんな状態になってもいつも毒舌で、時に洒落にならないことを言い出す人なのだ。
休憩ルームに着くと看護師さんがでは短めでお願いしますと言ってその場から去っていった。私たちは早速スマホのカメラを近くのテーブルに置いてそこからみんなの配置を決めた。勿論夫が中心で私がその隣。そしてみんなで私たちを囲んだ。何度もテーブルと行ったり来たりしてようやく配置が決まると私はスマホのタイマーをセットしてみんなと一緒にポーズをとってカメラのシャッターを待った。しばらくしてシャッターが鳴った。さて、ちゃんと写っているかどうか……。
私はカメラを持ってきてスマホを確認した。残念ながら写真はぶれてしまっていた。私はみんなに写真を見せてもう一度撮るか確認したけど、やっぱりみんなも同じ意見だった。夫は私に向かって「やり直し!」とかすれた声を張り上げて言った。
それでもう一度みんなで撮りなおすことにした。今度もさっきと同じようにタイマーをセットしてもう一度撮った。今度は上手くいった。ブレはなかったしみんなの表情もしっかり撮れている。なのに夫は不満そうな顔でダメだと言い出した。夫によると私も含めてみんな作りかけの表情で撮られているとのことだ。「お前らは俺との最期の記念写真をこんな中途半端な顔で撮っていいのか?ちゃんと完璧な表情で撮ろうと思わないのか?」と夫は言う。全くどうしようもなくめんどくさい男だ。しかしタイマーだしなかなかタイミングも合わせづらい。かと言ってこの中の誰かに撮影させたらその子がのけ者になっちゃうし、と思っていたところにさっきの看護師さんが現れた。
「あの~、他の患者様のご家族様もいらっしゃいますのでそろそろ空けてもらいたいのですが……」
私はこれ幸いと思い「もう少しだけ時間をお願いします」とまず看護師さんに謝ってそれから彼女に一枚でいいから私たちを撮影してくれと頼みこんだ。看護師さんはいきなりの頼みに驚いたようだったけど、私たちと入院してからずっと看護していた夫の顔を見て了解してくれた。
「私なんかでよければ撮りますよ。ただ私あまり写真は撮ったことありませんのでどうなるかわかりませんが」
「大丈夫です。私がカメラ位置とピント決めますから、合図したらシャッター押してください」
ええと看護師さんはうなずいた。私は早速みんなの位置を確認したけど、みんなさっきの位置から動いていないのですぐに位置は定まった。ピントもさっきのままで特に問題はない。私は看護師さんにスマホを渡して自分の位置に戻った。そして夫とみんなを見て大丈夫だと思って合図を出した。看護師さんは私たちに向かって「はい、チーズ」と声をかけてシャッターを押した。
さて今度こそうまく撮れているだろうか。私は看護師さんのところに行ってスマホを覗き込んだ。看護師さんは不安げに大丈夫でしょうかと聞いてくる。見たところ全く問題はない。それどころか完璧にさえ見える。立派な記念写真だ。私は看護師さんにありがとうございますと礼を言うと夫たちのところに戻ってみんなに写真を見せた。友達たちは写真を見て声を上げたが、看護師さんの厳しい視線にぶつかって口を閉じた。最後は夫だった。私は彼にスマホを近づけて写真を見せた。夫は車椅子から少し身を乗り出して写真を見つめる。さて彼から合格が出るだろうか。夫は顔を上げるとにこやかな表情で私たちに言った。
「いいねえ。俺の撮りたかったのはこういうのだよ。ほら見てみろよ、まるで最後の晩餐みたいじゃねえか」
私たちはニヤニヤ笑いながらそう言う夫にただただ唖然とした。まさかコイツこんな事言うために写真撮りたがったんじゃないだろうな。私はさっきまで考えていたことが急にバカバカしくなった。友達たちはやたら上機嫌になっている夫に向かってハハなんて笑いにもならない声を上げて笑顔で応えた。その私たちに向かって夫はさらにこう続ける。
「今俺たち十二人だろ?最後の晩餐と同じ人数なんだよ。俺がキリストでヨハネはマタイはお前らの中の誰かでユダは……」
「お前だ」と夫は笑いながら私の顔を指差した。私はどや顔でそう言う夫を無視して看護師さんに向かって今すぐ病室戻りますと伝えるとすぐに一人で勝手に盛り上がっている夫の車椅子を押してみんなと一緒に病室へ戻った。
※※
季節は冬から春へと変わろうとしていた。私は先日医者から夫がもう長くないことと、いつ何が起ころかわからないから出来るだけそばにいたほうがいいと告げられていたので、それから毎日夫の見舞いに行っていた。私が見舞いに行くと夫は瘦せ切った手をわずかに上げて迎えてくれた。私は夫のそばに座って彼の耳元にごめんね毎日来ちゃってと謝った。だけど夫は笑って私に「どうせ……医者からなんか……言われてるんだろ?そういえばお前……この間紙に署名してたよな?」と聞き取れないほどのか細い声で言った。それから続けて言った。「いや……こんな体なんだからこれから何が起こるかなんてわかっているさ」
毎日見舞いで病室で会う度に私たちは病室にある二人の思い出の品。彼の言うコイツラを見たりしていつも同じことを語っていた。本当に同じこと。話す内容はその度毎に違うけど、結局展開も落ちの同じのワンパターンの話。こうして夫とコイツラを見ながら話していると私たちはただ同じようなことで同じように争い同じようなきっかけて仲直りして続いてきたんだといまさらながらに思った。喋っているのは主に私だけど、夫も私の言うことに同意したり反論したりした。私は弱り切った体で必死に喋ろうとする夫を見ていじらしくもあり悲しくもなった。
そんな会話の中で夫がふいにこんな事を聞いてきた。
「そういえばさ……俺たちさ……結婚しようってどっちが言い出したんだっけ?」
「へっ?いきなり何を言い出すの?」
「いや……俺どういうきっかけでお前と結婚したのか……さっぱり思いだせなくてさ」
私はいまさら何を言ってるんだと思ってその時の状況を思いだそうとした。だけど私もまったく結婚に至った状況が思いだせないのだ。あれこれ思い出してもどちらかがプロポーズめいた言葉を言ったらしきシーンが全然出てこない。私の記憶ではその場面が全く飛んでおり、いきなり双方の親に互いを紹介した場面に移ってしまう。これってどういうことなんだろう。もしかして私たちはプロポーズもなしに結婚したということなのだろうか。
「私も全然思い出せない。あなたと違って結婚記念日ちゃんと覚えているのに……」
「かッ、お前もかよ。全くしょうがねえな……」
夫はそう言って目をつぶって黙り込んだ。そしてしばらくしてから再び目を開けて言った。
「よく考えてみりゃ……俺たち二人とも好きだとか愛してるとか全然言ったことねえよな。俺はもちろん……お前もさ」
「二人とも感情出すの下手だからね。おまけに照れ屋だし」
「たしかに」と夫は言って軽く笑った。そして少し間をおいてまた私に聞いた。
「ところでお前……俺のどんなところが好きになったんだ?」
この夫の問いに私はこう答えた。
「う〜んと、とりあえずざっと言うとしっかりしてそうでだらしがなくっていつもカッコつけようとしてるけどボロが出まくりで皮肉屋で嫌味ばっかり言ってるけどだけど実は人一倍思いやりがある。そんなとこかな」
夫は私の言葉を聞いて呆れたように笑った。そして私にもっと近づくように言った。
「……全然ざっとしてねえじゃねえか。……じゃあ俺もお前の好きなとこ言わせてもらうよ。……しっかりしてそうで……だけどいざって時まるでダメで……だけどそれは表面的な話で……実はとっても強いとこだ」
私は夫の言葉がくすぐったくなった。今まで彼がこんなに素直に私について語ったことはなかったをそして私も夫に向かってこれほど素直に語ったことはない。
私は夫に向かってどうして私たちってこんな大事なこと今まで話して来なかったんだろうねと聞いた。それに対する夫の答えはこうだった。
「バカだなお前は……大事なことだからこそ滅多に離さないものなんだよ」
それから私たちはしばらく窓を見ていた。今日の夜はとても冷え込むらしい。私はふと夫を見た。彼はただ無言で空を見ていた。多分彼も疲れているだろう。そろそろ帰る時間かなと思って腕時計を見た時夫が私に声をかけてきた。
「あのさ……いつ何があるかわからないから……今のうちに言っとくよ。今まで俺と一緒に生きてくれてありがとう……お前がいてくれたおかげで楽しい人生を送る事が出来たよ……俺の人生は……ハッピーエンドだ」
夫の死

それから間もなくして夫は死んだ。あの異様に暖かかった日のことは今もハッキリと覚えている。私が働いている時突然電話がかかってきた。私は体全体がゾワっとして電話をとった。その私の耳に入ってきたのは夫が危篤だということでなく、彼が命を取り留めたということでもなく、夫が亡くなったという決定的な事実の報告だった。突然危篤状態になりそのまま呆気なく死んでしまったという。たしかにすでに事前要望書に記入はしていた。だけど昨日あんなに元気だったじゃないか。聞き違いだと思った。そんなにあっさり死ぬなんてあり得ないと思った。
会社から病院へと向かっている最中、ずっとバカな聞き違いであってくれと思っていた。病院のエレベーターに乗ると急に震えが襲ってきた。エレベーターが夫のいる階まで登っている間、私はあり得ない。絶対にあり得ないと目の前の事実をひたすら否定する事でなんとか心を落ち着かせていた。エレベーターが着くと私は駆け足で夫の元に向かった。その私を病室で待っていたのは抜け殻のような夫とお母さんの泣き声だった。看護師さんが私を出迎えて沈痛な顔で亡くなるまでの経過を話してくれた。彼女の話によると夫は睡眠中に亡くなったということだ。どうやら急激な気温の変化が良からぬ方に作用してしまったらしい。お母さんがすぐさま私を夫のところに迎えいれた。私はウソだろって思いながら横たわっている彼に近づいた。だがそこにはもうごまかしも否定できない死という事実がただそこにあるだけだった。私たちが来たのを見て夫の横に立っていたお医者さんが夫の胸に聴診器を当てた。それから触診を行なってからモニターが0になっている事を確認し、最後に夫の瞳孔にライトを当てた。それが全て終わるとお医者さんは看護師に向かって耳に響くような低い声で言った。
「午後一時四十八分五十六秒、死亡」
医者からの死亡宣告を聞いた時私は夫が自分のお父さんの死について語ったことを思い出した。全く彼の言っていた事は正しかった。『死ってのは今まで育んできたものをいきなりぶった切ってしまうただの現実なんだってわかったよ』とあの時彼は言った。たしかにそうだったよ。こんなに呆気ないなんて思わなかったよ。お母さんが号泣しながら私に抱きついてきた。私は今まで肉親を亡くしたことはなかった。これが初めてだった。だけどなんでよりによって彼なの?私の最も近しい肉親である彼なの?目の前がだんだん歪んできた。視界も心も体も全部、この全てが。私はいつの間にか泣いていた。その場に崩れ落ち自分でもあり得ないぐらい大声を出してただ泣いた。
※※
葬儀の間私はずっと泣き通しだった。そのせいで喪主としての務めをほとんど果たせずお母さんに代わりにやってもらう始末だった。友達が言うにはあんまり私が大袈裟泣き喚くので会場から笑いが漏れたそうだ。告別式も同じような有様だったという。私はその間ただ泣いて日々を過ごしていたようだ。
やがて日を経るごとに少しずつ涙はおさまりやっと周りを見渡せるようになってきた。私はとりあえず玄関にバッグに詰め込んだまま置きっぱなしにしていた病室に持ち込んでいた夫の私物や二人の思い出の品を片付けようと思った。だけど片付けようとするといちいち思い出が込み上げてきて泣いてしまいとても全く片付けが出来なかった。そうして泣きながら思い出に耽っている時、私はふと以前夫から遺書を貰っていた事を思い出した。貰ってから一度も中を見ずにずっと引き出しにしまっていたものだ。今までずっと読むのを避けていたけどら逆に今は彼の痕跡に縋りたかった。彼の言葉が聞きたかった。だから引き出しから遺書を取り出して一心に読んだ。
遺書の中身は夫の癖のありすぎる字で鬱陶しいまでに相続やら自分の持ち物の処分について細々とした事が書かれていた。この字と文章は彼そのものだった。まず先に死ぬ事を私に詫び、それから自分が死んだ後私が何をすべきか詳細に書かれていた。『お前はいざって時に何もできないんだからこうしてちゃんと書いてあげないと何もできない。いいからここに書いてある通りにするんだぞ』ああホントだよ。私何もできないよ。あなたがわざわざこんな事書いてくれたってさ。私バカなんだからしょうがないよ。でも私は手紙を読んでいる間夫がそこにいるような気がして嬉しかった。夫は手紙でも自分が車を売った事を詫びていた。彼は『お前には申し訳ないと思うが、これがベストの選択だと思う。俺の車の相続税なんてお前に払わせたくないし、車を売った金で多少お前の将来に役立てばいいから』なんで謝るんだよ。あなたらしくないじゃん。それから夫は自分の書斎にある本についても書いていた。自分の本は全てちり紙交換にでも出して構わないが、中には売れそうなお宝が眠っているのでメルカリかヤフオクに出せば結構な値段になるから探してみてくれとか書いていた。私は乱雑の極みのような彼の書斎を想像してそんなことできるわけないだろって遺書に突っ込んだ。それから最後に私への感謝と再度のお詫びが書かれていて遺書はこう締められていた。
『俺は自分の人生を生きた。お前も自分の人生を生きろ』
私は手紙を持つ手を震わせて泣いた。一体一日に何回泣くんだろう。今まで泣いたことなんて大人になってから全くなかったのに。
夫の葬式を終えてから私はしばらく家に引きこもっていた。勿論夫の死亡届を出したり、相続の手続きを取るなど必要な事はした。だけど必要なこと以外で外にはとても行けるような状態ではなかったし、友達が心配して送ってくれた沢山のメールにさえ返信出来なかった。あれほど恐れていた事態に今まともに対面している。私は夫が生前言っていた死の無慈悲さについて語った数々の言葉を思い出してやっぱりそうなんだって身に沁みて思う。夫はよく死んだらそれで終わりだ。死後に天国や地獄は待ってなんかいない。死は有機物が無機物へと変わるありふれた現象に過ぎないとよく言っていた。多分彼は幽霊になって来てくれないんだろうな。散々幽霊なんかいないって言っていたんだし。もし出てきてうらめしやぁ〜なんて言ってきたら思いっきり抱きしめてあげるのに。
私は部屋中を回って夫の痕跡を探した。至る所に彼の痕跡はある。いろんなものを拾い上げては思い出に浸った。彼の愛用していたクマさんのコーヒーカップ、彼のために料理を作って乗せていたお皿、彼がいつも使っていたお箸やスプーン。私は彼の書斎にも入った。生きていた時と全く同じように散らかり過ぎた部屋。だけどもう彼はいない。痕跡は余るほどあるのに肝心の本人がいないんじゃどうしようもない。こんなんでこれからどうやって生きていけばいいんだよ。私一人じゃ何もできないよ。だけど夫にそう呼びかけても答えなんて返ってくるはずがない。彼は死んでこの世にいないんだから。もう骨になってしまったんだから。私は寝室に置いてある夫の骨壺を思い浮かべた。骨壺には葬式の時に急拵えで作った遺影しか飾っていない。仏壇とか他に葬儀屋から渡されたものは全て押し入れに入れてある。やっぱり夫の気持ちを蔑ろにして仏壇なんかに彼を入れるなんて出来なかった。たしかに夫は最後に骨の処分は好きにしろと言った。だけどあれだけ宗教めいたものを嫌がった夫をお墓に入れたら彼を裏切る事になってしまう。その代わり思い出の品とかで彼を飾ってあげようとかなとは思うけど今はそうする気にはなれない。だけどいずれどうにかしなければいけないのだろう。そうやっていろんな事を考えていると、何もかもが嫌になって耳を塞いでしまう。夫は私に自分の人生を生きろと言ったし遺書にも書いていた。だけどどうやって生きればいいんだよ。進むべき未来をいきなり奪われてどう生きろってんだよ。
そうやって引きこもっているうちに冷静になってきたのか、自分の置かれている状況を客観的に見る事が出来るようになってきた。夫はこの世界にはもういない。呼んでも答えるはずがないと言う事が感じられるようになった。私の認識の中で夫がよく使っていた持ち物は亡くなった夫の持ち物に変わろうとしていたし、あの書斎でさえ亡くなった夫の書斎になろうとしていた。いずれ私の中で夫は今年死んだ夫。前年に死んだ夫。先に死んだ夫。亡夫。そんな風に対象化される存在になっていくのだろうか。そうして挙げ句の果てには死亡したという事実と懐かしい思い出だけで語るだけの存在になっていくのだろうか。私にはそんな事は耐えられないと思った。ついこの前まで言葉を交わしその手に触れられた夫がそんなただの事実と思い出だけの存在に変わっていくのが。だけどいずれそう思う時がくるのだろう。きっとそれが死を乗り越えるって事なんだから。そんな事を考えていると夫との思い出に溢れたこの部屋が急にもぬけの空のように思えてくるようになった。こうして夫を探してもどこにもいないんだ。呼びかけても彼は答えないんだ。あの彼の皮肉も笑えない冗談も二度と聞けないんだ。もう私はひとりぼっちなんだ。これからは一人で生きていかなきゃならないんだ。彼のいないこの世界をたった一人で。
※※
告別式が終わって一週間が過ぎた頃お母さんがふいに家に訪ねてきた。お母さんは私の顔を見るなり「よかったわ。この間の時より少し顔色よくなったみたい」と声をかけてくれた。私はお母さんの言葉に何と答えていいかわからず、笑みを作ってごまかした。それからすぐにお母さんを中に入れて改めて葬儀の際に泣いて何も出来なかった事を詫びた。しかしお母さんは笑顔で「私は大丈夫よ。あなたはずっと無理をしていたから限界が来ちゃったのね」と自分も辛いはずなのに堪えて私を慰めてくれた。
私は早速お母さんを骨壷の置いてある寝室に案内したけど、やっぱり仏壇もお線香もなく、ただ遺影と骨壷だけしか置かれている場所に連れて行くのはのは気まずかった。
寝室に入ったお母さんは遺影と骨壷だけしかないのを見て戸惑ったようだ。私はなんと言い訳していいかわからなくて何も言えずにいると、お母さんは軽くため息をついてから私に話しかけてきた。
「私ね、あなただったらこういう事にするんじゃないかって思ってた」
「すみません。私なんかあの人を裏切れなくて……。彼は確かに最後には好きにしろなんて言っていたけどそれでもやっぱり出来なくて……」
「あなたが謝る事ないわ。あの子の気持ちを一番よくわかっているのはあなたなんだから」
「すみません」
お母さんはそれから夫の遺影と骨壷の前に座ってただずっと夫の遺影と骨壷を見つめていた。私はそんなお母さんの背中を見て胸が痛んだ。お母さんにはもう誰もいなくなってしまったのだ。彼女の気持ちは私なんかに理解出来るわけがない。だけどお母さんはそれでもこうして私を心配してくれている。私はただ慰められるだけの自分が情けなくなった。その時ふいにお母さんが私の方を向いた。
「あの、あの子のあのお部屋どうなってるの?」
あの部屋というのは夫の書斎のことだ。私は今も生きていた時のままにしてあると答えた。そして書斎に行きますかと聞いた。しかしお母さんはまだ行く勇気がないと断ってきた。
「聞いといてごめんなさいね。やっぱり入る勇気ないわ。入ったら昔のあの子の思い出が溢れて来ておかしくなりそうになるの。おかしいでしょ?死んでから焼かれるまで散々あの子の死に顔見ているのに、お部屋見るってだけでこんなに動揺するんだから。あのね、私家でもあの子がいた部屋入ってないの。そこには何もないってわかってるんだけど、それでも子供の頃のあの子を思い出すのが怖くて。思い出すとどうしてもあの子はもういないんだって気づかされてしまうじゃない。それが本当に怖いの。全く情けなくてごめんなさいね」
「情けなくなんかありませんよ。私だって全くお母さんと同じ気持ちなんですから」
お母さんは私の言葉に涙を見せながらそうなのねと呟いた。それからお母さんは部屋を見回した。彼女は部屋の置物や壁の時計やカレンダーを見たりしていたけど心ここにあらずのようだった。私はその様子を見てお母さんが私に何か言いたい事があるんじゃないかと思った。それはどうやら当たっていたようだ。お母さんはしばらく部屋を見回した後私の方に向き直ってこう尋ねてきた。
「あの一つ聞きたい事があるんだけど、あなたあの子のお墓はどうするの?」
単刀直入の問いだった。お母さんは私を見つめてただ回答を待っていた。私はごまかしは聞かないと思った。お墓を決めている途中だなんて嘘をついてもお母さんはすぐに見破るだろう。だから私は正直に全てを話した。
「私お恥ずかしいですが未だに何も決めてないんです。彼はお墓に埋められるのを嫌がるだろうからどこか思い出の場所にでも散骨してやろうかなって思うし、その一方でやっぱり二人分お墓を買ってそこに埋めたいなとも思うし、それでずっと迷っているんです。彼の望みを叶えてやりたいって気持ちと、彼と死んでも一緒にいたいって気持ちで毎日葛藤してるんです。だけど未だに答えは見つかってません。もうそろそろ決めなきゃいけないって事はわかっているんですけど」
「なるほど」とお母さんは呟いて笑いながら言った。
「あの子つくづくいい奥さんもったわ。あの子に言ってやりたいわよ。あなたの奥さんはあなたをどうするか真剣に考えてくれてるって。お骨をどうするかはあなたが決めればいいわ。散骨する事になっても私文句言いませんから。そしてお墓に埋めることになってもあの子に文句言わせないわ。だってあの子を一番理解しているあなたが決めたことですもの」
しかしこう言い終えた途端お母さんは急に切羽詰まった表情になって私の手を取った。
「あの、一つお願いがあるの」
私は突然のお母さんの懇願に驚き「なんですか?」と問い返した。
「あの子の骨をほんの少しだけ分けて欲しいの。私あの子を旦那と一緒に埋めたいのよ。勿論こんな事あの子は望んでないし、間違いなく嫌がるだろうと思うけど、それでもそうしなきゃって思うの。あなたのような若い人には説明したってわかってくれないと思うけど私はおばあちゃんでやっぱり昔のしきたりを守りたい人なの。今じゃなくて全然いいわ。いつだって、あなたの好きな時でいいのよ。お願いだからうんと言って!」
私にはお母さんの気持ちが痛いほどわかった。だから私はお母さんの手を取って言った。
「お母さんが私なんかに頭を下げる事ないですよ。彼の骨は元々お母さんが受け取るべきものじゃないですか。分骨はお母さんの都合のいい日でいいですよ。彼には文句なんか言わせませんから」
お母さんは私の返事を聞いてホッとしたのか大きなため息を漏らした。
「ああよかったぁ〜!実は今日あなたの所に来たのはこれを頼みたかったからなの。私断られたらどうしよっていうより、もし頼みを聞いてくれたとしてもあなたが嫌そうな顔したらどうしようってここに来るまで気が気でならなかったの。私だってあの子の母親だからこんな事あの子にしたら親のエゴでしかないし、そんなものお断りだって言う事はわかっているから、あの子の代理人のあなたがどう反応するかずっと怖かったの。でもあなたはいいって言ってくれた。ねぇ、本当にいいのよね。あの子幽霊になってあなたに何故骨を分けるのを許可したんだって恨み言言わないわよね?」
「生前常日頃幽霊なんていないって言っていたのにですか?」
「そう、死んで自分が幽霊になって初めてあの子も幽霊が本当にいるってことに気づいたのよ」
お母さんがそう冗談めかして話したので私は思わず笑ってしまった。多分彼が死んでから初めて笑ったと思う。二人であの世で幽霊になってビックリしている夫を想像してしばらく笑った後、お母さんが急に真顔になっていけないいけないと独り言を言いながら手元のバッグから封筒を出した。私は封筒を見てハッとした。それはお母さん宛の夫の遺書だった。
「もう一つ大事なことあったの忘れてた。ごめんなさいね。このあの子が私に書いた遺書なんだけど、あなたにも読んでもらいたくて持ってきたの。本当は別の日におりを見て機会を設けるべきなんだと思うけど、私大事な事はまとめて片付けたい人間だからね。結局これも持って来ちゃった。個人に宛てた遺書なんてたとえ親族でも気軽に読ませられないと思うけど、この遺書あなたについて沢山書いてあるの。だからあなたに読んでもらった方がいいかなって思って。ねぇ読んでみる?」
私が頷くとお母さんはゆっくりと封筒を差し出した。私は封筒から遺書を取り出して広げた。遺書は多分私宛の遺書と同じ時期に書いだものだろう。例の異様に癖のある字で紙いっぱいに書かれていた。内容はまず先立つにあたってのお母さんへの真摯な謝罪が述べられていた。続いて幼少時代の思い出やお父さんの事に移り、次にお父さんの死に際についての話が長々と綴られていた。それから夫は自分とお父さんを重ね合わせこの遺書を書いた時点での彼の心境が書かれ、その中で夫は彼にしては感情的な筆致で親子共々先立つことになってすまないと改めてお母さんに対する謝罪の言葉が述べられていた。そうして便箋いっぱいに書かれた文章の最後のほうに私の事が書かれていた。彼はその中でお母さんにこれからも私と仲良くしてやってくれとか、面倒を見てやってくれとかそんな事を書いていたけれど、私はそこにこう書かれていたのを見て思わず便箋を顔に近づけた。彼はそこにこう書いていた。
『アイツがこれからどういう人生の選択をしても何も言わず見守っててやってほしい。あいつはきっと自分にとってより良い道を選ぶはずだから。あいつはしっかりしてそうでいざって時にヘタレなんだけど実はとっても強いんだ』
この言葉を読んだ瞬間私の頭に病室で夫と交わした日々の事が浮かんできた。夫が自分の父親の死に際について話した後、父親の死についてや人生のエンディングについてハッピーエンドなどありはしない死んだら何もかもそこで消えてしまうなどと人生や死について恐ろしくシニカルに語り最後に私に対して自分が死んだらお前はどうするんだと聞いた事。私がその夫のあまりにシニカルな口調に苛立って思わずたとえ人生があなたの言う通りだったとしてもそれでも人は自分の人生を生き、そして思いを人に伝えていくものだって夫の苦しみも知らずに偉そうに言ってしまった事。そして夫が最後に残してくれた私への自分の人生を生きろというメッセージ。それが、それが全部頭の中にあふれて来た。
夫と交わした無数の言葉がまるでブーメランのように私に返ってきた。あの時偉そうに自分が夫に言った言葉が今深く私の中に突き刺さってくる。自分であなたに言っといてすっかり忘れていたよ。あなたが死んだショックで自分の言葉も、あなたが残された私のために考えに考えてくれた最後のメッセージも全部すっかり忘れていたよ。いや、忘れたんじゃなくて無意識に頭から追い出していたんだよ。せっかく私が一人で生きていけるようにって考えてくれたのに。。人は自分の人生を全うしようと、相手に思いを伝えようと最期まで生きようとするもの。人生のエンディングを決めるのは他人じゃなくて自分だ。あなたは誰よりも深くそう思って最期に遺してくれたのに。でも私先に進むのが怖かったんだよ。これから一人で歩いていくのが怖くてたまらかったんだよ。私は便箋を持ったまま声を上げて泣いた。
「私たちって同じなのね」
とお母さんが泣いている私に声をかけた。私は顔を上げてお母さんを見た。やっぱりお母さんも涙を浮かべていた。
「私は旦那と息子に死なれたけど、あなたも同じようにあの子とお腹の赤ちゃんに先立たれた。違いがあるとすれば私はもうおばあちゃんであなたはまだ全然若いってことよ。私あの子の言う通りこれからあなたがどういう人生を送ろうとも全力であなたを応援するわ。それがあの子が一番望むことだし、あなたは強いからきっと間違った人生を歩むことはないと信じているから」
こう話すとお母さんはため息をつきながら上を向いてこう言った。
「はぁ~だ~れもいなくなっちゃったなぁ~!」
私はそう言って泣き出したお母さんを抱きしめてしばらくの間二人で思いっきり泣いた。
※※
死んだら人は消失する。それは夫が生前何度も言っていたことだし、私も夫が死んでからいやというほど思い知らされた事実だ。夫は自分の父親が死んだときにそれを知ったのだろうし、私はほかならぬその彼の死でそれを身を持って知った。死んだその人の存在は思い出として対象化され、やがて客観的な事実へと変わる。それは正しいけど同時に間違ってもいる。たしかに人間の記憶は記録媒体のようにありのままを記録するなんてできない。主観によって、あるいはただの勘違いによって事実とかなりの錯誤が生じる場合もある。だけど記録媒体はその人間の感情や思いを決して残してはくれない。人間の感情や思いを残し伝えていくのは、たとえ人によって都合よく書き換えられた思い出でも、たんに間違ったまま記憶してしまったものだとしてもやっぱり人間なのだ。私は夫のお母さん宛の遺書を読んだあの日からずっとこんな事を考えていた。死んだら確かにその人の存在は消える。文字通りあっけなく消える。夫もそのように消えた。だけど彼の存在はちゃんと私の中に残っている。彼とのいろんな思い出や彼が最後に遺してくれた言葉。それらは全部私の中にちゃんと残っている。夫は私に向かって自分のハッピーエンドを見つけろと言いそして最後に自分の人生をハッピーエンドだと満足して死んだ。その夫の生き様や死に様を思い出し私は自分がこれからどうすればいいか必死に考えた。
そうやって考えていると突然夫が私をすごく心配している顔が思い浮かんできた。それは私が流産した時に彼が見せたあの顔だ。流産した時も私は激しく落ち込み夫のいたわりの言葉さえろくに耳に入らなかった。だけど毎日その夫の心配する顔を見ているとかえって辛くなってきたので何とか立ち直ったふりをして彼を安心させようとしたのだ。あの顔が今私の瞼に現れてじっと私を見ている。その時私は夫が自分の心の中にいると思った。それは勿論幽霊なんかじゃない。この私の心に彼はちゃんと存在し今も生きているんだ。私はあの時のように夫のために立ち直ってやろうって思った。あなたに心配なんかされたくない。勿論揶揄われたくもない。彼は今も私のそばにいる。こうして私の中に生きているんだ。私はあなたが言ってくれたように生きて見せる。最後まで満足できるような人生を送って見せる。そう心から思った。
ハッピーエンド作成中

私は十日の忌引休暇を終えて職場に戻った。私が出社したとき上司や同僚は驚いた顔で私を迎えた。みんな葬式の時私が心神喪失していたのを見ていたから予定通りに復帰するとは全く思っていなかったのだ。もしかしたら私が退職すると考えていた人もいたかもしれない。みんな一様に心配して私に大丈夫なのか?と声をかけてくれたけど、私はみんなのやさしさにこの職場で働けて本当に良かったと思った。
それと同時に友達や知り合いから貰ったメールやLINEでのお悔みや心配のメッセージへの返信もした。そしたらみんなからすぐに返事が返ってきて、私はその励ましの言葉や、激励の言葉を読んでその温かさに心から泣いた。人生はつらいことばかりじゃない。生きていけば楽しいことだってたくさんあるんだってことを身をもって感じた。
そうして一か月たちだんだん身の回りが落ち着いてきた頃、私は亡き夫に向けて手紙を書こうと思った。勿論天国の夫に向けての手紙ではない。彼に言わせると天国なんてものは存在しないんだから。そうじゃなくて今も私の心の中に生きている夫に向けての軽い途中経過の報告のようなものだ。恐らく何事も起こらなければ、あるいは私の気が変わらければ、これからもこうやって夫に対して手紙を書いてゆくだろう。とりあえずこれがその最初の報告だ。
ハッピーエンド作成中
Dear 私の中にいるあなたへ
お元気ですか?そちらではいかがお過ごしですか。こんな事を書いたらあなたは多分凄く怒るでしょう。怒って骨壺から飛び出して私を怒鳴りつけるでしょう。勿論ただの冗談です。あなたがそんな事するはずがないし、出来もしないのは私が一番よく知っています。あなたは今は寝室の中にある骨壺に収められている骨なんですから。ところでまず報告があります。あなたのお骨の一部を近々お母さんに差し上げることにしました。お母さんはどうしてもあなたをお父さんのお墓に入れたいそうです。あなたは骨は好きにしろと言っていました。ですが心の中ではやっぱり納得がいかないでしょう。だけど私はお母さんのあなたを思う気持ちが痛いほどわかるのです。だから分骨することを承諾しました。責任はすべて私が背負いますから文句ならどこかで私と会った時にでも言ってください。決してお母さんを責めないように。とこんなことを書いたら、あなたはやっぱりそれじゃ俺がまるであの世にいるみたいじゃないかってプンプンに怒るでしょう。さて肝心のあなたのお骨の事ですが、残念ながらまだ何も決まっていません。あなたの言う通りどこか思い出の場所に散骨しようか、あなたは嫌でしょうか私と一緒のお墓に先に入ってもらうか、それともこのままずっと部屋に置いておくか。いまだにずっと考えています。どのようにしたらいいか、どれががあなたにとって最善の事か、考えに考えても答えは見つかりません。いっそあなたに来てもらって一緒に考えてもらえば一番いいのですが、あなたはきっと死んだ人間は存在しないんだから人を呼び出すなと言って絶対に来ないでしょう。ですのでもうしばらくお待ち下さい。
次は私の事を書きます。恥ずかしいことに私はあなたが死んだあの日からしばらくの間完全に自分を見失っていました。人が死ぬってことがこんなにあっけないなんてあなたが死ぬまで思ってませんでしたら。自分でもありえないぐらい泣きました。多分あなたは私が泣くところなんて一度も見たことないから見たらびっくりするでしょうね。もし見ていたとしたら絶対に私には言わないでください。忘れろとは言いませんが、自分の記憶の中だけにしまっておいてください。
その日々の中で私はずっとあなたとの日々とあなたが残してくれた言葉について延々と本当に繰り返し考えていました。あなたはあの時俺は死んだら二度とお前の前には現れないなんて言っていたけど、私の中にはあなたが今もこうしてちゃんと生きているんです。勿論生きていたころのように話すことも触れることも出来ません。だけどあなたが生きていた時のいろんな思い出やあなたがくれた言葉の数々、その一つ一つを思い出すたびにあなたが今も私の中にいきていることを感じるんです。
あの時あなたは私が他の人を好きになったら遠慮なく自分の事は忘れろと言いました。私にそんなことが起こるとは今の時点では全く思いませんが、将来起こりうることはあるかもしれない。だってあなたはいつも言っていたじゃないですか。未来は不確定性のものだって。ですが、もしそんなことになったとしてもこれだけは言えます。私は将来誰かを愛することがあっても決してあなたを忘れたりはしません。その人との暮らしの中でもあなたの事を毎日思うでしょう。なぜならあなたは私と一緒に長い旅をしてくれた大事な人だからです。私はこれから長い人生を、おそらくはあなたの倍は軽く生きると思います。でもその人生の中であなたと過ごした日々の出来事を忘れずに生きていきます。あなたのようにハッピーエンドと誇れるような人生を送るために。
只今、ハッピーエンド作成中です。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
