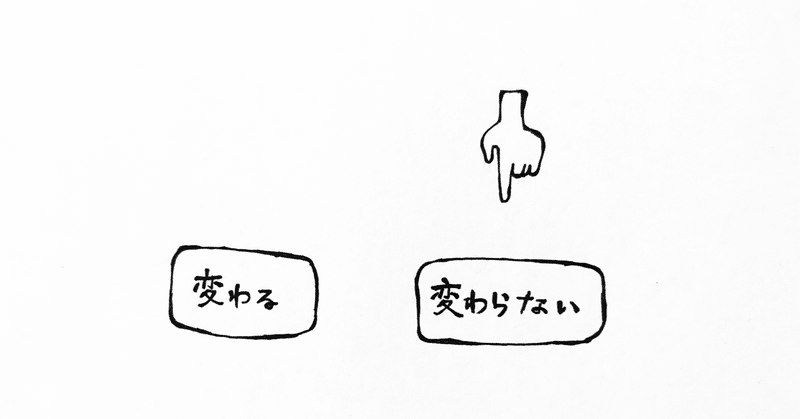
変わる、変わらない
時期に応じて、いろんな仕事をもらっているのだけど、現在は、いろんな街に行って対象の物件や街並みを撮影し、それらの魅力を伝える原稿を書いている。知らない街に行けば楽しいし、知っている街に行けば、また別の魅力を発見する。そしてついこの間は、”知っている街”――自分の通っていた大学のある街に行ってきた。
今から9年前に、わたしはとある短大を卒業した。栄養や調理などについて学んでいたのだが、結局その道に行くことはなかった。(いや、その道に行けなかった、という方が正しいか…)卒業後の1~2年は、大学の学園祭やサークル仲間たちとの飲み会に顔を出したが、今ではそのような場に足を運ぶこともなくなった。とはいえ、たまに誘いが来ると、嬉しくなる。
そんなわけで、卒業から数えると9年振りとなるその街に足を運んでみると、激しい高揚感こそなかったが、何となく落ち着く、見慣れた風景がそこにはあった。当時自分が通っていたコンビニや洋食店、入ったことはないけれど気になっていたお煎餅屋、老舗の酒屋など、変わらず営業しているお店もあれば、なくなってしまったり、別の店舗に変わってしまったお店もある。街が変わることは当たり前。その時代のニーズにあった、”求められる姿”の街に変わっていくのは当たり前だし、そういう街をまた人々が愛していくのも、自然なことである。
大学卒業後もときどき利用していた飲み屋も、なくなくなっていた。老夫婦が経営している小さな飲み屋だ。わたしが利用していたときから、店主らはおじいちゃん、おばあちゃんだったのだから、もうお店をたたんでいてもおかしくない。注文を取るのは毒舌でチャキチャキな一見怖そうなおばあちゃんだったが、お話し好きで、ときどき手相を見てくれる一面などもあった。(けれど結局「あんたは笑顔が良いから大丈夫!」と手相とはまったく関係のない診断をしてくれた)お店のあった場所は真新しい一戸建てになっていて、そこが彼らの住居なのか、まったく関係のない人が住んでいるのかは、分からなかった。
そしてもう一つ、わたしには訪れておきたいと思っていた場所があった。4年前に亡くなった友人が住んでいたアパートだ。…こう書くと、実にストーカーチックだが、そんなわたしの挙動も、非常にストーカーチックだった。最初は場所を間違えたりしたのだが、何とか例のアパートにたどり着く。外観はまったく変わっておらず、当たり前だが、人々が生活していることが伺えた。そんなアパートを、わたしはいろんな角度から眺めたあと、恐る恐る階段を上がり、友人が住んでいた部屋の前までやってきた。こんな不審な動きを咎められないだろうか…と、若干の不安と焦りを感じるわたし。しかし、一瞬でも良いから、友人がこの部屋に住んでいたという懐かしさを、胸いっぱいに感じたかったのだ。
友人が亡くなったあと、わたしは一度だけ彼の「叔父」に会った。彼は、友人が部屋を借りる際の連帯保証人になっていたらしい。そして、憔悴しきった友人の母親の隣で、叔父さんが放った言葉を今でも忘れられない。
「賃貸物件で自殺が起こると、賠償金とかいろいろあってな。僕保証人やから、結構な額、払わなあかんねん…。それとな。今回◎◎(友人の名前)の死因は自殺やから、あの部屋、事故物件って扱いになんねん。すると不動産っちゅーのは”告知義務”があって、次誰かに部屋を貸すときは”ここで人が自殺しとる”って言わなあかんのや。
んで、この”告知義務”ってのは、あの部屋に一人住んでしまえば、次の借主に告げる必要はない。…つまりな、君らのどちらか、あの部屋に住まん?そう長く住んでくれとは言わん。せいぜい1~2ヶ月でかまへんよ。その間の家賃の半分は僕持ちでええから」
この話を、わたしともう一人の友人(亡くなった友人と仲の良かった男友達)は、開いた口が塞がらないといった感じで聞いていた。すぐ「金」の話だ。悔やみの言葉さえ、ない。これはわたしの実の叔父もそうだった。うちの父が亡くなり、お骨を焼いているときに叔父が話し出したのは「相続」のことだった。
本当に胸糞が悪かったし、亡くなった友人が不憫でならなかった。わたしはきっぱり「住まない」と告げた。この叔父さんの気持ちの良いように話を進めたくなかった。
「あと、君ら、自転車いらん?◎◎が買った自転車があんねんけど…大阪に持っていくのも面倒やし」
失礼な叔父さんは、こうも続けた。彼は、今回の事件をただの”厄介なこと”としか思っていないらしい。何もかも、さっさと片付けたくて仕方がないのだろう。だんだん腹が立ってきたわたしは、強い口調で「彼の自転車を引き取る」と申し出た。”大阪に持っていくのが面倒”という言い分には頭がくるけれど、友人の遺品を引き取ること自体は嫌ではなかったからだ。叔父さんは「そうか、そうか!じゃあ外に置いとるから都合の良いときに引き取ってな~」と下卑た笑いを見せたのだった。
――そんなことも、改めて思い出した。あのジジイも、どこか同じ空の下で、生きているのだろうか…。このようにして、さまざまな思い出をたどりつつ、わたしの街取材の仕事は終わった。
なお、今回ちょっとだけ嬉しかったのは、友人の住んでいたアパートの近くに、まだアジアン系料理屋さんがあったことだ。このお店から出るスパイシーな匂いは、彼の部屋まで届く。4年前、友人が亡くなった直後に部屋を訪れた際、開け放った窓からその匂いを感じたのだ。
変わっていく街も悪くない。けれど、やはり”変わらない街”の方が、何倍もの嬉しさを感じるものだ。ときどき、あの街の空気を吸いにいきたいと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
