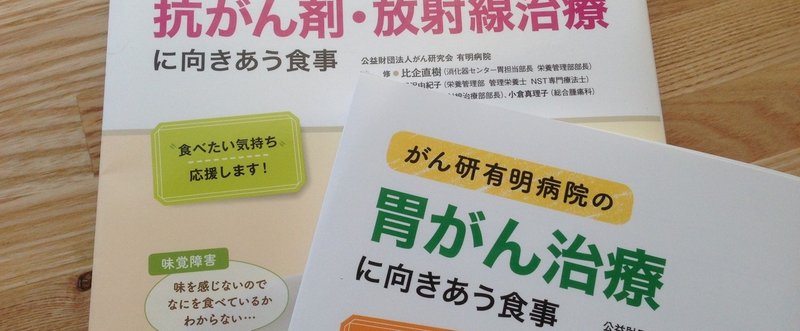2016年7月の記事一覧
2015.7.12 「なんで私が。」
整形外科に入院して2週間後、医師から説明があるとの連絡を受け、母と面談室に向かった。主治医の横には外科の医師がいた。
彼は、胃カメラの画像を見せながら、スキルス胃がんであること、手術では直せないステージであることを告げた。その鮮やかながんは、ほんの少し残った正常な部分と比較すれば、素人目にも病状が深刻であることを示していた。
母は「なんで私が。間違いでしょう?」と小さく叫んだ。医師は「そ
2015.7.12 「余命2ヶ月です。」
混乱する母に看護師がつきそい病室へ戻る。残された私に医師が「非常に厳しい状況です。」と告げた。余命は2ヶ月とみており、抗がん剤が効いたとして延命できるのは2ヶ月であること。高齢で体力がないため、とくに点滴の抗がん剤による副作用に耐えられない可能性が高いことが告げられた。
「楽に死ぬつもりが、苦しむというのではおかしい。何のために治療をするのかわかりません。残された時間を穏やかに過ごすために、
2015.7.25 「ひと口でも多く」
緊急入院から4週間。抗がん剤投与の可否を診断する診察予約を2週間後に入れ、退院した。
リビングに移したベッドで横になり、準備しておいた歩行器で食卓やトイレに行く動作を確認した。本人が思うほど体がついていかず、見ている私はひやひやしたが、本人は自由に過ごせることに心底ほっとしたようだった。
午後は複数の介護事業所、主治医の訪問があり夕方までバタバタと過ごした。母は主治医と話すのを心待ちにし
2015.7.30 「私、来ました。」
自宅で過ごしはじめて5日間。短い間にも母の様子は少しずつ変化していた。まぶたがむくんで開けづらくなったこと。手のむくみで、薬をパッケージから取り出せなくなったこと。ベッドから食卓への歩行時に転倒したこと。じわじわと症状は進行していた。
そんな生活を支える訪問介護はほぼ毎日毎食時にお願いしていた。週に19回のシフトを、3社・18名のヘルパーが支えてくれた。
その中に、同居していた叔母が生活