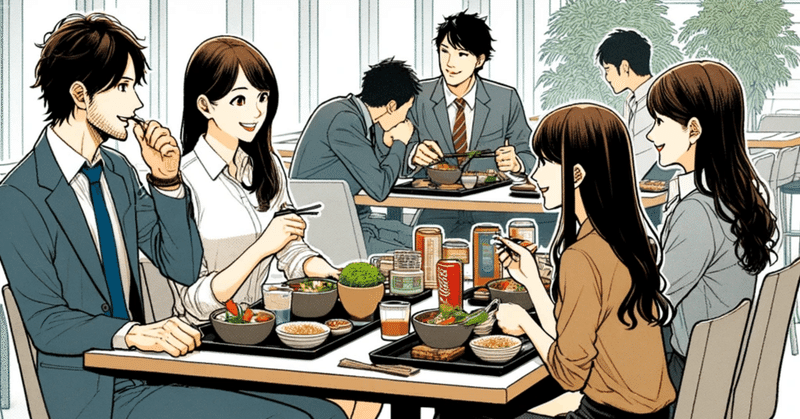
プランニングスキルとエグゼキューションスキルって何?
本ブログ記事は『ビジネススキル 完全攻略 -基本編-』からの抜粋になります。全部まとめて読みたい方は、是非、電子書籍をご購入ください。
プランニングスキル
インプット・プロセス・アウトプット
プランニングで求められる5つのスキルを構造的に整理するために、インプット、プロセス、アウトプットの3つの観点から整理してみたいと思います。
まず、インプットに紐づくスキルが「調べる」と「理解する」の2つです。次にプロセスに紐づくのが「考える」で、最後にアウトプットに紐づくのが「書く」と「作る」の2つになります。
図表にすると、以下のように整理することができます。

これら5つのスキルは、プランニングを実施していく時に重要な役割を果たします。
インプット段階では、情報を集めて、それを理解することが中心となります。
プロセス段階では、集めた情報をもとに施策や企画を立て、やるべきことを具体化します。
最終的にアウトプット段階で、考えた内容をドキュメント化し、具体的な成果物(提案資料など)を生み出します。
これらのスキルは相互に関連し合い、さまざまな業務を確実に遂行していくために求められるスキルです。
インプット:調べる
まず「調べる」というスキルでは、業務に必要な情報やデータを集めます。
これにはデスクトップリサーチ、市場調査、顧客分析などが含まれ、計画を立てる際の基本情報を提供し、市場の動向や競合各社の取り組みに関する示唆(インサイト)を見つけていきます。
インプット:理解する
次に「理解する」スキルでは、集めた情報を深く理解し、業務の目的や方向性を定めます。
問題を切り分けたり、目的を明らかにしたり、ステークホルダー(関係者)が求めていることを把握し、検討の方向性や目標をします。
プロセス:考える
「考える」というステップでは、戦略的思考、クリエイティブ思考、意思決定、問題解決といった能力が求められます。
ここでの役割は、インプットされた情報をもとに具体的な計画や戦略を立案し、正しい意思決定ができるようサポートしていくことです。
アウトプット:書く
次のステップ「書く」では、考えた内容をドキュメント化することで、情報を伝え、プロジェクトの進捗をマネジメントしていくことです。
これには文章をきちんと構造化して整理するドキュメンテーション能力が求められます。文書にすることで、考えや計画が関係者に分かりやすく伝えられ、プロジェクトの進捗を効果的に追うことができるようになります。
アウトプット:作る
最後に「作る」ステップでは、提案書やドキュメント類の企画作成において、提案内容の全体設計(骨子レベルで提案書を作成すること)、情報の構造化、理解を助けるビジュアル表現、説得力のある書き方、校正・編集(資料レビュー)といった能力が求められます。
これらのステップで、アイデアや計画を実際のスライドに落とし込み、仕事で実際に使える提案書や企画書を作っていきます。
プランニングスキルはなかなか手強い!
基本スキルの習得において、コミュニケーションスキルやエグゼキューションスキルに対して、プランニング系スキルの習得に一番時間がかかるということを前段で述べました。
それぞれのスキルで求められる能力を見て、「なかなか手強いなあ・・・」と思った人は多いかと思います。
たしかに習得までに時間はかかりますが、一度、マスターしまえば、より付加価値の高い仕事をすることができるので、頑張ってマスターしていきましょう。
エグゼキューションスキル
エグゼキューションスキルで求められる能力は、業務を確実に遂行できる能力のことです。
マネジメントの対象範囲(関わる人数)を横軸に、業務レイヤーを縦軸に整理してマトリックス化すると、以下のような図表に整理することができます。

マネジメントの対象範囲は、「セルフ(1名)」「チーム(3~5名)」「プロジェクト(10~20名)」「部門(50~100名)」の4つに分けています。
また、業務レイヤーは、「戦略立案」「施策立案」「実行計画」「時間(タスク)管理」の4つに分けています。
一般的に、エグゼキューションで求められる能力は、実行計画と時間(タスク)管理の業務レイヤーになりますが、マネジメントの対象範囲が広がることで、戦略立案や施策立案部分の業務レイヤーも関係してくることが理解できるかと思います。
セルフマネジメント
最も基本的なレベルである「セルフマネジメント」では、個人が自分自身の時間やタスクを効率的に管理する能力が求められます。
これには、自分の時間を計画し、優先順位を決める「時間管理能力」、自分の仕事や役割・責任を整理して進めていく「タスク管理能力」、そして自主的に仕事を進める自己規律が含まれます。
また、個人的なキャリアや業務目標を設定し、それを達成するための計画を立てる「目標設定能力」も重要です。
チームマネジメント
「チームマネジメント」では、自分以外にチームメンバーの時間管理やタスク管理を行う能力が求められてきます。
個々のチームメンバーの時間やタスクを効果的に管理するために、リーダーシップとコミュニケーションが鍵となります。
「リーダーシップ能力」は、チームメンバーを導き、モチベーションを高めるために必要になります。
「コミュニケーション能力」は、チームの中でうまく情報を伝え合い、お互いを理解するのにとても大切です。
また、適切なタスクをチームメンバーに割り当てる力や、チーム内の衝突や問題を効果的に解決する力も、このレベルのマネジメントには求められてきます。
プロジェクトマネジメント
「プロジェクトマネジメント」では、社外の人を含むプロジェクト全体の施策立案から実行計画、時間やタスク管理までを行います。
ここでは、プロジェクトの目標に合わせて戦略的に計画を立てる「施策立案能力」、必要なリソース(ヒト、モノ、カネ、時間など)を効率的に管理する「リソースマネジメント能力」が求められます。
また、プロジェクトに関連するリスクを見つけて対応策を考える「リスクマネジメント」と、関係者との関係を作り維持する「ステークホルダーマネジメント」も重要になります。
プロジェクトマネジメントでは、施策立案能力まで求められてくるため、エグゼキューション系スキルだけでなく、プランニング系スキルも求められてきます。
部門マネジメント
最も高度なレベルである「部門マネジメント」では、部門全体の戦略立案から間接的に担当者の時間管理やタスク管理までを行います。
これには、部門の長期的な目標と方向性を決める「戦略立案能力」や、部門全体の利益に基づく「意思決定能力」が必要です。
さらに、部門のパフォーマンス(実績)をチェックし、必要に応じて改善策を実施する「パフォーマンスマネジメント」と、変化に対応し部門内での変革を効果的に導く「チェンジマネジメント」が求められます。
部門マネジメントまでいくと、「What」や「How」だけでなく、なぜその事業を推進する必要があるのかという「Why(戦略立案能力)」まで、求められてきます。
これらマネジメントレベルごとに求められる能力は、それぞれのレベルで成功するためになくてはならないものです。
セルフマネジメントでは個人に限定したうえで、仕事の生産性や効率性が求められます。チームマネジメント、プロジェクトマネジメント、部門マネジメントではそれぞれ対象範囲が拡がっていくなかで人材やリソースの管理、戦略的な意思決定が重要になっていきます。
それぞれのレベルで成功を収めるためには、これらの能力を磨き、適切に適用することが求められます。
マネジメントの対象範囲で、求められるエグゼキューション能力に大きな違いがあるということが理解できたかと思います。
まず、早い段階でマスターしてもらいたいのは、自分自身をきちんとマネジメントする「セルフマネジメント」能力です。基本は、時間とタスクを正しく管理できる能力を身に着けることです。
また、入社2~3年以内に、自分自身で実行計画を作成し、チームメンバーの時間やタスク管理まで行う「チームマネジメント」能力まで身についてくると、自分一人では対応できないような大きな仕事もチームで対応できるようになります。
「段取る」のところで具体的に解説したいと思いますが、「プロジェクトマネジメント」に関しては、PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)と呼ばれるグローバルレベルの資格を取得すると、日本に限らず、グローバルレベルで通用するプロジェクトマネジメント能力を手に入れることができます。
次は、生成AIが基本スキル習得にどのような影響があるのか考察してみたいと思います!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
