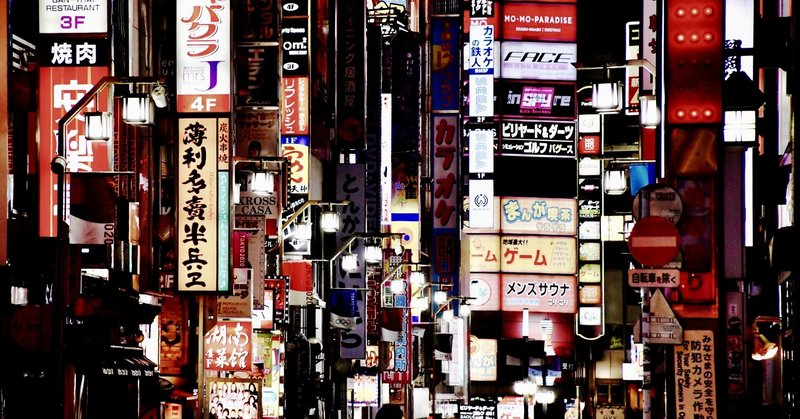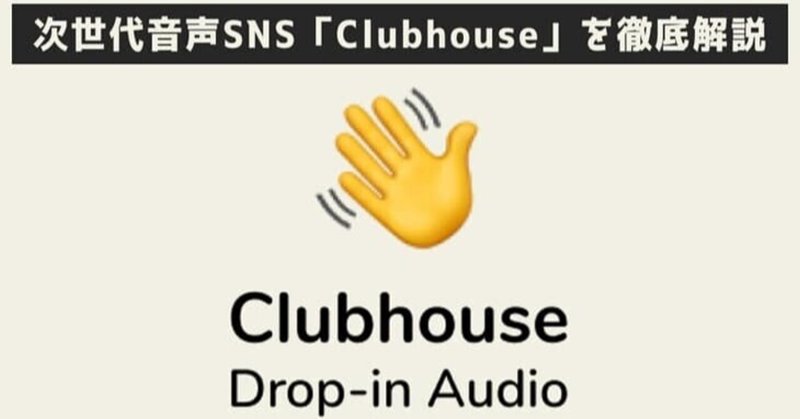- 運営しているクリエイター
#キャリア
#36 小さいお店こそ重要な「接近戦」
多くの飲食店が
顧客満足の追求、顧客第一主義の
理念を掲げている。
そのこと自体はとても大切だし、正しいと思うが、
その理念のために、日々何を実現しているかを
思い返すと、心許ない店舗は意外と多いのではないか。
お客様に満足頂くためには
まずお客様を知り、顕在しているニーズのみならず
潜在ニーズまでを把握する必要がある。
潜在ニーズを把握して
「行ってみたい!」「食べてみたい!」と
お客様自
#33 お客様は囲い込めない
「顧客を囲い込む」という言葉をよく聞くが
あまり好きな表現ではない。
虫取り網でチョウチョを捕まえるように
顧客を捕えて逃さないなんてことが、できるはずがない。
自分が顧客になってみれば、当たり前のことだ。
店舗は花を咲かせ、甘い蜜を出し続けること。
そこには「柵」で囲むのではなく、
「旗」を立てることを考えるべきだ。
そうすればチョウチョさんたるお客sまが、
お客様のタイミングで、ときどき
#32 店舗の三位一体の満足とは?
店舗における満足度の指標は3つある。
顧客満足・社員満足・店舗満足である。
これは三位一体でなければならない。
そもそも
顧客満足を得る活動を行ってくれるのはスタッフである。
そのスタッフが不満だらけだと顧客満足が得られるはずがない。
しかし
スタッフと馴れ合いになっても競争に勝てず
顧客満足は得られず、店舗はもたない。
スタッフ満足を得るために給料や休暇ばかり増やしていては、
店舗はもたない
#22 Clubhouse3日間使ってみて分かりやすかった記事一覧とどう使っていくか考察
いまトレンドのど真ん中の「Clubhouse」。まだアプリは英語表記で、やり方もあまり出回ってないので、分かりやすかった記事まとめて、どう使っていくのが良いか、飲食経営者の目線で考察します。
どんなアプリ?これを読めば、成り立ちやコンセプト・SNSとしてのポジショニングなどがわかります。それをもとにやってみるかどうか決めても良いかもしれません。ただ具体的な操作方法等は載ってないので、それはコチラ
#14 「飲食は好きだけど、仕事にするのはちょっと。。」
そう思う人、結構多いんじゃないかな?
自分自身もそうだったけど、大学生の時に飲食の仕事が好きで週5回くらいバイトしてた。お客様と接するのも楽しいし、一つの目標に向かって店舗一丸となって営業していく感じが、ある意味部活みたいで好きだった。
でもそのままそこに就職はしなかった。
何故か?
その当時は「水商売だし」とか「社会的な体裁が」とか「労働環境が」とか「親の反対が」とかいろいろ理由をつけていた