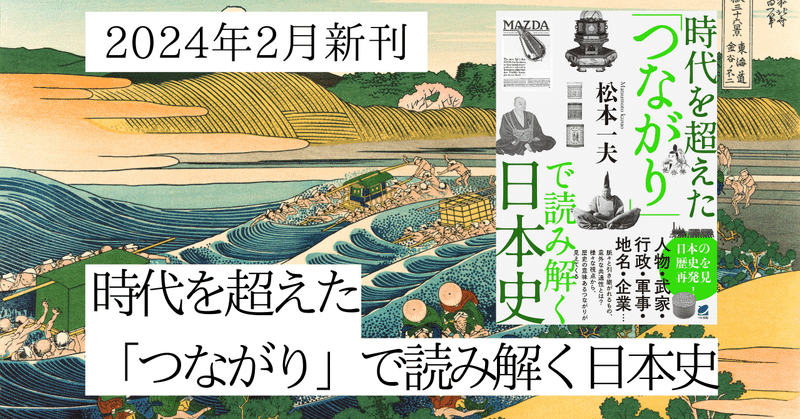
原敬は坂本龍馬の孫弟子だった!?
学校での歴史学習は、時代順ではありながらも、ともすると突然ある人物が登場したり、何かのできごとが起こったようにとりあげられ、しかもそうしたことが繰り返されるため、試験のために仕方なく覚えはしても、終わったらたちまち忘れる、という状態になってしまいがちです。これでは「歴史は暗記ばかりで、面白くない」という印象をもたれても致し方ありません。
しかし一見何の関係もないような人物やできごとが、実はある視点から見ると、とても意味のあるつながりをもっていたことに気づくと、「歴史っておもしろい、奥が深い」と興味をもち、さらには個々の人物やできごと自体も、より鮮やかに、かつ深く認識できるのではないでしょうか。
『時代を超えた「つながり」で読み解く日本史』(松本一夫・著)では、単なる時代の流れということではなく、むしろ時代というものにあまりと
らわれずにさまざまな視点を提供し、それによって導き出される人物やできごとのつながりの事例を紹介しています。

「原敬は坂本龍馬の孫弟子」といったら驚かれるでしょうか。しかし、この二人の間に陸奥宗光という人物を配すれば、この表現はまんざら誤りともいいきれなくなります。いったいどういうことなのでしょうか。
坂本龍馬と陸奥宗光のつながり
出会い
二人の出会いについては諸説あり、定かなことはわかっていません。坂崎斌(紫瀾、明治時代の政治記者)は、文久三年(一八六三)に龍馬が、当時京都の粟田口にいた伊達宗広(陸奥の父。和歌山藩重臣だったが失脚。学者としても知られていた)のもとをたびたび訪ねていたのがきっかけとしています。また陸奥本人はその自伝の中で、龍馬が陸奥の才を認めて神戸にある勝海舟の塾に入ることを勧めた、と回想しています。さらにその勝は、文久三年四月に海防視察のため紀州を訪れた際、藩主からの依頼で自らの塾に連れて帰った二十五名の「腕白者」の中に陸奥がいた(当時二十五歳)、としています。
これらの話を総合すると、陸奥は文久三年に勝海舟の塾に入り、そこで龍馬と接するようになったと推測されます。

海援隊における陸奥
その後、龍馬と陸奥のつながりはほとんどたどれなくなりますが、慶応二年(一八六六)十月の時点では、二人を含む土佐グループの人々が薩摩藩から毎月三両二分(米価換算で現在の約三十二万円)を支給されていたことがわかっています。
この前年、龍馬は長崎亀山を拠点として、西国諸藩のため運輸・貿易などを周旋する亀山社中を組織(後に海援隊と称す)、陸奥はそのメンバーとなっていました。慶応三年三月ごろ、陸奥は上方で金策や商売のために動き、薩摩藩の重役と交渉しています。七月には「商法之愚案」と題する意見書を作成し、翌月龍馬に提出しました。ここでは西洋のコンパートメント(同盟商法)の原理を説き、長崎に一大商社を設け、大坂、兵庫、下関、北陸要地にも支所をつくって商事取引を行うべき、との主張がなされています。そして陸奥は、実際に土佐藩のライフル銃購入や丹後田辺藩物産の長崎での販売や仕入れなどに関して周旋を行いました。

龍馬の陸奥への厚い信頼
龍馬はこうした陸奥の意見書や実際の働きぶりを高く評価し、厚く信頼していたようです。慶応三年十月二十二日付けの龍馬の陸奥宛て書状には、海援隊士がよく利用していた京都の旅館沢屋の主人加七が相談してきた件(仙台の商品をすべて海援隊が扱い、それに関して隊が一万両、現在の約一億円の出資を求められる)について、次のように記されています。
商売契約のことは陸奥君に任せているので、陸奥君さえ「ウン」といえば(原文も「陸奥さへウンといへバ」とある)、資金のことはともかくも貸すべきでしょう。しかし一万両などという大金はすぐには出せるものではありません。よくよく心づもりをわかってもらうよう、陸奥君に話してほしいと(加七に)申し聞かせているところです。 (意訳、一部)
これにより、商売に関して龍馬が陸奥に全幅の信頼を寄せていたことがよくわかります。また同年十一月七日(暗殺の八日前)付けの陸奥宛ての書状では、ある人物を海援隊に入れる件について注意を促した後、追伸の中で「(あなたと)世界の話でもできるでしょうか(原文は「世界の咄は なしも相成申すべきか」)」と述べています。前月に大政奉還が実現しましたが、よく知られているように龍馬はやがてできるであろう新政府のメンバーには加わらず、海援隊の規模を拡大して世界に羽ばたくことを望んでいました。その世界の話をしたいといっているのですから、龍馬が陸奥を心底から信頼していたということが、ここからもうかがい知れます。
陸奥宗光と原敬のつながり
出会い
原は東北・北海道を周遊中の明治十四年(一八八一)九月、宮城監獄に立ち寄った際に、当時同所に収監されていた陸奥を初めて見ました。またフランス公使館の書記官時代にも、当時欧米遊学中だった陸奥に会っていますが、お互い特に印象には残らなかったようです。
両者の間に深い信頼関係が築かれる端緒となった本当の意味での出会いは、同二十三年(一八九○)五月十七日のことでした。この日、第一次山県内閣の農商務大臣に就任した陸奥は、前任大臣の秘書官をつとめていた原を呼び出しました。そして十九日、原に対し「別に考えがあるか、自分(陸奥)に信用を置かないということなら仕方ないが、このまま秘書官を続けてほしい」と頼み、原はこれを承諾したのです。
この時点で陸奥は、原のことをよく知らなかったはずですが、なぜ秘書官に留任させようとしたのでしょうか。この点について近代史家の伊藤之雄氏は、初めて農商務大臣となった陸奥が、誰か信用のおける者を側近とする必要があったこと、原が伊藤博文や井上馨からの信用が厚いと聞いていたこと、ともに西園寺公望と親交があったこと、同じ藩閥外の出身で親近感がもてたであろうこと、などをあげています。

厚い信頼関係
まもなく陸奥は原の能力を見抜いたらしく、秘書官ながら官吏選考委員(陸奥は省内からの藩閥勢力一掃をめざしていた)に任じるなど、次々と仕事を任せていきました。
その一方で陸奥は、かつて欧米遊学中にイギリス政治を研究したり、駐米公使時代に共和・民主の二大政党が対立するアメリカの政党政治の様子を目の当たりにして、自分も将来、自由党かその後身の政党を背景とした内閣の首相となり、政権を担当することを夢見ていました。この点原も、新聞記者時代からイギリス風の政党政治を将来の日本がめざすべき理想の姿としていたので、陸奥に強く共鳴するところがあったと推測されています。
明治二十四年(一八九一)五月、原は陸奥の指示でいわゆる大津事件の状況視察のために京都へ赴きました。農商務省の仕事とは直接関係はありませんが、陸奥が閣内で発言する上での情報収集が目的とされています。
陸奥は、翌年の第二回総選挙の際に、民党圧迫のため選挙干渉を行った品川弥二郎内相の辞任を求め、これが実現すると自らも農商務相を辞めます。すると原も、これにならって同省を辞めてしまいました。このころには原は陸奥に深く信服し、「この人のもとで仕事がしたい」との思いを強くしていたようです。
同年八月、第二次伊藤内閣で外務大臣となった陸奥は、すぐさま原を外務省に招き、通商局長に任命しました(取調局長も兼任)。陸奥の外相としての大きな懸案事項の一つは、いうまでもなく条約改正問題であり、その際、それ以前に原が作成していた「現行条約意見」は、実際に交渉を進めていく上でのよりどころとなりました。
しかし陸奥は、原を条約改正の仕事に関わらせることはなく、主に二つのことを担当させました。まず一つめは朝鮮国との外交です。明治二十二年(一八八九)に起こった、いわゆる防穀令事件の解決のため、陸奥は原を朝鮮に派遣し、一定の成果をあげています(ただしその後、交渉は難航)。そして二つめは政党対応でした。陸奥は議会と内閣の関係調整を重視しており、第四議会における民党(藩閥政府に反対する政党)と伊藤内閣の対立を緩和させるため、原に議会における陸奥派幹部の岡崎邦輔と連携して工作するよう指示しました。
日清戦争後の明治二十八年五月、原は外務次官となります。一方このころ陸奥は持病の肺結核を悪化させ、大磯の別荘で静養することになりました。六月三十日、原は大磯へ行って陸奥と対面し、今後は一切外務省の事務は見ずに治療に専念すべきと勧告、陸奥もこれを受け入れます。八月二十三日、陸奥は病気を理由に外相の辞表を提出しました。これは確かに病気は重かったのですが、内実は第二次伊藤内閣の存立が危うくなったことを察して、原と協議して決定したことでした。しかし、この辞表は受理されず、明治天皇から静養が命じられました(外相臨時代理は西園寺文部大臣が兼任、原が実務を執る)。
陸奥の死と原との最後の会話
しかし結局、陸奥の体調は回復しませんでした。八月にはいよいよ重篤な状態となり、当時外務省を辞め、大阪毎日新聞の社長となる準備を進めていた原は、同月十二日からたびたび陸奥(当時は大磯から東京西ヶ原の自邸に移っていた)を訪ねています。十二日と十四日は陸奥が疲れていたり、薬を飲んで寝ていたため面会できませんでしたが、十六日に最後の言葉を交わすこととなりました。原は日記にこの時の様子を克明に記しています。
ふだんなら食事中なおさら面白い話をしていたが、私は心の中でこれが最後の会話になると思い、平然としていられず、伯(陸奥)もまた非常に疲れ、苦痛の中、勉めて私と話をしようとしている様子で見ていられなかった。しかし私は数年来、公私両面にわたってほぼすべてのことを伯と相談してやってきたので、この期に及んであらためて話を聞かなくてもよくわかっていた。それゆえ無益な長話をして伯をさらに疲れさせ、またお互いに深く悲しむのも耐えられないので、来月初めの大阪行き以前に、また何度も参上しますと述べて別れを告げ、部屋を出た。そしてまさに階段を降りようとした時、伯が再び私を呼んでいるというので、部屋に戻った。伯は「大阪に行って実施すべき方略については、なお聞きに来なさい」と言われた。私は「いずれ大阪に行ってみないとわかりませんが、それについてはよく考え、なおご意見を伺いに参ります。来月初めまでには間もあるので、たびたび参ります」と答えた。伯はなお私と話したいらしく、別れることを非常に嫌がる気持ちが表情にあふれていた。私も同じだったが、心で泣いていたたまれなくなり、またご家族もこれ以上の長話は望んでいないと思って、忍んで別れを告げたのである。(意訳)
三人を結ぶものとは
以上見てきたように、龍馬と陸奥、陸奥と原の間には、年月の長短はありますが、それぞれ厚い信頼関係がありました。私が知る限りでは、原が龍馬についてふれた文章はありませんが、この三人に共通する部分があるとすれば、どのようなことがあげられるでしょうか。まず何といっても、自らが抱いた大志が正しいと信じて、たとえその中途で倒れたとしても前向きに突き進んだ、という点でしょう。特に龍馬の人生は、このことをまさに具現化したものでしたが、この点に関し陸奥も獄中にあった時に書いた文章の中で、次のような龍馬の言葉を紹介し、「至極の名言」と評しています。
人はいやしくも一つの志を抱いたら、弱気にならず、常にこれを実現させるための方策を進めなければならない。たとえまだその目的を達成していなくても、その途中で死すべきである。ゆえに死生はまったく二の次のことである。(意訳)
そして考えてみればその陸奥も、一般的には条約改正や日清戦争時に活躍した外相として知られていますが、既に紹介したように最終的な目標は、政党の総裁として内閣を組織し、自ら首相となって日本を主導することでした。したがって、病のためその中途で倒れた、と見ることができるでしょう。この点原は、その陸奥の夢を引き継いで実現させたわけですが、首相在任中に暗殺されたのですから、やはり道半ばといえるかもしれません。
これに関連して、目標達成のためにとった方策も、かなり共通点があるように思われます。龍馬は土佐藩出身ですが脱藩していますし、陸奥や原に至っては政府の本流となる藩閥出身者ではありません。つまり三人とも背後に何の勢力基盤ももたなかったにもかかわらず、大局を見据えながら、自らの才を駆使して諸勢力を動かしていこうとしました。それが最もうまかったのは、龍馬かもしれません。そして、これを見て学んだであろう陸奥も、藩閥政府の外からではなく、中から働きかけて次第に自らの地位を高めていきました。
しかし、その舌鋒があまりに鋭かったため、多くの敵をつくってしまった面がありました。この点、原は陸奥とは異なり、例えば政治的には対立する面も多かった山県有朋ともうまく接し、ついには首相となることを認めさせてしまうなど、優れた交渉力をもっていたようです。
さらに龍馬は政官界には思い入れがありませんでしたが、海外にその目を向けていた点については、陸奥も原も外交官を(陸奥はさらに外相も)経験していますし、特に原は開明的な対外協調路線をとろうとしていた点も、間接的ながら何らかの影響を受けていたのかもしれません。
(以上、『時代を超えた「つながり」で読み解く日本史』より一部を抜粋・改変して構成しました)
【著者紹介】
松本一夫
1959 年生まれ。1982 年慶應義塾大学文学部を卒業後、栃木県の高校教員となり、20年間日本史、世界史等を担当する。専門は日本中世史。2001年博士(史学)。國學院大學栃木短期大学、宇都宮大学等で非常勤講師を務めた。その後、栃木県立文書館等を経て2020年3月、栃木県立上三川高等学校長で定年退職。南北朝期の歴史研究をする一方で、日本史教育の実践的研究にも取り組む。おもな著書は『疑問に迫る日本の歴史』『史料で解き明かす日本史』(いずれもベレ出版)、『日本史へのいざない』『日本史へのいざない2』(いずれも岩田書院)、『中世武士の勤務評定』(戎光祥出版)がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
