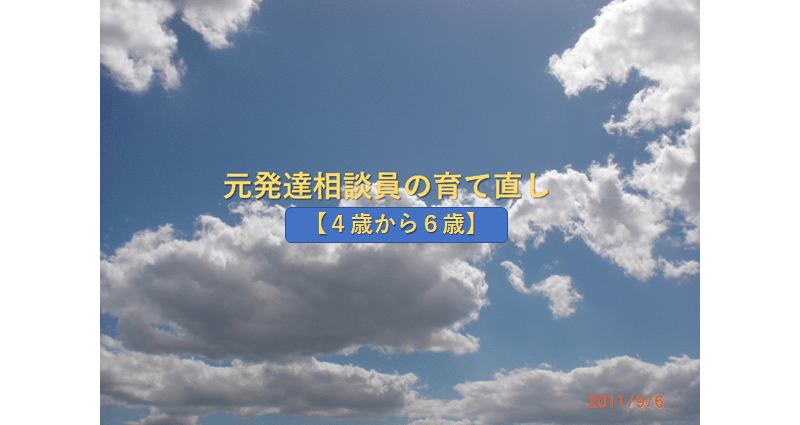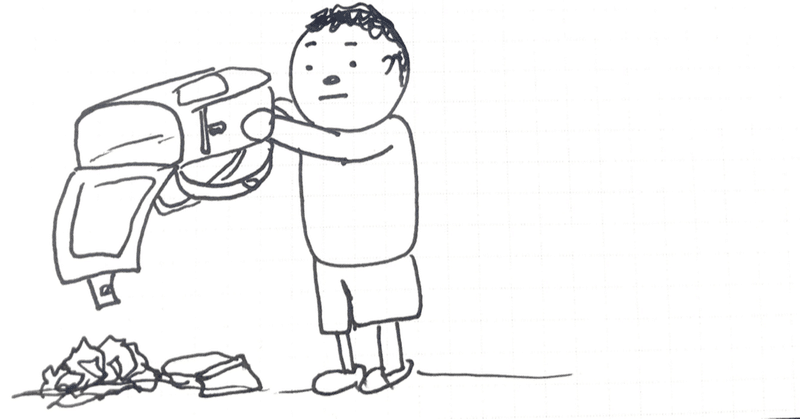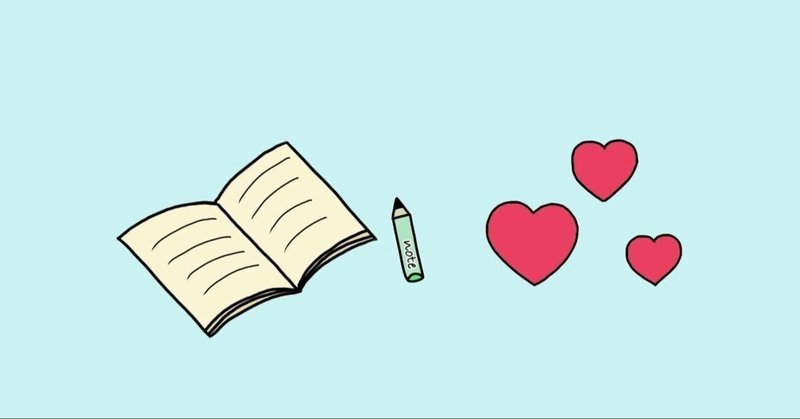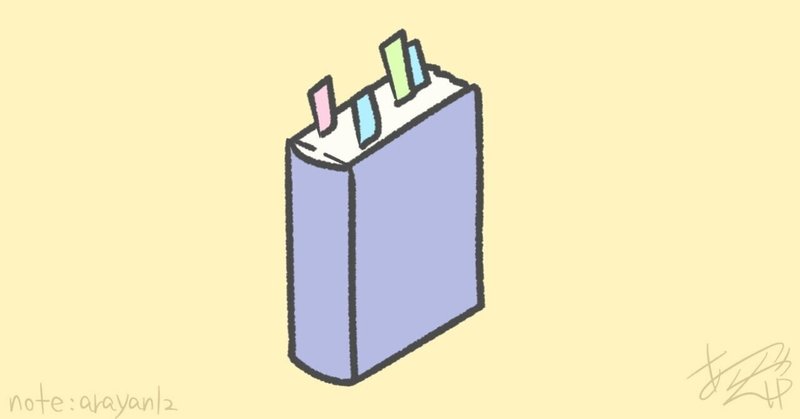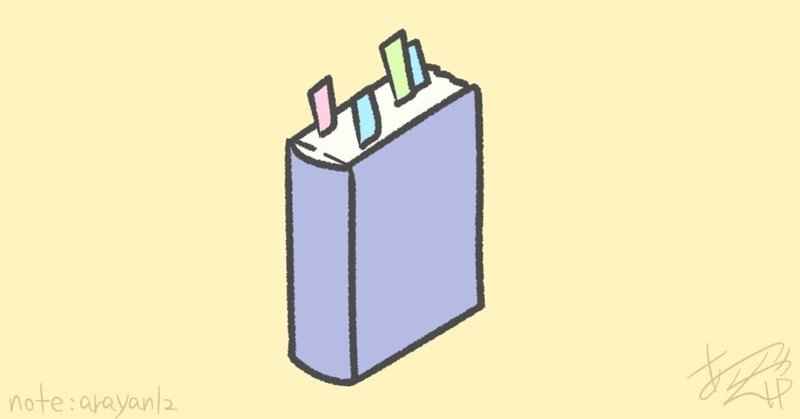#発達の凸凹
4歳から6歳までに『何をどう育てるのか』を、ものすごく具体的に書きます
「これから、何を書こうとしているのか」の説明編です。少し長いですが、読んでください。
1.4歳から6歳までの間に「どんなこと」を教えていけばいいのか 小学校に向けて、4歳から6歳までの間に「どんなこと」を教えていけばいいのでしょう。考えながら、子育てしているでしょうか?
平均タイプなら心配いりません。子どもから出てくる要求に合わせて子育てすれば、普通に小学校に適応するような子どもに育ちまま
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 3「チャイム」と「時計の見方」 その1
この項目には、2つの補助項目が付いています。まず、それを紹介し【解説】します。
1️⃣ チャイムと共に行動することの意味とその大切さを知る。
【解説】
小学校は、自立にむけて育てていく方針があります。そのため「自分で時間を見て行動すること」を求められます。しかし、各自が時計を持つのが難しかった慣習が残っていています。つまり「時計を持っていないので、チャイムで時間の変わり目を知らせます
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 4 休み時間の過ごし方 その2
1️⃣ 長い休み時間とお昼休み以外の休み時間は、トイレ休憩であって遊び時
間ではないと知る。 【育て方】
凸凹タイプの子どもは「一つの言葉は、一つの意味しか持っていない」と考えています。例えば、次のようなことがありました。
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 5 イスの座り方 その5
【育て方 実践編】
「凸凹タイプのこどもが、イスで座れる」ように育てるためには、うまく統合できていない感覚を探して、それを補っていけばいいのです。探し方は、「揺れる」「すべる」「力を入れる」「高いところから飛び降りる」「回る」の5つをチェックすればいいでしょう。少し試してみて、怖がったり、強く嫌がったりしたものが統合できていない感覚です。
5つそれぞれの「試してみること」(体ひとつでできるこ
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 6 机の上の使い方 その2
1️⃣ ノートと教科書、筆箱の置き方を覚える。 【育て方】
家庭では、食卓の上の使い方をマナーとして教えるといいでしょう。ご飯や汁物などの置き方を教えるのです。
「物を置く位置が決まっていて、それには意味があるのだ」と学ぶからです。そして、それを「覚えて守っていかないといけない」と知るからです。この経験が、学校で机の上の使い方を学ぶときの、知識に繋がります。
【セリフ】「やりとり」を使っ
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 8 消しゴムの使い方とカスの後始末の方法 その2
1️⃣ 持ってきていい消しゴムと、いけない消しゴムを覚える。【育て方】
文房具屋さんに一緒に行って、消しゴムを買えばいいでしょう。その時「覚えて」で、次にように教え込みましょう。
【セリフ】 「やりとり」を使っています。
「学校に行ったら、この消しゴムを使うのがルールらしいよ(「覚え
て」)。」
「こっちのヒーロー物がいい。」
「そうだね。そっちの方がかっこいいね。いつもテ
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 10 配布物の配り方 と 連絡袋に入れる方法 その2
1️⃣ プリントを後ろに配るときは、身体を捻り相手と目を合わせて「どう
ぞ」と言う。相手は「ありがとう」と言う。配布物が、足らないときは
どうするのかを覚える。
【育て方】
家でも、ものを「手渡し」する経験しておくといいでしょう。「すみません」を使って頼み「はい、どうぞ」と「ありがとう」をついでに経験しておくのです。練習ではなく、日常生活として普通にやりましょう。
クッキングをし
Ⅰ 低学年で覚えて欲しい生活スキル 13 給食当番の方法 その2
4️⃣ お代わりと残し方のルールを知る。 【解説】
給食は、基本的には全量食べることになっています。健康に育つように、一日の栄養量を栄養士さんが計画・計算しているからです。
しかし、最近では、それよりも子どもの思いを優先する教育がなされています。食べたくないものを無理やり食べても栄養にならないし、逆に嫌いな食べ物を増やすことが分かったからです。
だから、「事前に先生に申し出れば、減らすこ
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その3
補助項目の【解説】の続きです。
3️⃣ チョークの色とエンピツ色との関係を覚える。 【解説】
これは、小学生には分かりにくいルールです。凸凹タイプの子どもには、なおさらでしょう。
最近、チョークの色は増えています。しかし、有効に使える色というのは余りありません。かつ、板書で目立つように使った色を、子どもたちが同じようにノート使うと、あまり目立たないということも起こります。例えば、黄色で
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その6
1️⃣ 早く視写するときと、丁寧に視写するときの違いと方法を知る
【育て方】
これは、思考の柔軟性が弱い(固執性、こだわりがある)ことと関係しています。凸凹タイプの子どもは、多かれ少なかれこの特徴を持っています。
・一つのことを覚えたら、他のことを覚える気がない
・あることには、一つの方法しかないと思っている
・ある方法を覚えたら、それにこだわる
・いい方法があるのに、なぜ
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 18 ノートのとり方 その8
6️⃣ 資料をノリで素早く貼り付けられるようになる。 【育て方】
「紙をのりで貼るスキル」は、遊びやお手伝いで育てておきましょう。【解説】でも書いたように、結構学校で使いますしスピードも求められます。
ノリで遊ぶと言えば、貼り絵でしょう。広告紙や折り紙をちぎって貼って、たくさん遊びましょう。小さいときは、台紙の方にのりをぬたくったりしたあと、貼り絵をしたらいいでしょう。
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 21 辞書が引けるようになる その1
これにも、補助項目がありません。「辞書」ついて「その1」で【解説】します。そして「その2」で、幼児期での【育て方】を書きます。
学習指導要領上では、3年生のときに国語辞典の引き方を教えることになっています。しかし、それはほんの少しだけです。それだけでは、いけません。なぜなら「辞書を引くこと」には、大きな意味と効果があるからです。
今の小学校は指導要領が変わって、教師が一方的に知識を与え
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 21 辞書が引けるようになる その2
「辞書を引くスキル」の【育て方】を書きます。
4歳から6歳の子どもは、好奇心盛りです。「~は、なぁに?」「これは、なんという~なの?」など、いろんなことを聞いてきます。
そのときが「辞書を引くスキル」育てるチャンスです。知っていたら、ぱっと答えたいところですが、わざと「調べてみようか?」と「調べる」ことに誘ってみましょう。
【解説】でも書いたように、調べて知った内容より調べる過程を知る
Ⅲ 低学年で覚えて欲しい対人スキル 23 あいさつができる その2
2️⃣ 授業の初まりと終わりにあいさつする 【解説】
この「授業のあいさつ」は、学級経営と大きく関係します。1️⃣でも解説しましたように、発達に凸凹がある子どもは「授業のあいさつ」をしない子が多いのです。しかし、「授業のあいさつ」は「先生からの最初の指示」にあたります。だから、あいさつをしない子が一人でもいると、クラスルールが乱れていきます。
その流れは、次のようになります。