
「ウテナ」は、ファンじゃない人は理解しやすい劇場版を見るべし
今回は、アニメ界の鬼才・幾原邦彦について書きたい。
まぁ、この人は正真正銘の天才だよね。
仮に80年代というのが宮崎駿と富野由悠季の時代だったとして、じゃ90年代が誰の時代だったかと解釈すると、押井守、庵野秀明、そして幾原邦彦。
この3人が時代の大きな潮流を作ったと思う。
中でも、幾原さんの作家性の凄さは当時でも頭ひとつ抜けてたんじゃないかな?
・GHOST IN THE SHELL(1995年)押井守
・新世紀エヴァンゲリオン(1995年)庵野秀明
・少女革命ウテナ(1997年)幾原邦彦
ほぼ同時期に出た上記3作品の中で、一番難解なのはやはり「ウテナ」だと今でも思うんだわ。
また、幾原さんはビジュアル面でも他のふたりを引き離してたんだよね。
じゃ、当時の幾原さんのインタビュー動画を見てもらおう。
幾原さんって、その作風からもっと芸術家肌のややこしい感じと思いきや、意外とロジカルに話す、マトモで頭のよさそうな人である。
庵野さんとは昔から親交があったらしく、「エヴァ」の渚カヲルのモデルが幾原さんだというのは有名な話だと思う。
さて、今回取り上げたいのは本編のTVシリーズではなく、劇場版「アドゥレセンス黙示録」の方である。
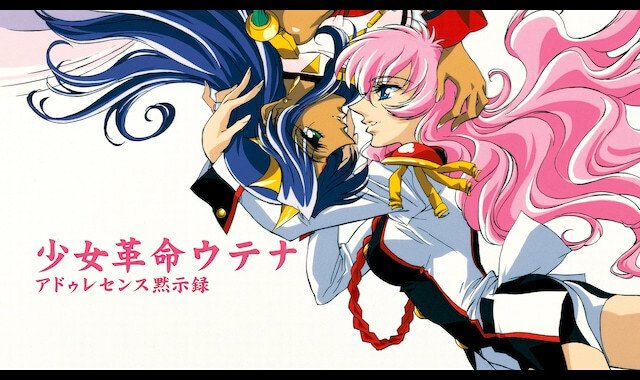
この映画の凄いところはテレビ版の総集編的なものでなく、かといって続編的なものでもなく、キャラはそのまま、ただし設定を全部変えた再構築編という形の完全新作なんだよ。
私の知る限り、こういう形での劇場版というのは史上初だったんじゃないだろうか?
後に、「エウレカセブン」がこれと似たコンセプトで劇場版を作るんだよね。
「ポケットが虹でいっぱい」というやつ。
これ、めっちゃ評判悪かったと思うけど(笑)。
一方、「アドゥレセンス革命」の方は「あり」とされてたと思う。
まだ「ウテナ」を見たことない人、あるいは見たけど全39話が長すぎて途中離脱してしまった人、そういう人たちはこの劇場版から入ってみるのも悪くないんじゃないかと。
テレビと設定を全く変えてるから、予備知識ゼロでも全然いけるし。
それでいて、幾原さんの美学はこの映画からでも十分感じ取ることができる。
そして、テレビよりもこの映画の方が分かりやすく作られてると思う。

アンシーは本編よりもビジュアルがフェミニンに振られてて、とても美しい
まず、この「設定を全部変えた」という部分から既に伏線なんだよ。
それは「エウレカセブン」の「ポケットが虹でいっぱい」も全く同じ考え方だったと思うし、確か「エウレカ」は、それに続く劇場版3部作シリーズで
現実世界(ブルーアース)⇔虚構世界(グリーンアース)
というセカイ全体構造、多次元宇宙構造を開示したよね。
多分、「ウテナ」もそれと同じなんだ。
この映画は、虚構世界の中の物語である。
いや、それをいうなら、テレビ本編もまた同じ。
どちらの物語も
「決闘で勝った者が薔薇の花嫁(アンシー)を手に入れ、世界を革命する力を手に入れる」
という構造は同じなんだけど、皆さんはテレビ版の最終回、終盤でウテナがどこかに消えたこと、そしてアンシーがウテナを探しに旅に出るというワケの分からん締め方で「??」とならなかったか?
あの締め方があまりにも難解すぎて視聴者に伝わらなかったがゆえ、分かりやすく噛み砕いてくれたのが「アドゥレセンス黙示録」だと解釈してくれ。
じゃ、テレビ版のウテナの行方、およびアンシーの向かった先、そして劇場版ではふたりがともに向かった先、これらは一体どこだというのか?
多分、それはテレビ版にせよ、劇場版にせよ、どっちにしても同じ場所さ。
「アドゥレセンス黙示録」の中で、アンシーはそれをはっきりと言葉にしている。
「外の世界」に行く、と。

これは、劇場版「エウレカセブン」でエウレカがブルーアースに出た流れとも酷似しており、多分「エウレカ」スタッフは、めっちゃ「ウテナ」の影響受けてるんだろうなぁ・・。
うん、「ウテナ」を見たことある人には「エウレカセブン」を見てほしいし、逆に「エウレカセブン」を見たことある人には「ウテナ」を見てほしいものである。
この「ウテナ」の世界は、全てが虚構、仮想現実世界。
バーチャルワールド、すなわちそれはプログラムであるがゆえ、書き換えも可能であり、その書き換え⇒「革命」ってことね。
ほら、「エウレカセブン」でもエウレカがレントンの死を受け入れられずに何度も書き換えを実行し、無数のセカイを作り出してたでしょ?
あれが「ウテナ」でいうところの「革命」なんだが、結局それは全て徒労に終わっている。
なぜって、それは虚構を無駄に増やしてるにすぎず、現実は何も変わってはいないんだから。
だから、結論は「外の世界」へ、ということになったのさ。
虚構の世界に閉じこもるのはもうやめて、現実の世界に出よう、と。
アネモネはエウレカを外へ連れ出し、ウテナはアンシーを外へ連れ出した。


奇しくも押井守、庵野秀明、幾原邦彦という3人の鬼才が、ほとんど同時期に今後のセカイとの向き合い方を作品で示してくれたのが興味深い。
★押井守「GHOST IN THE SHELL」
現実世界を捨てて、草薙みたいにあっち(電脳世界)に行っちゃうのも選択肢のひとつでは?

★庵野秀明「新世紀エヴァンゲリオン」
セカイを書き換え、セカイを肯定しよう

★幾原邦彦「少女革命ウテナ」
自分に都合のいいセカイに書き換えるとかじゃなく、まずは外の世界(現実世界)と向き合いましょう

こうして見ると、一見不健全そう(アブノーマル)に見える「ウテナ」が実は一番健全だということをお分かりいただけるだろうか。
この物語の構造を最も分かりやすくまとめると
ウテナが、アンシーという主体性のない女の子を虚構世界から現実世界へと連れ出す物語
ということになる。
明確にフェミニズムの物語だね。
まず、皆さんはアンシーの肌の色を不自然に思わないか?
「薔薇の花嫁」として多くの男性たちが奪い合う存在だというなら、むしろ色白であった方がいいと思わない?
だけど、彼女の肌は褐色。
私が思うに、これは「機動戦士ガンダム」ララァの引用だよ。

ララァは「ガンダム」における「薔薇の花嫁」的立ち位置で、彼女はアムロとシャアとの間に挟まれ、ひたすら闘い続ける2人の男性に心を痛めつつ、特に何もできないまま死んでいったという哀れな女の子である。
このへんの女性の描き方が全共闘的な富野由悠季イズムなんだが、幾原さんとしてはこういうのを全否定したかったんだろう。
80年代的価値観の否定といってもいい。
ララァ、お前はどうしたいんだ?
お前自身の主体性はないのか?
ってね。
そこで、ララァを「ウテナ」でアンシーというキャラに置き換えて、「少女革命」をさせたわけだ。
アンシーひとりでは革命など到底無理なので、彼女を引っ張っていく存在としてウテナという特殊なキャラクターが設定された。
ここでポイントなのが、ウテナが女子の優しさを持ちつつも、一方で男子のような強さを持つジェンダーが曖昧な存在、ユーティリティともいえる存在だということ。
こういうユーティリティは「ガンダム」にいなかったし、現実世界にだっておらんわな。
というか、アンシーをこの世界から連れ出すには、両方に通じる万能性こそが求められたということだろう。
ひょっとしたら、ウテナはアンシーと違って架空の存在なのかもしれない。
そのことを「アドゥレセンス黙示録」は、ウテナがなぜかクルマに変身するという終盤の描写で暗示している。

なんていうかさ、みんな幾原さんのことを芸術家っぽく捉えてるから誤解をしがちなんだけど、彼は思いっきりロジックで物語を構築してくれてるわけよ。
掴みどころのない感性による描写ではなく、全ての描写が実は「理詰め」である。

こういうビジュアルだから誤解されて当然なんだが、ずっと誤解され続けてきた人なんだろうなぁ・・。
やってることは至極真っ当で、実は健全である。
ただ美意識だけがちょっと特殊で、彼とは高校時代からの友人という脚本家榎戸洋司(「ウテナ」のチーフライター)によると、高校生の頃に彼の家に遊びに行くと、J・A・シーザーの音楽(「ウテナ」の決闘の時にかかる曲を作った人)が大音量でかかってた、という話である(笑)。
高校生の頃から、ちょっと変わってたか・・。
ところが、性格はめっちゃいい人らしい。
これまで幾原作品に触れたことがないという人は、ぜひ一度見てほしい。
「少女革命ウテナ」のみならず、近年の「輪るピングドラム」「ユリ熊嵐」「さらざんまい」もお薦めである。
彼が日本最高峰のアニメ作家のひとりであることは間違いないと思うよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

