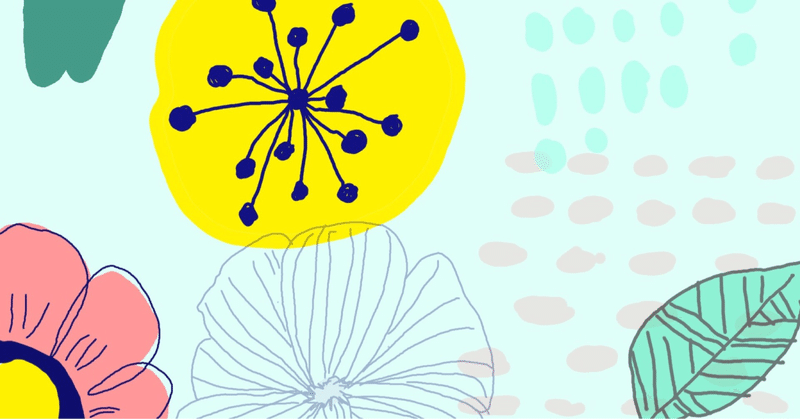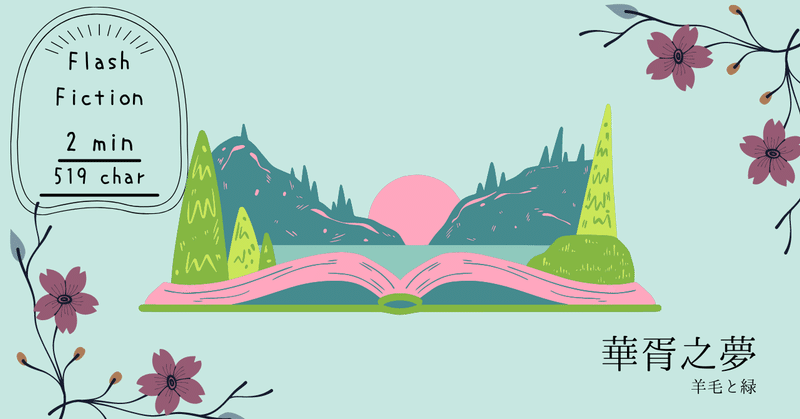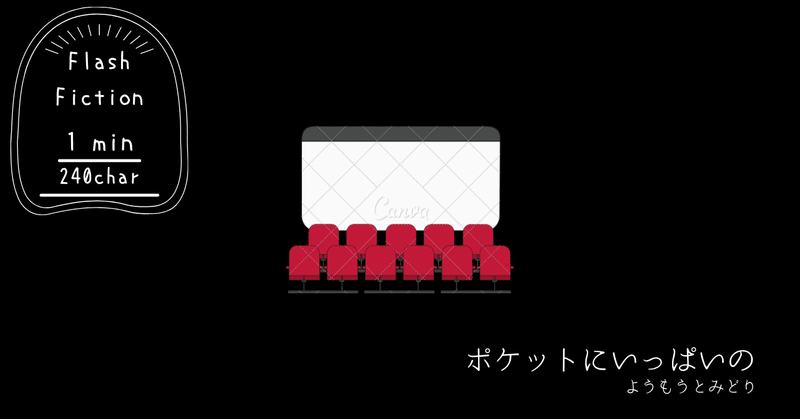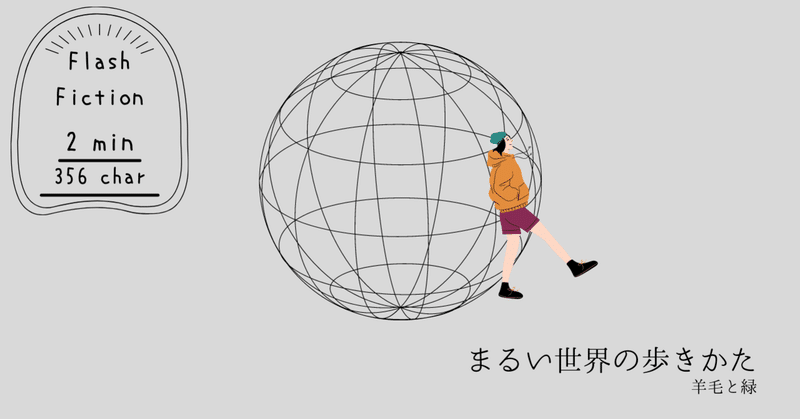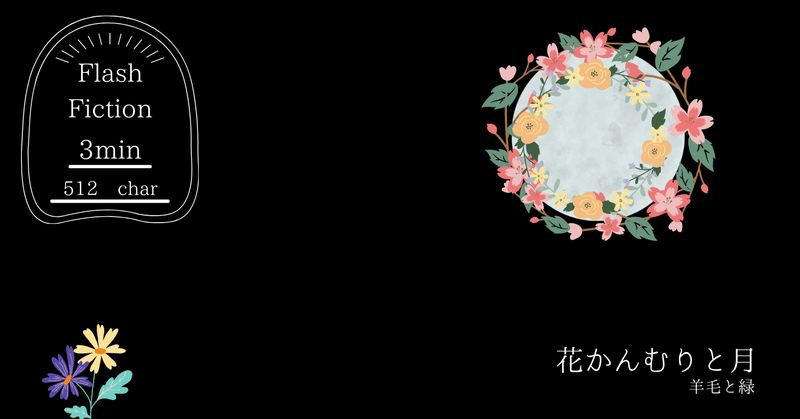#小説
ポケットにいっぱいの
どこから吹いているのかもわからない風が首筋を撫でる。定間隔に置かれた椅子とライトは、いつも変わらずにと手入れをされている。
「わたしはこうなの。最も適した形状をしているはずよ」
背もたれを調整できない席がかたる。あえて不満を漏らす輩もいないが、素晴らしいと讃える人もいない。
「でも、ぼくはわりと好きだなあ」
「ね、意外とわたしも好きかもしれない。まあ、家にはいらないけどね」
わずかに灯りが
まるい世界の歩きかた
まるい世界の歩きかた。題名は内容を語る。
本を手に取り、想像できない内容に心躍らせる。彼女がいるのはまるい世界ではなかった。だからこそ、理解できたらとねがった。
碁盤のように細かく張られた網に吊り下げられた家と街。人は糸を伝って生活し、命が尽きれば網から落ちていく。それが当たり前となっていた。
網の底になにがあるかを人は知らない。戻ってこれた者もない。人々は世界が網で構成され、先にも後にもそれ
たかくて、やすくて、
「随分高そうなところに住んでいるね」
彼はそんなところに敏感だ。ここは安い。ここは高い。そんなことを価値基準に置いていて、感情の波を引き立たせるも削いでしまうもごく簡単なものだった。
「ここは階数によって値段はないよ。上であるときはそりゃ少し鼻が高くなる人もいるけれど」
「あるとき?」
「何のために呼んだと思うの?おたのしみだよ」
「少しくらいヒントをくれたっていいのにさ」
秘密を知りたいと
シャッターをきるまでは
宙に浮かぶ綿毛を探す丸は、右往左往と動き回るも、見つけることはかなわなかった。きいろい花が種子をとばす、そう噂を聞きつけやってきたものの、徒労に終わりそうだった。
「いつか見つかりましょうかね」
四角はいつ自分に役割が回ってくるかとソワソワしながらたずねる。
自分の番になれば、きれいにラミネートされ、願わくばその色が褪せないようにと祈りが送られる。その役割に誇りを感じ、はやる気持ちを抑えきれず
フリッパーがはばたけば
「彼らの翼はフリッパーと呼ばれ、水の中で泳ぐときに使われるヒレとしての役割を持ちます。二足歩行で歩いているときはバタバタさせて、腹ばいになったときは足で地面を蹴るようにすることもあります」
スピーカー越しに聞こえるお姉さんの声は、楽しそうだった。
もう小学校だって二年もすれば卒業するんだ。だからもうこういうところが楽しいとは考えていなかったのだけど、悪くない。そう思って見て回っていると、いつ
編み込まれたセーターは
私がその言葉を見つけたとき、物語は水色をしていた。別の物語を読んだとき、それは薄い黄色だった。そこには、登場人物たちの感情があったのだ。それを覗いた私という存在は、彼らに色を感じたのだ。
物語を覗くというのは、私が彼らの一つ上の階層にいる存在とも考えることができるのかもしれない。それは難しい話ではなく、水槽を眺めているようなものである。隔たりがあって、その外側から内側に目を向けている存在がい
シリコン製の山を下る悪魔
何か報われない夢を見て、なんとなくやるせない気持ちになった。こぼした牛乳をぞうきんでふき取り、それを飲む夢だったんだ。しかもそれは、誰かに強制されたものでなく、夢の中の自分が自発的にやったんだ。
どうしようもない、そんな言葉が似合う状況だったね。朝起きた時には、涙なんか流して、これはなんだって思ったもんだよ。
「シリコン製の山を下る悪魔は、雑草に恋をした」
夢を見ているとき、誰かにそうさ