
【コラム】プロダクトビジョン(コンセプト)の重要性
【SYNCAオープン!】
経営管理部門・バックオフィス特化型の転職サイト「SYNCA」(シンカ)がオープンしました😁
皆様是非ご活用ください!
はじめに
もう随分と前の話ですが、とある大きめの会社の役員のおじさんが何度も似たような質問を社員に投げかけていました。
主なものは以下のとおりです。
「君の正義はなに?」
「君はなんでうちの商品をお客様に売るの?」
「お客様なら誰でもいいの?」
このおじさんはなかなかに凄い人で、営業というスキルだけで役員の座までのし上がり、年収が8,000万円を超えた時期が何年間もあったらしいです😑バブル
あれから十数年。
おじさんの根底にある考え方は正しかったんだなと確信しております!
営業マンにとって重要な価値観は、その商材を取り扱う「正義」であり「理由」であり「顧客は誰か」という概念です。
これらの根底にある考え方が「プロダクトビジョン」または「プロダクトコンセプト」です。
ここが緩いままだとただの商材販売になってしまい、本当の意味で自律的な事業者にはなれません🤔
会社の経営理念やビジョンと近いものだと思いますが、より小さく「事業」や「プロダクト」単位で見たときも、ビジョンやコンセプトがないとどうやって組織を運営していったらいいかわからなくなります。
だからこそ、事業担当者になったらまずはここを確定すべきだと思います。
今日はそんなお話をしたいと思います。

1.プロダクトビジョンとは
プロダクトビジョンとは、そのプロダクト(製品に限らず、サービス等の事業を含みます。以下省略。)で実現したい未来のことをいいます。
会社経営で掲げる「ビジョン」の「プロダクト版」と思っていただければ。
これは、プロダクトコンセプトと言い換えてもほぼ同じ意味です😁
そのプロダクトを作った目的や基本理念のことです。
単体のサービスやプロダクトを扱う会社では、プロダクトビジョンがそのまま「コーポレートメッセージ」「ミッション」「バリュー」などになっていたり、様々な呼ばれ方をしたりしています。
厳密にはそれぞれ違う意味がありますが、統一された学問上の定義はまだないので、覚えやすいもので覚えてください。
今回の記事で言う「プロダクトビジョン」は、そのプロダクトを通じてどんな未来を築きたいのか、どんな理想があるのかという点を扱います。
それを考え抜いて、一言で表現できるようにしておく必要があります。
プロダクトを作って実際に販売するようになると、チームのメンバーが様々な問題にぶち当たると思います。
その際に頼りになるのはビジョンだけです。
羅針盤のような役割を果たしてくれるものなので、ここはしっかりと考え抜いた方が良いと私は思っています。
ビジョンがないプロダクトでは、発生する様々な論点で統一的な判断ができなくなってしまいます😑
場当たり的に判断をせざるを得ないので、論点Aについては利益優先で判断、論点Bについては業務フローを優先して判断という風に、先が読めなくなります。
そこでビジョンがしっかりしていれば、理想の状態から逆算して決断を下せます。
誰が判断しても同じ結論に至るという推測が働くので、自信を持って意思決定できます。
極めて重要な考え方だと思います🤔

2.ケーススタディ
プロダクト単体でビジョンを定めている会社はそこまで多くないので、多くの人が知っている「会社のビジョン」や「ミッション」「コーポレートメッセージ」等の中で、秀逸なものを見ていきましょう!
(1)清水建設
皆さんご存知清水建設のコーポレートメッセージは、以下のとおりです。
「子どもたちに誇れるしごとを。」
めちゃくちゃ秀逸じゃないですか?🤔
神がかっていると言っていいです。
建設業に携わっている全員が胸に刻むべきコンセプトだと思います。
建設業ならではというか、建設業だからこそ響くメッセージ性があります。
子どもができて、その子が5年生くらいになったときに
「このビル、パパが作ったんだよ」
って言いたいですよね!
子どもからしたら「マジで!?父ちゃんすごい!」と思うでしょう。
私だったらそう思います。
そういう情景が一発で脳内に浮かぶ。
最高のコンセプトだと思います。
現在、耐震偽装や手抜き工事等をはじめ、様々な問題が発生している建設業界ですが、このコンセプトが心の中に染み込んでいる社員なら、まずそんなことはやらないです。
仮にそういう現場を見つけてしまったとしたら、すぐに上層部に報告してくれるでしょう。
なぜなら、子どもたちに自分の仕事を誇れなくなるからです!
このコンセプトが染み付いている社員ならば、自分が難しい問題に立ち向かわないといけなくなったとき、いつも子どもたちの目が、表情が、すぐに浮かぶようになるでしょう。
自分が今しようとしている決断は、子どもたちに誇れるものか?
事あるごとにこの問が頭をよぎるようになります。
その結果、正しい判断ができる。
たった十数文字のコンセプトですが、極めて深いコンセプトだと思います。
なお、コンセプトがいくら秀逸でも建設業の事件はゼロにはできません。
構造上、どう考えても不正が起きやすい構造だからです。
事件を未然に防ぐことは当然ですが、それと同等に大事なことは、事件が発生した後どう動くかです。
隠蔽に走るのか、誠実かつ迅速に対応するのか😑
ここでコンセプトの浸透度が問われます。
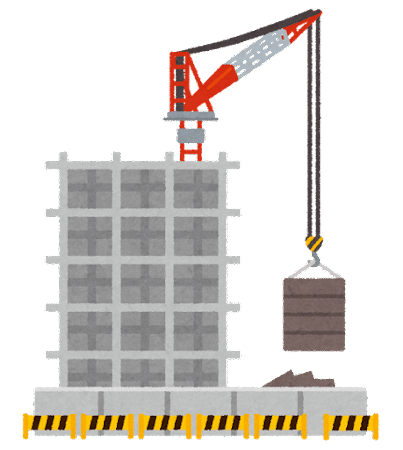
(2)freee
続いてfreeeさんのミッションを見てみましょう。
スモールビジネスを、世界の主役に。
クラウド型会計ソフト「freee」を提供しているfreee社のミッションもなかなか秀逸ですね!
現在、会計ソフト業界は戦国時代です😑
弥生会計、マネーフォワード、勘定奉行、freeeなどがひしめき合っています。
でも、上記のミッションでピンとくる。
『freeeさんはスモールビジネスを対象にしているのね!』と。
自分たちが「誰を顧客としているのか」というのが一発で解る素晴らしいミッションだと思います。
「顧客は誰か」という論点は、経営戦略において極めて重要な論点です。
freee社の顧客は個人事業主と小規模を中心とした中小企業なのだというのがミッションからすぐにわかる。
たぶんfreee社のほぼ全社員がしっかりそこを認識しているのではないでしょうか。
プロダクトのUI(ユーザーインターフェース)・UX(ユーザーエクスペリエンス)にもその価値観が反映されています。
会計ソフトのfreeeを使ったことがある人はわかると思いますが、極めてわかりやすいソフトウェアです。
簿記の知識がなくても使えると思います。
これは会計に明るくない中小企業のユーザー及び個人事業主のユーザーを対象としているからこそ練り上げられたUI・UXです。
素晴らしい🤔


3.プロダクトビジョンは変化する
プロダクトビジョンというものは、通常「変化していくもの」です。
むしろ、変化しない方が問題だと思います🤔
そもそも、プロダクトには誕生から消滅までの一連のプロダクト・ライフサイクルがあります。
上記の記事でもご紹介しましたが、プロダクトの一生は以下の4つの段階を経て消滅していきます。

私が思うに、プロダクトビジョンが最も重要となる時期は、導入期~成長期です。
その事業を立ち上げて、成長させるまでの間が一番労力がかかります😵
チームを作って、ビジョンを共有して、共通認識・共通言語を浸透させて、同じ理念を持って販売していく。
徐々に売れ始めると今度は組織が大きくなっていくので、事業責任者はビジョンの浸透度を下げないように繰り返し繰り返しチームに発信し続けないといけません。
ビジョンの明確性や浸透度が甘いと、チームからどんどん人が抜けていきます。
そうすると、頻繁にチームメンバーが入れ替わってしまうので、結果的に価値観も浸透せず、事業が上手くいきません。
そのため、導入期~成長期は無理な拡大をせずに慎重にチームを作ることに専念すべきだと思います🤔
自分の身の丈にあった組織成長を心がけることが大事です。
そして、ある程度軌道に乗ってきた頃には、チームのコアメンバーに対して権限を委譲している状態になっているはずです。
もしかしたらプロダクトの機能も多角化して、それぞれに部署ができ、一つの会社のような状態になっているかもしれません。
こうなってくると、プロダクトビジョンの抽象度を上げないといけなくなることがあります🤔
導入期におけるプロダクトビジョンはかなり具体的なビジョンで良いと思いますが、規模が大きくなってくると徐々に会社のビジョンに近づいていきます。
別の言い方をすると「抽象度が高くなります」
このあたりのイメージはベンチャーにお勤めの皆様ならすぐにできるだろうと思うので、省略します😁
大事なポイントは、プロダクトビジョンは変化するものなので、規模に合わせて作り変える作業をすると良いという点です。

4.SYNCAの場合
せっかくなので、プロダクトビジョン策定の実例をやってみましょう🤔
現在、私が所属している株式会社WARCでは、経営管理部門特化型の転職サイトである「SYNCA」(シンカ)を絶賛立ち上げ中です。
SYNCAは、企業用サイト(求人を募集している会社用)と転職者用サイト(転職希望者用)があります。
【企業用サイト】
【転職者用サイト】
SYNCAは、WARCの創業者である山本さんが長年抱えていた課題感から生まれた事業で、私自身もかなり思い入れのある事業です。
SYNCAのプロダクトビジョンは、現在山本さんがじっくりコトコト考えて言語化しているところだと思うので、今回のこの策定例はあくまでも私個人の見解を基礎にしています😁
この点ご了承ください。
ただ、大枠の価値観は同じだと思います。
(1)転職サイトの特殊性
まず前提として、転職サイトというビジネスモデルの特殊性からお話します。
通常、プロダクトビジョンは一つ考えればそれで足ります😁
顧客は誰か?を考えたときに、普通は一つの集団にターゲットを絞れるからです。
しかし、転職サイトでは2種類の顧客が存在します。
一つが、求人を募集している企業様です。
もう一つが、転職を希望している転職者様です。
どちらか一方を重視するわけにはいきません。
なぜなら、誰かが損をするビジネスモデルなんて存在価値がないからです!
転職市場における最大の問題は、転職させればさせるほど手数料が入ってくるという点です。
その結果、人材紹介業では、無理に転職を勧めたり人材を企業にゴリ押しする行為が横行しています。
そのようなやり方は、企業にも転職者にも何のメリットもありません。
だからこそ、転職サイトというビジネスモデルでは、顧客を企業様と転職者様の両方であると認識すべきです。
そうなると、プロダクトビジョンも2つ必要になってきます🤔
もしくは、2つ作ったあとに統合する必要があります。

(2)企業用SYNCAのビジョン
では、SYNCAのプロダクトビジョン(企業側)から考えていきましょう!
プロダクトビジョンを考える際は、まずそのプロダクトの存在意義から考えていくと良いです。
どんな課題を解決したいのかという点です。
この点、WARCはそもそもスタートアップやベンチャーを支援するために創業された会社です。
そのため、SYNCAもこの理念を引き継いでいます。
したがって、SYNCAが対象とする顧客も、原則としてスタートアップやベンチャー企業(以下、「スタートアップ等」といいます。)です。
そして、スタートアップ等にとって、経営管理部門のマネジメントにおける最大の課題は、
「経営管理部門の採用難しすぎないか!?」
という問題です。
私自身、法務部長や執行役員等を務める中でこの問題に何度も直面しています!
経営管理部門のリーダー以上の人材が、転職市場に全然いないのです😫
なぜ人材がいないのかという点をご説明します。
そもそも、経営管理部門というのは、経理・財務・法務・労務・人事・IR・PR・経営企画・経営戦略などの部署の集合体です。
そして、そこに所属する全メンバーが何らかの専門分野を持っています。
そのため、経営管理部門というのは、専門家集団です。
逆にいうと、専門家集団じゃないなら、経営管理部門とはいえません。
そして、経営管理部門の人員割合は、会社全体の10%程度しか存在しません。
現実的なお話をすると、その中で本当の意味でのプロフェッショナルは、多くて5%程度だと思います。
つまり、転職市場の中に、経営管理部門のリーダー以上として活躍できるプロフェッショナルは5%程度しかいないということです😵
しかも残念なことに、その5%の半数近くが大手企業様にしか興味がありません😭
スタートアップ等は、よほど特殊な会社でもない限り、原則として大手企業には敵わないのです。
財務基盤がまるで違うので……。
この時点で極めて難しい採用活動になるというのがお解りいただけるかと思います……。
各部署のプロフェッショナルになるともっと数が減ります🤣
そのため、ベンチャーやスタートアップが、経営管理部門のハイクラス層(マネージャー以上)を採用する場合は、経営陣のお知り合い等から引っ張ってくるか、又はハイクラス層専門のエージェントを使うことになります。
運良く知人等から引っ張ってこられたらいいのですが、なかなかそう簡単に見つかりません。
したがって、多くの会社ではエージェントを利用します。
しかし、エージェントを活用する場合、その費用が結構高いのです。
新しく採用する方の年収の約40%が手数料としてかかります。
なかなかのコスト感です🤔
ハイクラス層の採用は難易度がとても高いのでエージェントを使うことも致し方ないと思いますが、これをミドル層(サブマネージャーやリーダークラス)やジュニア層(新卒~3年目くらいまで)にまで支払っていたら、経営管理部門の採用コストで利益が圧迫されます。
そこで、多くの企業では、採用コストを下げるため、またはより確実に欲しい人材にアプローチするために、ダイレクトリクルーティング(企業側から積極的に接点を持ちに行く採用手法)を活用しています。
しかし、経営管理部門特化型の転職サイトがほぼ無いのです😫
しかも、経営管理部門のスキルを正確に理解している人も少ない。
このような問題を解決するために、SYNCAは存在しています!
まず、SYNCAでは、経営管理部門に特化した人材プールを作っています。
そして、経営管理部門のスキルセット(能力指標)を徹底的に細かく設定していて、どのレベルの人材なのかがひと目で解るようになっています。
このスキルセットの項目は全部山本さんが直接作っています。
長年ベンチャーのCFOとして経営管理部門の採用を行ってきたからこそできる「リアルなスキルセット」です。
よって、企業側のSYNCAのプロダクトビジョンを一言で表現するとすれば、以下のようになると思います。
「経営管理部門のメンバー獲得をより確実に!より安く!」
このプロダクトビジョンは私が今思いつきで書いているだけなので、実際のプロダクトビジョンは山本さんを中心にしてチームで練り上げて行くことになります😁
SYNCAはまだ公開して間もないので、これから数多の機能改善を繰り返して成長していくと思います。
ただ、プロダクトの根底に流れる理念はきっと変わりません😁
スタートアップ等が、より良い人材に、より安く出会えるようなプラットフォームを作ろうとしているのです。
(3)転職者用SYNCAのビジョン
次にSYNCAのビジョン(転職者側)を考えてみましょう。
(企業側)で検討したとおり、WARCのターゲットはスタートアップ等です。
したがって、転職者側に対しても同様に「スタートアップ等に興味を持ってくださっている転職者様」をターゲットにしています。
そして、SYNCAは原則としてミドル層・ジュニア層をターゲットにしているので、年齢層的には20代~30代を対象としています。
この時点で極めてニッチな市場を対象にしているといえます(笑)
スタートアップ等に転職してみようかなと考えている若手の転職者様にとって最も重要なことは、転職で成功すること(失敗しないこと)です。
そして、「転職で成功する」の定義は人それぞれです。
おそらく共通しているところは「良い会社に入る」ことだろうと思います。
では良い会社とは何か🤔
これを一般化することは少し難しいです。
経験を重視する人、一緒に働く人を重視する人、報酬を重視する人など様々です。
そこでSYNCAでは、
・厳選されたスタートアップの求人を掲載
・「お試し転職」という制度を導入
・エージェントによるキャリア相談も可能(希望者のみ)
などの試作を行っています。
スタートアップ等を志望する様々な価値観を持った方が、自分の価値観にあった転職先を見つけられるようにいろいろと考えて試作を打っています。
また、スタートアップ・ベンチャー業界についてイメージを持ってもらえるように、私自信もこのnoteを書き続けています😁
すべては未来のスタートアップ等のためにです!
今現在若手の皆様も、ほんの数年先にはベンチャー業界を支える主翼になります。
山本さんがかつてそうだったように、若手の皆様の中には「未来の創業者」が必ずいます。
そういう未来の経営層ために、WARCはSYNCAを存在させています。
以上を前提にすると、転職者側のSYNCAのプロダクトビジョンは以下のようになります。
「未来のスタートアップの経営陣のために現在(いま)の出会いを。」
念の為もう一度いいますが、これは私の勝手なプロダクトビジョンですw
でも、ちょっと良さげじゃないですか?🤣
今20代~30代前半の人たちって、これから数年間でメキメキと経験値を積むんですよ。
IPO準備中のスタートアップ等で働いたりしたら、そりゃもう凄い成長を遂げるはずです。
その中の一部の人たちは絶対マネージャー以上になるし、中には役員を務める人も出てきます。
SYNCAをキッカケとしてスタートアップに入って、そのスタートアップの拡大に伴って出世し、数年後に上場ベンチャーの経営層になる……
あぁ、素敵😍

ということで、若手の皆さん、SYNCAに登録してくださいませ😁
もちろんベテランの皆さんも大歓迎です!
おわりに
今日は、プロダクトビジョンについて私見を撒き散らしてみました🤣
全く参考にならなかったかもしれませんが、最後までお読みいただきありがとうございます!
最近知人のスタートアップ経営者の壁打ちに付き合っていて、ちょっと盛り上がっちゃったんですよ🤔
プロダクトビジョン考えるの楽しいです。
ベンチャーは夢を語れる場所なので、これからもどんどん夢を語りたいです。
ここ数ヶ月で改めて思うのですが、やはりベンチャー業界は楽しいです。
いつもヒリヒリしているし、問題ばかり起こるけど、根明が多くて笑えます🤣
普通に仕事しているだけでもネタが量産されていくんですよね。
その問題が起こっている最中はたまったもんじゃないんですが、通り過ぎればネタになります。
そんな楽しい毎日です。
ただし、変化耐性は必須です😑
ということで、ベンチャー業界に興味を持ってくださっている若手の皆さん。
是非SYNCAにご登録を!
未来の経営層目指しましょう!
ではまた書きます😁
【お問い合わせ】
この記事は、株式会社WARCの瀧田が担当させていただいております。
読者の皆様の中で、WARCで働きたい!WARCで転職支援してほしい!という方がいらっしゃったら、以下のメールアドレスにメールを送ってください😁
内容に応じて担当者がお返事させていただきます♫
この記事に対する感想等もぜひぜひ😍
recruit@warc.jp
【WARCで募集中の求人一覧】
【次の記事】
【著者情報】
著者:瀧田 桜司(たきた はるかず)
役職:株式会社WARC 法務兼メディア編集長
専門:法学、経営学、心理学
いつでも気軽に友達申請送ってください😍
Facebook:https://www.facebook.com/harukazutakita
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/harukazutakita/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
