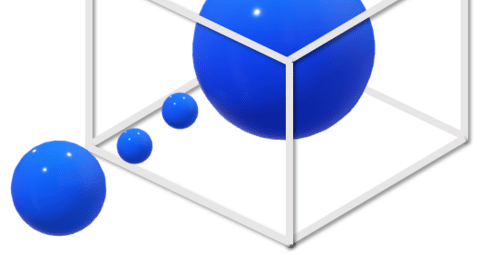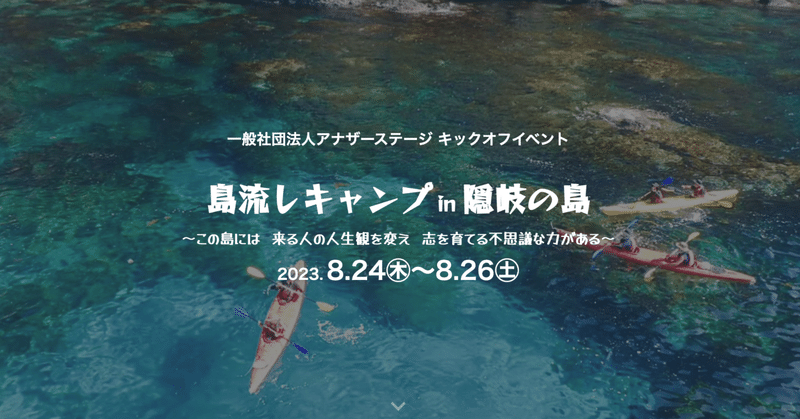#学校
'学校からの流人' 大歓迎! 不登校の小中学生の【逃げ場所=自分らしく生きられる場所】をクリエイトする一般社団法人アナザーステージの理事になりました。
2023/8/24-26開催、キックオフイベント「島流しキャンプ in 隠岐島」はこちら!
学校に行くことをやめた子どもたちへ、保護者の方へ
2023年1月に岡山・広島・香川への出張がありました。その際に、会いたい人がいて、それとは関係なく行ってみたかった島、島根県の隠岐島を訪問しました。冬の日本海の天気が安定しているはずもないのですが、この時に行かなければ二度といくことが無い気がして、顔を合わ
しあわせに生きる基本はどこで作られると思いますか?家庭?地域?子どもたちはほとんどの時間を学校で過ごします。教室の影響はとても大きいのです。みなさんはどんな学校を自分の子に行かせたいですか?
「こんな学校に子どもを行かせたい」
「こんな学校を作りたい」
そんなことを考えたことはありますか?
そんなすごいことをやってる方々のお話を聞くイベントを準備しました。
あすキラLab vol.5 学校を創る。学びってなんだろう
2022/06/16 (木) 19:30 - 21:00
私は若い頃には、そんな思いはなかったんですね。学校って、どれもそんなに違うとは知らなかったから。そして、学校が
コロナ禍で学びの機会を失った子どもたちにチャンスを!オンライン「世界一周スタディーツアー(World Immersion Tour)」4月22日提供開始
ちょっと前の話になりますがこんなサービスを開始しました。まずは動画でご覧ください。
ニュースリリースはこちら!
打ち合わせのたびにどの学校からも同じ声が聞こえてきて、そして先生方はまるで自分たちが悪かったように、「子どもたちが可哀想で、、、」と肩を落としていました。
世界一周スタディツアーでは生徒が選ぶ5大陸をオンラインで旅をしながら人生を考え今を学ぶと言う仕組みです。
私たちもそうですが