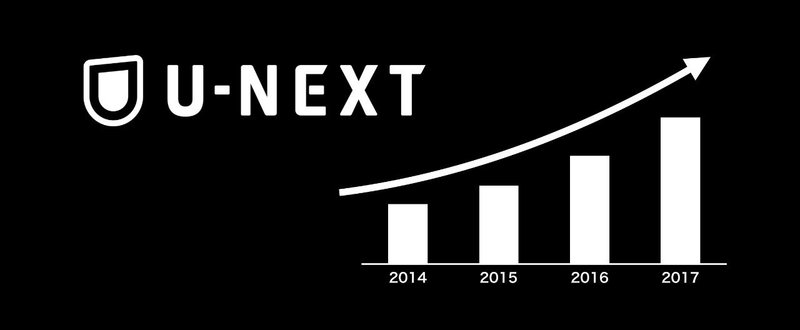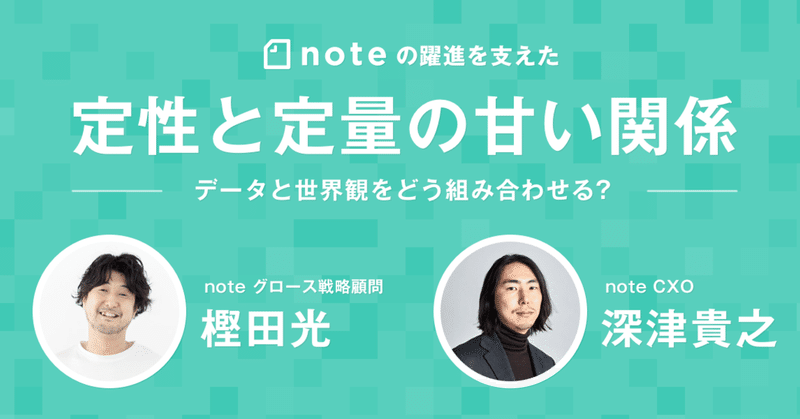#データ分析
グロースとは学びを得ること - 後編
こんにちは、THE GUILDの@goandoです。
「グロースとは学びを得ること - 前編」の続きです。
後編ではグロースにおけるABテストの価値について、グロースに取り組む中で得た気付きと世界の動向をご紹介します。
正しいABテスト多くの方がご存知のABテストですが、時折見かけるのが「改善案Aと改善案Bの方法のどちらがより良い結果に繋がるかを検証」するための方法として利用し、更には全てのユ
エンゲージメントの深さと収益の質 - Diligence at Social Capital : Part 5
BY JONATHAN HSU 翻訳 : 和田健太郎・玉井和佐
このシリーズの第1・2回目の投稿では、グロースアカウンティングをどのようにエンゲージメントと収益の分析に応用していくかについて説明した。第3回目の投稿では収益を産むビジネスに対する実用的な顧客生涯価値(LTV: Life Time Value)の分析フレームワークを紹介し、第4回はこのLTVフレームワークをどのようにユーザ
サービス改善やグロースハックでぶち当たる「これは正しい因果か、因果が逆なのか、ただの相関なのか問題」の解決法
グロースやサービスデザインのメンタリングをする中で、しばしば相談を受けるのが、
「ある機能Aを使っているユーザーの継続率が高いことが分かったが、これは正しい因果関係かどうか、どうやって確かめればいいか?」
という相談だ。
具体的には「ある機能Aを使っているユーザーの継続率が高い」ときに以下の3つのパターンが考えられる。
A)順因果:機能Aを使うことがユーザー継続率の押し上げにつながっている