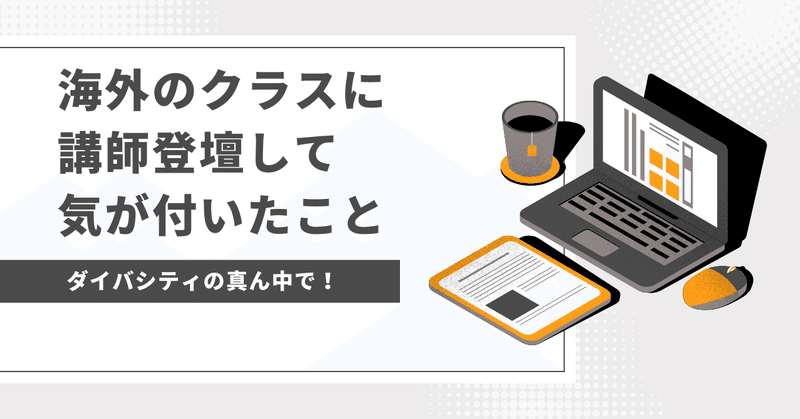
ダイバシティの高いクラスに講師登壇して気が付いたこと
私は、グロービス(ビジネスパーソン向け教育業)という会社の東南アジア統括拠点(シンガポール)に10年駐在していました。
自分の時間の70%くらいは事業運営・会社経営に時間を使い、30%くらいは大学院教授・研修講師として英語で授業をしていました。
担当したクラスの参加者は、東南アジア+インド・オセアニアからと多様性に富んでいます。
出身国ももちろんのこと、経験もみんな違います。日本では経験したことのないダイバシティ度合いの高さでした。
ある日、受講生の方が、私のところにきてこんな質問をしてくれました。
「このようなダイバシティの高い中で、ファシリテーションするコツは何でしょうか?自分たちはこういうダイバシティの高い環境のマネジメントに苦労しています」と。
私が、ダイバシティの高い環境で大事にしていることを書きたいと思います。
まず大前提として、一定のファシリテーションスキルは必要となります。
これは日本語・英語関わらず必要なスキルで、学んで損はないと思いますので是非学んでいただきたいとは思います。(ファシリテーションスキルの研修は世の中にたくさんありますね。)
その上で、の話を今日は書こうと思います。
①まず、失敗を恐れないこと
とにかく、「やってみる」ことが成功のカギになると思い、私はとにかく場数を踏みました。失敗してもいいので「量」を積みました。
習うより慣れろとは言いませんが、
習ったら慣れろ、というのはあっています。
最初から1度で成功する(成功させよう)と思わないようにしていました。
最初は自分でも反省することばかりが出てくるとは思いますが、振り返りを必ずする。
しかも、記憶が鮮明なその場ですぐにする。
振り返り、インプルーブしたいところは、徹底的に原因究明と改善策を考えます。
そして、次もやってみる。
3-5回、時には10回くらいやれば、ある程度はできるようになります(もっと早く習得できる人もいるかもしれませんね)。
できるようになるまでやれば、そこまで粘れば、できるようになります。
②2つ目は、「同じ」という発想からスタートせず、「違う」という発想を持つこと。
日本語で日本人に教える場合と同じアプローチが海外でも使えるに違いないと思うと、「違い」しか見えてきません。
「違うアプローチでないと、通用しないに違いない」というところからスタートすると、「ここは同じなんだ!」と思える部分があります。
思考の仕組みをうまく使った方が、楽な気持ちで挑めるのでアドバンテージになります。
③3つ目は、違いは悪いことではないという発想を持つこと。
以前ある人がこんなことを言っていました。
「日本語での「違い」という言葉には、Wrongの意味と、Differentの意味があるからややこしい。異なっていることは悪いことだと認識されがちである」と。
違いとは、互いに異なった「隠れた前提」があるから作られるもの。
この前提の存在に気づき、互いに合わせれば、違いを超えられれます。
メカニズムは意外にシンプルです。
ー意見・考え方の違いは必ず存在することを理解して、
ーその違いの大元にある「隠れた前提」をいち早くつかみ取り、
ーその前提合わせを互いにする
というスキルを駆使すると前に進むことができます。
論点はどこがどう違うのかをいち早く読み取るスキルを強化すると、ダイバシティマネジメントにも大いに役立つと思います。
私もダイバシティの中でのファシリテーション力をこれからも磨き続けていきたいと思っています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
