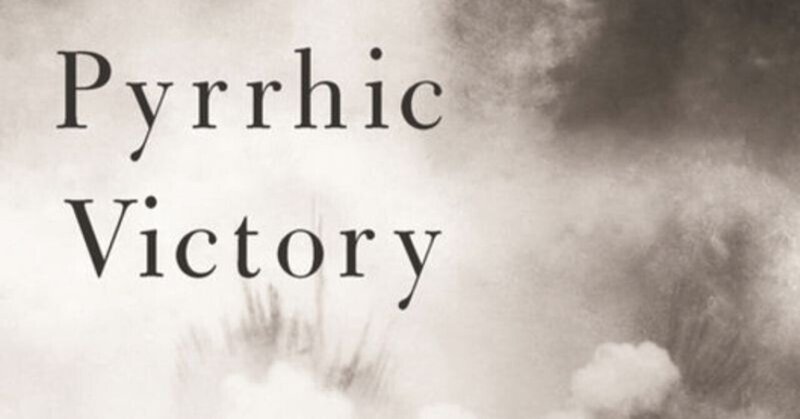
第一次世界大戦におけるフランス軍の戦略と作戦を分析したPyrrhic Victory(2008)の紹介
第一次世界大戦(1914~1918)でフランスは西部戦線の作戦で中心的な役割を果たしました。フランス軍が戦場に送り出した兵の数は841万名に上り、そのうちの138万名が命を落としました。Robert A. Doughty氏の『ピュロスの勝利(Pyrrhic Victory)』(2008)は陸上戦を中心にフランス軍の戦略と作戦の変遷を記述した研究成果です。
Doughty, R. A. (2008). Pyrrhic Victory: French Strategy and Operations in the Great War, Belknap Press.

1914年に開戦した当初、フランス陸軍総司令官として作戦を指揮したジョセフ・ジョフルは、マルヌの戦いでドイツ軍の進撃を阻止しました。その功績は高く評価されましたが、著者はその後に実施された1914年から1915年までの作戦は失敗に終わっており、彼の手法に限界があったことを指摘しています。第一次世界大戦でフランスが被った人的損害の半分近くがジョフルの無理な攻勢によって発生したものであるという著者の指摘は重要です。
大きな犠牲が出たことを踏まえ、フランス陸軍では複数の作戦アプローチが検討されるようになりました。一つは、圧倒的な物量を確保した上で、複数の正面から圧力をかけ続けるという構想であり、この構想に基づく攻勢作戦は1916年にソンムの戦いで大きな損耗を出すことになりました。
当時の技術環境で部隊を攻撃前進させることが技術的、戦術的に不利であることを認める考え方もあり、敵の攻撃を防御戦闘で破砕した後で反撃を加えるという作戦アプローチも提案されるようになりました。フィリップ・ペタンは1916年のヴェルダンの戦いを通じて近代戦における防御戦闘の重要性を確かめました。
さらに別の作戦アプローチとしては、特定の地域に砲兵の火力を集中させることで、部隊が迅速にそこを突破するという構想があり、1917年にロベール・ニヴェルはこの構想に基づく作戦を指導しましたが、実際には予想していたほどの戦果を上げるには至りませんでした(第二次エーヌ会戦)。
著者は、これらの作戦アプローチから得られた経験が蓄積される過程で、より小さな損耗でも実行可能な構想が模索された経緯を詳細に記述しています。1917年5月、ニヴェルの後任として陸軍総司令官に任ぜられたフィリップ・ペタンは、人員単位の数的優勢に頼るのではなく、航空機、火砲、戦車、化学兵器の4つの装備を基盤とする大規模な改革に着手しました。特に航空機はペタンの改革で特に重視された装備でした。著者は次のように述べています。
「4月にドイツがシュマン・デ・ダム(引用者注:第二次エーヌ会戦)の上空を制したことにより、味方の砲兵の準備が著しく混乱したことで、航空優勢の重要性が明確になった。 そのため、フランスは航空機の性能を向上させ、航空機の数を増やそうと試みた。1917年1月に北部から北東部のフランスでフランス軍は1,420機の航空機を保有していた。6月までに彼らは2,100機を保有し、そのうちの700機が戦闘機で300機が爆撃機であった。航空学校、予備、マケドニアに配備された航空機を含めると、フランス軍は約6,000 機の航空機を保有していたが、その多くが旧式だった。ペタンは成功には航空戦力が「不可欠」であると主張し、9月6日に2,870機の最新鋭の航空機を目標とするプログラムを開始した」
戦場における航空優勢の獲得を図るだけでなく、ペタンは砲兵の近代化にも取り組みました。フランスの工場では155mm榴弾砲を重点に製造が進められ、5月31日の時点では82門だった毎月の生産目標が、8月31日には180門に引き上げられています(Ibid.)。その代わり、威力が十分ではない75mm榴弾砲の製造は縮小されました(Ibid.: 369-70)。1917年1月からフランス陸軍では砲兵の機動的な運用が模索され、ニヴェルによってすでに一部の部隊の編成は完成していましたが、ペタンはこの部隊を拡大させることを決定しました(Ibid.: 370)。
ただし、この部隊に使用させようとしていたのは通常の弾薬ではなく、化学剤でした。ペタンは過去の経験から対砲兵戦や塹壕戦で化学兵器が敵を無力化する上で有効であると判断していました(Ibid.)。また、突撃の過程で歩兵部隊が被る損耗を減らすため、軽戦車FT-17の生産を拡大しました(Ibid.)。この軽戦車は1917年に試験が始まっており、1918年からは部隊での運用が始まりました(Ibid.: 371)。
1917年から1918年の前半にかけて続いたペタンの改革は着実に成果を上げていましたが、戦況は大きく動いていました。東部戦線では同盟関係にあったロシアの体制がロシア革命の影響によって崩壊しつつありました。もしロシアが戦争を続けられなくなれば、ドイツ軍が東部戦線から西部戦線に部隊を再展開させ、フランスやイギリスに対する圧力を増してくることは避けがたい状況でした(Ibid.: 371-3)。
1917年7月26日の連合軍首脳部の会議で、ペタンは東部戦線のロシア軍を支援するために、西部戦線で攻勢をとる案があることを踏まえた上で、それを明確に拒絶し、イギリスやアメリカの同盟国からも理解を得ました(Ibid.: 375)。今すぐに攻撃を開始して消耗することは避け、アメリカ軍の来援で西部戦線の状況が連合軍にとって有利になるまでは防御に徹し、戦力を蓄えることが有利であるというのがペタンの考えでした。しかし、イギリス海外派遣軍の指揮をとるダグラス・ヘイグは、このような消極的な方針には批判的な考えを持っていました。
フランスの情報組織はドイツ軍が3月中旬以降に大規模な攻撃を開始する準備を完成させると予測し、特に危険が大きい地域も特定していました。しかし、連合軍の内部ではフランス軍とイギリス軍の戦略が調整されていませんでした(Ibid.: 406-7)。
ペタンが防御的な戦略を支持する中で、ヘイグが攻撃的な戦略を支持していたため、両軍の戦略を調整することが難しかったことも著者は指摘しています(Ibid.: 407)。1918年3月にドイツ軍が西部戦線で攻勢を開始すると、連合国軍の総司令官としてフェルディナン・フォッシュが指揮をとることが決まり、ペタンとは異なる攻撃的な戦略が模索されるようになりました(Ibid.: 407-8)。
1918年の夏にフォッシュはドイツ軍の攻勢を食い止めると、反撃に転じる戦機と判断し、数個師団の小規模な反撃ではなく、30個師団近くを投入する大規模な反撃を主張し、7月12日には反撃に慎重だったペタンの同意も得ました(Ibid.: 463-4)。
フランス陸軍が、攻撃的な戦略を受け入れるようになった主な理由は、西部戦線にアメリカ軍の部隊が展開し始めたことが挙げられています。フォッシュは、1919年も戦闘が続くと予想し、1919年の春に十分な優勢を確保した上で本格的な攻撃を開始するためには、1918年末までに215個師団から220個師団が必要と見積っていました(Ibid.: 464)。そのため、フランスはアメリカに対して1919年7月までに少なくとも100個師団を派遣するように求めていました(Ibid.)。
戦力の強化を進めながらも、フォッシュは主動的な地位を保持するため、7月に攻勢作戦の実行を主張しました(Ibid.: 474)。この作戦は成功を収め、8月8日以降にドイツ軍に大規模な損害を与えました。このときの連合国はわずか4日間の戦闘で3万名弱の捕虜を獲得しています(Ibid.: 478)。
この決定的な敗北を受けて、ドイツ陸軍の首脳部でも戦争の継続が困難という判断に傾くことになり、和平を模索することもやむを得ないという見方が台頭してきました。その後も戦闘は続きましたが、11月11日に締結された休戦協定によって、戦闘行為は停止されることになりました(ドイツと連合国の休戦協定)。こうして長く続いた戦闘が終わりましたが、著者はその後の和平交渉を通じてフランスが外交的に満足いく結果を得たわけではなかったことも指摘しています。
「ドイツは屈服し、混沌とした状況に陥っていたが、フランス人は自らの勝利を祝った。彼らは戦争を生き延び、独立を保持していた。命を落とした人々を悼み、戦没者を讃える記念碑を建てていたとき、彼らは未来に大きな希望を抱いており、平和条約でドイツが武装解除され、国境地帯の脅威が軽減され、損失と費用が補償されると期待していた。 ただ、クレマンソーができる限りの努力を払ったにもかかわらず、ヴェルサイユ条約はフランスとドイツとの間の根本的な戦略的不均衡を変えることはできなかった。つまるところ、フランスの政治的影響力は同盟国にドイツを解体するよう説得するにはあまりにも小さく、その陸軍は妥協なき和平を強制し、ドイツの軍事力を破壊するにはあまりにも弱すぎたのである。フランスの人民がどれほど復讐と安全の確保を望んだとしても、彼らだけでそれらを達成することは不可能だった。ドイツの人口は依然としてフランスの人口よりも多く、工業生産能力も優れていたので、最終的には将来に対する不安感が1918年11月の高揚に影を落としたのである」
そのため、戦争の終結はフランス陸軍にとって決して安心できるものではありませんでした。著者は第一次世界大戦でフランス陸軍が多くの犠牲を出しながら苦しい戦いを切り抜けたことを記述していますが、フランス陸軍が勝者として得たものが十分ではありませんでした。こうした結論は、本書のタイトルである「ピュロスの勝利(Pyrrhic Victory)」で端的に表現されています。第一次世界大戦でフランスは多くの犠牲を出して勝利をつかみ取りましたが、それは決して犠牲の大きさに見合ったものではなかったと考えられています。
関連記事
調査研究をサポートして頂ける場合は、ご希望の研究領域をご指定ください。その分野の図書費として使わせて頂きます。
