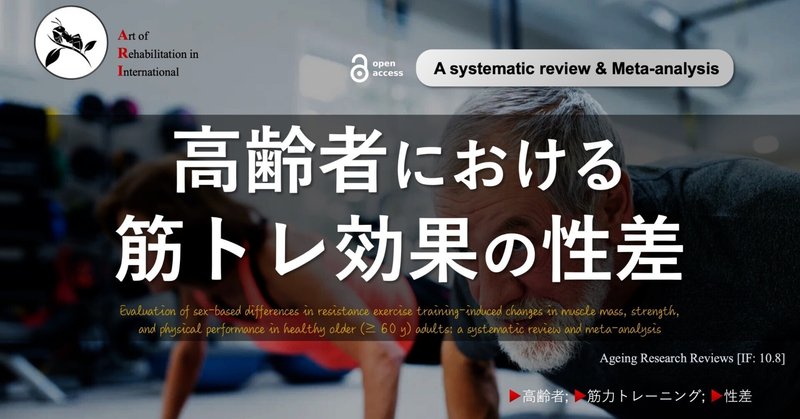
高齢者における筋トレ効果の“性差”
📖 文献情報 と 抄録和訳
健康な高齢者(60歳以上)における筋力トレーニングによる筋量、筋力、身体能力の変化における性差の評価:系統的レビューとメタ分析
📕Hawley, Stephanie E., et al. "Evaluation of sex-based differences in resistance exercise training-induced changes in muscle mass, strength, and physical performance in healthy older (≥ 60 y) adults: a systematic review and meta-analysis." Ageing Research Reviews (2023): 102023. https://doi.org/10.1016/j.arr.2023.102023
🔗 DOI, PubMed, Google Scholar 🌲MORE⤴ >>> Connected Papers
※ Connected Papersとは? >>> note.
🔑 Key points
🔹上半身と下半身の筋力の絶対的な変化は、高齢男性でより大きい。
🔹上半身と下半身の筋力の相対的な変化は、高齢の女性で大きい。
🔹全身の除脂肪体重の絶対的変化は、高齢男性で大きい。
🔹四肢や筋繊維レベルでの筋サイズの変化については、性差はない。
🔹身体能力の変化については性差なし。
[背景・目的] この系統的レビューとメタアナリシスの目的は、健康な高齢者における筋力トレーニングへの適応に性差があるかどうかを明らかにすることである。
[方法] スクリーニングの後、同じレジスタンス運動トレーニング介入後の骨格筋サイズ、筋力、および/または身体的パフォーマンスの変化について、高齢の男女(男性602例、女性703例、60歳以上)を比較した36の研究からデータを抽出した。
[結果] 研究の質の平均は16/29(修正Downs and Blackチェックリスト)であり、中程度の質と考えられた。
■ 筋力
・上半身の筋力(17の比較アウトカム;男性191人、女性265人)では、絶対的な変化は高齢男性で大きかった(ES = 0.81 [95% CI 0.54, 1.09], P < 0.001; I2 = 40.27%, P < 0.05)。
・対照的に、上半身の筋力の相対的変化は、高齢の女性で大きかった(ES = -0.46 [95% CI -0.77, -0.14], P < 0.01; I2 = 56.81%, P < 0.01)。
・下半身の筋力(39の比較アウトカム;男性508人、女性608人)では、絶対的な変化は高齢男性で大きかった(ES = 0.40 [95% CI 0.24, 0.56], P < 0.001; I2 = 34.85%, P < 0.05)。
・下半身の筋力の相対的変化は、高齢の女性で大きかった(ES = -0.24 [95% CI -0.42, -0.06], P < 0.01; I2 = 46.56%, P < 0.01)。
■ 全身除脂肪体重/除脂肪体重
- 全身除脂肪体重/無脂肪体重(23の比較アウトカム;男性328人、女性444人)では、絶対的な変化は高齢男性で大きかった(ES = 0.18 [95% CI 0.04, 0.33], P < 0.05; I2 = 0%, P > 0.05)。
・しかし、相対的(ES = 0.03 [95% CI -0.12, 0.17], P > 0.05; I2 = 0%, P > 0.05; Fig. = 0%、P>0.05)には差がなかった。
■ 四肢特異的筋肉量
・四肢の筋肉量/サイズの測定(23の比較アウトカム;男性354人、女性436人)では、絶対的変化(ES = 0.10 [95% CI -0.20, 0.41], P > 0.05; I2 = 74.66%, P < 0.001)、相対的変化(ES = -0.06 [95% CI -0.46, 0.35], P > 0.05; I2 = 29.28%)ともに、男性と女性の間に差はなかった。
■ 線維タイプサイズ
・I型線維サイズ(10個の比較結果;男性120人、女性103人)については、絶対的変化(ES = 0.12 [95% CI -0.78, 1.02], P > 0.05; I2 = 89.47%, P < 0.001)、相対的変化(ES = 0.04 [95% CI -0.79, 0.87], P > 0.05; I2 = 87.33%, P < 0.001; 補足図2)ともに、高齢の男性と女性の間に差はなかった。
・IIa型線維サイズ(7つの比較アウトカム;男性69人、女性62人)については、絶対的変化(ES=0.91[95%CI -0.15, 1.98]、P>0.05;I2=86.83%、P<0.001)、相対的変化(ES=0.59[95%CI -0.37, 1.55]、P>0.05;I2=83.77%、P<0.001)ともに、高齢の男性と女性の間に差はなかった。
・IIx型線維サイズ(6つの比較アウトカム;男性56人、女性51人)については、絶対的(ES = 0.53 [95% CI -0.77, 1.83], P > 0.05; I2 = 88.94%, P < 0.001)、相対的(ES = -0.07 [95% CI -1.74, 1.61], P > 0.05; I2 = 92.42%, P < 0.001)ともに差はなかった。
■ 身体能力
・椅子立ち上がりテスト(13の比較結果;男性226名、女性254名)では、高齢の男性と女性の間に絶対的変化(ES = 0.01 [95% CI -0.16, 0.19], P > 0.05; I2 = 0%, P > 0.05)または相対的変化(ES = 0.04 [95% CI -0.14, 0.22], P > 0.05; I2 = 0%, P > 0.05)の差はなかった。
・歩行能力検査(15の比較アウトカム;男性249人、女性356人)については、絶対的変化(ES=0.05[95%CI -0.31、0.41]、P>0.05;I2=74.10%、P<0.001)または相対的変化(ES=0.06[95%CI -0.33、0.45]、P>0.05;I2=77.57%、P<0.001)において、高齢男性と女性の間に差はなかった。

[結論] 今回のシステマティックレビューとメタアナリシスの結果は、60歳以上の健康な高齢者において、レジスタンス運動トレーニングに対する適応反応に性差があることを示している。
🌱 So What?:何が面白いと感じたか?
「性差医療」という言葉がある。
✅ 性差医療とは?
- 性差医療とは、男女の様々な差異により発生する疾患や病態の差異を念頭において行う医療である。
- また、これらの差異を研究する学問は性差医学と呼ばれる。
- これまでの医学は成人男性を標準として、病態とその推移、診断方法、治療方法などを確立してきた。しかし近年では、同じ疾患に対する危険因子でも寄与度に男女差がある場合があること、同じ医薬品でも効果に男女差がある場合があることなどが明らかになりつつある。
- 原因として男女のホルモンバランスの違い(生物学的要因)や生活習慣の違い(社会文化的要因)などが挙げられているが、いずれにしても男性を基準として作成した診断方法や治療方法をそのまま女性に適用した場合、最良の医療とはならない可能性がある。
- 性差医療とは、これらにおける男女差を研究し、医療に反映させようという行いである。
男女平等という旗印のもと、社会的には次第に平等に近づいていている印象がある。
しかしながら、外部刺激に対する身体反応においては、やはり違いはあるようだ。
今回抄読した論文は、筋力トレーニング効果の性差を明らかにした。
興味深かったのは、絶対的変化と相対的変化によって、その効果がひっくり返ることだ。
例えば、筋力に関していえば、変化の大きさは男性の方が大きいが、変化率は女性の方が大きくなる。
これはベースラインの違いなどが影響するのかもしれないが、筋トレ効果の説明の際に「女性の場合には男性より小さい」という、これまで僕自身が持っていた常識が一部崩れた。
性差についての理解を進めていきたい。
⬇︎ 関連 note✨
📕高齢者における筋トレ効果の“性差”
— 理学療法士_海津陽一 Ph.D. (@copellist) October 11, 2023
・36研究を包含
・筋トレ効果の性差について調査
🔹筋力:絶対的変化(変化の大きさ)は男性>女性
相対的変化(変化率)は男性<女性
🔹除脂肪体重:絶対的変化は男性>女性
筋力の相対的変化においては,
女性の方が効果が大きいことに驚きました😲#高齢者 pic.twitter.com/Gx0MFtUtww
○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥
良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』
こちらから♪
↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○
#️⃣ #理学療法 #臨床研究 #研究 #リハビリテーション #英論文 #文献抄読 #英文抄読 #エビデンス #サイエンス #毎日更新 #最近の学び
