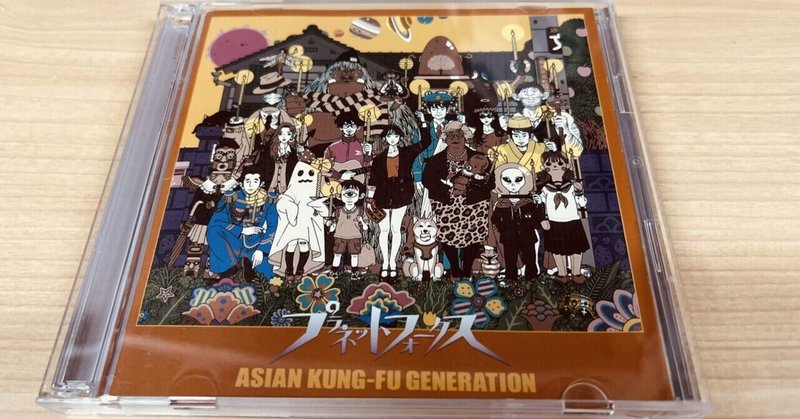
”分かり合えなさ“への抵抗〜ASIAN KUNG-FU GENERATION『プラネットフォークス』
心荒むことの多い時代だ。2020年の2月からより浮き彫りになっただけで、それよりもずっと前から価値観で傷つけ合い、思想で燃やし合うような日々は常に目の前に横たわっていた。そんな世界にあって、後戻りできない断絶とコミュニケーションの可能性を描いた濱口竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」が第94回米アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞したほか、世界中で評価されたことは1つの象徴的な出来事のように思う。言語の壁を超え、喪失の先に光るわずかな希望をこの星の誰しもが求めているような気がする。
音楽シーンからもそんな1作が3月30日に届けられたばかりだ。ASIAN KUNG-FU GENERATIONの10thアルバム『プラネットフォークス』である。このアルバムに貫かれているのは"分かり合えなさ"にどう抵抗していくかということだと思う。分かり合えないと匙を投げるその一歩手前に、分かり合えなくとも分かろうとすることはできるのではないかという視点をそっと与えてくれる。その音作り、そして歌詞の全てにおいて、意思が強く通っているのだ。
音が多彩であるということ
『プラネットフォークス』に収録された最古のシングル「Dororo/解放区」は2019年5月のリリース。所謂オーセンティックなアジカンを体現するギターロック「Dororo」とともにダブルA面で「解放区」が収録されていた時点でこのアルバムの幅広さは予見されていたように思う。ポエトリーリーディングの導入、多く友人や仲間を招き録音された最後のコーラスにただならぬ創作への熱を感じたのだ。その後も、塩塚モエカ(羊文学)とのツインボーカルでシンセベースを取り入れた「触れたい 確かめたい」、長年サポートメンバーを務めた下村亮介(the chef cooks me)によってプロデュースされたヒットシングル「エンパシー」など、様々な要素によってアジカンを更新してきた。
結果として『プラネットフォークス』はかつてなく外に向けて開け放たれた作品になったように思う。オープニングを飾る「You To You」はフィーチャリングゲストに三船雅也、つまりROTH BART BARONを迎えた。アジカンらしいスケール感をより荘厳に響かせる彼のコーラスとアレンジメントは祈りのよう。彼の声とアコギの調べが入ることで、彼の抱える想いまでもがしっかりと並走しているように聴こえるのが興味深いし、これこそがゲストを迎えることの意義のように思う。三船はかつて『極彩色の祝祭』のインタビューで「みんなで太鼓を叩いたり、歌ったりするだけで楽しかったんじゃないかって思うんです。そういう根源的な喜びを取り戻すことが、いま人類にとって必要なことなんじゃないか」と語っていた。この曲のサビにある、声を合わせるイメージはロットの楽曲とも強く共振しているように響き渡る。
中村佳穂バンドやKID FRESINOバンドのメンバーで知られる西田修大がサウンドアドバイザーとして2曲の音色作りに携わり、skillkillsのGuruConnectが「Be Alright」と「星の夜、ひかりの街」でビートメイクと編曲をサポート。アジカンの骨格であり土台である部分においても外から気鋭の才気が参加している。そして外だけなく、アジカンの内側でも制作においてユニークな革新が起きた。このアルバムで後藤正文(Vo/Gt)に次いで作曲を担当した山田貴洋(Ba/Vo)は、コロナ禍でアジカンに絞らずに多彩な楽曲を制作し続けていたという。本来はアジカンに持ち込まれない要素が、アジカンで形になった結果80sのフレーバー漂うレトロなシンセポップ風「雨音」のような異質な楽曲も生まれた。トラックを山田、喜多建介(Gt/Vo)、伊地知潔(Dr)が作り込み、メロディを後藤が担当するアジカン内でのコライト制作が確立されたのだ。
また多くのゲストを招いた2020年のGotchのソロ作『Lives By The Sea』の影響も大きいように思う。かつては棲み分けられていた活動はいつしか、その曲が求めるのであればアジカンでもソロでも問わずに編曲されるようになった(「ボーイズ&ガールズ」はその好例)。そして遂にラッパーの客演というアジカンとしては初の一手に結びついたのだ。chelmicoのRachelとSIMILABのOMSBが名を連ねた「星の夜、ひかりの街」ではマイクリレーを行うからこそ伝えられる、歌い繋いでゆくべき未来の破片が光っていると思う。アジカンに影響を受けた世代が縦書きの歌詞で言葉を刻む。この美しい循環を強く実感できる。必然性のあるコラボとしてその意義もクオリティも高水準だ。
実は前作の『ホームタウン』は『プレイリスト』という仮題で制作されていた時期もあり、元々はバラエティに富んだ様々な楽曲を収録する予定だったという。リヴァース・クオモ(Weezer)やホリエアツシ(ストレイテナー)、THE CHARM PARKが作曲に参加し、Homecomingsの畳野彩加がボーカルで客演するなど、アルバム本編とそれに付属したEP『Can't Sleep』の楽曲にも確かに"共作"の要素はあった。しかし、『プラネットフォークス』における"共作"はその時の聴感とはまた違う。次項では本作に至る道筋を振り返りたい。
「実験」へ、回帰の道筋
これほど多彩な音像という点で、『プラネットフォークス』は2010年の6thアルバム『マジックディスク』を彷彿とさせる。「新世紀のラブソング」を皮切りにシンセやホーンセクション、ストリングスの導入を行った実験的な1作だ。本作は後藤正文が1人でデモを作り込むというスタイルで練り上げられており、コーラスのダビングもほとんど自分の声で行っている。当時のインタビューで後藤は「曲としての性能を自分の中で磨かないとダメだなという思いもあった」「誰かと一緒にやるのではなくて、一人でやらないとダメだと思う。芸術とか表現というのは、一人ぼっちのところからしか始まらないから」とも発言しており、この作品は孤高がゆえの完成度を誇っていた。
しかし『マジックディスク』のレコ発ツアーでは求める音像にメンバー間で摩擦が生じ、解散寸前まで陥ることになった。そんな折に発生した2011年3月11日の東日本大震災。その後、アジカンの関係性は次作アルバムに向けて制作を進める中で自然と修復されていくこととなる。後藤はGotch名義でソロ活動を開始し、よりプライベートかつ自由で多彩なインディーロックを追求。アジカンでは肉体的かつ開放的なロックサウンドを鳴らすことを意義と捉え、2012年の7thアルバム『ランドマーク』として結実した。一方、アルバムツアーではサポートメンバーを迎えた7人体制で廻るなど、アジカンがアジカンとしてのびのびと演奏できる環境を整える時期だったと言えそうだ。
2013年、メジャーデビュー10周年を経たアジカンは自身の足場を確認しながらより強固なものにしていく作品を創ってきた。2015年の8thアルバム『Wonder Future』はフーファイターズのスタジオで録音され、轟音ともラウドロックとも形容できるような豪快なギターサウンドを更新(「Easter」や「スタンダード」はライブでも起爆剤となることが多いように思う)。2016年には2004年の2ndアルバム『ソルファ』を全曲再録し、バンドとしての地肩の鍛錬を音源に残した。2018年の9thアルバム『ホームタウン』は彼らの強みであるパワーポップを探究。懐かしさと新しさを同時に引き受けていた。
バンドとして揺るぎない存在になりつつあったアジカン。その風通しの良さはライブを観ても明らかだったが、これが大きく制作にも還元されたのが『プラネットフォークス』なのだ。『マジックディスク』のアプローチとは違う形で、これまでにないアジカン像を自然に刷新していくような、意欲的な成熟の形を示すことはこの整ったコンディションのアジカンだからこそ取れた1つの実験だろう。そしてコロナ禍も重なった。多くの芸術家たちがその存在意義を揺さぶられた時期に、同時代のアーティストたちと真摯に手を取り合って、その人たちの表現を必要として連帯して作品を作り上げることは言葉で話す以上の強いアティチュードを感じる。若手の起用も、未来へと音楽の流れを繋いでいくここ数年のアジカンの姿勢が如実に表れている。ただの「実験性への回帰」ではない、明確で大きな意思が通っていると思った。
愛と皮肉、ユーモアと怒り
アーティスト同士の強い結びつきに鼓舞され、多彩な楽曲を楽しく聴くことができるアルバムである一方で歌詞は"分かり合えなさ"への抵抗を最も明白に示しており、耐久性の高い言葉選びが為されているように思う。しかしずっと強く何かに抗っているわけでなく、時に愛で大きく包み込み、時に皮肉をたっぷりと込め、時にユーモアを持って接し、時に怒りに突き動かされる。そんなまだら模様の感情を1曲ごと、いや1曲の中にも数々映し出していく。一定ではない感情を嘘なく、現実と対峙しながら描ききっている。
だからこそ「解放区」の《笑い出せ 走り出せ 踊り出せ 解放!!!》のすぐ後に「Dororo」のようなギリギリの祈りを歌う曲が現れるし、言葉を交わし合う難しさと望みを歌う「ダイアローグ」の後、言葉がもたらす痛みや容赦ない粛清を描く「De Arriva」が訪れる。それでも「フラワーズ」や「触れたい 確かめたい」といった温かく切実な"生きた感情"を歌うことで立ち上がるのだが、その先には枯れ切ったアコギが虚しく響くまるでレクイエムのような「Gimmie Hope」があり、痛烈な風刺をポップに歌う「C'mon」もある。コントロールしきれない心象を時代のシーンに乗せ歌うその姿は頼もしくもあり、同時にこちらが心配になるほどにシリアスな向き合い方をしている。
このアルバムを締めくくるのが「再見」と「Be Alrght」であることは救いである。過去にも沢山の楽曲で歌ってきた"別れ"のモチーフを軸にしながらも、ずっしりとしたシンプルなロックサウンドで描かれる「再見」に滲むのは"もう1度出会うこと"のイメージだ。そして続く「Be Alrgiht」はゴスペルのような分厚いコーラスワークで"live"を歌い上げている。ライブ会場にもう1度集い、いつか声を重ねる日。この寄る辺ない時代にあって、それでも生き抜いていこうとしている日々。liveする、ということの意味をもう1度噛み締めるようなラストトラックに相応しい、巨大な生の肯定が刻まれている。
今のアジカンを象徴するモードが「エンパシー」であり、新たな代表曲となったこと。そしてこのアルバム全体を引っ張る大きなテーマになったことが『プラネットフォークス』、つまり惑星の民族、この星のフォーク(土着的で流浪の音楽)という題を導いたのも必然と言えるだろう。《君の吐息が弾む音》や《夜明けの街路が露を纏うこと》という、感覚的な情感をもって命の鮮やかさを描くこの筆致は、過剰に一体感を煽ることをせずとも真っ直ぐに誰しもが躍動的に生きる世界を描いており、そして強く願っている。アンセムという言葉を冠するに相応しい、何もかもを大きく包み込む1曲だろう。
このアルバムのジャケットはまるで百鬼夜行のようだ。人ならぬものたちとともに、女性らしき人物とアジカンが蠟燭を掲げて歩き出そうとしている。火は常に苛烈な感情と結びついているが同時に弔いや祈り、浄化のイメージとも離れがたく繋がっている。この百鬼夜行が何を示すものかは判然としないが、歩幅も体格も姿かたちもばらばらな生き物たちが皆同じ方向を向いていることが重要なのだと思う。この次の場面で、もしかしたら誰かは別の方向へと歩き出すかもしれない。しかしこの一瞬だけは同じ方向を見つめているのだ。個別の思想や固有の感情を持った僕や君をそんな風にしてしまえるのは、もしかすると音楽の力なのではないだろうか。『プラネットフォークス』は一瞬だけでも重なり合うその刹那について願った1枚なのだと思う。むしろ、その一瞬だけ重なり合った先に、それぞれの希望をばらばらの足並みで探し始めることができるのではないだろうか。そんなことを願える作品。
○ポッドキャストでも喋りました。Spotifyアプリからお聴き頂けると嬉しいです。
#コンテンツ会議 #音楽 #邦楽 #ロック #バンド #ロックバンド #邦ロック #考察コラム #音楽コラム #エッセイ #コラム #ディスクレビュー #アルバムレビュー #新譜レビュー #好きな音楽 #備忘録 #note音楽部 #今日の音楽 #asiankungfugeneration #アジカン #Gotch #プラネットフォークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
