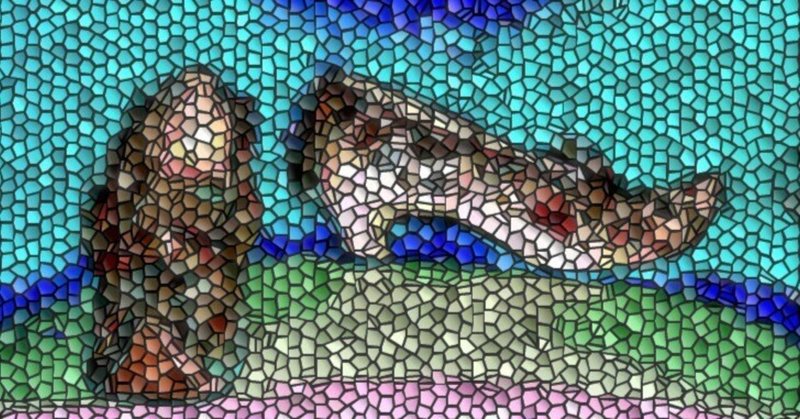
魔法の靴① 会社がなくなりました!
【あらすじ】
会社員の香奈恵には「夢」がない。人生のんびりすごせればいいやと、24歳にして前に進むことを諦めていた。幼なじみでオーボエ奏者の夢を目指す希美がまぶしい。
ある日、香奈恵が勤める会社が倒産し、やりたい仕事もないままに再就職活動を始めることになる。
夢があるのに追いかけられない人もいる。夢を見つけられない香奈恵は、夢を追いかけられずに足踏みしている人と一緒に前に進むために、10年前の子供の死について調べ始める。
ちょっとミステリー風味の長編お仕事小説です。
【本編】
プロローグ
5歳になったら、世の中のことは、なんでもわかると思ってた。なのに、さっぱりわからない。
どうしてぼくはこんなところにいるんだろう。
目が覚めたら、前も、右も、左も、ぜんぶ、海だった。夢かなあと思って腕をつねってみたら、痛かった。
砂浜が、遠い。松の林があるはずだけど、そのあたりは真っ黒な雲みたいにみえる。おうちは、もっともっと向こうの方だ。
お舟に乗っているわけじゃ、ないんだよね。足元がゆらゆらしないもの。
後ろには、さっきまで、大きなカメさんとカニさんとイカさんがいたはずだった。カメさんのこうらに寄りかかって、うとうとしちゃったんだ。でも、今は、なぜだか、真っ黒でざらざらでゴツゴツの固まりに、ぼくは背中をつけている。
頭のうえは明るい。夜だけど、お空にたくさん星が出ていて、まぶしい。
海の面に、きらきら光のかけらが浮かんでる。ところどころで白い筋になって押し寄せる波が、海に落ちてきた星の光を砕いて散らばらせてしまう。
足が、なんだか冷たい。さっきまで地面に立っていたはずなのに、今は足首まで水につかっている。変なの。
星が、くっきり光る。そのかわり、いつもの月が、今日はない。
あ、あの明るい星は、ぼく知ってるよ。こと座のベガ。それで、あっちの明るいのが、はくちょう座のデネブ。
「なつのだいさんかくけいっていうんだぜ。夏の星座だけど、秋になっても見えるよ」
お兄ちゃんが教えてくれた。
さんかくけいだから、もう一つあるんだ。わし座のアルタイルっていうの。ぼく知ってるよ。
アルタイルを探そうと思ったら、遠くから、声が聞こえた。
「……………………太ぁ」
お母さんの声だ! 遠くの砂浜の、もっと向こうから聞こえたみたい。
行かなくちゃ。お母さんのところに帰らなくちゃ。ぎゅっとしてもらうんだ。
歩き出したら、膝まで水につかっていた。おかしいなあ。さっきより海が深くなったみたい。
「しん、たぁ……」
また、お母さんの声がする。急いで行かなくちゃ。
一生懸命、右足を前に出したら、そこにはなんと、地面がなかった。ボコっと音がして、僕の身体は勢いよく右に傾いた。いけない。落ちちゃう。
なにかにつかまらなきゃ。そう思って手を伸ばしたら、黒いゴツゴツの固まりが、腕にひどく当たった。痛い! 痛いよ!
「いたいよぉ!」
叫ぼうとしたら、口の中に、しょっぱい海の水が入ってきた。ぺっぺっ。
「しんたぁ~! しんたぁ~!」
お母さんを呼ばなくちゃ。助けてって。
「お、か……」
でも、口を開けたら、海の水がどんどん口に入ってくる。しょっぱいだけじゃなく、苦いんだ。吐き出そうとしたら、のどの奥に入っちゃった。咳が出て、どんどん、水が入ってくる。
お胸が痛いよ。苦しいよ。
目を開けると、目がすごく痛くなった。空の星が、見えない。ぼんやりした光だけ。水の中だから。
もう、どうやったら頭が水の上に出るのか、わからなくなっちゃった。
苦しいよ。
助けて、お母さん……
× × ×
男児が海に転落、死亡 神奈川県湘ガ浜市
神奈川県湘ガ浜市の海岸で20日未明、男児が海に転落した。救助されたが、病院で死亡が確認された。死亡したのは同市の自営業、岡野慎治氏(52歳)の次男、慎太ちゃん(5歳)で、死因は溺死。
× × ×
「おまえが殺したんだ」
岡野慎治の押し殺した呟きは、部屋の隅で、きつく体育座りをして縮こまっている誠一にまで、はっきり聞こえた。
びくり、と、母・佳乃の肩がはねた。
二人の中央に置かれた白い固まりは、あまりにも小さく、あまりにも静かだ。子供用の白いタオルケットと、真っ白な布がかけられている。人形みたいにひっそりと帰ってきた10歳年下の弟、慎太だ。
いつもなら、ドアの向こうから、どたばたと、けたたましい足音で駆けてくるのに。ドアを開けたら、勢いよく、誠一にぶつかってきて「ただいまぁ! お兄ちゃん、あのね、すごいんだぜ、お隣の犬がね……」と、まとわりついて、見たものを全部報告してくれるのに。
今朝、帰ってきたときは、少しも音を立てず、静かだった。
どうしたんだよ。今日は、何も報告することないのかよ。いつも真ん丸に見開いて、こぼれ落ちそうな目は、どうしてそんなに堅くつぶっているんだよ。
慎太が布団に横たえられて、体を拭かれ、白い布で覆われていく様子を、誠一は霞がかかった光景としてしか覚えていない。実際、目には霞がかかっていた。涙が、こぼれていいものかどうか戸惑って、目の縁にいっぱいたまっていたから。
「おまえが殺したんだ」
また、父・慎治の声が響く。食いしばった歯の間から、しゅうっという息とともに吐き出されたその声は、低く不気味で、人間じゃないみたいだ。
「兄貴っ。やめろ。なんてこと言うんだ」
慎治の背中から、叔父・治彦の低く鋭い声が飛ぶ。
慎治の膝で、両手の拳が指をたてた。指先が真っ白だ。慎治はぐっと顎をひき、膝の間の畳をにらみつけた。
「おまえのせいだ……なんで……慎太は夜中に浜に……」
慎治の喉の奥で、つぶやきは途中で消えた。
一瞬後、慎治は音を立てて片膝をつき、拳を大きく降りかぶった。
「よせっ、兄貴!」「やめなさいよ、お義兄さん!」
治彦夫妻の声が重なり、治彦が慎治の肩を後ろから抱えようとする。
が、慎治の拳が振りおろされる方が速かった。
がつん、と、音とともに畳が揺れた。
慎治は拳を畳に打ちつけ、そのまま頭をがくっと垂れて、立てた膝に埋めた。背中がぶるぶるふるえる。部屋中に獣のような慎治の声が響きわたった。治彦夫妻は中途半端な姿勢のまま固まった。
慎治の吼え声にまじって、く、く、と、鳩に似た音がする。
ああ、この音、前にも聞いた。誠一は思い出した。実の父である晴雄が、火葬場の炉に入れられて、その扉が閉まったとき、母の喉から同じ音がこぼれた。当時、誠一は3歳だったけれど、はっきりと覚えている。
く、く、という、丸く小さな音は、佳乃が胸に閉じ込めようとして閉じこめられないものが、喉からこぼれ出る音だ。うつむいた唇は、きっと血が出るくらい噛みしめられている。
ばたばたと、佳乃の膝の前の畳に、大きな水滴がとめどなく落ちてくる。
誠一は、きっちりそろえた体育座りの爪先を見つめた。爪先が、じわっとにじんで見えなくなった。
と、治彦夫妻が解凍した。
「佳乃さん!」
そろった叫びに、再び誠一が目を上げると、佳乃が真横に崩れ落ちていた。
佳乃の体の向こうに、慎太の小さな白い固まりがあり、その向こうに、拳を畳に押しつけた慎治の体が微動もせずにそびえていた。
動いているのは、慎治と慎太を回るように佳乃のところへ駆け寄った治彦夫妻だけだった。
第一章
そして二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。めでたし、めでたし。
そのとき、村瀬香奈恵の頭に浮かんだのは、おなじみのフレーズだった。
シンデレラも、白雪姫も、眠り姫も、どんなおとぎ話も締めくくられる、その言葉。ハッピーエンドの決まり文句だ。
「なに、どうしたん? 急に黙っちゃって」
向かいの席から問いかけるのは、幼馴染の堀川希美。その頭上から、柔らかい光が降り注いで、茶色い髪に天使の輪を浮かび上がらせた。ハワイアン風のカフェの天窓が、ちょうど席の真上にあるのだ。見開いた希美の茶色い瞳も、透き通ってきらきらしている。白い肌に刷いたサーモンピンクのチークが、顔の輝きに生き生きとした効果を添えている。
人は、自分の道を見つけると、こんなにも輝くものだろうか。精神的にだけでなく、物理的にも。香奈恵は感嘆した。
希美は来春、音大の大学院を卒業し、交響楽団に入団する。専門はオーボエという木管楽器だ。大学3年生の時に全日本コンクールで3位を獲得したものの、就職活動は長引いた。あちこちの交響楽団の欠員募集を待っては応募し、さらなる欠員募集を待つために大学院に進学した。ようやく合格通知が届いたお祝いで、今日は香奈恵と会っている。
香奈恵は目を細めて、希美に見とれた。全身を穏やかな光に包まれてバナナワッフルをつついている。希美ちゃんはフランス人形みたいねえ。香奈恵ちゃんは、どっちかっていうと、日本人形だわねえ。幼いころに聞いた、大人たちの囁き。希美はフランス人形そのものだ。肌を陶器で作られた、アンティークのお宝人形。
「香奈恵、聞いてる?」
希美が身を乗り出して、右手のフォークを香奈恵に向ける。香奈恵ははっとして、プレーンワッフルに半分刺さって止まったままのナイフを進めた。
「ごめんごめん。何の話だっけ。ええと、夢がかなっておめでとう、って、さっき言ったっけ」
「もう! それはありがとうって、さっき言ったじゃん。で、香奈恵は夢とかないの? って聞いてるんだよ。何かになりたいとか、何かをやってみたいとか」
香奈恵のナイフが、また止まった。
「夢、ねぇ」
頭の中がもやもやして、考えがまとまらない。子供の頃から音楽一筋の希美と違って、こちとら何となく文系の大学に進学し、「正社員として雇ってくれればどこでもいい」状態で就職し、営業事務として地味に働いている会社員だ。今の仕事が夢とはいえないが、生活に不満はない。強いて言えば、給料がもう少し多いといいな。ほかになりたいものも、やってみたいものも、思いつかない。
ただ、望むことは……
「う~ん。やっぱり、ハッピーエンド、かなぁ」
「ハッピーエンドぉ?」
「うん。ほら、そして二人はいつまでも幸せに暮らしました、めでたしめでたし……っていう」
香奈恵は真面目に言って、メープルシロップがたっぷりかかったワッフルの切れ端を口に勢いよく放り込んだ。
希美が小さく吹き出した。
「そっか、香奈恵って、かわいいなぁ。うんうん、いつか王子様が現れてほしいよね」
くすくす笑いに、香奈恵はちょっと混乱した。
「王子様? なにそれ」
「ハッピーエンドっていったら、かっこいい王子様と結婚して、お姫様は幸せに暮らすんでしょ?」
「けっこん……結婚? うーん」
香奈恵はナイフとフォークをおいて、眉間に右手の指先を軽く当てた。今度は、希美がきょとんとした。
「なに、その反応は」
「うーん。結婚……は、面倒くさいから、あたし、王子様は、別にいらないなぁ」
希美が軽くずっこけた。
「ちょっと待て。王子様なきハッピーエンドって、なにそれ逆に聞きたいんだけど」
香奈恵は腕を組んで頭をたれた。
「あたしがいいなと思うのは……いつまでも幸せに、何事もなく穏やかに、の~んびり暮らす……そんなハッピーエンドだなぁ。王子様がいると、喧嘩したり、子供ができてママ友づきあいに苦労したり、姑とのつきあいに悩んだり、なんか大変そうじゃない? そういうの面倒くさいから、王子様はいらないわ」
二人のテーブルは、しばし、静寂に包まれた。
ぽとり、と、音がして、香奈恵が顔を上げると、希美のフォークからバナナのかけらが皿に落ちたところだった。希美は、ぽっかり口を開けて香奈恵を見つめている。
「なに、どうかした?」 今度は香奈恵が尋ねてみた。
「う~ん……いや、ええと」
香奈恵はフォークをおいて首をひねった。
「なんて言えばいいか、うーん。そうそう、この間さあ、朝の地下鉄の中で、頭のてっぺんに本物のトンボが止まってるおっさんがいたのよ~。気付いてないのか、わざとなのか、よくわかんなくて、誰も声をかけられなかったんだけど……そう、今、あのおっさんを見た気分」
「と、言いますと」
「24歳女子が、ハッピーエンドに王子様がいらないとか、マジ? 諦め?」
「諦め? ってなによ。ハッピーエンドは”いつまでも幸せに暮らす”ことであって、”二人で”は必須じゃないでしょ」
「……マジだったんですか」
希美は、深く長いため息をついた。
「なに? 何か問題でも?」
「素で不思議そうに、あたしに聞くな」
希美は、ワッフルを大きく切って、バナナと一緒にわしわしとかみ砕いた。
なんだか機嫌がよくないようだが、いったい、何がいけなかったのだろう。香奈恵は小さく首を傾げ、セットのレモンバームティーをすすった。
翌日は月曜日。いつも憂鬱な朝だ。香奈恵は目覚ましを止め、未練たらしく掛け布団を抱きしめてごろごろ転がりつつ伸びをして、ようやく起きあがった。
一人暮らしのアパートは、寝室兼リビングの六畳間のとなりに申し訳程度のキッチンがある。トースターに、冷凍しておいた食パンをぶち込んで、向かい側のバスルームにのたのたと足を運ぶ。洗面台で顔を洗い、髪をとかして出てくると、ちょうど、パンが焼き上がっている。
いつものようにティーバッグで紅茶を入れ、いつものようにテレビをつけて朝食をとる。いつものように歯を磨き、メイクする。いつものように選んだ服を着て、いつものように家を出て、いつもの時間の電車に乗って、定時15分前に会社の入り口に到着した。社長以下5人の小さな貿易会社で、オフィスは雑居ビルの7階奥の一室だ。制服はない。
「おはようございまっす!」
元気よく挨拶して入室するのが、入社時に躾けられたルールだ。
でも、いつものような「おうっす」という、ドスの利いた返事が、今日はない。扉の向こうは、がらんとした気配だ。電気もついていない。
あれ、一番乗り? いつも社長は朝早くから居座っているというのに珍しい。それとも、今日は祝日だったっけか?
香奈恵はバッグから手帳とスマートフォンを取り出して、今日の日付と曜日を確認した。祝日ではない。そもそも、いつものように通勤電車はスーツ姿のサラリーマンで満員だった。世間は平日のはずだ。
創業記念日とか……いや、聞いたことないよ、そんな話は。
香奈恵は、おずおずとドアノブに手をかけ、そっと回した。手応えなく、ドアは開いた。
隙間から、そうっと室内をのぞく。
やっぱり、だれも出勤していないようだ。
足音を立てるのが憚られ、香奈恵はひっそりと室内に入って電気をつけた。
がら~ん。
そう形容するしかない。
事務机の上のパソコンが、社長の机の上の名刺入れや分厚いノートが、棚のファイルが、……すべて、まったく、何も、ない。空っぽの机が、金曜日に退社したときと同じく整然と並んでいるだけ。
……は?
香奈恵は、ゆっくり、しだいに足を早めて、室内を歩き回った。
なんじゃこりゃ。なんで誰もいないのよ?
部屋の隅の金庫は、扉が開けっ放しで、香奈恵は初めて中を見ることができた。もちろん空っぽだ。
「も、もしかして……これが、事務所荒らしってヤツ? つまり空き巣? 泥棒? だったら……ケーサツ、警察、そう、警察呼ばなきゃ。え~と、188? 違う、119? 違う、110? そう!」
ぶつぶつ呟き、電話を探して室内をすばやく見回す。しかし、固定電話が一つもない。なんという徹底した空き巣だろうか。
香奈恵は自分の席にバッグを乱暴において、スマートフォンを取り出した。メモがあったほうがいいかと思いつき、空いた手で引き出しを開ける。
メモもペンもなかった。が、代わりに、何か紙が数枚入っている。香奈恵はスマホをいったん置いて、引き出しの中の紙を取り出した。
最初の1枚に、目が釘付けになった。音を立てて顔から血の気が引いていく。
極端な右肩上がりの癖がある、社長直筆の文字だった。
「ごめんね。申し訳ない。もうダメでした。今月の給料は同封します。この先、ご多幸とご活躍をお祈りします。今日で会社は終わりです。書類を持ってハローワークへ行ってください。お疲れ様」
……はぁ?
2枚目は「雇用保険被保険者離職証明書」とある難しそうな書類だ。「離職理由」の欄が浮き上がってみえた。「1.事業所の倒産等によるもの」という欄に、手書きで大きくチェックが入っている。
その下は、大きめの茶封筒。中を確かめると、年金手帳と、雇用保険被保険者証と、今月分の給与明細と、きっちり税と社会保険料を差し引いた後の手取り金額に相当する現金があった。
ええと、これはつまり……
「今日で会社は終わりです」「事業所の倒産等」……てことは、
会社がなくなっちゃった、ってことですかぁ?
(続く)
#お仕事小説部門 #小説 #オリジナル #創作 #長編小説 #連載小説 #創作大賞2023
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
