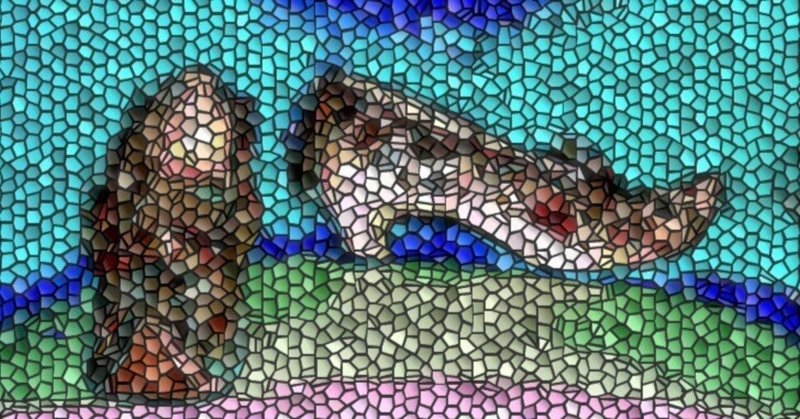
魔法の靴③ コンサートで大砲が鳴りました!
第二章
「年末はいつ帰る?」
スマートフォンのLINEの画面に、簡素な一文がぽつりと座っている。発信者は母親だ。香奈恵はふっとため息をついた。そこへ、新たな緑の吹き出しが現れた。
「お兄ちゃんは、また元旦だけです」
両親は、栃木の商店街で、昭和な雰囲気の荒物店を営んでいる。浅草駅から特急に乗れば、そんなに時間はかからない。でも、今年は帰省に心が動かない。
例年、香奈恵は12月28日の仕事納めの後、すぐ実家に帰り、1月3日までごろごろしていた。一応、大掃除を手伝うために年末から帰るのだが、実家には、早々と子供を作って結婚した弟夫婦がいる。
仲が悪いわけではない。ただ、香奈恵が帰ると、弟の嫁の美也さんは「小姑に手を出されるのは主婦のプライドが許さない」とばかりにきりきり立ち働く。母は母で「東京で疲れてるだろうから、ゆっくりしなさい」という。自分たちは頭に手ぬぐい、割烹着で臨戦態勢なのに、香奈恵には座布団と暖かいお茶と籠に山盛りのせんべいをあてがって、こたつに放り込んでくれる。
従って、年末の実家に香奈恵の仕事はほとんどない。
子供の頃は、ガラス拭きや障子の張り替えを手伝わされるのが嫌でたまらなかった。でも、大人になると、みんなが忙しく働いている家で一人、隠居のお客様状態で座っているのは、なかなか居心地がよくないものだと身に染みた。
香奈恵と一番話があう兄の翔太は、北関東では名を知られたスーパーに就職し、他県の店舗に配属されて実家を出た。年末年始は稼ぎ時で、元旦の夜しか帰ってこない。
母の孫、つまり香奈恵にとっては甥の尚人を中心に、三世代が和む正月に、未婚の小姑で隠居のお客様として混ざるのは、どうも身の置きどころがない。しかも今年は「失業中」という看板も加わっている。
せめて「失業中」を「転職してキャリアアップ」に変換した上で帰省したいものだ。
香奈恵は返信をひとまず先送りして、いったんLINEを閉じた。
と思ったら、またもLINEの通知でスマホが震えた。希美からだ。
「お暇?」
ああ、確認されなくても、ず~っと暇ですよ。知ってるでしょうに、ふん。やさぐれながらLINEを開ける。と、すぐ次の緑の吹き出しが現れた。
「お誘いが二つ~。音大のオケ、年内最後のコンサートが12月10日。定番の第九と、チャイコフスキーの『1812年』です。びっくり演出アリ!はあと」
闇を含んだ白うさぎがニヤリと笑うスタンプを挟んで、また吹き出し。
「その後ちょ~暇……どっかで飲まない? 彼氏ぴょんが『ローストチキンと手作りケーキで、おうちでクリスマスディナーパーティーなどいかが』と申しております。悪いけどイブはだめよん」
頭にお花畑が満開って感じ。香奈恵は目を閉じて、眉間に右手の中指を当てた。
でも、これは希美の優しさなのだ。
香奈恵が失業を打ち明けることが出来たのは、希美だけだった。単なる友達に失業なんて暗い話をまともにしたら「重い」と思われて疎遠にされる。誰だって、大して親しくもない相手の悩みなんて真剣に聞きたくない……男女関係のもつれ以外は。
希美は別だった。幼なじみで、お互い、お漏らしした布団を干されているところまで見て育ったゆえか、なんでもごく自然に話してしまう。たまにしか会わなくても、向き合えば、するっと遠慮やためらいが消える。親同士も知り合いだが、希美の口の堅さは信頼できた。
希美は元気づけようとしてくれている。
香奈恵は眉間のしわをゆるめ、気を取り直して返信した。
「さんきゅ。こっちはいつでも暇なんで……コンサートもパーティーも是非よろ」

12月10日。香奈恵は襟元にフェイクファーがついた白いニットに、黒いベロアのパンツと、お気に入りの黒いバレエシューズでコンサート会場に向かった。クラシックとはいえ学生オーケストラとあって、親しみやすくカジュアルな雰囲気なのがありがたい。
希美が通う音大の大ホールは、ほぼ満席だった。
年末恒例、ベートーベンの交響曲第九番「合唱付き」は休憩を挟んでプログラム後半。前半が「1812年」だ。作曲したチャイコフスキーは知っているが、希美の演奏を除けばクラシックを聴かない香奈恵には、こんなタイトルは聞き覚えがない。
荘厳な雰囲気で始まって間もなく、希美のオーボエが短く、物憂く美しい旋律を奏でた。黒いシフォンのブラウスに黒のロングスカートで、やはり黒を基調とした細長いオーボエの金具が銀色に輝いて映える。体をゆったり揺らしながら軽々と操る希美はかっこいい。その筒先から流れ出る音は、細く繊細だがユーモアたっぷりに膨らんで、ホールの隅々に広がっていく。
再び旋律は弦楽器に引き取られ、希美のオーボエは響きの中に沈む。と、聞いたことがある旋律が、金管楽器のまっすぐな響きで高らかに流れてきた。え、フランスの「ラ・マルセイエーズ」? なんで、チャイコフスキーでフランスの国歌?
香奈恵が首をひねっていると、舞台下手から、黒子の衣装をまとった数人が、あるものを押して登場した。
客席がざわついた。
数人の黒子は、指揮者の近くまで来ると、押してきたものの向きを変えた。スポットライトがひときわ明るく、運ばれてきたものを照らし出す。
木製の大きな車輪2つに挟まれ、真ん中に据えられた、鈍い銀色に光る1メートル弱の筒。その黒々とした円い口が、まともに客席に向けられた。
それは、大砲のように、香奈恵には見えた。
「あれ、アメリカの南北戦争で使われたモデルじゃ……かっけぇ」
香奈恵の真後ろの席から、若い男性の声がした。低い響きが、なぜか耳になじむ。
いや、それはどうでもよくて。やっぱり、あれは大砲なのか。香奈恵はその口がまっすぐ自分を向いていることに気づいた。今すぐ逃げるべきだと思ったが、あいにく列の中央の席で、満員の客席を乗り越えて左右の通路にたどり着くのは至難の業だ。周りの客は席を立つ気配もなく、あろうことか大砲を指さして笑っている。
黒子がなにやら、砲身の後ろでごそごそと作業を始めた。手が空いたらしい1人が自分の耳に両手を突っ込み、体を低くした。まさか、マジで点火する気じゃ……オーケストラの演奏は何事もなく進んでいく。
指揮者が全身を大きく伸び上げて、曲が大きな盛り上がりに差し掛かった。右腕の先の指揮棒が、勢いよく振りおろされる。と……
どごぉ~ん!
香奈恵は反射的に、前の椅子の背もたれの陰に身を縮めた。
どごぉ~ん!
これは、明らかに大砲の音ではないか 。
ここ、音楽ホールよね。戦場じゃないよね。
どごぉ~ん!
ホールの壁を、腹に響く衝撃音が連続してたたく。
香奈恵の周りの客は、なぜか手をたたいて大受けだ。なぜ? みんな、避難しないの?
どごぉ~ん! どごぉ~ん!
衝撃音は5回、響いて止んだ。入れ替わりに、金属の鐘が乱打される音がやかましく響く。なんの騒ぎだろう。
香奈恵がそっと身を乗り出して舞台と客席を見渡すと……砲撃の痕跡はどこにもなく、舞台の一番奥に据え付けたチャペルの鐘のようなものを、黒子の1人が激しく揺らして鳴らしていた。大砲の周囲の黒子はなぜか、客席に向かって整列して正座し、両手をあげて万歳を繰り返している。
黒子が二人、のっそりと立ち上がり、大砲の後ろに回る。立ち上がらない黒子は両耳に指をつっこんだ。まさかまた……
フィナーレ。最後に指揮者が腕を振りおろすと同時に、再び、あの音が響いた。
どごぉ~ん! どごぉ~ん! どごぉ~ん!
舞台の大砲は微動だにしない。え? 映画で見たけど、大砲は撃ったら反動で後ろに下がるんじゃ……
客席から拍手がわき、場内に「ただいまより、15分間の休憩に入ります」と、滑らかなアナウンスが流れる。
「や~、楽譜に『大砲』のパートがある珍曲とはいえ、模型まで持ち出すとは……」「音は録音? シンセサイザー?」「本当に撃ってほしかった~」「室内じゃ無理だよ」
周りで、拍手と一緒に、笑いを含んだ声が飛び交う。
ああ、あれ、模型か……香奈恵は、椅子の背にへたりこんだ。
その上から、低い響きの笑い声が振ってきた。
「あんた、マジで撃ってると思ったろ? 大砲、本物だと思ったのかよ? ごそごそ隠れてんの、あんただけだったぜ」
それは、さっき「南北戦争で使われたモデルじゃ……」と呟いた声だった。香奈恵がむっとして声の主を見上げると、短い茶髪にピアス、あごひげを刈り込んで、ラフなセーターをだらしなく着込んだ、クラシックのコンサートに全く似つかわしくない風貌の若い男性だった。薄い色の澄んだ瞳は、見間違えようがない。
「あれ、あんた」と、男性が香奈恵を指さす。
「あっ」。香奈恵も気づいた。
地下鉄の駅で「そのパンプスはおまえの足に合ってない」と、いちゃもんをつけてきた、あの男だった。
「なんであんたがここにいるのよ」
この男に、模型の大砲にびっくりして椅子の背に隠れるところをみられるとは。不覚だ。香奈恵は頬が赤くなるのを感じた。
「いいだろ別に。てか、おまえこそ。今日も、あの潰れたパンプスかよ」
「違います~。今日はちゃんと、歩きやすいバレエシューズです~」
「ほんとかよ」
「ほんとです~」
「見せてみろよ」
香奈恵は反射的に足をあげようとした。が、そのとき「すみません。邪魔なんですけど」と、後ろからいらいらした声がした。
「あ、す、すみませ……」
香奈恵は謝る暇もなく、そのまま通路側に押し出されてしまった。背中で、低く短い笑い声がしたのが腹立たしい。
後半の第九では、香奈恵はステージに集中し、後ろを全く振り向かないよう最後まで気をつけた。アンコールが終わっても、絶対に後ろを振り向かない。周りの席がだいぶ空いたころ、香奈恵がコートを羽織りつつちらりと振り向くと、後ろはもう空席だった。
は? さよならの一言も無しかよ。
香奈恵は、我ながら理不尽な怒りだと思いつつ、頬をぷっと膨らませた。

希美の「おうちでクリスマスパーティー」は、1週間後だった。シェフは希美の彼氏、拓也くん。料理が大好きな音楽家で、希美の話では「音楽で飯が食えなくなったら、家庭料理の店を開いて食っていく」と決めているらしい。
ま、クリパとはいえ、おうちだし。香奈恵は気軽に、無印良品のタートルネックセーターに両腕と頭を突っ込んだ。色は、お気に入りのターコイズブルー。あとは、いつものジーンズにスニーカーだ。色気のかけらもない。
拓也くんには何度も会っている。オーケストラの金管楽器でひときわ巨大な、チューバという低音楽器を担当している。学部を卒業したら都内のプロオーケストラの欠員募集がすぐ見つかって、今はプロ奏者だ。
希美の住まいは、音大の近くにあるオートロックで防音完璧のマンションだ。香奈恵には贅沢極まりないと思える広いリビングが独立した1LDK。リビングにはダイニングテーブルセットのほかにグランドピアノがある。希美はオーボエ専攻だが、ピアノのほうがキャリアが長い。さすが栃木の元特定郵便局長の一人娘。香奈恵とは生活のレベルが違う。
玄関のドアには、枯れ木とフェルトで装飾されたクリスマスリースが下がっている。すでにオートロックの玄関で到着を伝えてあるので、香奈恵は気軽にドアを開けた。
と、玄関のたたきに脱いである靴が、やけに多いように感じた。
女性もののブーツが3足もある。これはまあ、どれも大きさが同じで色や素材が違うところから、希美のものと解釈して問題なかろう。
問題は、明らかに男性ものの靴が、2足もあることだった。しかも、2足は明らかにサイズが違い、デザインのテイストは似ている。辛子色に近い茶色のスエードのモカシンと、栗色のスエードの巨大なワラビーだ。これを一人の人物の靴と見なすのは無理がある。
てことは……希美の彼氏のほかに、だれか男性の来客がいるということだ……聞いてないぞ……
と、そこまで香奈恵の頭が素早く回転したところで、部屋の奥から希美の声がした。
「あ、香奈恵、来たかな。せいくん、ごめん。ちょっと出て」
せいくん? 希美の彼氏は拓也くんのはず。せいくんって、だれ?
続いて、どたどたと足音がして、かなり高い位置から低い声が降ってきた。
「いらっしゃい……あれ」
スニーカーを脱ぎつつ声の方を見上げると、どこかで見た顔が、細い目を丸くしている。
「なんだ、また、あんたか」
それは、地下鉄の駅で「そのパンプスはおまえの足に合っていない」といちゃもんをつけ、希美のコンサート会場で模型の大砲に身をすくめた香奈恵を「本物だと思ったわけ?」とせせらわらった、あの顔だった。薄い瞳の色。短い茶髪にピアス、だらしないセーターに腰履きのダメージジーンズと、豪奢な音大生向けマンションにはまったくもって似つかわしくない風体。間違いない。あいつだ。
「なんであんたがいるのよ」
「関係ねえだろ」
「ここは、あたしの幼馴染で、栃木きってのお嬢様で、将来有望な音楽家である希美様のマンションよ。あんた、誰の許可でこんなところにいるのよ」
「うっせーな」
「答えないと通報するから」
「通報って、どこにだよ」
「決まってるでしょ、110番よ!」
香奈恵はバッグからスマートフォンをさっと取り出し……取り出そうとしたものの、仕切りがないトートバッグに放り込んだ荷物の地層はあいにく地殻変動が激しくて、スマートフォンは埋まっていた。上層部に浮かび上がったマフラーやティッシュやタオルハンカチの間に手を突っ込み、下層部に沈み込んだ財布やポーチの間をごそごそ探る。
「……もしかして、電話、探してる? 通報にそんな時間かかってたら、犯人、簡単に逃げるぞ」
低い声が嘲笑の響きを帯びる。香奈恵は頬を赤くしてにらみあげた。こうなったら、素手か。たぶん、勝ち目はないが。
「なにやってんの、香奈恵、早くあがってよ……って、なにやってんの?」
言いながら顔を出した希美の語尾が、本気の疑問形になる。香奈恵はバッグから引っこ抜いた手で男をまっすぐ指さし、叫んだ。
「この男! 不法侵入でしょ? はやく110番!」
希美のあごが、かっくり落ちた。ただでさえ大きな目が、こぼれそうにまん丸になる。
「……あ、あのさ。この人、の、こと?」と、右手の手のひらを上に向けて上品な仕草で男を指す。
「そうだよ、決まってるじゃん。こんなチャラそうな男、希美の知り合いにいないでしょ? 拓也くん呼んで! 女2人じゃ危険だよ」
「や、えーと、違……」
希美の口があわあわと動いた。後ろから、ひょいと拓也の大きな体がのぞいた。
「おーい。もうチキン焼けるよ……何の騒ぎだ?」
(続く)
#創作大賞2023 #小説 #連載小説 #連載長編小説 #第九 #チャイコフスキー #連載
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
