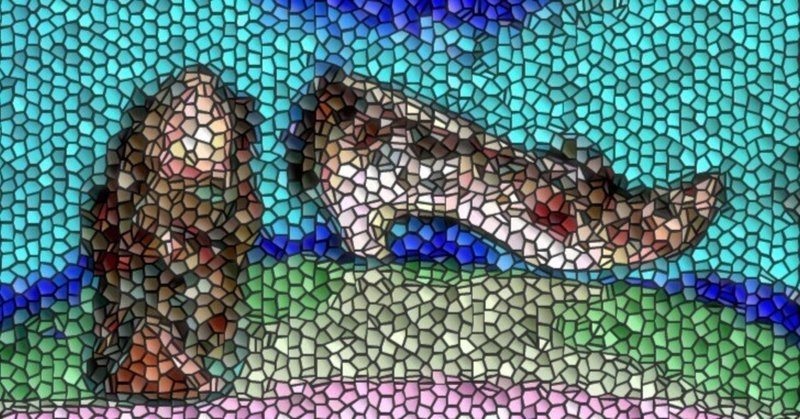
魔法の靴⑨ストーカーの才能ありました!
第五章
都心の駅の近くには、たいがいスターバックスカフェがある。道路に面した窓側の四人掛けのテーブルで、香奈恵と希美と拓也は背中を丸めて座っていた。平日の午後とあって、客席は半分以上空いている。香奈恵の前にはスターバックスラテ、希美はキャラメルマキアート、拓也はクリームたっぷりのカフェモカ。三人ともほとんど手が着いていない。拓也のは生クリームが溶けて、かしいでいる。
香奈恵はハンカチを握りしめて、窓の外を必死に凝視していた。観察に値する対象があるわけではないが、油断すると、目の縁から涙の粒がまつげを越えて転がり落ちてきそうになる。泣くのはまだ早い。誠一が行方不明になったからって、まだ泣くほど親しくはないずだ。
隣に座る希美が、温かい手で背中をなでてくれている。
向かいで、拓也が、何度目かのため息を長く引き延ばした。
「どうしてなんだろうなあ……あいつ」
あいつとは、もちろん誠一のことだ。消えたことを希美から拓也に知らせた。二人は、香奈恵のアルバイトのシフトが入っていない日に会わせて、休みを取ってくれた。
拓也は一足先に、誠一が一人暮らしするアパートも確かめていた。室内から応答はなかったが、郵便物がポストから溢れているとか、ベランダに洗濯物が雨に打たれてほったらかしだとか、そういう不穏な気配はなく、普通に住人が生活している雰囲気だったという。
「オレの見立てでは、あいつの健康を心配する必要はない」と、拓也は断言した。
その根拠は、誠一が仕事を投げ出すように辞めるのは初めてではないからだった。香奈恵からいきさつを聞いて、拓也は言った。
「あいつが前の仕事を辞めたときと同じだ」
誠一は、靴づくりの専門学校を主席で卒業し、最初はシューズデザイナーの卵として順調なスタートをきったという。
「シューズブランドの『ホメロス』って知ってる?」
拓也に聞かれ、香奈恵は目を見張った。
「もちろん知ってるよ」
ホメロスは、都会に住んでいれば知らずにいられないほど有名な、超高級メンズシューズブランドだ。『デザイン、機能、履き心地……我々の靴は壮大な叙事詩である』というキャッチコピーの広告はファッション誌でもおなじみだ。世界的なベンチャー企業経営者やスポーツ界のスーパースターがモデルになった広告写真は、香奈恵にとってはおとぎ話の絵本と同じ扱いだ。
誠一はそこに入社したという。もちろん正社員として。
「え~っ」。香奈恵は両手で口を抑えた。
「誠くん、ほんとに才能があるんだね」。希美がひゅ~っと口笛を吹く。
「だけど、3年たって、あいつ、突然辞めちゃったんだ。今回みたいに無断欠勤して、そのままクビ」
「なんで?」「もったいない!」 香奈恵と希美の声がそろった。拓也はむっつりうなずいた。
「もったいない話だ。理由を聞いたけど、さっぱり要領を得なかった。直前まで楽しそうに仕事していた。休日に誘っても『お前とつるむより靴を作る方が楽しい』って失礼な断り方しやがって」
「実はスランプだったとか?」
「到底そうは思えないな。本当に嬉しそうだった。そうだ、あの時もチームリーダーに抜擢されたんだ。なのに翌日から会社に行かなくなった」
なるほど。今回と同じだ。抜擢されたところで糸が切れた凧みたいにいなくなった。
「あいつに誘われて一緒に飲んだことがあるホメロスの社員から、オレに捜索のメールが届いたんで、事情がわかったんだよね」
「抜擢されたのに、どうして」。希美が首をかしげる。
香奈恵は、いなくなる前日、抜擢された瞬間の誠一を思い出した。みんなに拍手されていたのに、挨拶のために前に出た誠一は、凍り付いた顔だった。今考えると、何かに追いつめられた表情にも思える。でも、何に?
「ホメロスを辞めたときは、誠くん、どうしていたの?」 希美が拓也の話の先をせかす。
「しばらく連絡が取れなくて、何をしていたのか詳しくわからない。でも、一つだけわかったことがある」
「なに?」 香奈恵と希美の声が、またそろった。
「靴づくりは止めてなかった」
拓也は自分の言葉にうなずいた。
「ある日、あいつから電話をしてきたんだ。『おう、オレだよ』と、何事もなかったみたいに。で、『靴、作らしてくんない?』と来た。そんで、今履いているワラビーを作ってもらったんだ。どうして仕事を辞めたのかも、いなくなった理由も、一切何も話さずに、答えの代わりみたいに靴をくれた。これが、ものすげぇいい靴だもんで、もう大丈夫だなと思って、オレも聞くのをやめたんだ」
希美が、よくわからん、という感じで頭をゆっくり振った。
香奈恵は窓の外をぼんやり眺めた。何か、かすかな糸口をつかんだような気がする。
仕事を投げ出しても、靴づくりは止めなかった……今回も同じかもしれない。
ということは、もしかしたら、あそこにいるのではないか。

山手線から私鉄に乗り換えて約30分。都内でも有数の商店街を抱える急行停車駅で降りる。
数ヶ月前にたどった風景を思い出しつつ、香奈恵は商店街のアーケードに入っていった。約1キロメートルは延びている商店街の外れまで歩く。アーケードが終わったところに、昭和な雰囲気の「たばこや」の看板がある。そこを曲がると、記憶通りに、その場所があった。
間口が狭い入り口に、見過ごしそうな、地味な手書きの看板。
「真下靴工房~open」
ふらりと立ち寄るには敷居が高い雰囲気の、丸いノブがついたベニヤの扉は、今日も閉まっている。横の壁の、よく見ないと気がつかないところに、小さなベルのマークがついたボタンがある。
ゆっくり手をあげ、ボタンに人差し指をつけ……香奈恵はしばし止まった。
工房というものは、もしかしたら事前に予約を取ってから来るべきなのだろうか。でも、今さら電話をかけて、なんて言う? 「今から行ってもいいですか? 1秒で着きます」……怪しすぎる。
香奈恵は人差し指に力を入れた。
ブー。
古めかしいブザーの音が、建物の奥で鳴り響く。ばたばたと雑な足音が近づいてきて、ベニヤの扉が押し開けられた。
「いらっしゃいませ……おや」
顔も体も固く締まった真下が顔を出す。その低い肩越しに、細長い工房の奥が垣間見える。
色とりどりの革がつっこまれた棚の下、古びたミシンに向かう背中が一つ。
デニムのシャツの背中に、頑丈そうなキャンバス地のエプロンのひもが交差している。細身の長身が小さく折り畳まれて、ミシンをのぞき込んでいる。
「覚正さん!」 叫びが口からほとばしる。
真下がドアに手をかけたまま、首をねじって振り向く。同時に、ミシンに向かった体がひねられ、顔がこちらを向いた。細い目、ライオンみたいな大きな鼻……誠一だ。
が、雰囲気が違う。香奈恵は一瞬、おののいた。茶髪だったはずの髪は脱色されてほぼ真っ白。耳だけでなく、鼻にもピアスが光っている。知った仲でなければ、香奈恵はまず間違いなく近寄らない風貌だ。有り体に言って、怖い。
が、誠一は、香奈恵の顔を認識した瞬間、身を縮めた。瞳が不安そうに開かれ、唇がふるえる。
「どうしてここに……」低い声がくぐもる。
それを合図に、香奈恵のまつげを次々に乗り越えて、涙が頬に伝わった。
「どうして、いきなり、いなくなっちゃうの! あたしを置いて、何してたのよ!」
自分でもびっくりする大声がほとばしった。誠一は明らかにひるんだ。
2人の間で、真下が固まっていた。

香奈恵を招き入れ、熱いお茶を入れてくれて、真下は「ちょっとコンビニに行ってくる」と、姿を消した。工房には誠一と香奈恵だけが残った。
香奈恵は涙を止めようと力を込めた。ところが目からこぼれるのを止めた涙は鼻の内側を流れ落ちる。
まずい。鼻をたらすわけにはいかない。お茶と鼻水を一緒にすすって、盛大にむせた。バッグからティッシュを取り出そうとしたが、あいにく、中身の荷物が地殻変動を起こしていて、ティッシュが埋もれている。不格好に片手で鼻を押さえて片手でごそごそ探る。
誠一が無言でティッシュボックスを差し出した。「ありがと」と、あわただしくティッシュを抜き出し、鼻をかむ。
「人前で鼻をかむな」
やっと誠一の声が聞こえた。
「すびばせんね」
香奈恵が謝り、誠一は吹きだした。笑ってくれた。
「なんでオレがここにいるってわかったんだ?」
「……なんとなく」
「ストーカーの才能あるな」
「失礼な」
香奈恵は、誠一が差し出した屑入れにティッシュを丸めて放り込んだ。
本題を切り出す。「クッカで、みんな心配してるよ」
誠一は下を向いた。香奈恵は続けた。
「なにより、お客様が、もう大変なんだから。『覚正さん、今日もお休みですか?』って。がっかりして帰っていくの、見るの辛いよ」
誠一は固まって動かない。
「覚正さんがいないと、みんな困るんだよ」
「……オレは」
とても低い呟きが、誠一の白髪の下から聞こえた。
「……オレなんか」
声は途切れた。誠一はぴくりとも動かない。
「今、オレなんかって言った?」
香奈恵は苛立った。
「何それ。みんな、覚正さんが頼りなんだよ。なのに『オレなんか』とか、何それ」
「やめてくれよ」
低い声が割れた。
「オレは、頼られたり認められたりしちゃ……いけないんだよ」
「え……」。香奈恵の唇が凍った。誠一の言葉は耳に入ってくるが、意味が分からない。
「オレなんか、頼りにすんなよ。オレは……認められちゃ、いけないんだよ」
「意味わかんない」。香奈恵は爆発した。「覚正さんは知識が豊富で接客も熱心で、お客様の信頼も厚くて、靴が好きで頑張ってるのに。なんでよ」
「だめなんだ」
誠一は下を向いたまま怒鳴った。香奈恵はびくっと固まった。
「オレは。一人で認められて誉められちゃ、だめなんだ。あいつを置いて、一人でなんて……だめなんだ」
「あいつって誰?」
「しんた……」
誠一の声はまた、聞き取れないほど低くなった。
ガチャリと音が響き、ベニヤの扉が開いた。工房の空気が動く。香奈恵は風の元を振り向いた。真下が「ただいま」と、陽気に帰ってきた。
立ち上がろうとした香奈恵より、誠一の方が早かった。
傍らの椅子にひっかけていたショルダーバッグを乱暴に引きむしり、真下と入れ違いに扉のほうへ大股に歩く。
「オレ、今日は帰ります」
言葉を放り投げ、誠一は扉を外から音を立てて閉めた。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
