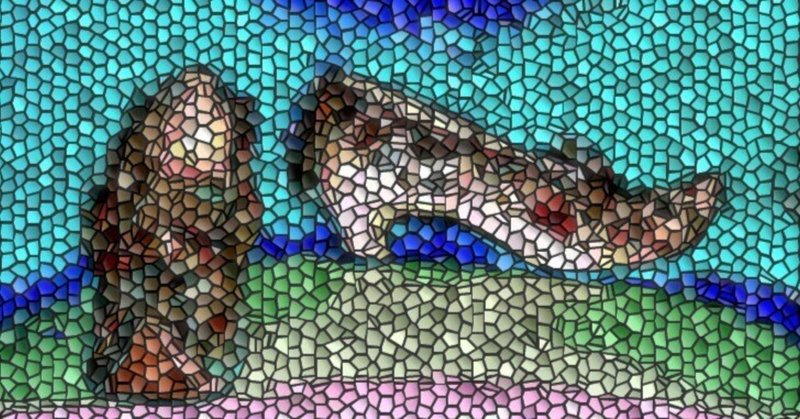
魔法の靴㉑親と子って何なんでしょうね?
香奈恵は、品川駅での、小倉少年との別れ際を思い出していた。
「ねえ、慎太くんに、あの神様の話をしたのは、誰なの?」 香奈恵は、歩きながら小倉に問いかける。
「いま、思い出しました」。小倉がかすれた声を出す。
「絵本じゃなかったです。慎太は、あの話を、直接教えてもらったそうです。誰にも内緒の話で……男と男の約束だぞって言われたから、内緒なんだって」
「男と男の約束?」
香奈恵は立ち止まった。小倉も立ち止まる。
「あれは、お母さんに読んでもらった絵本じゃないの?」と、香奈恵。
「違います」と、小倉はきっぱり否定した。
「はっきり思い出しました。お兄ちゃんが、僕に教えてくれたんだ。慎太は、そう言ってました。で、慎太は僕にも、男と男の約束だから内緒にしてねって頼んだんです」
「お兄ちゃん?」
「そう、お兄ちゃんでした」

「……オレなんだ」
誠一の笑顔は、力なく爽やかだった。
「高校に入る直前、オヤジに『医者になるのは許さない』と断言された。そのとき、オヤジにとって息子は慎太だけなんだと、心から理解した」
佳乃の両手首を握る誠一の手に力がこもるのがわかる。
「もともと、オヤジはオレを息子だと思っていなかった。最初からわかってた。でもオヤジなりに、オレを責任持って育てようとしてくれた。それもわかってた。なのに慎太が生まれて、すべて変わってしまった」
誠一は短い笑いとため息をもらした。佳乃がうつむいた。
「慎太だけが、オヤジの息子だった。慎太だけが、オヤジの宝物で、自慢だった。オレがどんなに頑張っても、オヤジは誉めないどころか目もくれなかった。中学で学年トップになって、トップクラスの県立高校の理系コースに合格したことも、言うまで知りもしなかった。オヤジがオレに笑顔を見せるのは、慎太をかわいがったときだけだった。慎太をかわいがることしか、オレがオヤジに認めてもらうすべはなかった」
誠一の声は割れた。
「飯を食わせてくれるのも、学校に通わせてくれてくれるのも、ブラスバンドをやらせてくれるのも、オヤジだから、感謝はしてた。母さんは、父さんが死んでからずっと必死だったし、オヤジと一緒に幸せになってほしかった。慎太もオレになついて、かわいい弟だった。オレが我慢して『オヤジがこっち向いてくれない』なんて子どもじみた妬みを捨てれば、すべてうまくいった。でも」
顔が赤くなって歪む。
「高校に合格して、入学手続きの相談をしたら、オヤジは言ったんだ。『慎太がパイロットになりたがっている。うちは、慎太をパイロットにするので精一杯で、おまえを医者にする金はない。高校は仕方がないから通わせてやるが、卒業したら店を手伝え』って。国立大しか受験しないし浪人もしない、奨学金も使うと言ったのに、許してくれなかった」
誠一は、涙の固まりを飲み下したようだった。
「それから、真剣に思うようになったんだ……慎太さえいなければよかったのに。慎太がいなくなればいいのにって。そんなこと、考えちゃいけないとわかってた。忘れようと頑張った。けど、駄目だった。日に日に強くなるばかりだった」
「誠一は悪くない。私が岡野を説得できればよかったの。私が悪いのよ」
悲鳴のような佳乃の叫び。誠一は首を振った。
「馬鹿なガキだったんだ。今にして思えば、オヤジの承諾なんかなくたって、勝手に大学を受験して、返さなくていい奨学金をもらえる成績を取るとか、どうにでもなった。でも、オレは諦めた。全て慎太のせいにして、慎太さえいなければと思い込んだ」
香奈恵に向ける誠一の目は、透明で、うつろだった。
「あの夏、慎太が星座に興味を持ったので、星座の神話をいろいろ話してやった。あいつは全部本当のことだと思い込んで、神話の英雄や神様に会いたがった。それで、ふと思ったんだ。海の神様が湘ガ浜の沖に集まったら、あいつは会いに行くんじゃないか? 新月の夜なら浜辺は暗いし、あいつはまだ大潮をよく知らない。普段は見えない岩が沖に現れたら、神様だと信じて近づくんじゃないか? そして潮が満ちれば……うまくいなくなってくれるんじゃないかって」
「でもさ」。香奈恵はそっと口を挟んだ。「そのやり方は、確実じゃないよね。慎太くんが神様を信じて会いに行きたがっても、家を抜け出せないかもしれないし、眠くなって出かけないかもしれない。浜辺に行っても沖までは進まないかもしれないし、引き潮の間に戻ってくるかもしれない。慎太くんが亡くなる保証は、どこにもないよね?」
「そうだな」。誠一は寂しそうに笑った。「実際のところ、本当に慎太が死ぬなんて、思っちゃいなかった。ただ嘘を教えて、いたずらして鬱憤を晴らしたかっただけだ。慎太を言いくるめて浜辺に出向かせて、それで慎太が無事に帰ってくれば、たぶんオレは、ああよかったと安心しただろう。殺そうなんて思うわけがない。小さくて、いつも汗と砂まみれで、やんちゃで、なついてくれて……オレを尊敬して。大事な弟だったんだ」
誠一の目の縁が真っ赤になっている。
「あいつが何も言えなくなって帰ってきたとき、オレは……そう仕向けたくせに、なんで本当に夜中に抜け出しやがったのかと、慎太を恨む気持ちすらあった。悔しくて、空しくて、悲しくて、あんな話をした自分に腹が立って。死んだ慎太にも、慎太が抜け出すのに気づかなかった母さんにも怒りを感じて……どうにもならなかった。誰もかれも、弟を亡くしたオレを気遣うばかりで、何かしたかと疑うことは一切なかった。だからオレは、行き場がなくなって、家を出たんだ」
誠一の手から力が抜けた。佳乃の両手が緩やかに離れた。
「そうか。あいつはオレの夢をかなえるために、沖に行ったんだな」
短い笑い。がっくりうなだれるその体を、自由になった両手で、佳乃がしっかり抱きしめた。
胸の中の誠一を見下ろす佳乃の顔は柔らかだ。
佳乃は、すべてを知っていたのかもしれない。誠一が慎太の死を願ったことを知っていたからこそ、自分の心ない噂に一切反論せずに受け止めてきたのではないか。そうすれば、誠一に疑いの目が向くことはないから……香奈恵はふと、そう感じた。

佳乃は、おかわりのチャイを作っている。
抜け殻のような誠一に、香奈恵はおずおずと声をかけた。
「なんで、あたしを止めなかったの?」
誠一がのろのろと顔を上げる。すべてを吐き出したあとの、空虚でさっぱりした表情だ。
「あたしが、十年前の慎太くんの事故を調べようって言ったとき、止めてよかったのに。本当のことがわかったら困るのだったら、調べるなって言えばよかったのに」
「ああ、そうかもな」。誠一のうつろ瞳の奥に、何かが隠れている気がする。
「原因があったとしても、やっぱり慎太くんは事故で亡くなった。あたしは今日のことを誰にも話さないよ」。香奈恵は身を乗り出した。
「ああ」
のろのろと誠一の両手が伸びてきた。香奈恵の肩に両手がかかり、徐々に手の間隔が狭くなる。
「わかってる……本当のことを知ってるのは、おまえだけだ……」
感情がない低い声の響き。香奈恵の背筋の毛が一斉に逆立った。
いまや、誠一の顔は、香奈恵のすぐ目の前に迫っていた。その瞳に隠れていたのは……後悔、恐怖……自暴自棄? 誠一の息が荒くなる。
知っているのは、あたしだけ。あたしさえいなくなれば、みんな元通りになる。邪魔なのは、あたしだけ。
誠一の両手が、ほとんど香奈恵の首元にかかった。そのまま上に上がり、香奈恵は自然に仰向く形になった。首を絞められる……?
次の瞬間、誠一の左手が香奈恵の後頭部を支え、その唇が唇に重なった。頭が一瞬で真っ白になる。
気づくと、誠一の瞳が、温かく穏やかに、香奈恵をのぞき込んでいた。抱きしめられる。
「ありがとう」
誠一の低いささやきが耳をくすぐる。
「え?」と、聞き返す。誠一は香奈恵の身体を離さない。
香奈恵の耳元で、誠一はひとり言のように呟いた。
「おまえが慎太の事故を調べようと言い出したとき、オレ、ガキみたいに期待した。おまえなら、もしかしたら違う結末に連れていってくれるんじゃないかと思った。ずっと、慎太の事故に事実と違うストーリーを探し歩いて、慎太を死なせた誠一と違う自分になりたくて、あがいていた。でも、事実は変えられない。オレはやったことを認めて、向き合って、初めて前に歩いていけるんだ……教えてくれたのは、香奈恵だ」
「そんな」。香奈恵は両腕を誠一の背中に回し、力を込めた。「お礼を言うのは、あたしだよ。誠一さんは、あたしに、前に進める魔法の靴をくれたんだから」
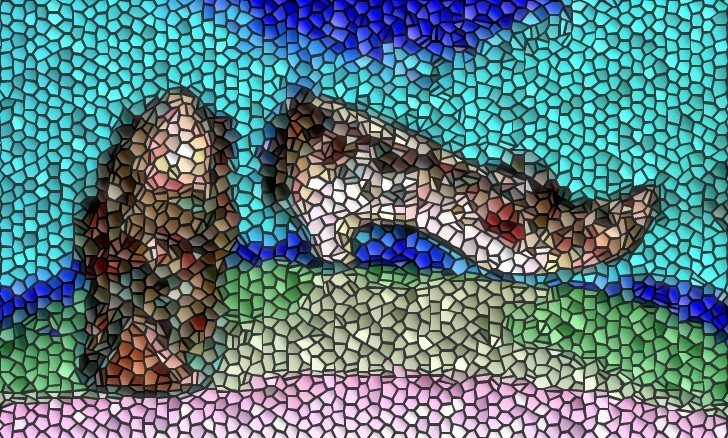
第十二章
それから、香奈恵は一人になった。
毎日、クッカに通勤し、お客様のスニーカー選びに専念した。夜は真っ直ぐ帰って半身浴で疲れを癒した。
休みの日にすることは、掃除と洗濯くらいになった。
誠一は、佳乃の靴を作るため、真下の工房に引きこもっている。今後のことは「自分の心を決めたら連絡する」と言われ、香奈恵は待つしかなくなった。
希美とは相変わらず連絡がつかない。
香奈恵は風呂場の天井の黴をモップで丁寧に拭いている。予定がぱったり途絶えて以来、家じゅうの汚れ落としに専念してきた。風呂場の天井をきれいにしてしまえば、もう、狭い家で磨き上げるべきところはほかにない。
もうじき、世間はお盆休みだ。クッカのバイトもローテーションで休みを取れる。さて、どうしよう。
ついに天井はピカピカになった。これで、季節外れの大掃除をする余地はどこにもない。コーヒーを入れて焼きドーナツを齧りつつ、ベッドに放り出してあったスマートフォンを手持無沙汰にいじくる。と、母からLINEが届いていた。
「元気ですか? 忙しくて大変だね。お盆にでも、たまに顔を見せてくれると嬉しいです」
そう言えば、今年は、失業を言えなくて実家に帰らなかったから、一年半以上、親の顔を見ていない。お盆なら、年末と違って、大掃除のさなかにお客様扱いをされて身の置き所が無くなる恐れはないのではないか。もはや失業中ではないわけだし。
今なら、帰省してもいいのではないだろうか。

久しぶりに降り立った栃木の駅は、蒸し暑かった。海から遠いせいか、蒸篭に入った肉まんになった気分だ。
ロータリーに、父親の軽自動車が止まっている。迎えに来てくれたのだ。助手席のドアを開けようとした香奈恵の手が、一瞬、たじろいだ。運転席にいたのは弟の妻、つまり義理の妹の美也だった。
と、美也はすばやくシートベルトをはずし、上半身を大きく伸ばして内側から助手席のドアを開けた。そのまま、華やかな笑顔で真っ直ぐに呼びかけてくる。
「香奈恵おねえさん、お帰りなさい! 早く早く。後ろ、車が来てるから」
香奈恵は焦って助手席に体を押し込んだ。美也の真っ直ぐな声が明るく飛んでくる。
「しばらくです~。お正月にいらっしゃらなかったので、さびしかったですよぉ。やっぱり家族がそろわないと、なんだか物足りなくってね」
そうか、あたしは家族なんだ。香奈恵は、妙な気分になった。父と母と、弟夫婦と幼い甥。それだけが家族で、独立した兄と、一人暮らしで未婚の小姑である自分は、余計な付属物のような気がしていた。
美也は、実家の門で香奈恵を降ろし、そのまま、父と弟を手伝いに、商店街の荒物屋に向かった。香奈恵は一人、玄関の扉を開ける。
「あら、お帰りぃ」
母の声が、廊下の向こうから、当たり前のようにのどかに聞こえた。
ダイニングテーブルの椅子に座る。香奈恵が子供のころから使っていた、うさぎ柄の京焼の湯呑が出てきて、お茶が注がれた。
「これ、まだあったんだ」
香奈恵が言うと、自分の湯呑に茶を注ぎながら、母親が笑った。
「そりゃ、あるわよ。香奈恵の湯呑なんだから」
気付けば、ダイニングテーブルには椅子が六脚とベビーチェアが一つ、計七人分の場所があった。香奈恵が無意識に座ったのは、子供のころから掛けていた場所だ。首を回すと、無駄に広い居間のテレビの前には、見慣れた大きなちゃぶ台があり、その脇の壁に座布団が十枚も積んである。隣の襖は明け放たれ、奥の部屋の小さなベッドで、二歳になる甥が眠っている。
見慣れたものばかり。部屋の匂いも子供のころと変わらない。番茶の味も、昔と同じ。卓上の籠に積まれたせんべいは、いつもの歌舞伎揚げだ。
あたしの居場所は、いつでもここにあったんだ。「身の置き所がない」なんて、どうして思ったんだろう。
「お茶、熱いよ。麦茶かなんか、ないの?」
香奈恵が文句を言うと、母はおどけた顔で口をとがらせた。
「暑いときには熱いお茶が病気知らずなんだよ」
ああ、母の夏の口癖だ。
母はせんべいを齧りながら、テレビの料理番組をちらちら見る。「あら、こういうやり方もあるのねえ。今度、やってみようか」といいつつ、メモをする様子はない。昔からそうだった。
「お母ちゃん。あたしね、仕事変えたんだ」
さらっと言えた。
「ああ、そうなの。今度は、どんなお仕事?」
母も、さらっと受けた。香奈恵の心が、ふわっと軽くなった。
「靴屋さん。大手の靴メーカーの直営のお店でね。まだアルバイトだけど、頑張れば正社員になれるかもしれないの」
「あらそう。それで年末年始は忙しかったんだね。風邪ひかなかった?」
「うん。大丈夫。……あの、ごめんね。あたし、嘘ついてた」
香奈恵は湯呑を両手で抱えてうつむいた。
「あら、なぁに」と、問いかける母の声は平静だ。
「年末年始、仕事が忙しくて帰れないって言ったでしょ。実は失業中だったんだ。前の会社がつぶれちゃって、次の仕事がなかなか見つからなくて。今の靴屋さんにバイトで入れたのは、今年の春なの。失業って言いづらくて、嘘ついた。ごめんなさい」
母は、しばらく何も言わなかった。恐る恐る、上目づかいに母を見上げる。
そこには、佳乃と同じ、包み込むような温かい笑顔があった。
「そう。大変だったんだね。頑張ったね。香奈恵はおっとりしてるけど、根は強い子だから。お母さん、あまり心配はしてないよ」
ふと頭をよぎったのは、希美の涙だった。「お気楽で中途半端な甘ちゃん」なあたしが、頑張った? その言葉に値する努力を、あたしはしたことがあるのだろうか。
「ううん、あたし、頑張ってなんか、ないよ」
言いながら、ふいに涙が勝手に盛り上がり、瞼を越えた。母が目を丸くする。
「おや、どうしたの?」
「あたし、ぜんぜん頑張ってないよ。頑張ってるのは希美なんだよ。あたしは、希美と違って駄目なやつなんだよ……」
泣き声に言葉がぐじゃぐじゃになる香奈恵の背中を、母がゆっくりなでる。
「希美ちゃんと、なにかあった?」
静かな母の声が、心のブレーキを振りほどく。香奈恵は、希美のデビュー演奏会での出来事を、行ったり来たりしながら打ち明けた。
「あたし、ずっと励ましてもらってたのに、希美にひどいこと言った。それまでも、希美と違ってあたしは適当に暮らせればいいみたいなことばかり言って……夢に向かって頑張ってる希美は、どんなに苛々してたか」
「希美ちゃんは、努力してるところや泣いてるところを人に見せたがらない子だからね。昔から、香奈恵のお姉ちゃんみたいだったよねえ」
香奈恵の胸に、すとんと何かが落ちた。希美の強さを、同じ年の香奈恵には見えなかった視点から、母は理解していたのだ。
「希美と、連絡が取れないんだよ」
香奈恵が言うと、母はくすくす笑った。
「妹みたいな香奈恵に、弱いところを見られちゃって、どうしていいかわからないんじゃないの?」
似たような話を誰かに聞いた。拓也だ。「香奈恵ちゃんにあたっちゃって、決まりが悪いからじゃないかな」と言っていた。
香奈恵と違う立場で希美を知っている人たちは、香奈恵が悪いとは言わない。不思議だ。
母が軽く手を打ち合わせた。
「そうそう。希美ちゃんも帰ってきているみたいだよ。遊びに行ったら?」
「でも、希美はあたしに会いたくないんじゃないのかな。LINEもずっと未読だし」
「直接会うほうが、話が早いこともあるんじゃない?」 母はいたずらっぽく目をくるめかせた。「子供のころは、電話だのLINEだの、なくても遊んでたじゃないの」
(続く)
#############################
1回目から読みたい方はこちらからどうぞ↓↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
