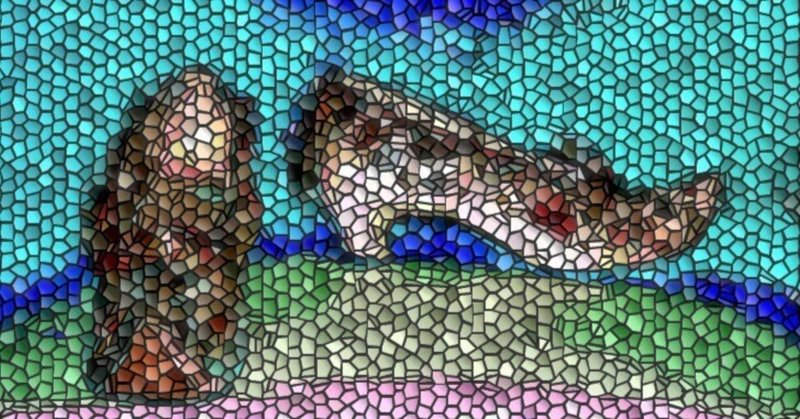
魔法の靴⑧抜擢されたらバックレました!
「なんか生き生きしてるね」
フルーツ山盛りのスイーツで話題の新しいカフェで、白く磨きこまれたテーブルの向こうから、希美が顔をのぞき込んできた。
生き生きしてる? あたしが? 香奈恵は反射的に、両手で頬を包んだ。
「仕事、順調なんだね」。希美が微笑んだ。
「まあ、なんとか。覚えることがたくさんあって大変だけど、わりと面白い。体はきついけどね、立ち仕事だから」
「ふーん。目がきらきらよ。よっぽど楽しいんじゃない? もしかして、職場に、気になる人とか、いるの?」
「気になる人……」。言葉が途切れた。ぽんと浮かんだのは、もちろん誠一の長い顔だ。が、ぶるぶる頭を振って追いやる。「いや、そんなんじゃなくて」
「はああ、いるんだ~」。希美の声が弾む。
「いや、別に、覚正さんはどうでもよくて」
「覚正……誠くん? 気になる人って、誠くん? わああ」。希美が、両手で口を覆って、大げさにのけぞった。ほっぺたがピンクになっている。
む? あたしは今、失言をしたか。あっ……なんで誠一の名前なんか、こぼれちゃったかな。
右手をぶんぶん顔の前で振り回し「そんなんじゃなくって!」と、強調する。にやにや笑う希美の流し目を何とかしたくて、お返しに尋ねてみる。
「そっちこそ、プロのオーケストラはどうなのよ。かっこいい人、いる?」
「拓也よりいい男なんて、この世にいるわけないじゃん」。即答。大変失礼いたしました。
「でも……」と、希美は顎に人差し指を当てた。こいつがやると様になるのが憎らしい仕草だ。「目標になる人は、いるよ。オーボエのトップの原田さん。ストイックで厳しいけど、音がすごく豊かなの」
「ふーん」。音楽の話はよくわからない。でも、大筋は共感だ。「目標になる人がそばにいるって、いいもんだね」
「そうだねぇ……誠くんとか」。また、小憎らしいにやにや笑いが始まった。
香奈恵の頬が勝手に赤らむ。頭に血が上る。すると、あろうことか、口が自動的に誠一を語りだしてしまった。何のスイッチが入ったんだろう。
「覚正さんの、靴にかける情熱って、すごいよ。職人魂かな。既製品選びをお手伝いするのも、すごく真剣。売場の靴を、中敷きを調整して、魔法みたいに、お客様にぴったりの靴にしちゃうの。あれは、かっこいいよ。あたしもいつか、ぴったりの靴にする魔法ができるかな~って」
「お」。希美の目と唇が丸くなった。「夢なんかない香奈恵ちゃんが、夢を語れるようになったか!」
「夢?」 香奈恵は戸惑った。「うーん……夢ってほどじゃ……夢っていうのは、覚正さんの靴や、希美のオーボエみたいに、一生見つめて追いかけていく何かでしょ。あたしは、ちょっと覚正さんの魔法がかっこいいって思っただけで、そんなに強くは……」
「でも、夢のしっぽをつかんだかもしれないじゃん?」 希美はフレッシュマンゴーがぎっしり詰まった巨大なロールケーキをつついた。「それ、大事。あたしだって、はじめから『オーボエを一生やる!』と、はっきり思っていたわけじゃないし」
「そうなの? 意外」
「中学のとき、いい音が出るな~と思ってオーボエを習い始めたけど、ピアノのほうが好きだったし、音楽高校では最初はピアノ科だった」
「そうだっけ」
「そうだよ~。大学受験は、ぎりぎりまで悩んだよ、ピアノでいくか、オーボエにするか」。希美は腕を組んで目を閉じた。
「大学はオーボエで受けたよね。なんで?」
「それはね~」と、希美は目を閉じたまま、右手の人差し指をたてた。「オーボエの方が浪人しなくてすみそうだったから」
「えっ、そんな理由?」 ずっこける。「希美はオーボエ一筋と思ってた」
「いやいや。あたし、ちっちゃいときは『ピアニストになりたい』って言ってたじゃん。音大をオーボエで受験することに決めたとき、実は、けっこう、挫折だったのよ。あたしのピアノは現役で音大に入れるレベルじゃないって思い知ったんだから」
「えっ希美が挫折!」 心底おどろく。栃木で特定郵便局長を長くやっていた名家の一人娘で、蝶よ花よと育てられ、何かを諦めたことなんてないと思っていた。「音楽家になりたい」って、ジャンル指定で「ピアニストになりたい」だったっけ? 幼馴染でも他人の「夢」なんてそんなものか。
ただ、幼稚園の教室で、希美はおもちゃのピアノの前から離れず、ずーっと鍵盤をポンポンたたいていた。広い敷地の邸宅の離れには希美専用のグランドピアノがあって、子供のころに遊びに行くと、希美はいつもピアノを弾いていた。それはよく覚えている。
「あたしが挫折を知らないとでも思ってた?」 希美は勢いよくマンゴーロールケーキの固まりを口に放り込んだ。
「うん」。正直に頷く。「だって、子供の頃から音楽が大好きで、ずっと音楽をやっていて、めでたく仕事になってるじゃん? 希美はいつだって、未来を真っ直ぐ見つめて、折れずに歩いてきたと思ってた」
「ま、そのほうがかっこいいから、嬉しいけどね」。希美は曇りのない笑顔を浮かべた。
「覚正さんも、挫折とか、あったのかな?」 ぽろっと口からこぼれた。
「お、また誠くんかい?」 希美がにやにや笑う。せっかくかわいいのだから、油断のならない表情なんかにならないでほしいもんだ。
でも、希美はすぐ、真面目な顔に戻った。
「誠くんは、挫折してると思うよ」と、ぽつりと言う。
「そうかぁ? あんなに靴が大好きな人が……」と、言いかけて、はっと口を押さえる。思い出した。
「この間、メールしたじゃん。誠くんは昔、医者を目指していたんだって。高校は理系コースで、靴職人じゃなかったはずだよ」
「そう……だったね」
靴職人の工房で、窓から差し込む柔らかい光に照らされた、誠一の不思議な表情。笑っているのか、泣いているのか。「夢を追いかけるのは、当然の権利じゃない。目指せるのに最初から諦めたら、死んだヤツに失礼だ」と言った低い声。「誰か死んだ人がいるの?」と、不用意なあたしの質問に、黙り込んだ固い顔。
「でも、誠くん、どうして医者を諦めて、靴職人を目指したんだろうね」。希美が首を傾げる。
たしかに不思議だ。小さな弟を亡くしたからといって、どうして医者を諦めなくてはならなかったのか。そして、なぜ、まったく畑違いの靴づくりに情熱を見いだすことができたのか。
靴への夢を語る誠一の真っ直ぐな瞳の奥に、何かが隠れているような気がする。
聞いてみたい。みぞおちのあたりが、甘くうずいた。誠一の心の奥を、覗いてみたい。
でも……と、頭が冷える。香奈恵と誠一の距離は、そんなに近くない。弟を亡くしたことも、本人からは聞いていない。不躾で詮索好きなやつだと思われはしないかと、急に心配になる。
希美から聞かなきゃよかった。聞かなかったことにしよう。本人の口から、そのうち聞こう。
香奈恵はアップルティーをすすって、イチゴとキウイのタルトにナイフを差し込んだ。

売場は違っても、香奈恵は毎日、誠一の背中を追った。と言うより、自然に目が誠一をとらえた。
スニーカーの品番は、毎晩、お風呂の中で復唱して覚えた。
一口にスニーカーといっても、実はとてつもない種類がある。ごついスタイルと、柔らかくて足の形に近いスタイル。底が厚いのと薄いの。かかとが深いのと浅いの。底の形が平らなのと、イボイボがたくさんついているの。歩く人に向くタイプ、走る人に向くタイプ。普段、街中で履けるラインと、テニスなど特定のスポーツ向きのライン。流行もめまぐるしい。
商品の特徴は、山際チーフに聞いて、細かくメモした。メモはいつもエプロンのポケットにつっこみ、覚えにくいものは手の甲にボールペンで書いておく。
誠一を見ていると、メモもなしで、お客様にどんぴしゃりの靴を棚から下ろす。メンズのビジネスシューズの種類がスニーカーより少ないからじゃない。すべての型の特徴が、頭に整理されて入っているからだ。その証拠に、お客様が手に取った靴に、誠一はよくダメ出しをしている。煙たがられることもあるようだが、たいていのお客様は誠一の説明を聞くうちに身を乗り出し、靴をひっくり返して詳細に点検し、ラインを手でなぞったりするようになる。
靴を買いにくるお客様は、本当は何が欲しいのか、自分でもわかっていないことが多いみたいだ。そういう人が心から満足できる靴を提案できる。それがきっと、誠一の魔法の始まりなのだ。
誠一の動きを目の端でチェックして、香奈恵も少しずつ真似をする。誠一ならこう言うだろうと想像しながら、お客様の話を真剣に聞く。
「……街の中をウォーキングなさるのが、主な用途なんですね。それでしたら、底が薄くて柔らかい軽い靴よりは、厚手の底で、足をしっかりホールドしてくれて、少し重さがあるほうがいいですよ。今お持ちのスニーカーよりは、こちらのラインがお薦めです」
近くで棚の整理をしていた山際チーフが、香奈恵の接客に気づいて作業の手を止め、口をすぼめた。
シフトが終わりに近づき、最後に棚の商品を追加するためバックヤードに入ろうとすると、佐藤マネージャーの声が奥から聞こえて、足が止まった。
「村瀬さん、どんな感じ?」
「あ、頑張ってますよ」。山際チーフのはきはきした声が続いた。「まだ入って一ヶ月なのに、品番はほぼ完璧だし、商品の特徴も熱心に覚えてます。お客様へのアドバイスも的確ですし、見かけによらず使える子ですね」
わあ、たぶん誉められてる。足音をたてないよう、その場で小さく飛び上がった。
「あっそう。接客時間は? さくっと客をさばく感じ?」と、佐藤マネージャー。
「覚正くんに似たスタイルの接客ですね。彼の紹介なんで同じような性格なんですかね」
「そうなんだ。覚正タイプかぁ」。佐藤マネージャーが小さくため息をつく。「覚正くんは知識も豊富で熱心だが、効率がイマイチなんだよね。本当ならもっと売り上げが出ていいはずだよ。あのスタイルがもう一人って、ちょっと困るなあ」
なにおぅ? 両手が自然にぐっと握られる。あの誠一のすばらしい接客にけちをつけるとは、マネージャーでも許せない。お客様の信頼は絶大なのだ。
山際チーフは、幸い、香奈恵に近い感想のようだった。「うちの特徴の豊富な品ぞろえを最大限に生かすには、ああいうきめ細かい接客が大切ですよ。固定客の数は覚正くんが店でトップじゃないですか。つまりクッカのファンを増やしてくれているんですよ。それに覚正くんのおかげで、バイトさんにカツが入ってます」。きっぱり言い切ってくれた。
「ま、そうなんだけどねぇ……」と、佐藤マネージャーは煮えきらない。
「覚正くんは、そろそろ正社員のチーフにしてもいいんじゃないですか?」
山際チーフの提案に、香奈恵は音を立てないように拍手して、陰ながら賛成票を投じた。

昼食のタイミングが珍しく誠一と合ったので、思い切って誘ってみた。「おう。一緒にいくか」と、さらっと答えが返ってきて、香奈恵の心臓が跳ねる。
混雑するフードコートで、香奈恵は焼き鳥弁当、誠一は牛丼大盛りをトレイに乗せて、テーブルを確保した。
「頑張ってるじゃん」
誠一の飾らない言葉がうれしい。香奈恵は顔の横で髪をくるんと触った。
「覚正さんみたいに、早くなりたいなと思って」。言葉が甘く転がって出てくる。
「オレか」。誠一は短く笑った。「簡単なヤツだな。目標はもっと高く持て。手近ですませるな」
「覚正さんは、十分高い目標だよ。お客様の信頼は、店で一番だよ」。口が尖った。
「……そりゃ、ありがたいな」
誠一の目から一瞬、光が消えたような気がする。なんでだろう。
誠一は、珍しく、少しぼうっとして牛丼をつつき回している。無防備な表情は、心の扉に隙間が開いているように感じさせる。もっと押し開けて奥を見てみたい気分が、むくむく湧いてきた。
水をぐいっと飲んで、思い切って聞いてみる。
「ねえ、覚正さんは、どうしてそんなに靴が好きになったの? もともと、靴づくりを目指していたの?」
誠一の茶髪が、ゆっくり下がった。あれ?
「……聞いちゃいけなかった?」 香奈恵はにわかに不安になって、おずおず確認した。
少し間を置いて顔を上げた誠一は、よかった、笑っている。
「聞いちゃいけないことはないよ」
安心して、香奈恵は小さく息を吐いた。
でも、誠一はしばらく黙って、どこか遠くを見つめている。視線の先に何かがあるのかと、身をよじって追ってみたが、そこは単なる壁だった。
やがて、誠一は少し頭を左右に振って笑みを浮かべた。
「大した話じゃないけどな。オレが靴に興味を持ったのは、高校一年の冬だった。実はオレ、家出したんだよね」。軽く笑い飛ばす口調なのに、口元が辛そうにゆがむ。ぐっと唇をかんだ。
「えっ、家出?」と、あえて明るく素直に聞き返してみる。
「そう。家出。夜の夜中に家をこっそり抜け出して、一晩、闇雲に歩き回った。どこに行くかなんて決めていなくて、とにかく家を離れたかった。うちは海沿いの国道に近いところにあったけど山が近くて、けっこう森が深くてさ。林道を懐中電灯で照らして、とにかく歩いた」
「勇気あるね」。あくまで軽く返す。
「そのとき履いてたスニーカーが、学校のお仕着せでさ。男子はみんな、かっこつけて踵を潰してたんだ。それで一晩、山を歩き回ったら、どうなると思う?」
「う~ん……足が痛くなりそう」
「そう」と、誠一が人差し指をたてる。「靴擦れはできるわ、水膨れになって破れるわ。朝になったら一歩も足が動かなくて、森を出たところの家の車庫に座り込んで、痛いわ情けないわでボロボロ泣いた」
「……うん」
「そしたら、気配を感じて、家から人が出てきた。それが」。誠一がふっと笑った。「真下さんだったんだ」
「真下さん……工房にいた、靴づくりの師匠か」
「当時、真下さんは、湘ガ浜の山の中に自宅兼工房兼店舗を構えていた。今はフルオーダー一本だけど、そのときは修行中で、注文を待たずに靴を作り、完成品を売ることもしていた。で、血塗れの靴を履いたオレを工房に入れて、絆創膏を貼って、完成品の在庫から適当な革靴を見繕って履かせてくれたんだ」
「へえ」
「オーダーメードじゃなくても真下さんの腕は確かだ。踵を潰したスニーカーなんか比べるのも失礼なくらい、夢のような履き心地だった」
「お代は?」
「思いつきもしなかった。真下さんは、オレがなんでそんな時間にそんなところを血塗れの足でうろついていたのか、聞きもせず、金もとらず、ただ、夢みたいな履き心地の靴を一足くれた。それで」。誠一の声が途切れた。左手が目を覆う。
続いた声は、少し割れていた。
「真下さんは言った。『そんな靴じゃ、一歩も前に進めない。辛いときこそ、足にあう靴を履け。靴が体だけでなく、心も軽くしてくれる。靴が、君を前に進めてくれる』って」
似たような言葉を、以前、誠一の口から聞いた。
「それが、オレと靴との出会い」。誠一は細く長いため息をついた。「それからオレは、真下さんの工房に入り浸って、革の端切れをいじらせてもらうのに熱中した。家にはほとんど寄りつかなくなって、工房に寝泊まり。学校も行かなくなった。真下さんは、説教を何一つ言わず、バイト代わりに工房の掃除とか雑用をさせてくれた。そのうち『靴づくりを学びたいなら基礎から身につけてこい』と、専門学校を紹介されて、オレは東京に出た」
「……家出のきっかけ、聞いてもいい?」
それはダメな質問だとわかっていた。それに、香奈恵の脳は、答えを半ば予測していた。高校一年生の冬、誠一の人生に起きた衝撃といえば……
しかし、誠一の答えは、予想と違った。
「母が、おやじと別れたこと」
「そ……」。たぶん、口が大きく開いたと思う。
誠一は、香奈恵の様子に頓着していなかった。遠い目だった。
「そんで、別れた原因は……弟が死んだこと、かな」
「そう……」。最終的には、予想に戻ってきた。でも聞くべきことだったのか、もやもやが大きくなる。
弟の死とともに、誠一の家族も終わった。それが、誠一の靴への夢のスタート地点だったのか。
まだ友達ともいえない距離感のあたしが引きずり出していい記憶では、なかったのではないか。後悔と申し訳なさが次第に大きくなる。香奈恵はもくもくと焼き鳥弁当を片づけることに集中する振りをした。
誠一は静かな笑顔だった。それからは何も言わずに、残りの牛丼を淡々と口に運び、昼休みの時間通りに香奈恵を促して席を立った。

1週間後。香奈恵と誠一は閉店までのシフトだった。店内の掃除をしていると、佐藤マネージャーが「人事の発表があるから集まって」と声を張った。一同、わらわらと小柄なマネージャーを取り囲む。
佐藤マネージャーは、もったいぶって咳払いした。隣で、山際チーフがこっそり吹き出す。佐藤マネージャーは気づかない様子で、本題を切り出した。
「今日、本社から正式に通知がきました」。間を置いて、ぐるりと一同を見渡す。最後に誠一を指さして、軽く手招きした。
誠一は「オレですか?」と、自分の鼻を指さして、小さく一歩前に出た。
「覚正誠一くん。来月から、君はクッカの正社員になります。で、メンズビジネスシューズコーナーのチーフになってもらう。今のメンズビジネスの鍋山チーフは来月、本社企画部に異動です。というわけで、覚正くん、しっかり引継してもらってね」
誠一の細い目がまん丸になった。佐藤マネージャーの隣で、鍋山チーフが軽く頭を下げる。
「鍋山チーフの送別会は、別途、日程を決めます。幹事は山際チーフ。覚正くん、明日からもっとビシビシ働いてもらうよ。こっちで一言挨拶して」
佐藤マネージャーに促され、誠一は呆然とマネージャーの前に立った。香奈恵たちのほうを振り返ると、小柄なマネージャーは背が高い誠一に完全に隠れてしまう。いや、幅は誠一より佐藤マネージャーのほうが広いから、両脇からはみ出して制服のエプロンが見えている。香奈恵はくすっと笑った。自然にアルバイト陣から拍手が起こり、次第に大きくなる。鍋山チーフも山際チーフも笑っている。アルバイトたちも笑顔だ。香奈恵は「おめでとう」と声をかけた。
でも、誠一は笑わない。
緊張しているのだろうか?
誠一の言葉に備えて、拍手が止んだ。みんな、誠一の声を待つ。
誠一が口を開いた。いったん閉じる。また開く。
声が出ない。
お客様にはあんなに饒舌に靴を勧めるのに、今の誠一は、言葉を失くしたみたい。
チーフもアルバイトも、笑顔がだんだんだるくなってきた。早く、何か言ってよ。無言の圧力が強まる。
なのに、誠一の声は出ない。
ふっと顔がゆがむ。誠一は腰を深く折って、膝に両手を当てた。そのまま動かなかった。

翌日から、誠一の姿は売場から消えた。無断欠勤だった。
「せっかく正社員になれるっていうのに、どういうこと? もっと責任感がある子だと思ったのに」
山際チーフが嘆く。
「村瀬さん、何か聞いてない? 覚正くんの紹介でしょ。仲、いいんでしょ?」
焦った様子の鍋山チーフに尋ねられ、香奈恵は力なく首を横に振った。香奈恵だって、誠一が無断欠勤するなんて想像もできなかった。
「覚正さん、今日もお休みですか?」
売場に誠一を訪ねてくるお客様が、毎日、残念な顔をして帰っていく。ほかのスタッフじゃ、だめなのだ。鍋山チーフだって、誠一の代わりはできない。お客様は、誠一の魔法を求めて来るのだから。
香奈恵は何度も誠一にLINEを送った。通話も試した。どれ一つ応答はない。返事が来ないことを確認するたび、香奈恵の胸にどんどん重苦しい固まりが積みあがる。
ねえ、生きてる?
どうして、返事をくれないの?
何かあったの?
お店がいやになっちゃったの?
それとも、あたしの前から、姿を消したかった?
誠一がいないと、お店が締まらない。お客様だけでなく、スタッフもチーフもマネージャーも、なんだか変だ。
無断欠勤が始まって1週間。香奈恵は、希美経由で拓也に頼ることをようやく思いついた。拓也なら、もしかしたら何か知っているかもしれない。
バイト帰りに、香奈恵は慌ただしく希美にLINEを送った。
「覚正さんがいなくなっちゃった。どうしたらいいかわからない。ねえどうしたらいい?」
送ってから気づく。これじゃ、希美には訳が分からないだろう。改めて状況を説明する文章を組み立てようと努力する。冷静に、冷静に。
途中で、指が止まった。頬がなま暖かい。スマートフォンの画面に水滴が落ちてきた。
あたし、泣いてる? 香奈恵は慌てて、手のひらで頬を拭った。
だって、誠一がいる風景が、もう当たり前だから。あの魔法が、あたしを動かしていたのだから。
ないと困るの 。
(続く)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
