
◆読書日記.《日影丈吉『孤独の罠』》
<2024年2月7日>
<あらすじ>
推理小説史上、特異な位置を占める、幻想の詩人・日影丈吉の代表的長編。舞台は、榛名山に近い寒村。縁の薄かったわが子の火葬に立ち会った仰木は、そこで奇怪な事件に巻き込まれた。1体のはずの乳児の骨が、2体も出てきたのだ。忌わしい事件を仕組んだ犯人の意図は? 閉鎖的因習や錯綜した人間関係を追いながら、謎を探る。
<編著者略歴>
日影 丈吉(ひかげ じょうきち、1908年6月12日 - 1991年9月22日)は、日本の小説家、推理作家、翻訳家。東京都出身。本名は片岡十一。幻想的な作風で、代表作として長篇小説「真赤な子犬」「内部の真実」「応家の人々」、短篇小説「猫の泉」「吸血鬼」、探偵右京慎策の活躍するハイカラ右京シリーズなど。
日影丈吉『孤独の罠』読了。
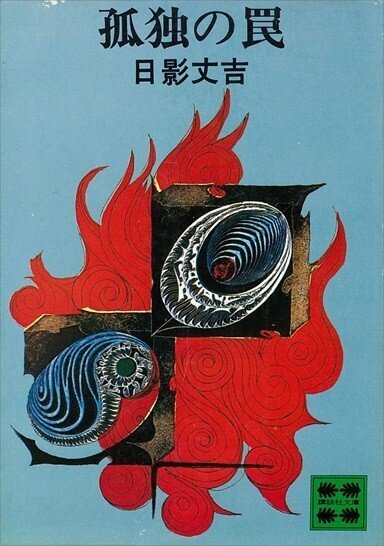
日影丈吉は、戦後に出た探偵小説専門誌『宝石』誌上で「かむなぎうた」を江戸川乱歩に激賞されデビューした小説家である。
日本の推理文壇の中でも随一の名文家としても知られ、60~70年代にかけての異端文学ブームの中で小栗虫太郎や夢野久作、久生十蘭、国枝史郎といった作家らと共に再評価されたのが日影丈吉であった。
この数年、新年はキリリと冷えついた新年の空気の中でこの人の文章を味わうのが正月の習わしだったのだが、去年は何だか小説を読む気が失せていたために読まずに過ごしてしまった。
という事で二年ぶりに日影丈吉の未読だった長編小説を読む事となった。
とは言え、日影丈吉の長編小説はさほど数が多くないので今年は何を読もうと悩んでいたのだが、せっかくなら久しぶりにこの人の本格的に「文学」に拘っているタイプのものを読みたいと思い、今ではかなり入手困難となったこの一冊を手に取ったという次第。
日影丈吉は、短編では文学性の強いものも多く書いているのだが、長編については、スタイルに工夫を凝らしたフランス・ミステリのような傾向の作品のほうが多い。
例えば『一丁倫敦殺人事件』や『多角形』などはまさに著者がフランス・ミステリを意識して書いているというのが分かる作品だし、異国情緒豊かな作風で文学的にも評価の高い『内部の真実』や『応家の人々』といった作品も、やはり推理小説的なスタイルは色濃い。
が、本作『孤独の罠』については、作風は短編の代表作『かむなぎうた』や、長編『女の家』『夕潮』といった作品に近く、推理小説的なスタイルよりも文章や文学性に拘っているようなタイプのミステリである。
だからそもそも、本作は昨今の売れ筋ミステリのように派手な展開があったり、分かり易いどんでん返しがあったり、サスペンスフルなストーリー展開が望めるようなものではない。
という事で、これを普通に「推理小説を読みたい人」が読んでも、あまりぴんとは来ないだろう。
ネットに挙げられているレビューでも、本書をして「トリックが……」とか「読みにくくて……」という、ちょっとピントが外れているかな?と思わせられるものが多い。
そういう人というのは、せめて読み始めたら「文体」によってこの本の著者の意図する所を読み取り、「読み方」の意識を切り替えたほうが良かったかもしれない。
ぼくも学生時代辺りの未熟な読み手だった時期には、この手の経験は良くある。ぼくも、中学生くらいの時に本作を読んだら、退屈で仕方がなかっただろう。
「意外性がなく地味で面白味のない小説だ」といった、本作のレビューでよく見かける評価というのは、まさしくぼくが学生時代にはじめて日影丈吉の代表作『かむなぎうた』を読んだ時の感想だった。――因みに、現在ぼくが好きな短編ミステリを10個上げるとしたら、『かむなぎうた』は確実にその中に入るほど評価している作品である。
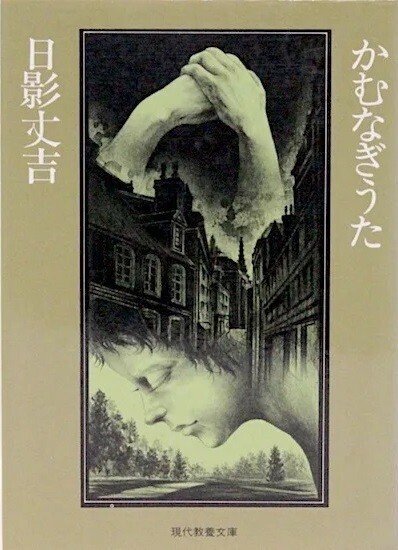
ぼくは学生時代、おそらく4~5度ほど『かむなぎうた』を読む機会があっただろうか。
その当時、とにかく推理小説に詳しくなりたいと、『日本の推理小説傑作選』といった類のアンソロジーを読みまくっていた時期があった。
その手のアンソロジーに日影丈吉の『かむなぎうた』は、ほぼ必ずと言って良いほど収録されており、その度に再読する事となったのである。
何しろこの作品は派手な展開が起きない、明確なストーリーラインもない、普通の推理小説のように「事件発生‐捜査‐探偵の推理‐大団円」という普通の展開にはなっていない……という作り方だから、読み終わってから何も印象に残らなかった。
当然、その当時のぼくは「日影丈吉は、たいした事のない作家だ」という結論に至る。
しかし、『日本の推理小説傑作選』『日本の代表的名作ミステリ集』といったアンソロジーには、この『かむなぎうた』は必ずと言って良いほど収録されているし、解説を見てもどの評者もほぼ手放しの絶賛をしているのである。
『日本の推理小説傑作選』的な本を図書館から借りてくるたび、そのタイトルを目にして「あれっ、これどんな話だったっけ?」と首を捻ったものである。
「――では『かむなぎうた』は、いったい何が凄いのか?」というのは、その当時のぼくには一つの大きな「謎」であった。
自分が読んで楽しめない、というのは仕方がない事だとしても、評論家をしている先生がたがどういう所を褒めているのか、何を面白いと思っているのか――最低でもそういった部分だけでも理解したいと思ったわけである。
それを理解した上で「あー、なるほど。そういう事なら、確かにぼくがこの作品を読んでも楽しめなかったわけだなあ。それなら仕方がない」と納得したかったのである。
それは、学生時代のぼくにとって「良い推理小説とは何なのか?」「評価される推理小説とはどういったものなのか?」ひいては「良い小説とは、いったいどのようなものか?」といった事を考えさせるきっかけとなるのである。
――余談が過ぎる、と思われるかもしれないが、本作の評価にも繋がって来る話なので、もう少々お付き合いを。
『かむなぎうた』はそもそも、普通の推理小説とは求められる「読み方」が全く違うのだ――とやっと気が付いたのは、ぼくがこの作品を4~5度目ぐらいに手にした短編アンソロジーで読んだ時だったと覚えている。
普通の本格推理というものは、「謎」を推理して解明していくプロセスを楽しむものだし「トリックの面白さ」というものは、読者の意表を突くアイデアとしての面白さを追求したものだ――というのが通常の見方であろう(これはあくまで古典的な見方ではあるが)。
だが、『かむなぎうた』の場合、作品の中に出てくるトリックは、この物語の「中心」にはないのである。それはあくまで、この作品で語りたかった事を成立させるためのアイデアの一つでしかなかったわけである。
だから、ぼくにとっては当初『かむなぎうた』は、トリックだとかストーリーだとかは全く思い出せないのに、「雰囲気」だけが色濃く印象に残っている――そういう小説でしかなかったのだ。
推理小説を読む時に、「謎」の魅力やらトリックやら犯人当てやらといったものを楽しむのが推本来の理小説というものだ……という「自分の期待」にこだわり過ぎると、その作者が何を意図してその小説を書いているかという部分には盲目になってしまいがちになる。
小説を読む時に、自分の先入観から「自分の期待」を、過剰に作品に押しつけてはいけない。
それが、学生時代に『かむなぎうた』から受け取った、ぼくの教訓であった。
『かむなぎうた』は、あくまで郷愁的で幻想的な雰囲気の横溢した、何よりその雰囲気を成立させるための極上の文章が用意されている小説であったし、その味付けとして、ピリリと「トリック」が効いている、という作品であった。――だから、『かむなぎうた』のトリックは、この作品の「中心」にはないのである。
今回採り上げる日影丈吉の長編『孤独の罠』も、その手の小説であったのだ。だから、ある意味「分かりにくい」し「面白がりにくい」のである。
この小説は、殺人事件が起きて警察が捜査に乗り出し、犯人が告発されるという、一見して推理小説としての体裁を採ってはいるが、その実、この物語はトリックだとか推理だとかといった所に、あまり重きを置いていない。
それどころか、本作で発生する殺人事件でさえ、著者の意図するところの「中心」にはないのである。
――その点を見落としてはならないだろう、と特に若手の本読みには注意を喚起しておきたい。
例えば、日本の推理小説のオールタイムベスト選定企画には必ず取り上げられる中井英夫の傑作推理小説『虚無への供物』を読んで「トリックがつまらないよ」なんていうのはお門違い――というのと同じ事だ。
もっと一般的なもので例えるなら、能や歌舞伎などの古典芸能を見た若い人が「アイデアが古臭くて退屈だ」と言った所で、「味わうべき所が違っている」と、逆に笑われてしまうだろう。
「そこ」を理解したうえで、作品として評価できるかどうか、自分にとっては楽しめたのかどうか評価すればいい。
無論、作品評価というものは自由にすべきものではあるが、「そこ」を見抜けていないのに、分かったような評価をするのは恥ずかしい事なんですよ、という事なのである。
前置きが長くなったが、本作はそれだけ簡単には評価しきれない作品で、必ずしも普通の推理小説と同じ見方はできない、という事なのだ。
因みに、この物語の眼目の一つである「心理ドラマ」の分析をしようとすると、それがそのままこの小説の真犯人と主人公との関係性について分析せざるをえなくなるので、それはネタバレレビューのほうで行う事にする。
要するに、本作の推理小説部分と心理ドラマの部分は不可分の関係なのである。
◆◆◆
さて、上に述べた通り、本作についてはストーリーやトリックといった一般には売れている本格ミステリの評価のされ方と同じ観点では、評価するのは十分ではない。
『かむなぎうた』は、日影丈吉自身が「内容よりも文章に興味を持って書いたことが記憶に残っている(『宝石』増刊、昭和三十八年四月)」と言っているそうだが、本作『孤独の罠』もそれと同じく著者が文章にこだわっているという事は一目瞭然で、何かしら「文体」についても言及しなければ、この作品について完全に語った事にはならないだろう。
本書の解説によれば、日影丈吉は過去「私はね、細部の描写を重視するんですよ」等と言っていたそうであるが、本作の場合は、まさに彼の言葉の通りの凝った文体で綴られている。
日影丈吉の文章は外連味のある所がなく、派手な描写はしない、抑えたトーンの冷静な描写が特徴としてあげられる事が多い。
そういう特徴があり、何より推理小説を書いている作家だという事もあって、その文体は理知的な硬さを持ったもの……というイメージもありそうだが、今回改めてじっくりその文体を味わった所、意外とこの人は感性的な表現を得意としているのだな、という事に気が付いた。さすが、画学校に通って絵を勉強していただけあって、この人の感性は鋭いのである。
しかも、感性的な文章でありながらも、その心理描写はウェットではなく、どこかドライな所があって、そこが日影丈吉の特異な文体の特徴なのだろうと思わせられた。
日本のミステリ文壇の中でも日影丈吉と同じく「名文家」と称される連城三紀彦は、ぼくの印象だと非常に論理的な文体の人だという印象がある。
連城はダブル・ミーニングをトリックだけでなく文体にも応用しているという点が一貫していて、非常に技巧的な文体なのである。
そういう所は、日影丈吉とは逆であると思える。日影丈吉の場合は、もっと「感性の鋭い文章」なのだというのが、今回感じた印象であった。
ここで注意したいのは――普段、一般的にも「感性が鋭い」という表現は良く使うが、では一体「感性が鋭い」とは、何を以てしてそう言うのか、という事である。
改めて考えてみると、この表現は非常に曖昧な所があるのではないかと思うので、ここでぼくの考えを提示しておきたい。
ぼくが思うに「感性が鋭い人」の特徴は、「人とは違う所に"論理的ではない"観察眼が良く届いており、そこに良く気が付く人」なのではないだろうか。
逆に「論理的な観察眼」というのは何かと言えば、物事の因果関係をよく理解しているから良く気が付くだとか、知識や経験が豊富だから、それに基づいて色々な事を良く理解し良く気が付くだとか、そういったタイプである。
その逆のタイプが「感性の鋭い人」だというわけである。直観的な洞察力が鋭く、その洞察が深い人がこういう風に言われるのではなかろうか。
「感性の鋭い人」というのは、例えば「人の気持ちを汲んで行動できる人」だったり「日常の中で多くの感動を発見する人」と言った風に表現される事がある。
感性の鋭い人と話していると、「ああ、この人は良くもまあそんな所に気が付くな」とか「この人は、こういう所を見て感動しているのか!」と、こちらも新たな発見をさせられて感心させられるものである(ぼくが美術大にいた頃、クリエイターの卵たる同級生らは皆、そういった人たちばかりだった事を覚えている)。
「感性が鋭い人」の文章も同じ事で、そういう人の文章を読んでいると、その人が普段、どんな所を見ていて、どんな事を考えているのか伝わってきて、そういう所に「この人は、こんな所に目をつけて感動しているのか」という、その人の個性や人間性が滲み出ているのが分かるものだ。
逆に言えば「感性が鋭い人」の反対は「ニブい人」という事になるだろう。
「ニブい人」の書く文章というのは、とにかく誰が書いてもそういう書き方になるだろうとしか思えないような無個性な文章になるものだ。通り一遍の、表面的な部分しか見ていない、誰でも気付くような所しか気付けないタイプの人というわけである。
「文体」というものは、映像作品で言えば「演出」と似たようなものだと思えば、少しは分かり易くなるかもしれない。
例えば何気ないオフィスの風景を描くにしても、観察眼が行き届いている人と「ニブい人」では、その「演出」にありありとした差が出てくる。
アニメを例にとって恐縮だが、例えば昨年放映していたアニメ『うちの会社の小さい先輩の話』の2話に出てきたオフィスの風景などは、あまりにも分かり易い「ニブい人の書いた絵」だろう。

……この絵のおかしさにお気づきになられるだろうか?
デスクトップPCのある固定デスクなのに、固定電話もなければ電話メモもペン立てもファイルボックスも処理途中の書類の束も電卓も卓上カレンダーもドリンクホルダーも私物のフィギュアも置いてない。
って言うか今までこんなスッキリしすぎているデスクなど一度も見た事ない。
自分個人が使う私物を一切持ち込み禁止の高セキュリティなオフィスでもこんなに何もない所などない。
たいていは、自分の仕事がしやすいように、そういう細々した小物がどこの職場のデスクでも置いてあるものだ。
例えば、ぼくの場合だったら仕事で使う参考書籍をうず高く積み上げていたものだった(笑)。
つまり、この絵を書いた人は、オフィスでどういう人たちが、どういう仕事をしているのかという事に想像が行き届いていないのである。
だから、このようなモデルルームのような全く人の生活感の感じられない、清潔すぎるオフィスになるのである。

そもそも、そういうちょっとした小物などでリアリティやキャラの個性といったものを出すのが演出家の腕というものだ。よく言われるようにリアリティは細部に宿るのである。
例えそれがコメディ作品であっても、ここまで非現実的な「絵」を許容できるというのは、もはや監督のセンスの問題でもある。スタジオジブリだったら、死んでもこんな演出しないだろう。

「人間がそこにいて生活を営んでいる」という事は、その場所にもその「生活の痕跡」というのが、必ず残っているものである。それが「生活感」というものだ。
「感性の鋭い人」というのは、そういった部分に非常に良く気が付いていて、それを普段、良く見ているし、そういったものに「人の肌感覚」を受け取って、感動しているものなのである。
ぼくとしては、本作『孤独の罠』を読む人には、ぼくと同じように日影丈吉のそういった「感性的」な部分にも、ぜひ目を向けて味わってもらいたいと思うのだ。
本作の文章は、ストーリーを説明するため"だけ"にあるのではない。
その時代、その土地、その人々の雰囲気を浮かび上がらせるためにあり、それを絵画と同じように鑑賞するためにある。これは日影丈吉の他の作品――『内部の真実』にも『応家の人々』にも『夕潮』にも、当てはまる事だ。
そういった「絵」を浮かび上がらせるために、日影丈吉は非常に様々な所に目が向いている。その驚異的な観察力を味わわなければ、この作品を読む価値は半減してしまうのではないかとさえ、ぼくには思えてしまうのである。
本作の成立時期はおそらく1960年代といった所か。
主人公は東京に住んでいて、その当時の東京のサラリーマンの生活と、主人公の妻の郷里であった群馬県の山村の生活とが描写されていて、そのコントラストがたいへん面白い。
何よりその演出が巧く、その当時の人々の息遣いが感じられるような文章である。
東京でサラリーマン生活をしている主人公は、妻を亡くして独り暮らしになってしまったから、諦めて電気式の洗濯機を買っただとか、派出婦を雇って家事を手伝ってもらうだとか、暖房はコタツと長火鉢を使っていて、長火鉢の上の「猫板(初めて聞いた言葉だ!)」にいつも派出婦への言付けの手紙を置いておくとか、東京の夏はスモッグと水不足が名物だったとか、そういった生活のこまごまとした描写があるから、その当時の生々しい現実が見えてきて、現代との生活の差が、それだけで興味深い。
田舎の風俗も物珍しくて読み込んでしまう。
井戸水と水道水を両方使っていて、土間の隅の炊事場で料理をし、炉部屋の炉を囲んで縁板の上に直に椀を置いて食事をするだとか、その描写だけで、その当時の風俗だとかその人たちの生活感覚が浮かび上がってくるような書き方を、しているわけである。
白布で包んだ小さな棺をかかえて土間におりたのは、典代の兄だった。土庇の下を出ると、空の青いことがわかったが、杉のこずえから振り落とされる雪片が、羽毛のように飛んでいた。たくましい地鶏が、家から出てきた人達の邪魔になるのも意に介しないふうで、雪の上をつつきまわしていた。兄はほいほいと声を出して鶏を追った。
――これは冒頭に出てくる、主人公が失った幼い息子の葬式を、妻の郷里である群馬県の山村で行う場面でのワンカットである。
この短い部分を抜き出してみるだけでも、その当時の生活の様子や当時の人々の息遣いが、何とはなしに浮かび上がってくるのが、分かるのではないだろうか。
ここでは登場人物に行動をさせて物語を進行させながらも、同時に周囲の環境に関する描写を入れ込んで、その当時の時代性や暮らしぶり等も説明している。
そして、上に説明してきたように、この繊細な書き方から、日影丈吉が普段から人々の生活のどういった所に目を向けていて、それをどれくらいまで観察していたのかという事も、分かるであろう。
(因みに、この作品の舞台となった群馬県渋川市の山村について、日影丈吉は「一種の郷愁のほかには十分な予備知識をもついとまがなかったことを、残念に思っています」と物語の末尾に、遠慮がちに注釈を付けているが、それでも上にあげたレベルで想像力が細部まで行き渡っているのである)
そして、その「目線」の内容がそのまま、日影丈吉という小説家の個性になっているわけで、そういった彼の文体をも味わえなければ、本作をじゅうぶんに理解した事にはならないのではないか、とそう思うのである。
そういった所に作者の意図がある小説というものは、通常の推理小説のように「トリックと犯人が分かったら、もうこのミステリは再読する必要がない」といった類のものではなく、何度でも絵画を鑑賞するように、その文章の「味わい」を鑑賞できる。
だから、そういう作品は「読み捨て」にはされずに、長く読み継がれる「文学作品」となるのだ。
◆◆◆
さて、では以下からは本書の推理小説的な部分であり、同時にそれが「心理ドラマ」になっているという、真相に関わる部分になるので、ここからネタバレの解説という事となる。
上にも説明した通り、本作は推理小説としての「真相」を明かしたところで、それで即その小説が面白くなくなってしまう、という類の作品ではない。が、いちおうこの部分も本作の見所の一つになっているからには、ネタバレの注意書きをせざるを得まい。
◆◆◆◆◆以下ネタバレあり◆◆◆◆◆◆◆
《注:以下、日影丈吉『孤独の罠』の中核的なアイデアに触れるレビューとなっています。本書を未読の方、またネタバレをされたくないと思っている方は、以下文章を読む際はその点をご考慮の上ご覧頂ければと思います》
◆◆◆◆◆以下ネタバレあり◆◆◆◆◆◆◆
本作のタイトルにある通り、恐らく本作のテーマの一つは「孤独」なのだろうと思う。
では、なぜその「孤独」が「罠」になるのか――というのが、本作の真相に関わってくる部分になっていると言って良いだろう。
本作の主眼の一つとなっているのは、主人公・仰木信夫と、彼が岡惚れしている女性・古間朱野との関係性であろう。
そして、この作品の底に隠されてある心理ドラマというものには、人には二面性があり、またそれは日本人のコミュニケーションの曖昧さによって微妙に隠されていて、そのために勘違い・すれ違いを生み出してしまう――という考え方が流れているのではないかとも思うのである。
ここで言う「日本人のコミュニケーション」の特徴というのは、例えば最近上げたレビューで言うなら小此木啓吾『日本人の阿闍世コンプレックス』で説明した「察し」「配慮」「共感」「同一化」といったような、遠回しなコミュニケーション・スタイルの事である。
本作は何しろ、冒頭から主人公の幼い息子の葬式から始まっているので、出てくる登場人物が軒並み主人公に対して気を使い、遠慮し、遠回しに促し、互いに様子を伺っている様子が描写されるのである。
主人公の仰木の性格は実に控えめで、抑えが効き、あまり感情を表には出さず、そして若干旧弊な日本の道徳観を有しているという点が特徴といえよう。
このような人物だからこそ、余計に周囲がどういう風に声をかけて良いものか、恐る恐る接しているのが分かる。こういう所に、日本的なコミュニケーションの「機微」というものが仄見えてくるのかもしれない。
その後も、続けて本作の登場人物らは互いの腹の探り合い、顔色を伺い、察し、察され……という遠回しなコミュニケーションのやり取りがなされる。
それが、結局は様々な人を勘違いさせ、心のすれ違いを生み、相互のディスコミュニケーションが判明した時点で初めて「犯人の悪意」が露呈するという心理ドラマを産むのである。
もしかしたら、アメリカ人のように「物事はハッキリと主張する」というコミュニケーションを採っていれば、こういった事態にはならなかったかもしれない。
本作の主題の一つは、こういった時代に生きた男の恋愛の悲劇的な結末にあると言って良いだろう。
相手も自分も、あからさまな本心などストレートには言ってくれない。だから、相手の気持ちを知るためには遠い遠い迂回を経なければならず、色々と考えた末にやっと相手へのアプローチが始まる。
彼の古間朱野に対する恋心も、最初はハッキリとしたものではなく、淡いものだった。
何しろ親戚の奥方なのだから、旧弊な道徳観を持つ仰木には自分の好意を相手に悟らせまいと自分を抑制するし、夫の古間が死んだ後も、しばらくは彼女への思いを抑制しなければ不謹慎だと考えるのである。
彼が古間朱野に惹かれた理由は、歳が近い美人で古なじみであるという理由だけでなく、作中には直接的には書かれていないが、やはり妻と息子を立て続けに亡くしたための「孤独」もあったであろう。
「孤独」を感じるのは、何者かと繋がりたいというフロイト言う所の「エロス」の欲求があるからとも言える。友人がもっと欲しい、恋人がいなければならない、妻となるべき女性と添い遂げたい……その「繋がりの欲求」が、あるいは今回の主人公・迎木の目を曇らせていた原因だったのかもしれない。
仰木は妻と息子を亡くしたというだけでなく、妻の郷里の山村の人たちとも血のつながりが断ち切れた、と感じている。
その上、更に母も亡くなった。
自分に肉親と呼べるのは、妹の叶絵だけだったが……肝心のその妹の行動は、いつも自分には理解できず、彼女に微妙な距離を置かれてしまう。
そんな彼は何故、この物語の最後の最後に、自分が思いを寄せていた古間朱野が自殺した、と悟った時「彼はまた誰からも切りはなされて、一人になったように感じた。しかし、彼を呪縛していた孤独感からは、やや解放されたような気もしていた(本書P.287)」と思ったのだろうか?
仰木は、肉親の叶絵がいるにも関わらず「誰からも切りはなされた」と感じていたわけである。
自分を理解してくれる「肉親」としての、母も妻も息子も親戚からも切りはなされた。唯一の肉親の妹は自分とだいぶ心の距離がある。
そのために、彼は自身の抱えた「孤独」を、思い人である古間朱野によって埋められるのではないか……とそういう「呪縛」にかかっていってしまうのである。
だが、本作のラストに現れた真相は、――古間朱野は仰木を騙しており、夫がいる身分にもかかわらず他の男性と情交を持ち、あげく夫を謀殺しているのである。あまつさえ、最後には仰木とこの罪状の秘密を分かち合うように自分の肉体で篭絡しようとさえ考えていた。
――ここで、仰木は旧弊な道徳観の持ち主であった事を思い出そう。さすがにここまで来ると、仰木も目が覚めたことであったろう。
だから、本書のタイトルは『孤独の罠』だったわけである。
だから主人公の仰木は、古間朱野が自殺する事で、再び「一人になったように感じた」と同時に「彼を呪縛していた孤独感からは、やや解放された」という、若干相矛盾するかのように思える心理を抱いたわけである。
彼は、「孤独感に呪縛されていた」わけである。
古間朱野の態度は、はっきりせず、仰木もはっきりと物を言わない男だからこそ、仰木は、徐々に徐々に、古間朱野に惹かれていくのであり、彼女の態度をどんどん肯定的に解釈してその気になっていってしまうのである。
だが、実際の古間朱野は、仰木の考えていた人物とは全く違っており、彼女は彼女で、仰木の態度を「自分への無言の告発」と勘違いして受け取り、仰木とはっきりと話し合いもせずに一人で自滅の道を選んでしまうのである。
最終的に、仰木も朱野も、両方ともお互いの事を全く分かっていなかった、という事が、ラストに明かされる本書の最大の「真相」であった。
こうして見てみると、本書に出てくる推理小説的な仕掛けというのは非常に些細なもので、少なくとも物語の大枠を支えている「中心」ではないという事が分かる。
この両者のすれ違いは、上に挙げたように「察し」「配慮」「共感」「同一化」の絡んだ迂遠なものであり、非常に古風な日本人的なコミュニケーションではないだろうか。
こういった遠回しなコミュニケーションを互いに続けていれば、普通の人であったら、けっきょく相手の心の内など最後まで分からずに人生を終える事になるものではないだろうか。
実際の人生では本作の様に、これほどハッキリと、相手の真意や相手の秘密が表に暴露されるという事はないだろう。
「日本人の特徴であった迂遠なコミュニケーション」のために普通だったら裏に隠れていたはずの曖昧な男女関係――その隠された心理を、表面にさらけ出すための装置として、本書における「推理小説的な仕掛け」があったわけである。
ぼくが、本作に於いて推理小説的な仕掛けは「中心」にない、と主張したのは、そういう意味だったのである。
以上、こうやってこの物語に流れる「心理ドラマ」の構造を説明してしまうと、割とありふれていると思えなくもない。
が、本作ではそういう心理の機微を、上に述べたような感性的な文体によって、繊細に書き出しているのである。
日影丈吉が、この長編小説については推理小説的な派手な仕掛けを幾分抑えめに、それよりも「文体」のほうにこだわったのは、そういう「繊細な心理ドラマ」を成立させるためのスタイルだったのではないか、とそう思うのである。
――本書のような推理小説を語る時の論点は、昨今の売れ筋ミステリのようなストーリーテリングや意外な犯人や奇抜なトリックばかりではない、と言った意味が、これで多少なりともご理解頂けただろうか。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
