
◆読書日記.《ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』》――その1
※一冊目:岡田雅勝『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』
https://note.com/orokamen_note/n/n257f5daa24bf
※二冊目:中村昇『ウィトゲンシュタイン、最初の一歩』
https://note.com/orokamen_note/n/n4e32ad044420
※三冊目:飯田隆『ウィトゲンシュタイン 言語の限界』
https://note.com/orokamen_note/n/n38cb48c62166
※四冊目:鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこう考えた』
https://note.com/orokamen_note/n/n234dc8b18591
<2024年6月11日>
今回のレビューは久しぶりに日記形式でお送りする事とした。今後、何日かに一回、読み進めたぶんの成果を報告する形で書いていこうと思う。
というのも、今回は3冊の本を同時平行で読んでいるので、後から内容をまとめるのも大変ならば、その分量も膨大なものになりそうだと考えたからだ。
まずは、今回読み始めた3冊の本を紹介しておこう。
1冊目:ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』
光文社古典新訳文庫・丘沢静也/訳 2014年1月20日

2冊目:ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』
ちくま学芸文庫・中平浩司/訳 2005年5月10日

3冊目:野矢茂樹『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』
ちくま学芸文庫・2006年4月10日
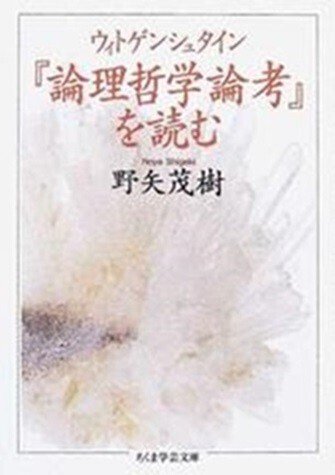
ちなみに、以前ぼくが一度読んだ事があるのは「2冊目」の中平浩司/訳の『論理哲学論考』である。
ぼくは一度この本を通読したのだが、以前の記事でもご紹介した様に、本書はある種「命題集」といった体裁で、ただ単に通読しただけでは意味をなさず、「つまり?具体的には?」という部分は全く書かれていない。
だから、「この本を読む」という事は、自分自身でそれぞれの文章の意味を考え、具体化し、各項目の文章間の繋がりとその構造を考えながら、自ら「この本の肉付け」を行わなければならないという事になるのだ。
とにかく、詳しい説明をほとんど削り取った内容なのである。
だからこそ、それぞれの命題について考えていると、いくら時間があっても、いつまで経っても読み終わらない。
その上、ぼくとしては『論考』の記号論理学に関する議論に関してあまり興味が持てなかったために、さほど内容の濃い読み方はしなかったわけである。
そんわわけで『論理哲学論考』については、いつかリベンジをしたいと思っていたのだ。
今回は事前準備を念入りにして、今までの記事でご紹介してきたように、入門書や解説書などを事前に4冊ほど読んで事前知識を入れ、更には2種類の訳書を用意し、更には『論考』を精読する内容の野矢茂樹『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』を準備して、これで万全の態勢で挑もうとしているのである。
と言う事で今回、副読本的な位置づけを想定して手に入れた『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』だが、この本はちょこちょこと拾い読みしてみたところ、どうやら鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこう考えた』のようにウィトゲンシュタインの遺稿を元にしてその内容を解読する、というような内容ではなかったようである。
この本で野矢茂樹は、大学で受け持っているゼミで『論考』を3年間通じて精読し、その成果として本書を書いた、というのだそうだ。
つまり、この本の内容は鬼界彰夫の前掲書とは違って「ウィトゲンシュタインの"真意"を、遺稿を紐解いて解読する」という内容ではなく、あくまで『論考』のテクストのみを使って、野矢茂樹のゼミで得られた「読み」の結論としての成果を、ここに纏めている、というようなのである。
いわば本書は、もっと正確に書けば『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む野矢茂樹』という「著者の意見/解釈」が強い内容だと言えるだろう。
ちなみに、この著者である野矢茂樹は、専攻は哲学であるものの『論理学』(東京大学出版会)、『論理トレーニング』『論理トレーニング101』(産業図書)などの論理学に関する著書を持ち、更に岩波文庫版の『論理哲学論考』を訳している研究者である。
と言う事で、本書は鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこう考えた』で紹介していたウィトゲンシュタインの「本意」とは関係なく「いち哲学者の読解」を見せられる、というわけである。
そして、その専門からして、おそらく『論考』の解釈も、ウィトゲンシュタインの裏に隠されている「本意」としての宗教思想、神秘思想的な部分にはあまり触れず、「論理学」の部分で大いにその読解を見せてくれるものだと期待している。
こういった事情は、ウィトゲンシュタインにこれから詳しくなっていきたいと思っている初学者、一般読者は良く理解しておいたほうがいいだろう。
つまり、野矢茂樹『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』はあくまで「いち解釈」であり「これが正解」などというものではないのである。
だから「これが正しいウィトゲンシュタイン思想なのだ」というスタンスで読むべきではないだろう。
実を言うとぼくは、このような本書の「いち哲学者の自分なりの解釈本」というのは、ウィトゲンシュタインの『論考』に関せば「あり」だと思っている。
それは、以前の記事でも言った通り、ウィトゲンシュタインはそのテキストでじゅうぶん示している通り、「明快に答えを教えてくれる思想家」ではないと思っているからだ。
彼は一時期、教育者をしていた事もあってか、その著書の言葉は極限まで説明が省かれ「あとは自分自身の頭で考えるべきだ」というスタンスなのだと思う。
だからぼくとしては野矢茂樹『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』は、「例えば、論理学者が『論考』を読んだら、どんな解釈をするのか?」という、具体的なケース・スタディとして、活用させてもらおうと考えているわけである。
そして、残りの2冊は、訳者の違う二つの『論理哲学論考』である。
ちくま学芸文庫のほうの訳者・中平浩司は在野の研究者だったようで、高校教育を行いながらも「ウィトゲンシュタイン考察を続けた」人だという紹介がある。
そして光文社古典新訳文庫のほうの訳者・丘沢静也はドイツ文学者である。
野矢茂樹は論理学系の哲学者であり、中平浩司は在野のウィトゲンシュタイン研究者、丘沢静也はドイツ文学者という事で、それぞれ分野が違っているというのはなかなか面白い。それが、今回どういう「違い」として出てくるかと言うのも、今後注目したい部分である。
◆◆◆
ちなみに、冒頭の「序文」と命題「2」の辺りまで読み進めた時点で、もう既にそれぞれに異なった部分が見られた。
中平/訳の「命題1」の訳文は「世界とは出来事たる一切である」となっているが、丘沢/訳のものは「世界は、そうであることのすべてである」とある。
「中平:出来事」=「丘沢:そうであること」の違いである。
故に、今後の命題にもある「出来事=そうであること」の出てくる文章は、訳し方のニュアンスが微妙に異なってくるわけである。
ちなみに、ここの部分は岩波文庫版の『論考』を訳した事もある矢野茂樹の訳によれば「世界は成立していることがらの総体である」となる。
「中平:出来事」=「丘沢:そうであること」=「矢野:成立していることがら」
このように並べてみると、訳し方の差でだいたいのニュアンスの振れ幅というのが分かってくるとは思えないだろうか?
ぼくが、最初にこの『論考』を読んだ時に難しいと思ったのは、こういった些細な言葉のニュアンスをどう採ればいいのか、という事に頭を悩ませた事だったと覚えている。
その後も、「事実」とか「事態」とかいう単語が出てくるが、専門用語ではないとはいえ、正直「事実」とか「事態」とか改めて言われても、こちらも読んでいてその差をハッキリ説明する事ができないのである(因みに、この「事実」と「事態」の差に関しては矢野茂樹『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』に解説が載っているので(P.326)、これに頭を悩ませている人はこちらを参照してみてもいいかもしれない。やはり訳語なので日本語とはニュアンスの違いがある)。
また、これらの言葉も、やはりそのままの日本語のニュアンスで受け取ると微妙に「ズレているな」と感じる所もあるので微妙に隔靴?痒の感があった。
丘沢の著書である古典新訳文庫は「いま、息をしている言葉で」というコンセプトで訳されているので、おそらく丘沢はかなり砕けた表現を試みているのだろうが、こういった言い方にするのが良いのか悪いのか、人に寄るかもしれないが、「命題1」に関しては、ぼくとしては中平の「出来事」という硬めの訳語のほうが感覚に合っている。
何しろ、この「出来事」というのは、今後深まってくる「論理学」の学説に接続していくわけだから、ある程度硬い表現でいてくれたほうが、ぼくとしては感覚が一貫していて通り易いと感じる。
それに、その後に現れる「命題1.12」では、中平/訳「なぜならば、事実の相対が出来事たることを規定し、また、すべて出来事ならぬことも規定するからである」となっているところ、丘沢/訳の場合「ひとつのことはそうであるか、そうでないかのどちらかだが、その他のことはすべてそのままである可能性がある」となっているように、全てひらがなで砕けた訳語だと、逆にややこしい表現になってしまっているところもあるからである。
しかし、他の言葉となると逆に丘沢/訳のほうが分かり易く、中平/訳のほうが分かりにくい……という事もあるので、そういった事で翻訳は2種類あると、1種類の時よりも読解が捗るのである(あくまでぼくがやり易さを感じるというだけだが)。
このように「翻訳者の解釈の違いによって、その言葉の意味の振れ幅に対してある程度の想像がつくようになる」……というのは、ぼくがロラン・バルトの『テクストの快楽』を読んだ時に学んだ教訓であった。
『テクストの快楽』も、1種類の訳書だと意味が分からないものでも、2種類の訳書を同時並行で読む事で、その「言葉の意味の振れ幅」に対して想像がつくようになり、ある程度のニュアンスを掴む事ができたと考えている。

まぁ、2冊ぶん読むなんて言う苦労をするくらいだったら、素直に原著を読めばいい話なのだが、ぼくにとっては外国語の原著を辞書を引きながら読むくらいだったら、日本語の訳書を読んだほうが何倍もラクなので、このような事をしているわけである。
フランス哲学も、ドイツ哲学も、英米哲学も、全てを読もうと思ったら、そういう風に割り切ったほうがいいと思いませんか?
◆◆◆
現在読んでいる3冊の内、丘沢静也/訳の『論理哲学論考』には、冒頭に「高校生のための『論考』出前講義」という、『論考』の内容を分かり易く要約した文章が掲載されている。
つまり「これから読む本はこれこれこういう内容ですから、それを頭に入れて読むと良いですよ」という入門講義的な内容だ。
この「高校生のための『論考』出前講義」は、本書の訳者である丘沢静也ではなく、野家啓一という人が執筆している。この方のプロフィールが見当たらなかったのでWebで少し調べてみたら、物理学から哲学に入った人で、科学哲学と分析哲学が専門の人だと分かった。
だからだろうか、やはりこの解説文はウィトゲンシュタインを、フレーゲとラッセルの記述論理学を継承する思想家として捉える見方を採っているようなニュアンスを感じるのである。
「真理関数の理論」を通じて「トートロジー」という概念を確立したことこそ、「論理学の革命」へのヴィトゲンシュタインの最大の貢献でした。この命題論理に相当する「真理関数の理論」は『論考』を支える重要な柱のうちの一本にほかなりません。
『論考』が当時のヨーロッパの哲学界に衝撃を与えたのは、現代論理学に基づく厳密な論理学的世界像を構築したこともさることながら、それを基盤に偶像破壊的な哲学観を提起したことによります。
こういった説明は、ぼくが知りたかった「ウィトゲンシュタイン思想の"何"が当時のヨーロッパに影響を与えたのか」という部分を明快に答えていて参考になる。
が、この人の説明はけっきょくウィトゲンシュタインの功績のうち、分析哲学の文脈のほうを重く扱っているので、例えばウィトゲンシュタイン自身が師のバートランド・ラッセル(記号論理学の祖の一人でもある)に対して指摘した「誤読」については、あえて目を瞑っているように思えるのである。
ウィトゲンシュタインの本意としては、「命題7」の「語る事ができない事については、沈黙するしかない」が『論考』の重要なメッセージだったようだが、ウィトゲンシュタインを分析哲学の側から受け取ると、また別の見方となるようなのだ。
内側から境界線を引き終えたとき、そこで哲学の活動も停止するのである。おそらくはその境界線上に立ち尽くしたまま、ヴィトゲンシュタインは「7 語ることができないことについては、沈黙するしかない」とぶつやいて本書を締めくくります。語ることのできないものを前にした彼の深い沈黙は、まさに世界の重さと釣り合っているのです。
このように、野家啓一のニュアンスだとこの「命題7」に含まれる意味とは、「立ち尽くした」「深い沈黙」などと言った、どちらかと言えばネガティブ寄りな捉え方と言えるのではないだろうか。この、内側の「哲学の活動」の範囲内こそが、真にウィトゲンシュタインの語りたかった部分であるかのように。
これは、ぼくが飯田隆『ウィトゲンシュタイン 言語の限界』や鬼界彰夫『ウィトゲンシュタインはこう考えた』を読んだ時とは、逆のニュアンスと感じられる。
――ところであなたは私の主要な論点を本当に把握されていないのではないでしょうか。論理的命題に関する作業は私の主要な論点からすればたんに付随的なことにすぎません。主要な論点は、命題によって――すなわち言語によって――表現し(語り)得るもの(そして同じことですが、思考し得るもの)と命題によって表現され得ないで、ただ示され得るものについての論究なのです。この論究こそ哲学の中心問題だと信じます。
上の文章(※バートランド・ラッセルが『論考』に寄せた序文について、ウィトゲンシュタインがラッセルに送った書簡の内容)を見ても分かるように、ウィトゲンシュタインにとってみれば「論理的命題に関する作業は私の主要な論点からすればたんに付随的なこと」にすぎなかったわけである。
つまり、ウィトゲンシュタインからすれば分析哲学的な部分をメインに受け取ってもらうのは「本意ではない」と考えていた様子なのである。
が、ぼくとしてはこういう学者の立場による見解の違いというのは、非常に興味深い。
ウィトゲンシュタインの真意については、鬼界彰夫の著作で説明されていた、遺稿研究によって明らかにされた内容によって、ある程度その内容は知る事ができた。
それに対して今度の読書で期待できるのは、『論理哲学論考』のテクストのみによって影響を受けた分析哲学派の側の『論考』の受け取り方が理解できるのではないか……という部分でもあるのだ。
そして何より重要なのは、当時の西洋思想に影響を与えたウィトゲンシュタインというのは、こちらのほうで解釈されたウィトゲンシュタイン像なのだ、という事である。
今回副読本的に利用しようと思っている『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』の野矢茂樹も、恐らく「論理学」の側から『論考』を解釈してくると予想しているので、ぼくの『論考』理解もより重層的なものが期待できるのではないかと思えるのである。
◆◆◆
※以下、「◆読書日記.《ルートヴィッヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』》――その2」に続く。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
