
◆読書日記.《岡田雅勝『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』》
<2023年4月1日>
<概要>
私がウィトゲンシュタインに魅せられたのは"ことばの問題"であった。彼は、私がそれまでに触れたどの書よりも、言語を人間的な生に基礎づけていた。彼は、哲学の問題をことばの展望にみて、それを生の流れにおいて把握したのであった。彼の哲学探究は、人間的生の理解と深く結びついている。
彼は自分の生を振り返り、つぎのように語っている「人は何度も躓き倒れるが、なすべきただ一つのことは立ち上がり、やり直し継続することだ。少なくともこのことが私の生涯でやらなければならないことであった」。彼は生涯不安や憂愁に悩まされ、激しい精神の苦悩に陥った。しかし彼は、何事にも情熱的で、純粋で、誠実であった。それだけ一層、生みの苦しみを通して綴られたウィトゲンシュタインの厳しい思索は、きっと私たちの生の真実の何かについて大いなる示唆を与えてくれるであろう。
<編著者略歴>
岡田雅勝(おかだ・まさかつ)
1935年北海道に生まれる。1963年北海道大学大学院文学研究科(修士)修了、専攻、哲学。旭川医科大学名誉教授。著書『ウィトゲンシュタイン――人と思想』(清水書院)、『小熊秀雄――人と作品』(清水書院)。編著『知ることと生きること』(東信堂)。訳書 バーンシュタイン『パースの世界』(木鐸社)、モンク『ウィトゲンシュタイン』(全2巻、みすず書房)、プライス 『ホワイトヘッドの対話』(共訳、みすず書房)。監修訳書 カルバー/ガート『医学における哲学の効用』(北樹出版)ほか。
岡田雅勝『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』読了。
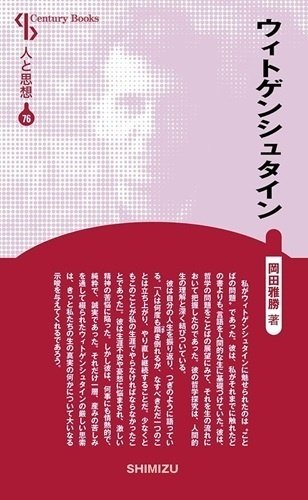
自分は毎年、詳しく学ぼうと思っている思想家を一人絞って、その人に関する本を集中的に読んで勉強し、最終的にその思想家の主著の一つを通読する事を自分への宿題として課してる。
この習慣を続けるようになってから6~7年くらいたっているだろうか?
その成果として、西洋近代哲学についてはある程度ものを言えるようになったのではないかと思っている。
で、今年はルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインである。
ぼくは書店や古本屋で西洋思想・哲学本をチェックする事は多いのだが、ウィトゲンシュタインは割と入門書や概説書なんかが割と多い人なんじゃないかと思っている。
西洋思想家の中でもプラトン、カント、ヘーゲル、マルクス(とりわけ『資本論』関連)、フロイトなどは日本人の著作も非常に良く見かける。次いで、ハイデガー、フーコー、レヴィ=ストロースあたりか。
ここら辺の思想家は、入門書や概説書は割と充実していて勉強しやすいんじゃないかと思う。
それに対して、ここ数年でチェックした内では、サルトルやソシュールは、意外と関連書籍が少なかった。
ソシュールは『一般言語学講義』以外に著書がないから仕方ないとして、サルトル関連の書籍については、一時期のもてはやされ方から比べて驚くほどの少なさだった。
ぼくが今年ウィトゲンシュタインを課題に選んだのは、単に今までウィトゲンシュタイン関連の本で気になったものを購入していたら、自然と十数冊ほどに膨れ上がっていたからである。これを、ここでいったん消化しておこうというわけなのだ。

それで、その第一冊目として選んだのが、思想家を学ぶ際には必ずと言って良いほどチェックしている清水書院さんの「人と思想」シリーズである。
ぼくは毎年思想家について勉強する際は、まず評伝から入るのがいつものパターンとなっている。
たぶん思想家の概要を知るためにその人の評伝から入るというのは、ぼくの中ではマルクスとフロイトを勉強した時からの習慣になっていると思う。
その人がどういう生い立ちでどういう性格で、どういった行動を好み、何に影響を受け、どの国で何を学んだのかは、意外にその人の思想を知る際には馬鹿にならない情報だと思っている。
(ちなみに、マルクスの評伝についてはイギリスのコラムニスト、フランシス・ウィーンによるマルクスの伝記『カール・マルクスの生涯』が抜群に面白く、内容も纏まっていたのでお勧めだ。フロイトについてはラッシェル・ベイカーの『フロイト その思想と生涯』が非常に読みやすくて面白い)

例えば、共産主義を批判するのに「マルクス主義」の教祖のような存在であるカール・マルクスをやり玉にあげる、なんていうのは単純な間違いだ(「間違い」というよりかは、「それは十分ではない」或いは「きわめて紛らわしい」と言ったほうが正確かもしれないが)。……というのは、マルクスの性格と人柄を知っていればやらない間違いだろう。
そもそも共産主義思想を作り出したのはマルクスではない。
マルクスが共産主義者の中で神格化されたのは、スターリンや毛沢東といった人物らが、勝手にマルクスの名を担ぎ上げていただけなのではないかと思っている。
例えば、フランスの新しい政党が「自分らはマルキシストである」と宣言したと聞いた時、マルクス自身は「少なくとも、私はマルキシストではない」ともらしたとも言われている。<第1インターナショナル>総評議会の代表も、断れずしぶしぶ引き受けたほどである。
マルクスは、基本的には群れない個人主義者だ。
マルクスの本質は、陽気で戦闘的な「論争家」で、酒と煙草とジョークが大好きな陽気な社交人であって、真摯な哲学者たらんとした怒れるアジテーターだった。
そんな「毎晩酒場に現れる髭モジャの怪人物」が、マルクスという男であった。

マルクスは、批判すべき点は味方でさえ容赦なくコテンパンに批判したので、若い頃の友人のほとんどが論敵になったそうだ。
マルクスの本質は「論争」にあるので、その著作のほとんどは「批判」に充てられていた。巨大な著作『資本論』でさえが、そうであった。
こういう性格から言って、マルクスは党派的な考え方はさほど持っていない。間違った考えだと思えば共産主義者だろうと「マルクス主義者」を標榜する人物だろうと、徹底的に批判しただろう。
こういう「マルクス個人の思想」というのは、ぼくは『資本論』全三巻を通読してもなかなか見えてこず、「マルクス入門」的な本を読んでもサッパリそこら辺の言及が無かった。
それがマルクスの評伝『カール・マルクスの生涯』を読んだ事で「ああ、そういう事であんなに厄介な『資本論』なんてシロモノを作ったのか」とスッキリ理解できたのである。
◆◆◆
……という事で、ウィトゲンシュタイン入門の第一弾として、世界の思想家の思想と生涯を紹介する清水書院さんの「人と思想」シリーズ『人と思想76 ウィトゲンシュタイン』である。
ウィトゲンシュタインについては過去、『論理哲学論考』だけは通読した事があったのだが、これは読みだしてからすぐ「これはただ単に通読しただけでは意味がない本だな」と思ったのを覚えている。

『論理哲学論考』の中身をペラペラとでも眺めた事のある人だったら、すぐその特徴に気付くだろう。
具体的な理論や結論を提示しているというよりかは、ほとんど「命題集」といった感じで、それら個々の命題について全く具体例がないために「ウィトゲンシュタインの提示した骨格を具体化し、肉付けしていくのは読者の役目」といった風なのである。
つまり『論理哲学論考』という著書は一文一文、自分の中で「これはどういう事なのだろうか?」「つまり、具体的に言えばどういう事なのだろう?」という作業をしなければ意味がなく、抽象的な数式を見せられているだけといった感じなのである。
『論理哲学論考』の分量自体は少ないものの、そういった作業が必要なので、単に「通読した」からと言って、その本を理解できたとか、少なくともぼくの中では「読んだ」などと納得はできなかなかったわけである。
そんなわけで『論理哲学論考』は、いつかリベンジが必要だな、と以前から少しずつ入門書の類を集めていたわけである。
◆◆◆
本書は非常に読みやすい内容で、ウィトゲンシュタインの思想についても(詳細な内容にまでは踏み行っていないものの)俯瞰的に見渡せて、入門としては非常に良書だなと思った。
やはり思想家の評伝は面白い。本書は評伝としても非常に面白く読めたがのが良かったと思う。
ウィトゲンシュタインの人柄というのも随分とはっきり把握できたのが良かった。
彼はウィーンのユダヤ系の大富豪の家に生まれた八人兄弟の末っ子だった。
1889年生まれで、同じ年に生まれたのがアドルフ・ヒトラーであり、20世紀最大の思想家と言われたマルティン・ハイデガーであり、イギリスの歴史家トインビー等といった人物らがいたそうだ。
ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが生まれたオーストリア=ハンガリー帝国の首都ウィーンは自然豊かで、芸術の都、音楽の都としても有名。ウィトゲンシュタイン家の兄弟たちも芸術に影響を受けており音楽家、画家などを志望していて、末弟のルートヴィヒも芸術に親しんでいた。
この家の父・カール・ウィトゲンシュタインは実業家として当時ドイツのクルッペ、アメリカのカーネギーに匹敵する大財閥を率いており、プロテスタント倫理に支えられ異常な熱心さで仕事にあたっていたという。
兄弟たちは、そんなカールの後継ぎとして非常に厳しく育てられた。長兄ハンスなどは父の跡目を継がせるために楽器の演奏を禁じられていたともいう。
兄や姉たちは非常に優秀な人たちだったようだが、四人いた兄のうち実に三人が自殺している。
ルートヴィヒさえも、しばしば彼の日記や書簡に「自殺」をほのめかす内容が書かれている事からも、何故かこの家の兄弟たちは若い頃から軒並み憂鬱症、自殺衝動に支配されていた事が分かる。
本書を読んで思ったぼくの印象としては、その後のウィトゲンシュタインの人生を見ていっても、彼は「厳格な父・カールの重圧」を内面化していたのではないか、などと思ってしまうのである。
ウィトゲンシュタインは非常に情熱的な所があるが、どうも他人との距離感を計れない人物だったようで、しばしば知人と衝突している。しかもそれはだいたいウィトゲンシュタインから当たっていたトラブルだったらしい。
彼はIQが高すぎる人特有の、他人とのコミュニケーション・ギャップがあったんじゃないかとも思える。本書によれば、俗物や低レベルな人を露骨に見下すような傾向もあったという。
この人はどうも頭が良すぎるだけではなく、「ほどほどの所で妥協する」というブレーキが壊れていたんじゃないかと思えるところもあって、そのためにしばしばトラブルを起こしていたのだろうと思われる。
彼がトラテンバッハの小学校の教師となった際、「情熱的な指導」という事で生徒を容赦なく平手打ちにしたり頭をげんこつで叩いたりしていたという。それに無理解な親にも寛容ではなかったらしく、自分から誤解を解こうともしなかった。
揚句、もともと身体の弱かった生徒を平手打ちにしてしまった事で生徒が気絶して倒れ、その事が原因で教師を辞任してしまったという。
そんな人だったからこそ他人とはなかなか相容れず、自分の思想を突き詰めるために寒村に引き籠って質素な生活をしていた事もあった。
確かに、そのほうがこういう性格の人にとっては、楽だったのかもしれない。
「異常なほどの徹底的な完璧主義者。自分にも他人にも絶対に妥協を許さず、全力で情熱的に事に当たるために、しばしば精神的にも肉体的にも疲労困憊していた難儀な人」……というのが、ぼくのウィトゲンシュタインの印象だ。
「厳格な父・カールの重圧」を内面化していたのではないか……というぼくの精神分析的な予想は、こういった性格傾向から考えた事であった。
検閲官としての「父」が自分の内面に存在し、彼の思想や行動を常に監視している。だから彼は物事を中途半端に妥協する事を自分自身に許されず、また自ら内面化している「父」が、他人にも妥協を許さなかったのではないか……というわけだ。
ウィトゲンシュタインの、自分に対してさえ妥協のない厳しさというのは、ほとんど自罰的とさえ言えるのではないかという所までいっている。
前述したように、彼はしばしば自殺について考えていたという事もあるが、例えば、大学で教えていた頃などは、しばしば自分に対しても罵倒を与えていたという。
自分の講義で納得がいかない生徒がいれば直ちに反論を求め、それができないと「ストーブと議論してるみたいだ!」と激しく非難する一方、自分の考えに納得できないと「ちょっと待って、考えさせてくれ!」といって授業中に一人、しばらく沈思黙考に入ったという。そして「私はバカ者だ!」「君達は酷い教師を持ったものだ!」等と、自分自身を酷く罵倒したりもしたのだという。不幸な性格をしている。
彼は子供の頃にカトリックの洗礼を受けているが、彼自身がカトリック信仰を実践したとはいえないと言われている。
しかし、ウィトゲンシュタイン自身は「私は宗教的人間ではないが、私はどんな問題も宗教的観点からしか見ることができない(本書P.202)」と言っており、何故か「宗教」には生涯にわたって拘っているのである。
ウィトゲンシュタインは、彼自身の性格と経験から審判者及び救済者としての神の考えを納得することができたと思う。しかし創造とか永遠とかの観念から導かれる宇宙論的な神の考え方は彼には我慢ならないものであった。
つまり、ウィトゲンシュタインの深層心理の中で、「神」の座にある検閲官であり審判者である「父・カール」の存在があったからこそ、彼に神の存在のうち「審判者及び救済者としての神」の側面のみを受け入れさせていたのではないか、とそう思うのである。
彼は一時、イギリスでプロペラの設計なども行っており、数学では数学基礎論に興味を持っており、数理科学などにも適正があった。
それだけロジカルな考えを持ち、徹底的に突き詰めて考える性格の彼が「神」という存在の内で「審判者及び救済者」の部分のみは、その存在理由を許したという所に、彼なりの複雑な心理が隠れているようにも思えるのである。
◆◆◆
ウィトゲンシュタインの前期思想はカントの超越論的観念論と似た所があり、超越論的言語論といったスタンスが見えるという。
この人の性格は確かにどこかカント的な所があるかもしれない。
はっきりと物事の区別を求め、ごまかしや曖昧な所を嫌い、究極の答えを常に求めているというスタンスだ。
こういう究極的なものを求める思考傾向というのは、確かに数学的に答えが一意的に決められる学問には親和性があるだろう。
だが、そういった数学的思考では道徳や信仰や人間関係といった問題には答えられない。
『論理哲学論考』のコンセプトを考えると、彼はその事に酷く悩んでいたのではないかと思えてくる。
「神」の存在証明というのは、デカルトやスピノザがやっていたように、昔から西洋哲学では重要なテーマであった。
だが、その「神」の存在証明というのは、遂にカントによって「神の存在は、われわれの扱う論理では証明する事が出来ない」と言う事を完全に証明させられてしまったのである。
ウィトゲンシュタインも、妥協を許さぬその考えから、そういう結論に至らずにはいられなかっただろう。
だが、それでも彼は「神」や「道徳」といった、論理では説明する事のできない<価値>について否定する事がなかったようだ。
カント的なロジックでは、「神」は死ぬしかないだろう。
が、それでもウィトゲンシュタインは「神」を延命させた。彼にはそれを延命させたかった、という動機があったのではないかと思うのである。
その妥協案として、論理的なわれわれ人間の認識では捉えきれない領域を以てして「語りえぬことについては沈黙せねばならない」という線引きをしたのではないか。
それが『論考』執筆の動機になっていたのでは……と、まだウィトゲンシュタイン入門の一冊目の段階ではあるが、今の所そういう予測を立てておこうと思っている。
「神を信じることは生の意味に関する問いを理解することである。神を信じることは世界の事実によって問題が片付くのではないことを見てとることである。神を信じることは生が意味を持つことを見てとることである。」――ウィトゲンシュタイン『日記』より。
◆◆◆
さて、このようにざっと見ていくと、その人の人生が、その人の作り上げた思想に全く影響を与えていないなどと言えないだろう。
思想家の性格が見えてくると、その人の思想傾向というのも何となく見えてくる。
そういったものが見えてくると、無味乾燥な思想に思えるものにも、その裏にあるその人なりの血の通った肌触りのようなものが感じられるようになる。
フロイトもマルクスも、その評伝を読んで、その思想には彼等の生きてきた人生における何かしらの影響の痕跡がある事が分かったし、それによってその人の「基本スタンス」というのも、ぼくには理解しやすかった。
これが、ぼくが毎回のように思想家の評伝を読む動機になっているのだ。
