
◆短評集・その1
<前口上>
昨年あたりからこの「note」にUPしている文章の分量を意識して長くしている。
それは在野のぼくでも、いわゆる「職業批評家」と呼ばれている、雑誌などに書評を乗せてお金を貰っている職業の人たちと変わらないレベルの記事を書く事は出来るのだ――と、何より自分自身に対して証明したいがために、雑誌なんかに載る記事のレベルを想定して書いているためだ。
そのため、当然ネットで読む人向けの書き方にはなっていない。
最近では1万字を越える記事もコンスタントに書くようになった。
さすがに、ブラウザなんかでぼくの記事を読んでくださってる人なんかには、長くてキツイかろうなァとぼく自身も思っているのだが。
それでもあえて、バズるタイプの書き方にはしていないのである(申しわけない……ぼくの記事が読みにくい、という方はプリントアウトして読むほうが読みやすいかもしれません)。
という事で、ここしばらくは読むよりも、どちらかと言えば書くほうに注力している部分があるかもしれない。
なので読了後に「あまり参考にならなかったな」とか「これはぼくが何か書いても屋上屋を架すだけになっちゃうな」とか、そういった諸々の事情でレビューを書かないでいた本が何冊かある。
さほど価値を感じなかった本に対して今まで通り本気で分析して時間をかけてしまうよりも、他のSNSでサッと簡潔に短評を書いて済まして、早々に次の本に移ろう……と、していたわけである。そのほうが効率的だろう、と。
しかし、最近はその手の本にあたる機会がちょこちょこあったので、「note」のほうにレビューを掲載する間隔も随分と開いてしまった(これはプライベートがバタバタしているという事情も関係しているが)。
そういうわけで、これまで簡単なレビューしか書かずにいた本が何冊か溜まってきたので、その内のいくつかををまとめて「短評集」という形で紹介しておこうと考えた次第である。
<恩蔵絢子『脳科学者の母が、認知症になる』>
<内容>
六五歳の母が認知症になった――記憶を失っていく母親の日常を二年半にわたり記録し、脳科学から考察。得意料理が作れない、昔の思い出に支配されるなどの変化を、脳の仕組みから解明してみると!? アルツハイマー病になっても最後まで失われることのない脳の可能性に迫る。「認知症の見方を一変させる」画期的な書。
<著者>
恩蔵絢子 (オンゾウ アヤコ)
1979年神奈川県生まれ。脳科学者。専門は自意識と感情。2002年、上智大学理工学部物理学科卒業。07年、東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻博士課程修了(学術博士)。茂木健一郎との共著に『化粧する脳』、翻訳書に『顔の科学』などがある。
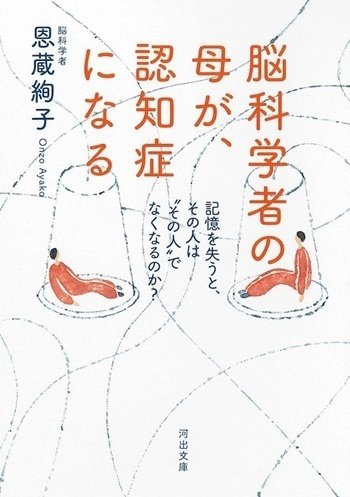
実はぼくの父親は7~8年ほど前から認知症にかかっており、ぼくもたびたび実家に戻っては父親の身の回りの世話をしなければならない状態になっていた。
その父親も昨年、遂に一人では風呂もトイレも行けない状態になってしまったので、流石に24時間介護をするわけにもいかず、介護老人施設に入ってもらう事となった。
そういったわけでぼくも今後は少し余裕ができるかと少しホッとしていたのも束の間、今度はいつの間にか母が認知症にかかっていた事が発覚する。
地元の警察官の方から「貴方のお母さまから家に泥棒に入られたと通報を受けたので御宅に来ているのですが、調べたところ、その形跡は全くありません。ですが、お母さまが納得されておりませんので、こちらに来ていただけませんか?」とぼくの所に連絡が来たのである。
そんなわけで実家へ急行してお巡りさんと相談、どう考えても母の思い違いとしか思えない状況なので、母と一緒に実家じゅうを引っ繰り返してやっと「泥棒に盗られた」と称する通帳の類を見つけ出したのだが、これが一日がかりの作業となってしまった。
改めて母とじっくり話してみると、どうやら「盗難妄想」がかなり進行しているようだという事に、そこで初めて気付いたのだった。
「盗難妄想」というのは、本書にも書かれているし、認知症の専門外来のある病院のホームページにも必ずと言って良いほど紹介されているほどには、アルツハイマー型認知症にかかった人にはあらわれやすい症状なのだそうだ。
お財布は、とても大事な物なので、強く存在を覚えている。そして、本人が「お財布はどこだったかな?」と確認しようとしたとき、たとえば、前回出かけたときに、いつもとは別の鞄で出かけて、お財布をそれに移し替えた、ということを忘れているとすると、いつもあるべき鞄に「今ない」という事態が生じる。
アルツハイマー病の人にとっては、最近の出来事の記憶は頼りにならないので、「今ない」という事実しかないことになる。「ない」のはおかしい、自分は何もしていない(通常誰でも自分が自分でお財布を隠すということは考えづらいはずだ)、だからこそ、自分以外の「誰か」が何かしたのではないかと推測することになる。自分以外にやる人は、他の人しかいないからである。
現状のおかしさには、脳は、なんとか理由を付けて理解しようとする。だから、この病気の人でなくても、大事な物をなくすなどして、うまく理由を辿れないと、「あいつが悪いのではないか」と他人を疑ってしまう。今現在の状況(「大事な物がない」という状況)と、常識(「自分で自分の物を隠したりはしない」という常識)から、普段からそれを一番やりそうに見える人に濡れ衣を着せてしまうのだ。
で、ぼくの母の場合は「隣家の親父が自分の知らない内に家の中に侵入してきている」と思い込んでしまっていた。
ぼくがすぐピンと来たのは、ぼくの友だちが以前「note」に上げていた春日武彦 『屋根裏に誰かいるんですよ。』のレビューで「侵入妄想」について紹介していたのを思い出したのである。
ぼくの母は、まさしくそれであった。
それからというもの、母から「大事な通帳が盗られたんだけど、警察に連絡したほうがいい?」とか「保険証が盗られた、きっと隣の親父のせいだ!」とかいった電話が頻繁にかかってくるようになる。
先日などは、母が「銀行のカードを盗られた」と思って銀行に連絡して口座を凍結してしまった騒ぎがあった。
これで父母両方の銀行の口座が使えなくなってしまったので、これを再度再開させるために各銀行を母を連れて回り、各銀行の担当者の方々に父の介護施設まで来てもらって手続きをして……という非常に面倒くさい仕事をしなければならなくなってしまったのだ。
これだけでないのが頭の痛い所なのだが、徐々に実家の状況が本格的にヤバイものだと判明してきた。
母の記憶がかなり頼りなくなっているため、現在実家の通帳やら保険証書の類やハンコやその他重要な書類などの場所が曖昧で管理されず、ぐっちゃぐちゃになっていたのである。
いま家の資産がどれくらいあり、それは何を見れば分かるのか、母がまったく理解していなかったのだ。
それどころか「隣の親父に見られると危ないから、家計簿をつけるのをやめてしまったの」と言う理由で、現在の実家のお金の出入りについてもほぼ管理できていない状況だったのである。
ついその一年ほど前までは、高齢者であってもまだ母は意識も考えもちゃんとしていると思って油断している合間に、とんでもない事態になっていたのだ。
徐々に状況が分かると同時に、ぼくの顔も青ざめていったのもご理解頂けるのではなかろうか(高齢者を抱えた家庭にはこういうトラブルが起こる可能性があるという事、皆さまも知っておいて損はないでしょう……)。
実際、ぼくはその当時かなりショックを受けていたと言えるだろう。
しかし、パニックになってはいけない。
恩蔵絢子さんの『脳科学者の母が、認知症になる』は、この事態について自分なりに不安や混乱を収め、自分の中で状況を整理するための知識の一つとして参考にしようと手にした一冊なのである。
いつでも正しい知識と理性は、人の心を落ち着かせてくれる。これは「未知の事態」ではないのだ、対処の方法はあるのだ……と考えるだけでも、自分の不安をいくらかは静めてくれる。
著者も指摘している通り「知る」「理解する」という事は安心に繋がるのだ。何より、著者の恩蔵絢子さんはぼくとほぼ同年代だというのも、何だか心強く思えた。
そんな本書は脳科学者の恩蔵絢子さんが、65歳で認知症になった自分の母親との暮らしを踏まえ、認知症とは何かという事を脳科学的に考察して「メディアで話題」となった本なのだそうだ。
確かに個人的に読んで自分の当時不安だった心情はある程度和らいでいったというのはあるのだが、「レビュー対象」としては、あまり触れられる部分が少ないな、と思ったのが正直な感想であった。
理由は幾つかあるが、これは単純に本書が一方的に悪いというわけでもない。
読んでいて気付いたのは、本書の著者である恩蔵絢子さんは「脳科学者」ではあっても専門は「自意識と感情」であって、あくまで認知症の臨床や研究に関わっているわけではないという事だった。
要するに本書は「認知症の専門家ではない著者が、脳科学の知見を認知症に罹った母に当てはめて考えてみた」という内容だったのである。
ぼくも著者が「脳科学者」という肩書を前面に押し出しているために、てっきり認知症についても専門家なのかと思い込んでしまっていたが、そうではないのである。
ぼくも脳科学については興味があって何冊か読んでいるが、本書で紹介されている知見はその手の脳科学の本から得られるものが多く、普段から脳科学についての本を読んだ事のない人にとっては非常に分かり易く親切な解説になっているものの、少しその手の本をかじった事のある人にとっては、ほぼ想像の範囲内の話に終始してしまっていたのである。
また、認知症の高齢者に対する接し方についても、多くは認知症外来を行っている病院のホームページに書かれている情報よりも役立つ、というほどのものでもない(病院のほうが専門で認知症を扱っているのだから当然なのかもしれないが)。
本書のメイン・テーゼである「感情こそ知性である」……つまり、認知症で記憶が失われたとしても、その人本来の感情の豊かさであり性格であり、といったものは変わらず、本人らしさが失われたわけではない、人が変わったと言って恐れたり不安になったりせず、理解しましょう……という結論についても、次々に認知症にかかっていった両親を抱えて日々コミュニケーションをとっている内に自然とその考えになっていたので正直「え、そういうもんじゃないの?」とあっけなささえ感じてしまった。
だが、こういった認知症や脳科学についてまだじゅうぶん知らない人にとって本書は、今後高齢者と接する際の心構えにもなりそうでなかなか良い内容なのではないかとも思う。書きぶりも難しくなく、エッセイ感覚で読めるかもしれない。
ぼく個人としても、同世代の人間で同じような悩みを抱えた人物いると知れただけでもじゅうぶん心強いものがあり「気晴らし」的には良かったが、内容については、そういった個人的な事情以外にはあまり触れられる点はぼくにはなかった。
自然、ぼくのこのレビューもほとんどエッセイ的な書き物になってしまったわけである。
<杉晴夫『日本の生命科学はなぜ周回遅れとなったのか』>
<内容>
明治維新以降、日本への欧米の科学技術の導入は見事に成し遂げられ、直ちに生命科学史に名を刻む巨人たちを輩出した。しかしこの輝かしい成果はその後すぐに破壊されてゆく。原因として、一、独創的研究を評価せず他人を妬む国民性、二、大学教授たちの利己性による後継者の矮小化、三、教授たちの提案を唯々諾々と受け入れる政府の人々の見識の欠如、四、真に独創的な研究を評価し広く報道すべき新聞や学術誌編集者の能力の著しい劣化がある。さらに深刻な打撃となったのが国立大学の独立行政法人化である。現在もワクチン等医薬品の開発でも世界に対し周回遅れの日本。九十歳近い今も研究を続ける筋収縮研究者が、自身の経験を振り返りつつ、日本の生命科学を若い独創性に富む研究者の力で救い出す方策を提案する。
<著者>
杉晴夫(すぎはるお)
1933年東京生まれ。東京大学医学部助手を経て、米国コロンビア大学、米国国立衛生研究所(NIH)に勤務ののち、帝京大学医学部教授、2004年より同名誉教授。現在も筋収縮研究の現役研究者として活躍。編著書に『人体機能生理学』『運動生理学』(以上、南江堂)、『筋収縮の謎』(東京大学出版会)、『筋肉はふしぎ』『生体電気信号とはなにか』『ストレスとはなんだろう』『栄養学を拓いた巨人たち』(以上、講談社ブルーバックス)、『論文捏造はなぜ起きたのか?』(光文社新書)、『天才たちの科学史』(平凡社新書)、Current Methods in Muscle Physiology(Oxford University Press)など多数。日本動物学会賞、日本比較生理生化学会賞などを受賞。1994年より10年間、国際生理科学連合筋肉分科会委員長。

以前のぼくのレビューで日本の電器産業の第一線で活躍して来た著者が本の電機産業の凋落の原因を解説した桂幹『日本の電機産業はなぜ凋落したのか』という本を紹介したが、ぼくが本書のタイトルを見て思ったのは「うわー、日本は生命科学の分野でも周回遅れになってるのか……」という事だった。
まぁ、薄々感づいてたけどネ。
という事で、本書は著者の主張する「日本の生命科学が周回遅れとなったワケ」を詳しくお聞きしようと思って読み始めたものである。
これは、もしかしたら桂幹『日本の電機産業はなぜ凋落したのか』にも共通する原因が出てくるかもしれない。
例えば、全く違う業界であるにも関わらず、似たような原因での凋落が起こっている場合は、個々の業界の特殊事情が絡んでいるというだけではなく、何かしら日本の文化的な瑕疵や日本組織の構造的な欠陥のようなものも見えてくるのではないか……という腹づもりもあった。
それにしても、著者のプロフィールが凄い。
戦前生まれの学者で日本の生命科学の分野でもう60年以上も研究を続けている人だそうで、本書を執筆した時点で御年88歳。その上まだ研究を続けていた現役研究者だったという。
今回、改めてプロフィールを調べて見たところ、つい先日の2月26日にお亡くなりになられていたらしい。
本書はサブタイトルに「国際的筋肉学者の回想と遺言」とあるように、最晩年に自ら体験して来た日本の学界についての問題点や不満点をまとめて忌憚なくぶちまけてやろうという気概が感じられる。
何しろ、冒頭からけっこう怒りに任せたような記述がちらほらと見られるほどである(笑)。
著者は「はじめに」にて、本書のメイン・テーゼたる「日本の生命科学が周回遅れとなった原因」を大きく以下の四点に分けて説明している。
一、独創的研究を評価せず他人を妬む国民性
二、大学教授たちの利己性による後継者の矮小化
三、教授たちの提案を唯々諾々と受け入れる政府の人々の見識の欠如
四、真に独創的な研究を評価し広く報道すべき新聞や学術誌編集者の能力の著しい劣化
上のうち「一」と「二」の原因については、もう数十年も前から筒井康隆が『文学部唯野教授』にて大学内の政治的駆け引きや子供じみた嫉妬と足の引っ張り合い等といった状況を暴露しているし、フランス思想の内田樹がその著作で学会の若者の発表姿勢が「ポスト欲しさ」である事に失望したと書いており、またその後も大学の内幕暴露本は数々出ているなど、日本の大学内部の状況の問題についてはぼくも様々な所で見聞きしていた。
また、著者も指摘している通り、文科省による国立大学の独立行政法人化と、これに伴う競争的研究資金制度の問題についても、昨今X(旧Twitter)で話題になっていたのは記憶に新しい。
といったように、著者の指摘は昨今の学界関係者も声を挙げている事もあって、大筋間違った事は言っていないのだろうな、とは思うものの、この人の問題はそれをあまり説得的には説明していない所にある。
サブタイトルに「国際的筋肉学者の回想と遺言」と書かれているように、学界の問題については著者の「回想」によって告発されているものが多く、それらの根拠は「個人的な経験」に基づいているのである。
「自分はこんな仕打ちを受けた事がある。こんな事をやっていては学界はダメになってしまうだろう」「あの組織はいつもあんなことをやっている、あれではダメだ」といった内容では、少々説得力が薄い。
また、関係者の名前は角が立たないようにイニシャルでぼやかしてあるために、余計に説得力が下がってしまった。
要するに、その主張に関する傍証となる数値や具体的証拠といったものが弱いのである。もっと定量的な説得材料はなかったのか?
例えば、冒頭に掲げられている生命科学を衰退させた原因の一つである「独創的な研究を評価し報道すべき新聞や学術誌の編集者の劣化」についても、著者が自信を持っていた自分の研究成果について「以前の記者は自分の新聞で紹介してくれたのに、昨今の記者は紹介してくれないので、ほとほと呆れた」などというエピソードを紹介してその根拠としているのである。
その他にも、そういった科学記者の劣化の原因の一つとして著者が挙げているものは「ゆとり教育」というのもあるようだ。
二〇〇五年の新学期、最初の授業を始めて驚いた。これまでの新入生は、初めて聞く生理学の授業に緊張して静まり返っていたものだが、この年の新入生は、最初からだらけきっており、教室は私語でざわついている。
授業を始めると、さらに驚いた。何を話しても、「それがどうした――」としらけきっている。もちろん講義が終わっても質問に来る学生はいない。私の友人である国立大学で講義をしている者に尋ねると、みな学生の態度の急変に驚いている。
これが、あの悪名高い「ゆとり教育」を受けて高校を卒業してきた学生たちの出現であった。私は不愉快になり、その年から講義を止めてしまった。
こういった書き方をしているものだから、これはどうも著者の単なる「恨み節」なのではないか?と疑問に思わざるを得なくなってしまう。
特に学界の教授らにアンケートや統計をとったとか、学界のほうに問題提起してこのような反応が得られたとか、この人なりの客観的な調査や情報といったものは乏しく、個人の主観に基づく意見が多いのである。
特にマズイのは第一章「明治維新に夜欧米の学問の我が国への移植」であった。
これは蛇足であるだけでなく、この章があるために本書の全体的な論旨さえも胡散臭くなってしまったという印象が強い。
著者によれば、日本が東洋で唯一西欧文明の急速な移植に成功した要因を「武士が我が国の政治の実権を握ったため」だったとする。
これを証明するために日本の歴史を中世まで遡って説明するのだが、これはまるまる1章使って説明するほどの説得力があるわけでなく、著者の見解も「私見」どまりで論旨が粗雑。
更に最終章で今後の日本の科学界を立て直すための著者からの提言をする内容のラスト数ページが、著者が現在うちこんでいる研究内容のすばらしさを自己喧伝して締めくくっているのである。
考えてみれば、本書を読むと著者のプロフィールを見ずとも、自然と著者の生命科学分野での功績の数々を知る事が出来る……という書き方も、どうにも胡散臭い。
ぼくとしてはここら辺、筒井康隆『文学部唯野教授』の作中で恥かしげもなく他人に自慢話をする教授らと同じような雰囲気さえ感じてしまったほどだ。
本書のサブタイトルが「国際的筋肉学者の"回想"と"遺言"」となっているのは、著者があまり自制せずに、文句も自慢も好き放題言ってしまおう、という意思が出てるのではないかと思ってしまう。
……という事で、本書も学術的に参考になる知見は色々と掲載されてはいるのだが、それはほとんど「日本の生命科学はなぜ周回遅れとなったのか」という問題に答える部分ではなく、そのテーマから外れた科学史の部分であったり、著者の専門の神経科学の分野の知見であったりという部分ばかり。
情報量が多い割には「日本の生命科学はなぜ周回遅れとなったのか」というテーマを真正面から論じる部分に関しては情報量が薄くなり、関係者や組織名などの具体名は伏せ、個人的な経験則や私見で批判を行い、テーマとは直接関係のない部分についての学術的説明については饒舌になってしまうという、はなはだ偏った内容に終始してしまっていた。うーん、残念。
<増田四郎『歴史学概論』>
<内容>
歴史学とは何か。古代ギリシアのヘロドトスから、ローマ帝国末期のアウグスティヌス、ルネサンスの人文学者やフランスの啓蒙思想家を経て、十九世紀ドイツのランケに至って近代歴史学は成立した。その発達段階を明快に分析しながら、古代から中世への転換期の歴史意識の研究など、現代歴史学の問題点をも論及。西洋史学の泰斗が、「歴史することの妙味」と歴史を学ぶ心構えを懇切に説いた必読の書。
<著者>
増田四郎(ますだしろう)
1908年奈良県生まれ。東京商大卒業。一橋大学経済学部教授を経て一橋大学学長。現在、一橋大学名誉教授。主著は『独逸中世史の研究』『西欧市民意識の形成』『西洋封建社会成立期の研究』『西洋中世社会史研究』『都市』『ヨーロッパの都市と生活』『ヨーロッパとは何か』『社会史への道』『ヨーロッパ中世の社会史』など。

昨年から日本中世史家の網野善彦や西洋中世史家の阿部謹也など歴史関連の本も読むようになってきたので、ここで一度「歴史学」についての入門書を読んでおこう、という気になった。
が、ぼくがこの本について言及できる事はあまりない。
本書を読んでいて感じるのは、これは一般向けの歴史学入門書というよりかは、「歴史学を専門に学ぶ人向けの入門書」といった傾向が見られる事だ。
ぼくのような門外漢が読むには、本書で出される歴史学の考え方について、いちいち用語の正確な所を辞書やネットで確認してからでないと読み進められなかったのである。
例えば本書に出てくる「啓蒙主義」という用語についても、ぼくは自然と思想・哲学方面の考え方で読んでいたが、読み進めて行くうちに、あれっ、これはどうやらドイツ浪漫主義や歴史主義といった歴史学関連の思想の流れの中で読まねばならない用語らしいぞ?と気付いて、仕方なく辞書やネットでそれらの大まかな流れをチェックし直してからまた当該部分に戻って読み直す……といった作業を行わなければならず、しばしば読書を中断して調べ物をしながら読み進まなければならなかった。
これは例えば歴史学をこれから本格的に学んでいこうと思っている人に向けては有効となる、ある種ポータル的な書き方がされていて、今まである程度学んできた人向けに歴史学の情報を整理整頓するには割と良い内容なのかもしれない。
が、それらの説明が本書ではたびたび専門家の名前の羅列であり、有効となる書物の羅列であり、それら一つ一つには詳しくはここでは触れられない……というスタンスになっているので、一から勉強しようと思っているぼくのような一般人にとっては全く馴染みのない話ばかりになってしまっている。
すなわちこの期の偉大な歴史家としては、政治史におけるジーベル、ダールマン、ドロイゼン、トライチュケ、ミシュレ、トックヴィル、マコーレー、法制史におけるゲオルグ・ヴァイツ、マウラー、マイツェン、フェステル・ドゥ・クーランジュ、ギールケ、グナイスト、モルゼン、ストッベ、ブルンナー、文化史におけるブルックハルト、テーヌ、ビュッヒァー、シュモラー、イナマ・シュテルネック、ユダヤ・キリスト教史におけるウェルハイゼン、ルナン、クリューガー、ハウク等々の名が想起せられるが、古代史とか中世史とか、あるいは各国の近代史という観点からすれば、さらに別個の多数の史家を挙げなければならないのであって、詳しくは各領野における学説の発達史を、個別的に顧みる必要に迫られるであろう。補助的諸科学の発達に関しても、事情はまったく同一である。
……例えばこのような記述が続いたりするものだから、これは「資料」的な書籍としては悪くないとは思うものの、少なくとも「読み物」としては無味乾燥で、読み進めるにはかなりキツイ(笑)。
また、本書を読んでいて少し気になったのは、上の引用中に現れる人名などにも出ているように、著者が紹介する歴史学者や歴史書の多くがドイツ関連が多いという点であった(因みに、上の引用文中、歴史家25人のうちフランス人4名、イギリス人1名、その他ほとんどはドイツ系の歴史家であった)。
本書を読んでいても著者が明らかにドイツ史を専門としている事は文章からありありと伝わってくるものの、その他の、例えばフランス歴史学会やイタリア歴史学会、中国、ロシア、日本の歴史学会などの状況についてもほとんど触れられていない。
本書に何度も名前の上がる歴史家も、近代歴史学の父たるレオポルド・フォン・ランケはもとより、社会学のマックス・ウェーバー、唯物史観のマルクス、といったいずれもドイツ系の学者ばかりである。
著者の説明からすると、近代歴史学を確立させたのがドイツ歴史学会であり、また西欧のヨーロッパ史学を抜きにしては説明しえないから、西洋文献と西ヨーロッパの歴史学の発展を重点的に説明せねばならないという事なのだが、それにしてもドイツ史学に偏りすぎでは?と疑問に思ってしまう。
何しろそれまでの西ヨーロッパの歴史学の流れがまさに「ヨーロッパ中心主義」の史観で発展して来たという部分もあり、何がしかの偏ったスタンスがあるのではないかと疑ってしまうのである。
例えばフランス歴史学会について言うならば、『『アナール』学派と社会史』にて竹内敬温が「今世紀、歴史の研究にたいして、『アナール』学派ほど大きい影響を与えてきた学派はない」と言っているように、フランス歴史学の流れも無視できる内容ではないのではないか?とも思えるのであるが、本書では一言さえ「アナール学派」については言及せず、それどころかほとんどフランスの歴史研究については言及していないのである。
ぼくも歴史学については全くの門外漢なのでこの件については確かな事は言えないのだが、こういう事があるからこそ、一冊だけで確定的な事を言う事は出来ず、ぼくも新しいジャンルを学び始めるたびに何冊もの入門書を読まねば気が済まないのである。
……という事で、こちらを読み通すのはたいへんだった。次回歴史学の入門書に挑む際は、もうちょっとレベルを下げて一般向けの入門書にあたりたいと思う。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
