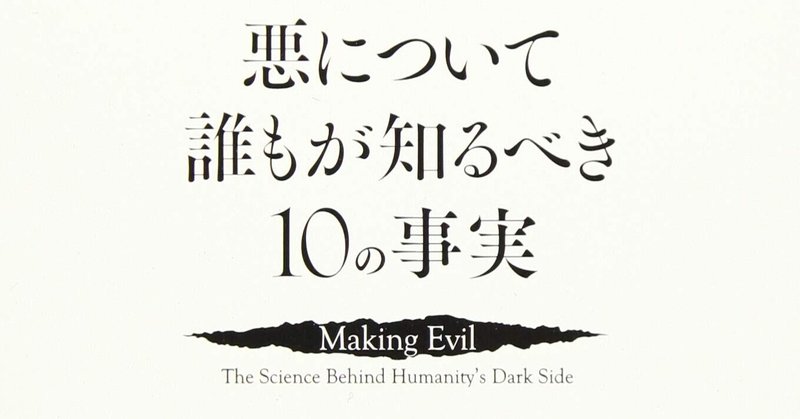
ジュリア・ショウ 『悪について誰もが知るべき 10の事実』 : 〈悪魔〉は存在しないという現実
書評:ジュリア・ショウ『悪について誰もが知るべき10の事実』(講談社)
『言ってはいけない 残酷すぎる真実』などの著作で知られる、橘玲「推薦!」の文字が帯に踊っていて、目を惹いた。しかも、タイトルが『誰もが知るべき10の事実』というのだから、きっと橘玲の前述書と同様、人間という動物の、あまり知りたくない科学的事実を突きつけてくる類いの本かと思って購入したのだが、予想していたのとは、ちょっと方向性が違っていた。
本書は、橘のそれのように、私たちがあまり知らない、あまり知りたいとは思わない事実を突きつけてくる態の本ではなく、おおよそのことは知っているけれど「あまり考えたくはない」と思うような問題について、それへの直視と思考をうながす、非常に真面目な本であった。
そして、そうしたものの実例として挙げられるのが、個人名で言えばヒトラーやアイヒマンであり、殺人犯を代表とする各種犯罪者や、最近ではあまり使わなくなった各種「性倒錯者」「狂人」の類いである。
私たちは通常、自分が「凶悪な犯罪者」の資質を秘めている人間ではないと思っているし、性的な「変態」の類いではなく、いたって「ノーマル」な人間だとも思っている。しかし、よくよく考えてみれば、相手に非があると思えた場合に、自分の親兄弟や子に手を出したことも一度や二度はあるだろうし、また男性ならばポルノDVDを見る場合に、単なる合意セックスものではなく、より刺激的な強姦ものや痴漢もの、近親相姦もの、SMもの、各種フェチシズムものなどを視たりすることもあったはずだ。
私は男なので、女性のことはよく知らないが、魅力的な金持ち男性とのSM恋愛に溺れる女性を描いた映画『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』が大ヒットするところを見ると、男性ほどではないにしろ、女性もアブノーマルなセックスに、ある種の魅力(性的刺激)を感じる部分があると見て間違いない。
男女の別なく、人間というのは、暴力に快感をおぼえる部分が確実にあるし、これは人間もまた弱肉強食の動物から進化して、当初は狩猟民であったことを考えれば当然の「本能」であり、何らかの理由で自制心(理性)が弱まれば、誰でも暴力を振るうし、人殺しだってする、ということだ。
また、自分が直接に手を下さないのであれば、つまり人の手を借りて殺せるのならば、その敷居は極端に低くなって、本書でも言及されるナチスのアイヒマンのようなことを、多くの人がきっとやってしまうことだろう。
変態セックスも同様で、自分は「比較的ノーマル」だという「保身的意識」は、当然のこと誰にもあるだろうが、完全に匿名性が担保されるならば、なんらかの変態的なセックスを試してみたいという人のほうが、むしろ多いのではないだろうか。
私は、自分で考案した格言として、以前からしばしば「知識人は、断然マゾである」ということを言っている。これはどういう意味かと言うと、人間というのは高度に知性が発達した動物で、そのためにその想像力は「本能」の域をあっさりと超越してしまう。また、そうでなければ、人間は高度な文明を築けなかっただろう。
つまり、知性が優れているほど「変態」性(倒錯性)を帯びているのは当たり前で、動物の攻撃本能や支配欲に似ているがために比較的受け入れられやすい「単純なサディズム」よりも、普通は恥ずかしくて公然とは認めにくい「複雑なマゾヒズム」の方がむしろ、よほど「知的な人間のものだ」と言えるからだ。
したがって、通常の場合、多くの人が自身について、公に自認しないのは無論、内心でも否定している、自身の暴力性や犯罪遂行性、あるいは性的な倒錯性といった、「悪」とされ、忌避されやすい性質は、じつのところ非常に一般的なものであり、さらに言えば(アーレントの言うとおり)「凡庸」なものでしかない。
言い変えれば、私たちは誰しも「殺人者(犯罪者)」であり「性的倒錯者」なのだが、しかし、それが「世間」から非難をされないように、あらかじめ私秘的に消費解消されているだけだ、とも言えるのである。
『 アーレントは悪とはありふれたものと論じ、ジンバルドーやミルグラムのような学者たちは、誰でも環境次第で邪悪になれると論じる。私はさらに先へ進み、悪があまりにありふれたものであることが、この概念の完全性を損なっているといいたい。誰もが邪悪である、あるいは誰もが邪悪になれるとすれば、それでもその言葉は意図する意味を持つのだろうか? 悪が考えられるかぎり最悪の不名誉に与えられるものでなければ、それはいったいなんのために存在するのだろう?』(P 280)
本書の中で、いちばん重要な指摘は、この部分だろうと思う。
つまり、人間を「善人と悪人に二分して、自分を善人の側に措く(ノーマルとアブノーマルに二分して、自分をノーマルの側に措く)」という、よくある「自己中心的二分論」が知的に論外なのは、議論の大前提である。
そのうえで、さらに「誰の中にも、悪はある。したがって、私の中にも悪がある」という反省的認識が「一歩前進」なのは言うまでもないが、「だから、本質的には、価値観の相違があるだけで、絶対的な善もなければ悪もないので、私たちは謙虚かつ慎重にならなくてはならない」と、いかにももっともらしく、実質的な「判断保留の傍観者」であることを自分に許してしまっては、何のための知性か、ということになってしまうので、「それでもこの難問に挑む態度こそが、知性の名に値する」という「結論」にこそ、私たちは至らなければならないのだ。
したがって、私たちは「絶対的な善や悪が存在しない」ということを大前提として、それでも「この世には、現に善も悪もあり、私たちは誰しも、時と場合によって善にも悪にもなる。だからこそ、その悪と戦わなければならない」という具合に、あらゆる事象に対して「是々非々の現実的かつ冷静な判断と行動」を選ばなければならないだろう。
私たちは、こうした前提において、頭の悪い絶対主義(二分論)にも、安易な相対主義(一体論)にもとらわれることなく、現実の「悪」と、慎重に対峙していかなくてはならないのである。
そして、本書の、やや感情的にナイーブな著者(「肉食パラドクス」を訴える場合に、「植物」の生存権への考慮が捨象されているのではないか)の訴えも、こうした点において基本的には正しいし、私たちは、著者の至らなさを挙げつらうことで、自己の「現状肯定的自己正当化」を謀ってはならないだろう。
いくら、著者の議論の穴を見つけたところで、その読者の中から、本質的な「殺人者性」や「性的倒錯性」が消えてなくなるわけではないからである。
つまり、私たちは、他者の「悪」を指摘することで、自分が「正当化」されると感じてはならないのだ。それでは、最も素朴な「善悪二元論」に立ち戻ってしまうことになる。
そうではなく、私たちは「私は悪だ。だからこそ、自分の悪と戦う手段として、他者の悪と戦うのである。そして、そうした戦いを遂行している時にだけ、私たちは善であり得ているのだ」と考えるべきなのではないだろうか。
初出:2019年11月18日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
