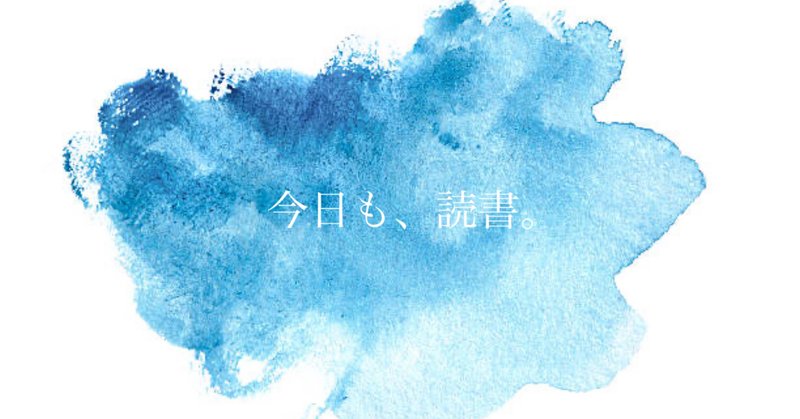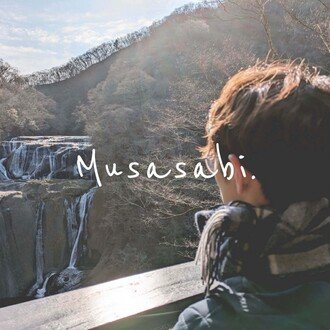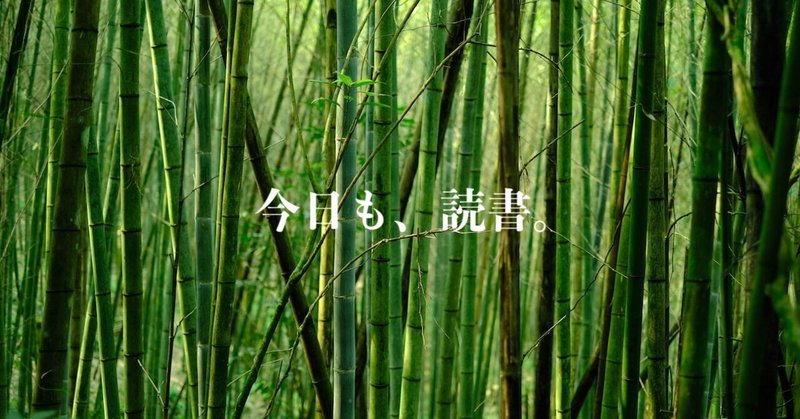#推薦図書
今日も、読書。 |”旅”と”旅行”の違いについて
旅について書かれたエッセイが好きだ。
若菜晃子さんの『途上の旅』や、星野道夫さんの『旅をする木』など、心に残っている作品はいくつもある。
自分の部屋で寝転びながら、遠い異国の地へ飛び立てる。旅のエッセイは、インドア派の私に翼を授けてくれる。
今回ご紹介するのは、私がこれまで読んできた旅に関する本の中でも、とりわけ面白いと感じたもの。
人類のDNAに古来から刻み込まれた、旅への欲求。それは現
今日も、読書。 |子供も大人も、見ている世界は同じなのだから
ブレイディみかこ|ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー
ものすごく有名な作品なので、説明は不要かと思う。2019年のYahoo!ニュース本屋大賞ノンフィクション本大賞受賞作。新潮社のベストセラーになっている。
著者のブレイディみかこさんは、イギリスのブライトン在住。アイルランド人の夫と、息子の「ぼく」と3人暮らし。現地で保育士として働きながら、ライターとしても活躍されている。
文庫版の
今日も、読書。 |本づくりに携わる全ての人へ、感謝を込めて
何冊も何冊も本を読んでいると、自分の手元に本があることが当たり前のように思えてくるが、この世に存在する本は一冊一冊すべて、本づくりに携わる誰かの手で、1から作られたものなのだ。
その人たちがいないと、私がこれまで出会った本も、今読んでいる本も、これから出会うはずの本も、存在せず読めない。
本を作る人たちのことを書いた本を読みたいと思い、安藤祐介さんの『本のエンドロール』を読んだ。本が好きだけれ
今日も、読書。 |"泣き本"をお探しの方へ
メフィスト賞を受賞し、横浜流星さん主演で映画化もされた、『線は、僕を描く』。
著者の砥上裕將さんは水墨画家でもある。水墨画のディープな世界を掘り下げながら、心に傷を負った青年が成長していく姿を描いた。
私は本作を読み終えたとき、砥上さんが次に書く小説は必ず読もうと決めた。心が掴まれるとはこのことか、と思った。
次はどんな題材を取り上げるのだろうと、ずっと楽しみにしていた。そして、あえて事前情
今日も、読書。 |児童文学、子供の頃の自分と対話する
今回取り上げるのは、Podcast「本の海を泳ぐ」のテーマ本として読んだ、神沢利子さんの『流れのほとり』だ。
大学生になってから本を読み始めた自分にとって、「児童文学」はあまり馴染みがなく、新鮮な気持ちで読んだ。
大人になってから児童文学を読むと、忘れかけていた子供の頃の感性が蘇り、当時の自分と対話するような読書になった。
「たまには児童文学も読んでみると面白い!」今回は、それを言いたいがた
今日も、読書。 |「だれかのための短歌にもなると思います」
2022年の秋頃から、東京の読書会に、月1回参加している。
読書会の魅力のひとつに、「普段自分では手に取らないような本と出会えること」がある。
読書会で紹介される本は、本好きが「他の人にも知ってほしい」という熱量を持って紹介しているだけに、素敵な本ばかりだ。
今回ご紹介するのは、そんな読書会で出会った作品である。
その本を持ってきた人がお話ししている間、あまりに良すぎて、私は終始うずうずし
今日も、読書。 |幼い頃のワクワクした読書を、無意識に探している
幼い頃、読書は今よりももっと新鮮で、キラキラしていた。そんな気がする。
私が本格的に本を読むようになったのは、大学生になってからだ。
しかし、高校までの期間にも、ごくたまに本を読んでは、「読書って楽しい」となんとなく感じていた。
小学生の時には、エミリー・ロッダのファンタジー小説『デルトラ・クエスト』に夢中になった。中学生の時に伊坂幸太郎さんの『ラッシュライフ』に度肝を抜かれ、高校生の時に森
今日も、読書。 |花咲く人情譚 ~「良い短編集」を読みたい人へ
時々無性に、「良い短編集」を読みたくなる。
例えば、サリンジャーの『ナイン・ストーリーズ』や、向田邦子さんの『思い出トランプ』、伊与原新さんの『月まで三キロ』のような。
短い物語の中で、しっかりと心を揺さぶり、感動させてくれる。そんな、完成度の高い短編集を、どうしようもなく読みたくなる。
乙川優三郎|五年の梅
乙川優三郎さんの『五年の梅』は、第14回山本周五郎賞を受賞した短編集。意外にも、
今日も、読書。 |内田洋子さんの魅力を伝えたい
内田洋子|カテリーナの旅支度 イタリア二十の追想
読書ラジオ「本の海を泳ぐ」、2回目のテーマ本として選んだ作品は、内田洋子さんの『カテリーナの旅支度 イタリア二十の追想』。数ページほどの短編が20作品収められたエッセイ集だ。
「本の海を泳ぐ」で自分が選書をする番になったら、最初は内田洋子さんの作品にしようと決めていた。内田洋子さんの作品の魅力を、少しでも多くの人に知ってもらいたかったからだ。
今日も、読書。 |信念と時代の狭間で
カズオ・イシグロ|浮世の画家
カズオ・イシグロさんといえば、2017年にノーベル文学賞を受賞したことで有名だ。長崎で生まれ、幼少期にイギリスへ渡り、以来英語で小説を執筆している。日本にルーツを持つ作家がノーベル文学賞を受賞したということで、当時非常に話題になった。
『わたしを離さないで』『日の名残り』といった彼の代表作に、「日本」の要素はあまり見られない。しかしデビューしたばかりの頃は、日本に
今日も、読書。 |世界を動かすのは、いつだって個人の努力と好奇心だ
J・ティプトリー・ジュニア|たったひとつの冴えたやりかた
聞き惚れてしまうような、美しいタイトル。
原題は「The Starry Rift」。直訳すると「星の亀裂」とでもなるのだろうか。浅倉久志さんの邦訳の、素晴らしさが光る。
J・ティプトリー・ジュニアさんの『たったひとつの冴えたやりかた』。本作は、3つの中編作品から成る。
宇宙の大図書館で、連邦草創期の人間(ヒューマン)に関する3つの文
今日も、読書。 |ダンテ『神曲』をめぐる追跡劇
ダン・ブラウン|インフェルノ
「インフェルノ」とは、「地獄」のことである。
ダン・ブラウンさんの『インフェルノ』は、ダンテの『神曲』<地獄篇>を題材としており、「地獄」が重要な鍵を握る。そして、物語に隠された「インフェルノ」のもうひとつの意味に気付くとき、読者は戦慄する。
ちなみに私は、ダンテ の『神曲』は当然の如く未読である。
『インフェルノ』は、『ダ・ヴィンチ・コード』で一躍有名になっ