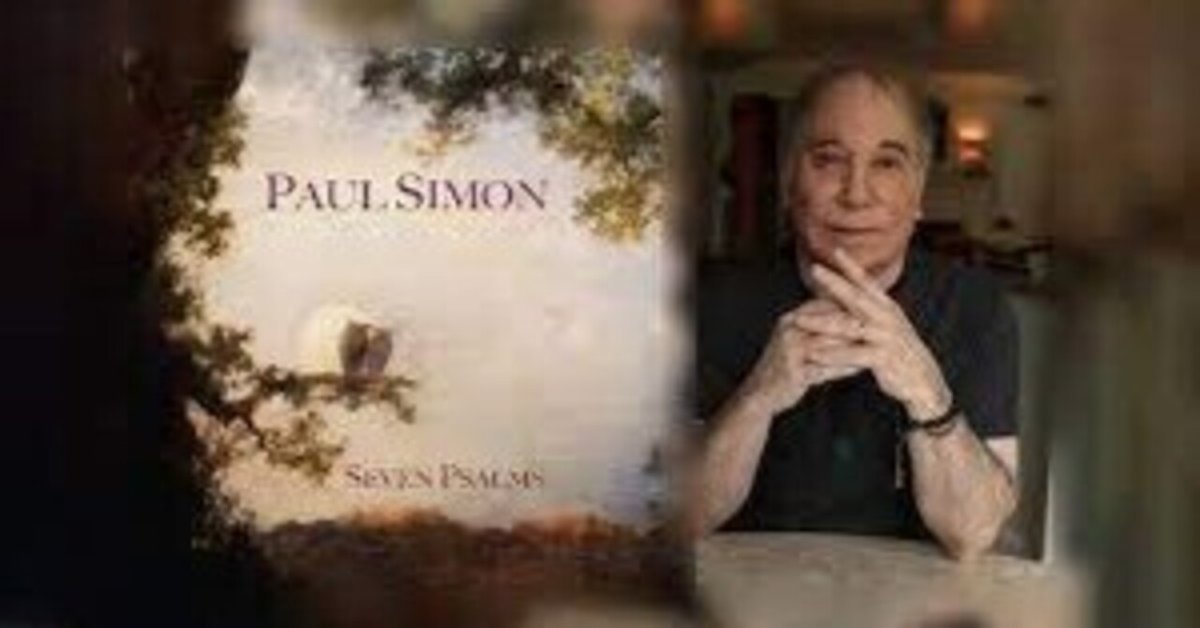
ポール・サイモンが伝える「神」の声 新アルバム「七つの詩篇」をめぐって
80歳を超えて宗教臭くなった?
ポール・サイモンは2016年、75歳のときにニューヨークタイムズのインタビューで、
「終わりが近づいている。ショービジネスに対する興味がなくなった。少しもない」
と述べ、引退を示唆した。
そして、2017年12月、長らくバンドメンバーだったギタリスト、ヴィンセント・ヌギニ(Vincent N’guini)が肝臓ガンで65歳で亡くなったのをきっかけに、2018年2月、正式にツアー引退を発表、9月に故郷のクイーンズで引退コンサートを行った。
しかし、その後もテレビで演奏を披露していたし、レコーディングも続けていたから、コンサート復帰の可能性をファンは信じていたはずだ。
そして81歳になった今年、タイムズのインタビューで、左耳の聴覚がほぼ失われたことを告白し、ファンに衝撃を与えた。
その難聴は、加齢によるものか、大音響を聴きすぎた演奏家の職業病か、あるいはコロナの後遺症なのか(彼はコロナに罹患していた)、正確なところはわからない。
彼自身によれば、2019年のある日、夢の中で「声」が聞こえ、夜中に起きてその声を書き留めた。その作業によってできたのが「七つの詩篇」の歌詞だが、それが完成したと同時に、聴覚が失われていったのだという。
同じタイムズのインタビューで、ポール・サイモンは、最近のゴードン・ライトフット(84歳没)やジェフ・ベック(78歳没)の死に触れ、
「私たちの時代はもう終わった」
と言って、ツアー復帰を重ねて否定している。
昔のヒット曲を並べて、「ポール・サイモンのカバーバンド」のような音楽をやるのは、もうイヤだという。そういうところが、よりエンターテーナーとして徹底しているポール・マッカートニーなんかより真面目だな、と思う。
(とはいえ、作曲やレコーディング、少人数でのアンサンブルなどの音楽活動は続けたい、と言っている)
そして、今月、夢の中の「声」をもとに制作した新アルバム「七つの詩篇」がリリースされた。歌詞の中では「神(The Lord)」について、そして「旅の終わり」「死」についての思索の跡が見える。
アルバムの発表にともない、ポールはいくつかのインタビューを受けているが、老けたとはいえ、声も、ギタープレイも、頭も、まだしっかりしていて、ホッとさせられる。(難聴によって歌のピッチがフラットするのでダビングで調整している、と言っている)
だが、最近の言動や、「七つの詩編」の内容から、インタビュアーや世間の関心が、
「ポール・サイモンは年をとって、抹香臭くなったのか」
「神がかってきたのか」
「自分の寿命(mortality)を意識しはじめたのか」
という点に集まるのは、仕方ないように思う。
ずっと「神」の声を聞いてきたポール
しかし、ポール・サイモンの音楽に長年親しんできたファンは、彼と「神」との関係は昔から変わらない、と知っていると思う。
彼自身、上掲のCBC(カナダ国営放送)のインタビューで、以下のように語っている。
「私は宗教的な人間ではない。しかし、昔からずっと、この世のこと、自分は何者で、人間はどこに向かっているのか、ということを考えてきた I ‘m not religious but I think a lot about what you know who are we where are we that’s why I think」
「私は人生とは何かを知りたいと努めてきて、それを音楽的に表現してきただけだ。何かが頭に浮かぶと、私はそれを素直に表現する。それは私の感情のフェアな表現だと信じている I was just trying to make sense out of the whole big thing and express it musically and when things came out I said as I always do well do I believe that did I just say something that I think is a fair expression of what I feel.」
「(死について言うなら)いずれにせよ、我々は生きるのをやめるわけにはいかない。歳をとれば(死を)より意識するようになる。近しい人が死んでいくのは、たとえ若いときでも起こる。それはショッキングだが、仕方のないことだ。意識はせざるをえないけれど、でも、死が『七つの詩篇』のメインテーマではない。それは要素の1つにすぎない I mean you can’t it doesn’t stop you from living. You become more aware of it as it as you get older you’re thinking about that because you’re reminded of it all the time there’s people that I know who have died whereas when you’re young, When somebody dies for you it’s kind of shocking like it seem like it’s appropriate you know now yeah it’s the this is it happens. That’s inevitably on your mind but I don’t think it’s the main thing the seven psalms is about I think it’s just an element of it」
注意深く特定の宗教や宗派に帰属する言葉は避けながらも、彼が常に宗教的なテーマとともにあり、彼なりに神と対話を続けたことが読み取れる。
そのとおり、ポール・サイモンが「宗教的」なのは、今に始まったことではない。
具眼の士は、はるか昔から知っていた。
宗教学者の島田裕巳氏は、サイモン&ガーファンクル時代の「明日にかける橋」(1970)の宗教性について語っていた。
(「明日にかける橋」の)「Your Time Has Come to Shine」の「あなたの時が来て輝く」というのは、キリスト教社会ではイエスが再臨するということでしょう。「僕が荒波にかかる橋のようになる」、つまり犠牲になると言っていることも考えると、この歌は非常にキリスト教的。現代の讃美歌みたいな性格を持っている。
1970年に、私は宗教学を生業にすると思っていなかったわけだけれど、その後宗教学をやるようになっていくうえで、こういうものを聴いていたことも影響しているかもしれません。
ボブ・ディランのノーベル文学賞には僕はどうなの? と思っているところがあって。詩人としてはポール・サイモンの方が上なんじゃないかなって。
黒崎政男・島田裕巳 オーディオ哲学宗教談義「音楽における宗教性」
ポール・サイモンの歌詞の宗教性が、島田が宗教学者になるにあたって影響したというのは、驚くべきことではなかろうか。
「明日にかける橋」と同時代、ビートルズの「レット・イット・ビー」にも「マリア様」が登場する。私は、そういうのは、キリスト教圏特有の文化表現だろうくらいにしか思わなかったが、当時からポール・サイモンには、(たぶんポール・マッカートニーよりも)真剣な宗教性があったと考えるべきだろう。
そして、1970年の「明日にかける橋」の宗教性を言うなら、1964年の「サウンド・オブ・サイレンス」にそもそも宗教的メッセージがあったとも言えるだろう。
また、以前にも紹介したが、noteにも、ポール・サイモンの宗教的側面に注目して訳詞和訳をしている方がいる。
それに、比較的最近でも、ポール・サイモンの深い宗教性が語られるアルバムは今回が最初ではなく、約10年前の「ソー・ビューティフル・オア・ソー・ホワット」のときに指摘されていた。
米国の著名なシンガーソングライター、ポール・フレデリク・サイモンが、半世紀にわたるこれまでの活動の中に、いつも霊的な側面があると語るが、最近のアルバム「ソー・ビューティフル・オア・ソー・ホワット」には自身もびっくりしている、と言う。神、天使、創造、巡礼、祈り、死後、などについての曲なのだ。
米宗教専門RNS通信によると、宗教的なテーマは意図したものではなかった。サイモン自身、信仰深いとは言っていなかったが、米公共放送(USPBS)のプログラム「宗教と倫理ニュースウイークリー」のインタビューで、霊的なものには魅了される、と語っている。
「霊的感覚といったものがある。わたし自身の中に認め、それを楽しんではいるが、全く理解していないものだ」と言う。(クリスチャントゥデイ)
「七つの詩篇」
私も、「七つの詩篇」に耳を傾けたが、私の英語力では、彼のメッセージ(あるいは、彼を通した神のメッセージ)を十分に理解できた自信はない。
最初の曲(詩篇)「The Lord」は、こう始まる。
私は「大移動」について考えていた
昼に夜に、群れを離れて
その行き先に思いを凝らす
I’ve been thinking about the great migration
Noon and night they leave the flock
And I imagine their destination
「the great migration」は、アメリカの黒人が南部での迫害を逃れて北に逃れた大移動のことだがーーそしてポール・サイモンは長年黒人と連帯して差別と戦ってきたがーーここではそのアメリカ史の1コマと、「この世からあの世」「生から死」への移動を重ね合わせて、比喩として使っていると思う。
彼は、歌詞の中でも、インタビューでも、「死」の話題には慎重になる。私は彼のユダヤ人という出自にこだわるわけではないが、ユダヤ教では「死」や「死後の世界」に直接言及するのを好まない。と、ユダヤ人指揮者のオットー・クレンペラーの伝記で読んだ気がする。「怪力乱神を語らず」と同じようなことかもしれない。
一方、「神」については、以前にもまして大胆に語っている。
神は私のエンジニア
神は私の地の座席
神は空気の中の顔
私が行き惑う小径
The Lord is my engineer
The Lord is the earth I ride on
The Lord is a face in the atmosphere
The path I slop and I slide on
(「The Lord」)
「神」がいかに彼に身近なものかわかる。(彼は「God」という言葉はあまり使わない。彼の感覚で「宗教臭くなりすぎる」と思うのだろうか)
いずれにせよ、例によって彼の詩は一筋縄ではいかないが、老年期の感慨として、私の心にもしみる一節がある。
私は列の最後に並ぶ
門が閉まる前に
あなたの赦しを得たいと願いながら
And I the last in the line
Hoping the gates won’t be closed before
Your forgiveness
(「Your forgiveness」)
この部分は、ユダヤ教徒が聞くと、ユダヤ教の「ヨム・キプール Yom Kippur(贖罪日)」のことを指していると聞こえるらしい。
英米文化や、キリスト教・ユダヤ教の比喩が散りばめられているらしいので、日本人にわかりにくいのは仕方ないと思う。
私は、日本人の中でも、宗教と縁遠い方だ。
でも、80歳を過ぎて、こうした詩的な創造をおこなう彼の姿は、それ自体が励ましになる。
意味は完全にわからなくても、音楽として美しくて楽しめる。
ギタープレイは躍動感を失わず、声には人間味が増している。
7つ目の詩篇「Wait」まで聴くと、死への不安を慰める音楽として全体が構成されていると解釈するのが、やはり素直だと思う(そして最後はエーメンで終わる)。
「法悦」の表現
そこから、ポール・サイモンの過去の曲もあわせていろいろ聴いていた。
そして、改めて彼の音楽を振り返ると、今に通じる宗教性の表現は、1966年の「59番街橋の歌」あたりまでさかのぼれるかもしれない、と思うようになった。
歌詞の内容というより、その曲調である。
少し前、ポール・サイモンが、「59番街橋の歌」作曲の事情を語る1967年のライブをnoteで紹介した。
そのときも書いたが、「59番街橋の歌」は、70年代のレイドバックの気分、いわば「スピリチュラルな癒し」を先取りしたような曲だった。
気分が落ち込み、自問自答して苦しんでいたとき、ニューヨークの59番街橋でポール・サイモンを突然襲った高揚した気分こそ、神と通じている、という感覚から起こるラプチャー(法悦)と言うべきではなかろうか。この曲には教会音楽風のフレーズも挟まる。
ポール・サイモンはその後、そうした「法悦」の音楽を追求していったのではないか。そう考えると、彼の一連の曲を、島田裕巳の言うように「現代の賛美歌」として聞き直すことができる。
その追求は、同時期の「いとしのセシリア」をはじめ、バッハの「マタイ受難曲」を下敷きにした「アメリカの歌 American Tune」などを挟み、70年代から80年代にかけ、カリプソ、そしてそのルーツであるアフリカ音楽へと向かい、1986年の「グレイスランド」で1つの頂点を迎える、という見方はどうだろう。
シューズにダイヤモンド Diamonds On The Soles Of Her Shoes (1986)
そこには、一貫して法悦感に包まれた「賛美歌」の響きがある、と思えてくる。
同時代には、それは時代の趣味に合った音楽的なアドベンチャーとしか思っていなかったが(同時期にスティーブ・ライヒがアフリカ音楽からミニマル音楽を追求していた)、ポール・サイモンにとっては、もっと宗教的な意味がある探求だったと考えるべきなのだろう。
それは、「時代の声」と混じっていた、ポール・サイモンの「個人の声」が、年をへるほどに浮き上がってきたということかもしれない。老境に入ると「個」に戻るのは、誰もが経験することである。
ポール・サイモン全詞集
日本では、7月に『ポール・サイモン全詞集 1964-2016』という本が出る(国書刊行会)。
内容紹介は以下のとおりだ。
偉大なるアメリカン・ソングライター、50年の全仕事を集成
「サウンド・オブ・サイレンス」「ボクサー」「明日に架ける橋」などサイモン&ガーファンクル時代の名曲から、「僕とフリオと校庭で」「時の流れに」「グレイスランド」などソロ時代の傑作まで全203篇を収録した決定版全詞集がついに登場!
サイモン&ガーファンクル『水曜の朝、午前3時』[1964]からソロアルバム『ストレンジャー・トゥ・ストレンジャー』[2016]までの歌詞を収録(原詞も掲載、対訳方式)。稀代のストーリーテラーにして詩人であるポール・サイモンの歌詞を文学作品として味わえる画期的新訳! アルバム未収録・未録音作品のほか、ミュージカル『ザ・ケープマン』の全歌詞も完全収録。読みやすい2分冊(352頁/348頁)・美麗函入の永久保存版・愛蔵版仕様。
https://www.kokusho.co.jp/np/isbn/9784336074799/
多くの人にとって、ポール・サイモンというアーティストを振り返る、いい機会ではないか。
ポール・サイモンは、「サウンド・オブ・サイレンス」のころは青春の痛みを歌い、「ユー・キャン・コール・ミー・アル」のころは中年期の危機を歌い、今は老境の感慨を歌っている。
このように、1人のアーティストの生涯にわたる軌跡を同時代に知る機会はそうない。
そして、その底には一貫して、彼だけの「神」との対話を通じた人生の意味の探求がある。
その過程が「宗教的」になるのは、私にはきわめて自然なことに思える。
彼は本当に、我々みなが悩むような人生の悩みを同じように悩み、同じように感じ、それを、彼が言うように「正直に、フェアに」、そして比類なく芸術的に表現してきたのだと思う。
こういうアーティストと同時代に生きたことは幸運で、ポール・サイモンに改めて賛辞と感謝を贈りたい。
<おまけ>
たぶんポール・サイモンの動画で最も視聴回数が多い(もう1億回を超えている)「コール・ミー・アル You Can Call Me Al」。落ち込んでいるときに見ると元気をもらえる。みんなそうなのだろう。チェビー・チェイスと共演したミュージックビデオの傑作であり、「グレイスランド」の1曲だ。前妻が主催したパーティで、フランス人の作曲家ピエール・ブーレーズに「ポール」と呼びかけられたが、それが「アル」に聞こえた、という些細な出来事から生まれた。「俺の人生、これからまだ大変なのに、こんなにお気楽に生きてて大丈夫?」という愉快な曲だが、「中年期の危機」を茶化しながら、「天使」や「ハレルヤ」といった宗教的暗喩も登場し、やはり一筋縄ではいかない曲。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
