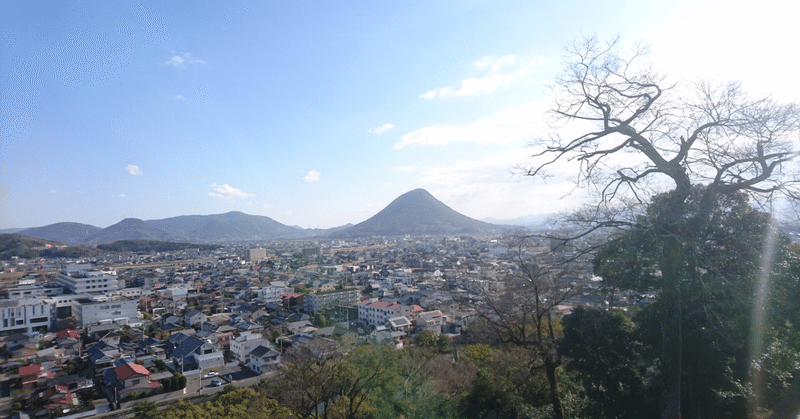2021年6月の記事一覧
富と貴きはこれ人の欲する所なり。その道を以ってこれを得ざれば処(よ)らざるなり。 (論語 里仁篇)
(意味) 富や名誉は誰でも手に入れたいものである。だが、真っ当な生き方をして手に入れたものでないならば、しがみつくべきではない。
仁を持った利でなければならない
日曜日(6月20日)の「大河ドラマ 青天を衝け」で引用されていましたね。そこで急遽取り上げることとしました。「論語と算盤」(渋沢栄一)では、「第四章 仁義と富貴」という章に現れます。
孔子は、富貴を卑しんでいる訳ではありません。そ
40歳になったので、思い切り迷うことにする。
本日2021年6月9日、40歳になった。
40と言えば、「不惑」。
論語でよく聞く、
「吾(われ)、十五にして学を志す」
から始まって、二十、三十ときて、四十がこれ。
「四十にして惑わず(四十而不惑)」
よくある日本語訳だと、
「40歳になると、心に迷いがなくなる」
「いやいや、そんなのムリでしょー」と思い、ひいては「論語のような清らかな生き方は、私には到底ムリだ」というイメージを抱い