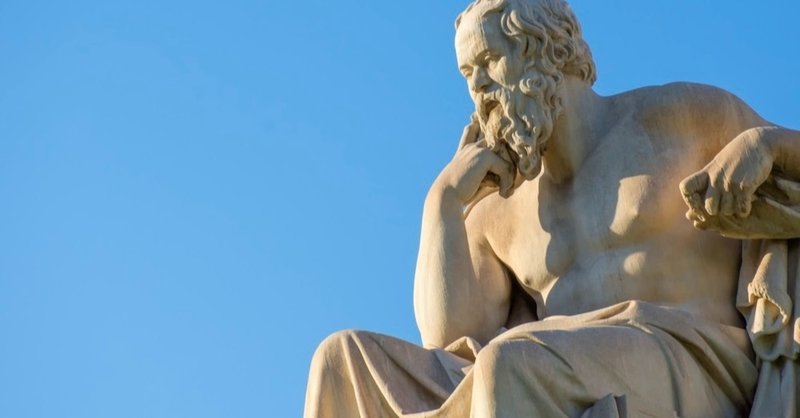
【note×standfm】読書の効用 偉人の金言編(PART1~PART5)
皆様、読書の秋、本番ですが如何、読書体験をお積みになっていらっしゃいますか?
私は4月からstandfmの配信を開始致しました。読書が飲み物の様に好きですので、最初は自身のインプット⇒アウトプット⇒アウトカムまでの射程の長い長距離マラソンを走りきるつもりでノロノロと配信を続けておりましたが、気づけば200回以上配信を続けるております。
note×standfmの読書の効用という配信を続けておりますが、他にも下記の3軸で活用をしております↓
◯私のstandfmでの展開方法
①通常収録=1冊の本にコミットして読み解く収録
②【マガジン】読書の効用=今回の偉人の金言も【マガジン】化して配信を続けております。その他個人の読書術や選書、マインド・セット、著名人の読書法、おすすめの書籍など・・
【note読書の効用】はこちら↓
③【コンセプト】
日々、書籍を飲み物の様に飲んでいるので、書籍の中でこれは!と思われる、キーワード(法則、理論、人物名称、地名、格言、金言)をブリコラージュして取っておいております。みなさんに共有出来るタイミングでダイヤの原石を加工して配信しております。
例えば・・・こんな感じです・・・
【第184回/エマニュエル・レヴィナス/他者の顔】
他者について向き合ってきた人は過去、たくさんいるので、その方々にご参集頂き、お話をして頂いております。マルティン・ブーバー、ミシェル・フーコー、フリードリヒ・ニーチェ、アルフレッド・アドラーなどなど・・・
以上①~③の3軸で活動をしております。
早速ですが・・・偉人の金言編へどうぞ~
読書の効用もDAY7(偉人の金言PART1)になりました。以前のstandfmの収録で二項止揚の話をさせて頂いた際に、二項対立をアップデートする形で二項止揚の思考について語りました。その際のテーゼが読書は無条件に良い行為だ!に対するアンチテーゼとして読書をするとアホになるを設定しました。その時に活用したのが偉人の金言でした。
アウフヘーベンすることにより、ジンテーゼとしてはより良質なインプットをしませんか?という内容になりましたが、今回はそのアンチテーゼの際に活用した偉人達の読書に対する金言を集めた回にしようと思います。ニーチェー、ショーペンハウアー以外にも読書の怪物の如き、リベラル・アーツを自身の血肉にしているような偉人たちの至極の一文をお届け致します。
【マガジン】読書の効用DAY7 偉人の金言①
1_フリードリヒ・ニーチェ
⇒ドイツ連邦、プロイセン共和国の哲学者ですね。ツゥラトゥストラはかくかたりきは有名ですね~アフォリズムの名手と読んでも良いですね
・万人受けする書物は常に悪臭を放つ書物である
・古い本をよむことで、新しい視点を持ち新しい仕方でアプローチ出来るようになる
2_アルトゥル・ショーペンハウアー
⇒ドイツの哲学者です。こだわりの強い哲学者だと個人的には思っております。
・読書は他人にものを考えてもらうことである、本を読むわれわれは他人の考えを反復的に辿るにすぎない
⇒他に読書についてではないですが・・・・人間のもっとも大きな罪は、彼が生まれてきたことにあるのだから・・と悲劇の真の意味を体現している一文です。
3_ルネ・デカルト
⇒フランスの哲学者。私の以前のstandfmでも方法序説を語りましたが・・・あらゆる学問を学んだ末・・・我思う故に我ありはとても有名な一言ですね。
・良き書物を読むことは過去の最も優れた人々と会話をするようなものである
4_セオドア・ルーズベルト大統領
⇒ご存知、アメリカの第26代目の大統領です。
ポーツマス条約の和平交渉に尽力して1906年ノーベル平和賞受賞
・私は自分がこれまでに読んだすべてのものの一部である
5_フランツ・カフカ
→不条理文学の代表選手ですね。カミュとならんで・・・
私の以前のstandfmでも変身を収録致しましたが、非常に性格の良い人だったようですね。
・書物は我々のうちなる凍った海のための斧なのだ
6_トーマス・ジェファーソン
→第三代アメリカ大統領/アメリカ独立宣言の起草者のひとり
・本がなければ生きられない
7_塩野七生
→日本の小説家、歴史作家・・・ローマ人の物語はあまりにも有名ですね。
・私は時間がなくて本も読めませんという弁解を絶対に信じないようにしています
8_ベンジャミン・ディズレ-リ
→イギリスの政治家、貴族
・たった一冊の本しか読んだことのないものを警戒せよ
9_ソクラテス
→古代ギリシアの哲学者、釈迦、キリスト、孔子と並び四聖(しせい)に数えられる。
・本を読むことで自分を成長させていきなさい。本は著者がとても苦労して身につけたことをたやすく手に入れさせれくれるのだ
10_丹羽宇一郎
→元伊藤忠会長、社長、元中国大使
・好きな本を読みなさい
11_フランシス・ベーコン
→イギリスの哲学者、神学者、帰納法や4つのイドラでも有名ですね。
ある本はその味を試み、ある本は飲み込み。少数のある本はよく噛んで消化すべきである
・信じて丸呑みするためにも読むな。話題や議論をみつける為にも読むな。しかし、熟考し熟慮するために読むが良い
12_手塚治虫
→日本の漫画家、映画監督。鉄腕アトム、ブラック・ジャックなど数々の作品を世に送り出してますね。
・漫画ばかりではなく、文学や科学書、紀行、評論集などの本に親しんで知識を広めることだ
・君たち、漫画から漫画の勉強をするのはやめなさい。一流の映画をみろ、一流の音楽を聞け、一流の芝居を見ろ、一流の本を読め。そして、それから自分の世界を作れ。
13_吉田松陰
→長州藩士、思想家、私塾である松下村塾(しょうかそんじゅく)を開所。伊藤博文、山県有朋などを排出した事でも有名ですね。吉田松陰自体は脱藩したり黒船に乗り込もうとしたり行動力が半端ではいない人でしたが。。
・今日の読書こそ、真の学問である。
14_モンテスキュー
→フランスの哲学者、著書の法の精神の中で三権分立を説いた事でも有名ですね。
・一時間の読書をもってしても和らげることのできない悩みの種に、私はお目にかかったことがない。
15_ゲーテ
→ドイツの詩人、劇作家、小説家、ファウストもご一読をオススメ致します。
・気のいい人たちは、読むことを学ぶのにどのくらい時間と骨折りがいるものか、知らない。私はそれに80年を費やしたが、今でもまだ目指すところに達したとは言えない。
【第162回/マガジン読書の効用DAY7】読書の金言①↓
【マガジン】読書の効用DAY8 偉人の金言②
前回は15人の偉人たちが語った、読書に付いての強烈なアフォリズの一文たちをご紹介をして、改めて読書とは何なのか?を語っていきました。前回ご招待して思う存分語って頂いたヤバ偉人の皆様は次の方々です・・・
今回も皆様・・・競合揃いでして、どなたも自身がまるでリベラル・アーツの如き人々でもありますが、その一文は本質を捉えており、その文章の裏側のメカニズムや時代背景に思いを馳せるだけでも相当に得られる物があると感じますね。
それでは、トップバッターですが。。。
16_M・J・アドラー
→コロンビア大学教授。以前のstandfmで収録しましたが、本を読む本の著者・アドラーによる金言です。
・すぐれた読書とはわれわれを励まし、どこまでも成長させてくれるものなのである。
17_三谷宏治
→虎ノ門大学院教授、元BCG、アクセンチュアのコンサルタントであり、経営戦略全史や新しい経営学、直近で私が収録した戦略読書の著者でいらっしゃいます。
・ひとは読んだ本で出来ている
18_国木田独歩
→小説家・詩人・ジャーナリスト/自然主義文学の代表選手ですね~
・読書を廃す、これ自殺なり。
19_キケロ
→古代共和制ローマの政治家、弁護士哲学者です。
・本のない部屋は、魂のない肉体のようなものだ。
20_司馬遼太郎
→小説家、ノンフィクション作家/梟の城や関ケ原/竜馬がゆくなどその書籍に影響を受けた人は膨大な数になると思われますが・・・
私も司馬先生の小説はたくさん読みますし、歴史的な背景を紐解くのにもとても参考になります。
・青春の思い出といえば、ふつう友人との間の思い出だから、図書館で友人もなく孤独でした。青春の思い出といえば、ふつう友人との間の思い出だから、図書館で友人もなく孤独でした。今、自分の十代の間に何ごとかがプラスになったかも知れないということを考えてみると、いくら考えても図書館しかない
21_ナポレオン・ボナパルト
→ナポレオン1世として皇帝になったことでも有名ですが、戦争の天才ですね。時代の要請により登場したとしか言いようがありませんが、一時期はヨーロッパの大半を勢力下においたほどでした。ブリアサヴァランの美味礼讃で語りましたが、食事はわりとせっかちに何でも食べる方だったみたいですよね。
・読書家の一族は、世界を動かす者たちなのだ。
22_ドストエフスキー
→ロシアの小説家、思想家。罪と罰、カラマーゾフ兄弟など非常に人間心理に到達した重たい内容の書籍が多く
・人間を理解にするには必読の書籍ばかりだと感じます。
・本を読むことを止めることは、思索することを止めることである。
23_オノレ・ド・バルザック
→19世紀のフランスの小説家。ゴリオ爺さんが有名ですよね。
・すばらしい書物とは、あらゆる思考の戦場で勝利を収めるものなのだ。
24_ジョン・ミルトン
→イギリスの詩人。失楽園が代表作ですね。ルネサンス期の長編叙事詩の代表作だと言えますね。
・良書を破壊する者は、知性を殺しているのだ。
25_トルストイ
→帝政ロシアの小説家、思想家、ドストエフスキーと並んでロシア文学を代表する文豪。
・すべての書を完璧に読む必要はない。心にわき起こる疑問に答えられるように読まねばならない。
26_アントン・チェーホフ
→ロシアを代表する劇作家の一人です。かもめ、三人姉妹などの戯曲がありますね。
・書物の新しいページを1ページ、1ページ読むごとに、私はより豊かに、より強く、より高くなっていく。
27_ヘルマン・ヘッセ
→以前のstandfmで車輪の下を収録しておりますので、ご興味あればご視聴下さい。ドイツ文学を代表する文学者ですね。ノーベル文学賞を受賞してますよね。
・書物そのものは、君に幸福をもたらすわけではない。ただ書物は、君が君自身の中へ帰るのを助けてくれる。
28_ビル・ゲイツ
→ご存知マイクロソフト共同創業者です。。。ビル・ゲイツも相当な多読家でよく書籍を初回してますしね。
・子どものころからたくさん本を読んで自分でものを考えろと言われて育った。両親は、本や政治や、その他いろいろなことについて、子どもたちを交えて話し合った。
29_福沢諭吉
→啓蒙思想家、教育者、著述家・・など肩書が多いですが・・・慶應義塾の創設者でもありますが・・・
・知識・見聞を広げるためには、他人の意見を聞き、自分の考えを深め、書物も読まなければならない。
30_ブレーズ・パスカル
→フランス哲学者、自然哲学、思想家。神童としても有名ですね。
・自然な文体に出会うと、人はすっかり驚いて、夢中になる。なぜなら、一人の著者を見ると思っていたところで、一人の人間と出会ったからだ。
【第165回/マガジン読書の効用DAY8】読書の金言②↓
【マガジン】読書の効用DAY23 偉人の金言③
読書について偉人たち・・ヤバい偉人達を総称してやば偉人達10人にお集まり頂き、読書に対する思いのたけを放って頂こうかと思います。強烈なアフォリズムを利かせた一文は読書に対する本質をえぐっておりますので、刺さる方も多いのではないでしょうか?
早速、トップバッターの方をお迎えしましょうか。
31_ルキウス・アンナエウス・セネカ
⇒ユリウス・クラウディウス朝時代のローマ帝国の政治家、哲学者、詩人。
私の以前のstandfmでも収録しましたが、人生の短さについては名著中の名著だと思います。
・気まぐれな読書は喜びを与えてくれるが、有益なものとするには注意深い指導が必要だ
⇒気まぐれ・・・これは私が言う所の無目的型読書法を意味しているのかもしれませんね。喜びは大きいですね。無目的ですので様々な分野を楽しくよめるので。ただ有益なもにするには注意深い指導が必要だと言っていますね
つまり何をインプットして残すのか?そしてアウトプットからアウトカムまでの射程の長いマラソンをどうリソース配分して読書体験を読み切るのか?を考えることが大切かと個人的に誤読致しました。
32_ジョセフ・マーフィー
⇒米国で活動したアイルランド出身の宗教家、著述家
潜在意識を利用・操作することで自らや周りの人さえも成功、幸福へと導く積極思考(ポジティブシンキング)「潜在意識の法則」を提唱した。
・読書の時間を大切にしなさい!1冊の本との出会いがあなたの生き方を
変えてくれることだってあるのだから
⇒書籍に書いてあることが全てではありませんが、人生を変えてしまうかもしれないスゴ本に出会う可能性もまだまだあると考えております
33_司馬遼太郎
⇒日本の小説家、ノンフィクション作家
『竜馬がゆく』『燃えよ剣』『関ヶ原』『坂の上の雲』など多くがあり語りつくせないですよね。戦国・幕末・明治を扱った作品が多いですし、歴史的拝見を勉強するのに教科書的なポジションを個人的に取っているように思えます。背景への洞察が素晴らしいといつも思います。
・自分には学校というものは一切存在理由がなかった。自分にとって、図書館と古本屋さんさえあればそれで十分であった
34_フランシス・ベーコン
⇒イギリスの哲学者、神学者、法学者、貴族である「知識は力なり」の名言は有名ですが・・・
先日4つのイドラでもご紹介しましたが・・・
1 種族のイドラ/人間という種族に基づく思い込みのこと
2 洞窟のイドラ/「個人の思い込み」のこと
3 市場のイドラ/、市場で聞いた話によって作られる思い込み/噂はなしで嫌な思いをするような事。
4 劇場のイドラ/両親の言っていることや、権威のある学者の言っていることをすぐ信じ込んでしまう。ミルグラム実験を想起しますよね、権威者への服従と言いますか。
・読書は充実した人間を作り、会話は機転の利く人間を作り。執筆は緻密な人間を作る
35_ヘルマン・ヘッセ
⇒ドイツの作家。主に詩と小説によって知られる20世紀前半のドイツ文学を代表する文学者である。私も以前、車輪の下を収録シましたが、非常に情景描写が美しい文学作品ですよね。
・この世のあらゆる書物も、お前に幸福をもたらしはしない。だが、書物は密かにおまえ自身の中にだが、お前を立ち帰らせる
⇒密かにというのがいいですね。結局読んだ物がどの様に自分の中に浸透したかは、ある課題に立ち向かうときの姿勢やマインドセットの中に宿るわけで、目に見えるわけでもないですしね。しかにナポレオンも言うように、読書家は世界を制するわけで、読書体験もわるいものではないですよね。
36_マーク・トウェイン
⇒アメリカ合衆国の作家、小説家、トム・ソーヤーの冒険』の著者として知られ、数多くの小説やエッセーを発表していますね。
・良い本を読まない人間は本を読めない人間と同じだ
⇒良書とは・・・この良書の定義は不明ですが、スゴ本だったり、古典・原典のことですかね。そして本を読めない人間と同じと言っていますので、良書の読み方、読め方次第で、本もだんだんと本質的な意味において読める、飲み込めるということなのかと誤読致しました。
37_小林秀雄
⇒日本の文芸評論家、編集者、作家。私も文章が難解過ぎて飲み込むことができない書籍もたくさんあります。読書については好きですね。
・私は、沢山売れる本は読みません。沢山売れる本を決して軽蔑しているわけではないのでして、私は本は勉強以外には読まぬ覚悟をしているだけです。遊びたい時には外の事をして遊びます。およそ、本を読むなどというとぼけた、愚劣な遊びは御免なのであります。
⇒売れる本・・・ニーチェのいう万人受けする書物を差すわけですが。。。
本を勉強以外に読まないというスタンスを決め込んでいるのが素晴らしいですね。何を読んで何を読まないかを考えることは同じくらい重要ですしね。
本を読むという行為は愚劣極まりない・・・と。ここまで来るとマキャベリが正装をして書籍と対峙するのに近いある種の神聖さを帯びてしまってますよね。
38_アルトゥル・ショーペンハウアー
⇒ドイツの哲学者。フリードリヒ・ニーチェへの影響は有名で先日の収録でも語りましたが、ニーチェはショーペンハウアーの書いた書籍を古本屋で手にして人生の難曲を乗り切ったというエピソードは有名です。
・読書しているときは、我々の脳はすでに自分の活動場所ではない。それは他人の思想の戦場である
⇒そうですね。読書をしているときはある種、他者の思想の中で著者とつかみ合って喧嘩をしている気分になりますね。格闘読書とは以前にもお話しましたが・・・ショーペンハウアーの読書については名著ですので、おすすめ致します。
39_サマセット・モーム
⇒イギリスの小説家、劇作家
月と六ペンスは名著ですよね。毎日自分の嫌いなことを2つ行うことは魂によいことだ・・・という名言もありますが、ストイックな方だと思います。
・読書は人に教養を与えてくれる。ただし、それだけでは聡明な人間にはなれない
⇒そうなんです。教養はたしかに身につきますが、聡明にはなれないでしょうね・・・それは自身の置かれている状況や文脈に落とし込んで日々の振る舞い、生き様ま落とし込まないと読書をはじめて飲み込んだことにもならないと感じます。まさに、リベラル・アーツを体現し続ける読書体験を積むことが大切かと個人的に誤読をしております。
40_ジョン・ロック
⇒イギリスの哲学者。哲学者としては、イギリス経験論の父と呼ばれますね。社会契約や抵抗権についての考えはアメリカ独立宣言、フランス人権宣言に大きな影響を与えましたよね。
・読書は単に知識の材料を提供するだけである。それを自分のものにするのは思案の力である。
⇒たしかに材料だけですね。読んでみて、ふむふむ。以上終了なんてこともあるでしょうが、やはり、思案や思索の旅に一人で出かける必要がありますよね。
【第214回/マガジン読書の効用DAY23】読書の金言③↓
【マガジン】読書の効用DAY24 偉人の金言④
読書について偉人たち・・ヤバい偉人達を総称して・・・やば偉人達10人にお集まり頂き、読書に対する思いのたけを放って頂こうかと思います。強烈なアフォリズムを利かせた一文は読書に対する本質をえぐっておりますので、刺さる方も多いのではないでしょうか?
早速、トップバッターの方をお迎えしましょうか。
41_フランシス・ベーコン
⇒イギリスの哲学者、神学者、法学者、貴族である「知識は力なり」の名言は有名ですが・・・
先日4つのイドラでもご紹介しましたが・・・
1 種族のイドラ/人間という種族に基づく思い込みのこと
2 洞窟のイドラ/「個人の思い込み」のこと
3 市場のイドラ/、市場で聞いた話によって作られる思い込み/噂はなしで嫌な思いをするような事。
4 劇場のイドラ/両親の言っていることや、権威のある学者の言っていることをすぐ信じ込んでしまう。
ミルグラム実験を想起しますよね、権威者への服従と言いますか。
・読書は心豊かな人を作る
⇒まさにそうですね。様々な著者の価値観にふれるので受容できる振れ幅が広くなるんですね。自身の尺度や判断軸もだんだん付いてくるので、ぶれないし動じなくなりますよね。
42_ヴォルテール
⇒フランスの哲学者、文学者、歴史家である。歴史的には、イギリスの哲学者である。ジョン・ロックなどと共に啓蒙主義を代表する人物有名な書作に哲学書簡 またはイギリス便りがありますね。
・読書は魂を広やかにする
⇒フランシス・ベーコン同様に受容出来る幅が読書体験を積むことで広くなるので、仮に突然のトラブルが起きてもカバリングできるように思考が回せるんですね。魂は常に穏やかに保てますし、多様な価値観に触れているので
日々様々起きる事柄にも臨機応変に対応することができるわけですね。
43_ヘンリー・デイヴィッド・ソロー
⇒アメリカの思想家。個人的な誤読ですが、エリック・ホッファーの様な生き様を感じます。自給自足の生活を送るなど、時代のフォーマットには、はまらないで自分の信じているものや美しい審美眼で世界を知覚しているような人かと感じます。
・物は、それが書かれた時と同じように思慮深く、また注意深く読まれなくてはならない
書いたのは著者で読むのが読者という事になると、著者と同じ思考や視座、視野、視点で読み解いていくという
まさに著者と対話をする様に読むことを示唆しているのだと個人的に誤読致しました。
44_エドワード・ブルワー=リットン
⇒初代リットン男爵、諸説「ポンペイ最後の日」は有名ですね。
戯曲「リシュリュー」の中の文句に「ペンは剣より強し」という直接的な暴力よりも独立したメディアの方が影響力が強いことのたとえで表現しているようです。
・目的のない読書は遊戯であって、読書ではない
⇒目的を持てと言っていますね。私の読書法で言えば早い読書に分類されるような、ビジネスや実務で即効性を求める様なスタンスを指しているのかと思いました。明確な目的を持つことは確かに大切ですよね。
45_サミュエル・スマイルズ
⇒イギリスの作家・医者です。天は自らを助くる者を助くで有名な自助論の著者ですね。
・人の品性は、その読む書物によって判ずることができる
⇒これは・・・三谷宏治さんの人は読んだ本で出来ていると同義の様なきも致しますが、ブリア・サヴァランも君がどんなもの食べたか言いたまえ、君がどんな人か言い当てて見よう!のような事も言っております。読んだ書籍からその人の思考を辿ることでどんな人物か判ずることも可能になってくるのだと思います。
46_ジョン・コリア
⇒イギリスの作家・・・不思議な話、不気味な話の数々。それでも、その中になんとなくユーモラスな雰囲気が漂っているのが作品の特徴ですね。
・書物は青年時代における道案内であり、成人になってからは娯楽である
道案内というメタファーが秀逸ですね。さらに成人になるころまでに精通していれば、成人を超えるころには道案内なしに一人、読書道へ思索の旅へ出かけられるということですね。
47_デーヴィッド・ハーバート・ローレンス
⇒イギリスの小説家・詩人。チャタレー婦人の恋人でも有名ですね。
・書物のほんとうの喜びは、なんどもそれを読み返すことにある。
出口治明さんもおっしゃっておりますが、読み返す事は非常に読書体験としては必要不可欠ですし、読み返すことで読書が完成へと少しずつ近づくような気も致します。
48_アルトゥル・ショーペンハウアー
ドイツの哲学者です。こだわりの人一倍強い哲学者だった様です。前回は⇒読書は他人にものを考えてもらうことである、本を読むわれわれは他人の考えを反復的に辿るにすぎない
・読書で生涯をすごし、さまざまな本から知恵をくみとった人は、旅行案内書をいく冊も読んで、ある土地に精通した人のようなものである
読書体験が増えてくると様々な領域、分野に精通してくるので、確かに旅行案内書を読み込んでいる様な感覚がありますね。秀逸なメタファーですよね~その領域=土地に詳しくなりますしね。
⑨洪自誠(こう じせい)/ 菜根譚(さいこんたん)
⇒中国明王朝の著作家。主として前集は人の交わりを説き、後集では自然と閑居の楽しみを説いた書物である
・書物を読んでも聖者や賢人の精神に触れなければ、文字の奴隷になる。学問を論じても、実践が伴わなければ、口先だけの修行にすぎない
⇒非常に本質を付いた洞察の鋭い一文ですよね。本を読んだだけではあまり効果は実感出来ないとおもます。良いこと書いてあるな~と思い数日後には少しずつ忘れているみたいな・・・小林秀雄さん的な読書になるのだと思いますし、岸見一郎さんもおっしゃっておりまが文体の先に人間がありありと
立ち上がるまで読み込むことが大切ですし、著者と対話しながら時には格闘しながら読んでいくことで、自身の状況や・文脈にレバレッジ掛かって少しずつ血となり肉となるのだと思います。
50_M・J・アドラー
→コロンビア大学教授。以前のstandfmで収録しましたが、本を読む本の著者・アドラーによる金言です。
・読む事はすなはち発見することであり、自然や外界を読み取る技術であり、教わることは本を読む技術、ないし話し手から学ぶ技術である
⇒技術であると言っていますね・・・エーリッヒ・フロムも愛するということは技術だとも言っていますが、自分の内なる世界の外側の世界を理解するためのスキルだと喝破している訳ですね。話してからは傾聴のスタンスを取り、吸収するつもりで一字一句漏らさず聞き取るという気迫が読み取れる
文章ですね。
【第216回/マガジン読書の効用DAY24】偉人の金言④↓
【マガジン】読書の効用DAY29 偉人の金言⑤
引き続き、読書について偉人たち・・ヤバい偉人達を総称してやば偉人たちに人にお集まり頂き、読書に対する思いのたけを放って頂こうかと思います。強烈なアフォリズムを利かせた一文は読書に対する本質をえぐっておりますので、刺さる方も多いのではないでしょうか?
早速、トップバッターの方をお迎えしましょうか。
51_エドワード・ギボン
⇒イギリスの歴史学者です。著書にローマ帝国衰亡史があります。
オックスフォード大学在学中にカトリックに改宗したが、当時のカトリックからの立身出世は難しいと父親が判断して、退学させられて、ローザンヌの父親の知人のプロテスタントの牧師に身を委ねられて、そこでプロテスタントに再改宗したそうです。
・インドの全財宝をあげても、読書の楽しみには換え難い・・
⇒これはムガル帝国の栄枯盛衰と読書の楽しみを比較したのだと思いますが、当時のムガル帝国の凄まじい財力と引き換えにしても読書の方が楽しいというまさに読書家であったギボンを象徴する名言ですね。。
52_フリードリヒ・ニーチェ
⇒ドイツの哲学者で実存主義の代表選手としても知られていまうよね。アフォリズムをきかせた文章は短い一文にもかかわらず読み手の心をえぐります。
・他人の自我に絶えず耳を貸さねばならぬこと、それこそまさに読書ということなのだ
⇒この人を見よの中で語られて一文です。ニーチェは読書を他人の自我と自分の自我がお互いに共鳴し合って、自然に耳を明け渡す現象の様なものだと捉えていたそうです。非常に深い一文だと感じます。
53_ハインリヒ・ハイネ
⇒19世紀ドイツの詩人・作家、文芸評論家。1797~1856年までを生きた人の様です。ベルリン大学在学中にはヘーゲルの教えも受けたそうです。またマルクスとも親交があったようです。
・退屈な本を読んでいてうとうとしたら、その本を読み続けている夢を見て、退屈のあまり目を覚ましてしまった。
⇒独特な表現ですが、退屈な本に出くわしたら、すぐに本を閉じて別の本へと移動をしたいところですが、あまりにも退屈すぎて夢まで見てしまったんですね。さらに退屈すぎて
目を覚ますという、退屈本への痛烈な批判が込められている様なきみしますし、ハイネのいう退屈とは文字通りの退屈ではないよう気も致します。
54_マルティン・ルター
⇒ドイツの神学者、作家。先日のプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神でも触れましたが、宗教改革の中心人物。信仰心もあり、神学者であったルター贖罪府について見過ごすわけにはいかなったようです。またマインツ大司教のアルブレヒトの野望を紐解くと
・権力ち地位を手に入れたい人の心の弱さを見てとれますね。いつの時代も変わらない欲望です。
・学力を増進するのは、多読ではなくして良書の精読だ
⇒多読とはたくさんの書籍を読むことであり、良書はこの時代から遡っての古典・原典や当時出回っていた骨太書籍のことをいうのだと思いますが、良書を読み漁っていて結果とし多読に行き着くのが個人的にはよろしいかと思います。
55_勝海舟
⇒江戸末期から明治初期の幕臣、政治家で初代、海軍卿です。江戸城無血会場でも有名ですが・・・
・人間の精魂には限りがある。多くの読書や学問に力を用いると、いきおい実務の方にはうとくなるはずた。
⇒精神のリソースの配分について語っているんですね。限りがあるから、読書や学問ばかりではなく他のことにも思考を振り向けよ!と言っているようですし、学問領域にばかり囚われて実戦経験が乏しいと実務がうまく回せないことを表現していますね。
56_寺山修司
⇒劇作家、演劇家ですね。青森県のご出身ですが、スキャンダルもありましたが・・・ 一方で多読家の側面を持っているアーティスティックな人でした。
・つまらない書物というのはないが、つまらない読書というものはある
⇒これも非常に深い一文です。書物自体ではなく自分自身の読書に対するマインドセットについて語っていますね。つまならくしているのは自分自身ですので。向き合い方ひとつで面白い、面白くない両方に極が触れますしね
57_日下部四郎太
⇒天才物理学者です。特に地震学を中心に磁気歪み、岩石の弾性などを研究したことでも有名ですよね。
・少なく読み、多くを考えよ
・無批判的な多読が人間の頭を空虚にする
⇒エッセンシャル思考を回していたんだと推測できますが、より少なく、より良くということですね。樺沢紫苑さんもインプット3 アウトプット7という比率を提唱されておりますが、まさによくよく考えるアウトプットとアウトカムの関係を考えることにも通じますよね。無批判はやはりハンナ・アーレントも言うように悪なわけですし、頭を空虚にするわけですね・
58_格言
・論語読みの論語知らず
⇒論語を読み、論語についての知識があるにも関わらず、その教えを実践できない人がいることや表面上の言葉だけは理解できても、それを実行に移せないことのたとえですね。たしかに、いくら本をたくさん読んで知識が豊富でも、その知識を実践に活かすことができなければ意味が無い。司馬遷も史記列伝の中で知ることが難しいのではない、知ったことに如何に身を処せるかが難しいと言っているし、ニコラス・ネグロ・ポンテも知ることは時代遅れだとも指摘してますしね。
59_寺田寅彦
⇒戦前の日本の物理学者、随筆家です。一流の物理学者として、日本の物理学の黎明期を支えた人でもあります。科学者でありながら文筆家でもあり、寺田寅彦は文豪・夏目漱石を「師」とあおいでいました。漱石も彼に目をかけていました。漱石の作品「吾輩は猫である」や「三四郎」には、寺田寅彦をモデルにしたと言われる人物も登場しましね。
⇒天才は忘れたころにやってくるという名言でも有名
・読みたくない本を無理して最後まで読まなくてい
・興味なかった本が時を違えて興味をもつ
⇒これは私も日々、実戦していますが、自分の置かれている状況や文脈に合わせた読書体験が良いとおもいます。一字一句よむ必要がないと感じたら読まない。というスタンスを決め込むことが大切ですね。
60_太宰治
⇒本名はつしましゅうじですが、自殺未遂や薬物中毒をしたことでも有名ですね。坂口安吾もヒロポン中毒だったことを思いだしました。太宰治のなりたい自分やヒーロー像は芥川龍之介と言われていますね。父は貴族院議員も務めていて、邸宅には30人もの使用人がいたそうです。
・本を読まないということは、そのひとが孤独でないという証拠である。
⇒この一文も太宰らしい文章ですが、本を読んでいる人は孤独であると言いたいということですね。著者との対話や格闘はある種の孤独感や虚無感、脱力感を埋め合わせてくれる活動でもありますね。
【第225回/マガジン読書の効用DAY29】偉人の金言⑤↓
【金言の効用】
ヤバ偉人達の痛烈な読書に対する一発を読み、自身の読書に対するマインドセットに揺さぶりを掛ける効果があります。自身の読書方法を棚卸しして点検することになるので、非常に金言は絵本同様に効果があると感じます。
また絵本や伝記にも同様の効果があります。
例えば・・・ヨシタケシンスケさんの絵本では・・・
私は娘の隣で、非常に難しい顔で生きるとは?や死ぬとは?働くとは?など抽象度の高い問いに向き合っております。大人こそ、絵本を読んだ方が得られる示唆が多いと思います。
以上、ヤバい偉人達の読書に対する金言をご紹介して参りました!!
◯日々の活動のご紹介です↓
【Twitter】
書籍に対しての配信メインです。2013年4月より活用しております。宜しければフォローをお願い致します。
【standfm】
読書について語る番組です。子育てとビジネスに身を置きつつ、具体と抽象の世界を往復運動する日々です。音声コンテンツは200個を超えてきましたので、何かお持ち帰り頂けるフレームや思考法を語っております。
宜しければ、ご視聴下さい。
【note】読書の効用
standfm×noteにて音声コンテツ付きの記事を書いています。まだ全く間に合っておらずですが、宜しければご一読下さい。
読書の効用という記事(23,000字程度/アップデート中)の内容を元に登壇する事もあります。主に読書に対するマインド・セット、お作法、選書方法、読書術、オススメの書籍をご紹介しております。
【schoo登壇動画】
恐らく国内向けだと最大規模になりますが、ビジネス・パーソン向けに動画で学習支援サイトを運営されておられる、schooさんの「プロフェッショナルの読書術」という企画に登壇致しました。動画視聴可能ですので、宜しければご視聴下さい。
ここまで、長らく有難うございました。
引き続き日々のアウトプットに関してはstandfmを中心に配信させていただきます。よろしくお願い致します。
#読書 #リベラル・アーツ #子育て #ビジネス #ビジネス・パーソン #哲学 #音楽 #心理学 #文学 #誌 #歴史 #人類史 #進化心理学 #自然科学 #経営戦略 #経済学 #地政学 #統計学 #SF小説 #マインド・セット #リーダー・シップ #フューチャーズ・リテラシー
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
