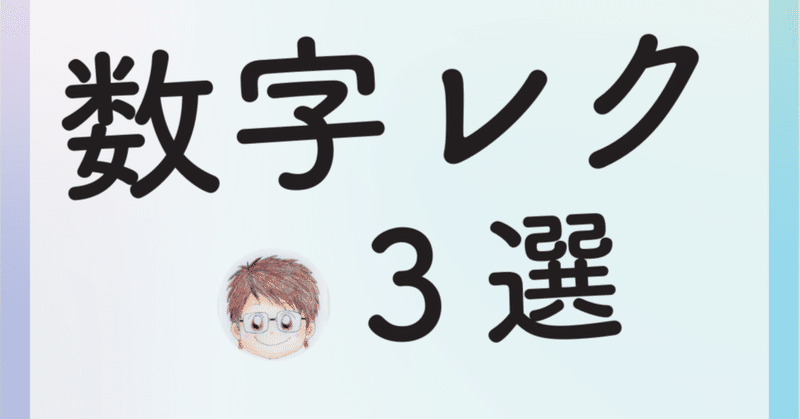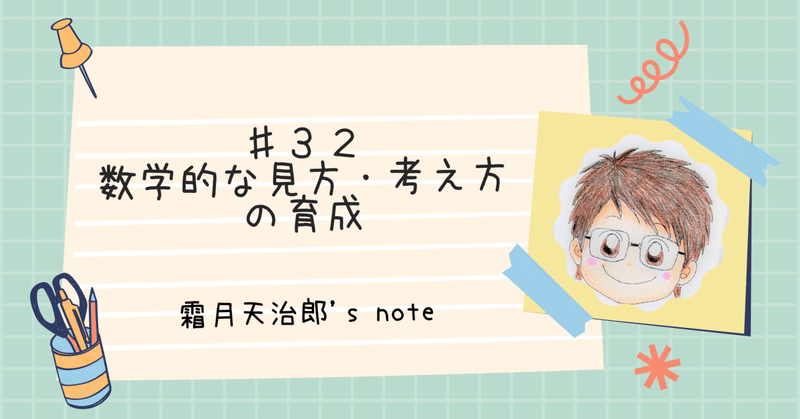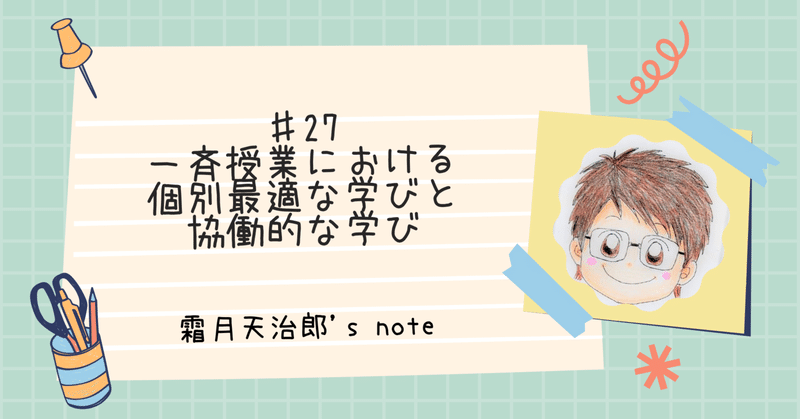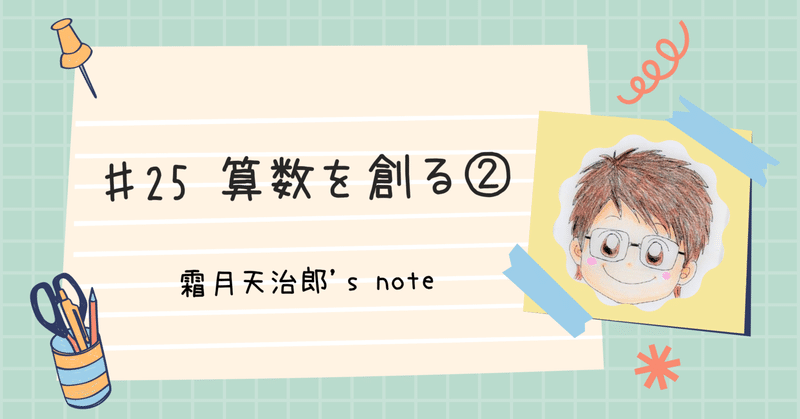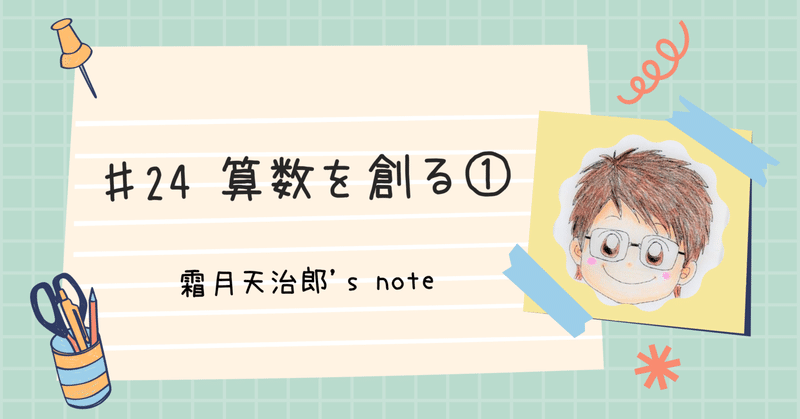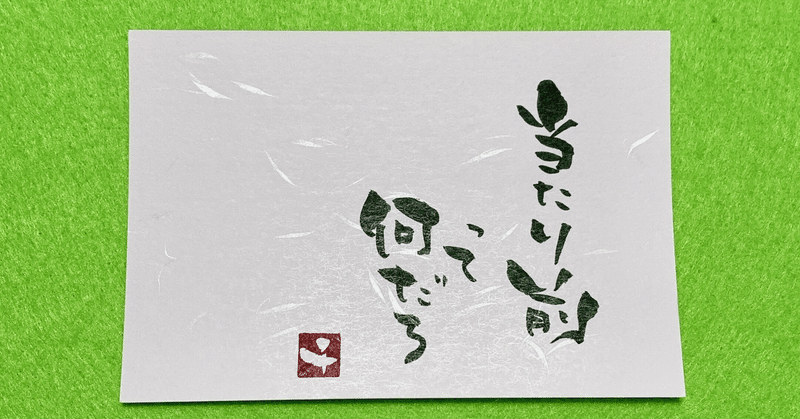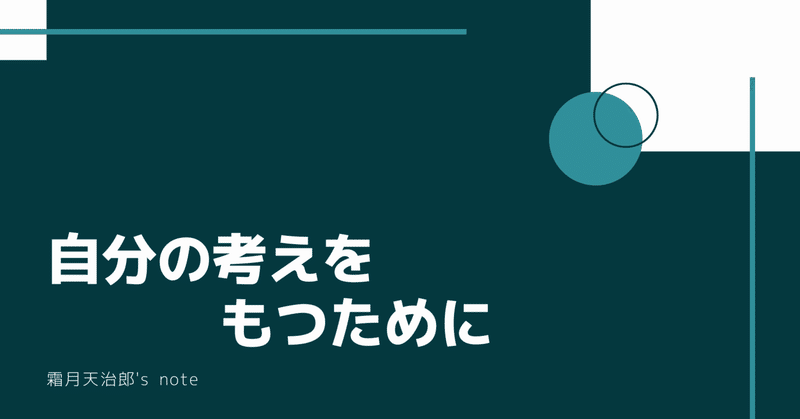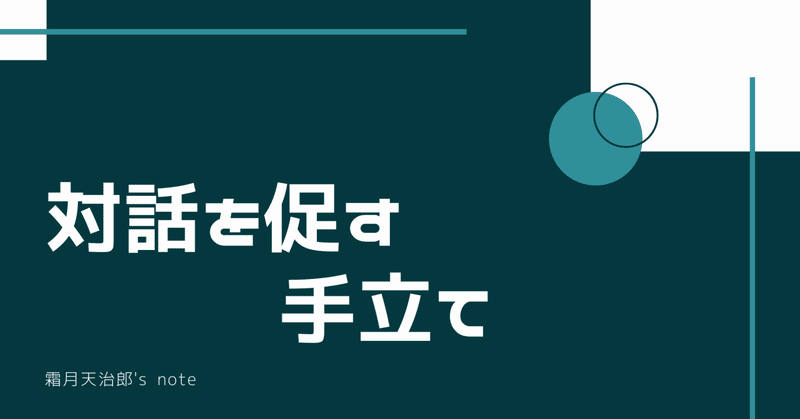#小学校
♯32 数学的な見方・考え方の育成
今回のテーマは、「数学的な見方・考え方の育成」です。実践家の視点から検討します。算数の授業をアップデートしたい方、見方・考え方への理解を深めたい方は、ぜひご覧ください。
(1)4者の見解から
加固(2019)は,「数学的な見方・考え方」と発問との関係について,
と述べています。そして,言語化し顕在化した「数学的な見方・考え方」がクラス全体で共有されていくことについて,以下のように述べてい
♯25 算数を創る②
25回目のnote投稿となりました、天治郎です.今回も前回に引き続き、「算数を創る」をテーマに論じて?いきます.今回は、「算数を創る」とはどういうことかについて、「創造性」の視点から捉えていきます.
本稿の要点は、以下の通りです.
創造性は,「創造力(創造的思考力と創造的表現力)」と「創造的人格(創造的態度)」からなるものである.
創造において「児童自らが問題発見をすること」また,「創造の
♯24 算数を創る①
24回目の投稿となりました、天治郎です。今回からは、私の研究テーマである「算数を創る」ということについて、論じていきます(誰得?)。少しお堅い話が続くかもしれません。
(1)人間の強みと算数
今の子どもたちやこれから誕生する子どもたちが成人して社会で活躍するころには,グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等により社会は大きく急速に変化しており,今以上に予測が困難な時代となっているであろうこ
♯20 当たり前を問い直す
20回目のnote投稿となりました、天治郎です。本稿の要旨は、以下の通りです。
「当たり前を問い直す」ということは、「子どもの立場に立って自らの教育観を見つめ直す」ことと同義ではないでしょうか。
(1)めがね旦那さんのお考えから Twitterをされている方は、「めがね旦那」という小学校の先生を御存知の方も多いでしょう。育休中に始めたTwitterで自身の教育に対する考え方を発信したところ、
♯16 算数の授業開き
16回目の投稿となりました、天治郎です。既に学校が始まっている自治体もあると聞きます。しかしながら、算数の授業開きは「月曜日」という方もいるのではないでしょうか?また、10日が始業式で、算数の授業開きをこの土日に考えようという方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、「①2年生向け」、「②3年生以上向け」、「③6年生向け」の算数の授業開き例を御紹介します。特に興味のある部分を読んでいただけ
♯15 対話を促す手立て
15回目の投稿となりました、天治郎です。新年度になりましたね!本年度もよろしくお願いいたします。
お忙しい読者のために、以下が本稿の要旨です。
・「やらされる対話」から「児童自らやりたい対話」へ…そのような手立てを講じていきたいですね。
・教師の発問は、いつしか子ども自身の問いへと変容していきます。子ども自身が問いをもてるようにするためにも、教師の発問・問い返しの工夫は欠かせませんね。
(