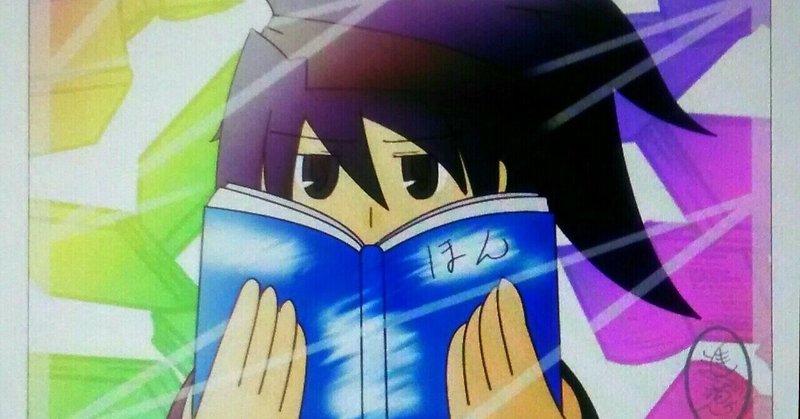
これまでの人生で読んできた文学作品の備忘録
こんばんは。
いつもお世話になっております。
今回は普段と少し趣を変えまして、自分が今までに読んできた本で記憶に残っているものを載せていきたいと思います。
(ただし完全に記憶頼りの為、思い出し次第増えていくと思います。)
現在手元にあるもの無いもの含め、主に文学作品と呼ばれるものを載せていきます。
(あくまでも自分用の備忘録として書いておりますので、メモ的な文章(個人的な意見や感想、内容も含みます)も一緒に載せています。
かなり昔読んだものも含む為、メモの内容が曖昧な場合もあります。)
文学作品メインなので、評論や資料的なものは基本的に載せません。
(漫画やライトノベル、絵本や画集などは数点のみピックアップしております。)
大体自分が好んで読むのは18世紀から20世紀頃の海外文学で、特に古典SFや冒険ものやサバイバルもの(騎士物語やゴシックホラーなども)。
(ただし基本的に外国語は読めないので、海外文学は全て邦訳されたものです。
翻訳は原文とニュアンス等が異なってしまう事が多いと思うので、本当は原文を読んだ方がより物語の内容や作者の意図が伝わるかと思います。)
定番なものも読んでいますが、読んでいないものもたくさんあります(読みたいものは、まだまだたくさんある)。
特にミステリーも好きなのでアガサ・クリスティー作品等も読みたいのですが、学生の頃に時間がなくて読めなかったのを今に至るまで引きずっているような形です(本当は全部読みたい)。
特に気に入っている作品等は、思い出しては取り出して繰り返し読んでいます。
形式は冗長になってしまってもどうかと思うで、基本的に「書名」と「著者名(敬称略)」(と「自分用メモ」)のみにしたいと思います(例外あり)。
初めに日本文学を、後の方に海外文学を載せていきます。
(著者自体が好きでその著者の作品を大量に読んでいる場合は、最後の方にまとめて載せます。)
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆日本文学
『ドクラ・マグラ』夢野久作
「初めにこれを持ってくるか?」という感じの混沌作品。胎児の夢がなんたらとか、脳髄論がなんたらとか。現代人が読んでも気は狂わないと思うけど、出版当時の人々が読んだら確かに「何じゃ、こりゃ!」ってなるかもしれない。日本三大奇書の一つ。
『南総里見八犬伝』曲亭馬琴
完訳版。かなり長い。冒険活劇、ちょっと(?)ファンタジー入りのシンプルに面白い勧善懲悪もの(勧善懲悪ものって、ほとんど読まないけど)。
『源氏物語』紫式部
現代語訳をところどころ読んで、あとは漫画で(しかし自分はやっぱりちょっと苦手)。
『日蝕』平野啓一郎
錬金術にハマってた頃に読んだもの。不思議な怪奇さがクセになりそう。
『五感』溝渕淳
感覚に関する奇妙なお話。最後に謎解き的な。
『蟲』坂東眞砂子
ホラーもの。不気味な妖しさがある。虫が苦手な人はちょっと厳しいかも?
『細雪』谷崎潤一郎
昭和の香り。
『山月記』中島敦
虎。
『高瀬舟』森鴎外
罪とは何なのか考えさせられる作品。
『こころ』夏目漱石
選択の葛藤と懺悔の気持ち。
『蜘蛛の糸』芥川龍之介
死の淵にいて、カンダタみたいにならない人ってなかなかいないと思う。
『人間失格』太宰治
人間誰しも恥の多い人生だと思う(自分を筆頭に)。
『走れメロス』太宰治
学校の授業で読んだ、定番。
『古事記』
抄訳版で。
『ノルウェイの森』村上春樹
青春の光と影。
『アレグリアとは仕事はできない』津村記久子
学生時代の課題図書。こういったタイプの本をあまり読まないので新鮮だった。生きるのってなかなか難しい。
『ひゃくはち』早見和真
学生時代の課題図書。こういったタイプの本もあまり読まないので新鮮だった。高校球児の青春と煩悩の葛藤。
『風の中のマリア』百田尚樹
学生時代の課題図書。こういったタイプの本もあまりy(以下略)。珍しい視点から描かれた、自らの使命を全うすることに命を燃やした小さき蜂の物語。
『鹿男あをによし』万城目学
学生時代の課題図書。こういったタイプのh(ry)。色んな意味で、かなり壮大なファンタジー。とても面白く、色々微笑ましい。すごく印象に残る。
☆江戸川乱歩
『鏡地獄』
『人間椅子』
不気味な世界観。鏡がまだ不思議な異物だった頃のお話と、日常に潜む予想だにしない展開が目を惹くスリラー。
☆宮沢賢治
新潮社
『新編 宮沢賢治詩集』
『新編 風の又三郎』
『新編 銀河鉄道の夜』
『注文の多い料理店』
『ポラーノの広場』
独特な世界観。卒論は宮沢賢治を主題にした。
☆荻原規子
『空色勾玉』
『白鳥異伝』
『薄紅天女』
『風神秘抄』
勾玉三部作+α。初めて自ら読みたいと思った本、ファンタジー色が強くて人間模様がしっかりと描かれている。
☆北杜夫
『さびしい王様』
『さびしい乞食』
『さびしい姫君』
学生の時に初めて読んだら、面白すぎて途中で笑いが止まらなくなって困った(笑)
☆向田邦子
『阿修羅のごとく』
『あ・うん』
『眠る杯』
『父の詫び状』
『思い出トランプ』
『霊長類ヒト科動物図鑑』
ホームドラマ風の本はあまり読まないが、たまたま読む気になった。人々の何気ない生活や複雑な人間模様などが、鋭い視線で描かれている。
☆五木寛之
『朱鷺の墓』
『大河の一滴』
人間の美しさもあり汚さもある内面をえぐるような小説と、今生きている人間がどういった存在であるのか、現実をどのように受け取り尚も生きていくべきなのかが書き表されている随筆。
☆ライトノベル
『テレパシー少女 蘭』あさのあつこ
初めてまともに読んだライトノベル(というか「青い鳥文庫」)、物語性も好きだが人間模様などが細かい。
『最後の夏に見上げた空は』住本優
悲しい運命を背負わされた子供達の物語、何度も読み直したくなる。
『Missing』甲田学人
都市伝説やオカルトものに興味を持ったキッカケ。
『断章のグリム』甲田学人
童話を元にしたお話、ゴシックホラー的な物語。
☆漫画
『鋼の錬金術師』荒川弘
自分にとってなくてはならない物語、相当影響されている。
『成恵の世界』丸川トモヒロ
宇宙ものでSF色の強い作品、宇宙船のデザインとかすごく良い。
『火の鳥』手塚治虫
学生の頃に読んだ、漫画に収まりきらないほど内容の詰まった神作品。
『動物のお医者さん』佐々木倫子
とにかくビジュアルが素敵、動物可愛い。とてもリアルっぽいお話。
『アキラ』大友克洋
アニメ版のコミックスで。有名な作品なので読んでおこうと思った次第。サイバーパンクが好きな人には良いかも。無法地帯感と終末世界感がすごい。
『新世紀エヴァンゲリオン』貞本義行
人間ドラマはもちろん、侵略もののSF感がたまらない名作。アニメや映画は元々見る習慣が殆ど無いので見ていないが、単行本も非常に迫力がある。
『海獣の子供』五十嵐大介
作者の方がムツゴロウさん(畑正憲さん)と対談しているテレビ番組を見て、興味を持ったので。海が好きなので、海の描写がたくさんあるのはとても嬉しい。とにかく美しい。
『風の谷のナウシカ』宮崎駿
漫画があるという事は前々から知っていたのと、漫画の方が物語がより深く語られていると聞いていたので読む事に。改めて「こんなに深い話だったのか」と思う。とにかくとても良い。王蟲も森も好き。
☆絵本
『100万回生きたねこ』佐野洋子
繰り返し何度も生まれて生きて、最後に真実の愛に出会った猫の物語。
『月からきたうさぎ』みなみらんぼう
ある日月から落ちてきた、金色の毛を持つうさぎのお話。悲しい。
『でんでら竜がでてきたよ』おのりえん
紙から現れ成長していく、小さな竜のお話。長崎の童歌がもとになっている。
『スイミー』レオ・レオ
かしこい小さな魚の物語。アメリカの作品(著者はオランダ出身)。
『おおきな木』シェル・シルヴァスタイン
一本の木と一人の少年のお話。愛とは何か。アメリカの作品。
『ずーっとずっと だいすきだよ』ハンス・ウィルヘルム
愛と命の物語。この世に生きる誰もが避けては通れない事。アメリカの作品(著者はドイツ出身)。
☆海外文学
『失われた時を求めて』マルセル・プルースト
生きている内に出来るだけ早い段階で読んでおきたいと思い、読み始めなければ読み終わらない(当然)とも思ったので読了。とある香りで幼い頃の記憶を思い出し、それを皮切りに様々な意識が流れていく「時」の物語。フランスの作品。邦訳全13巻。
『ユリシーズ』ジェイムズ・ジョイス
上記『失われた時を求めて』と共に「二十世紀を代表する文学作品」として語られる作品。とある一日を舞台とする、意識の流れを旅する物語。アイルランドの作品。邦訳全4巻。
『ハリー・ポッターシリーズ』J.K.ローリング
言わずもがなな魔法ファンタジー作品、ハリー・ポッターシリーズをキッカケに自分は長編物語を読めるようになった。イギリスの作品。
『ソフィーの世界』ヨースタイン・ゴルデル
子供でも分かる哲学の入門書的一冊。秀逸。ストーリー仕立てになっていて次々に読み進められる。ノルウェーの作品。
『ウンディーネ』フリードリヒ・フーケ
水の精霊と騎士の悲恋の物語。ドイツの作品。
『鏡の中の迷宮』カイ・マイヤー
イタリアのヴェネチアとエジプトのピラミッドを舞台に、不思議な旅が繰り広げられるファンタジーものの児童文学。作品全体の雰囲気がとても好き。ドイツの作品。
『ナゲキバト』ラリー・バークダル
一人の少年と老人の物語。命とは何なのか。とにかく泣く。アメリカの作品。
『アルケミスト』パウロ・コエーリョ
錬金術にハマっていた頃に読んだもの(アルケミストは錬金術師の意)。ストーリーも好きだが、作品全体に流れる雰囲気がとにかく良い。ブラジルの作品。
『ガリヴァー旅行記』ジョナサン・スウィフト
社会風刺の効いた不思議の世界漂流記。イギリスの作品(著者はアイルランド出身)。
『神曲』ダンテ・アリギエーリ
地獄→煉獄→天国を巡る壮大な長編叙事詩。キリスト教的な教義を豊富に含む。イタリアの作品。
『失楽園』ジョン・ミルトン
アダムとイヴ、そして彼らをそそのかしたサタンが「楽園」を永遠に追放される。サタンは地獄に下る。イングランドの作品。
『カンタベリー物語』ジェフリー・チョーサー
カンタベリー大聖堂巡礼に行くため宿屋に泊まっていた種々様々な客が、退屈しのぎにオムニバス形式で順番に知っている話を物語る。イングランドの作品。
『妖精の女王』エドマンド・スペンサー
アーサー王伝説を題材に、各巻に様々な徳の主題が設けられた物語。いわゆる騎士道物語。イングランドの作品。
『ドン・キホーテ』ミゲル・デ・セルバンテス
抄訳版で。騎士物語の読みすぎで自分を偉大な騎士と勘違いした郷士が、供を引き連れて旅に出るお話。少し下品な話あり。最後の空虚感が結構すごい;スペインの作品。
『最後のひと葉』オー・ヘンリー
岩波少年文庫の。タイトルの作品も好きだが、「都会の敗北」というお話がお気に入り。アメリカの作品。
『ケルトの薄明』W.B.イエイツ
古き良きアイルランドの風を感じる伝承譚。優しい緑の大地の物語。アイルランドの作品。
『モモ』ミヒャエル・エンデ
現代に通じる「時間」のお話。自分達の時間とは何の為にあるのか?ドイツの作品。
『秘密の花園』フランシス・バーネット
孤独な少女が、自然の中で生きる気力を取り戻していく物語。アメリカの作品(著者はイギリス出身)。
『赤毛のアン』M.モンゴメリ
孤児院暮らしだった少女が手違いで老兄妹の元に引き取られ、一人の人間として美しく成長していく。カナダの作品。
『若草物語』ルイーザ・メイ・オルコット
正直あまり内容を覚えてはいない。戦時中で、四姉妹が登場するお話というのは覚えてる。この本を読んだ後に『天路歴程』を読んでみようと思ったはずだが、未だに叶っていない。アメリカの作品。
『ジキル博士とハイド氏』ロバート・スティーヴンソン
人間性と獣性の葛藤。科学の踏み込んではいけない領域の恐ろしさを表したようなSF作品。スコットランドの作品。
『日月両世界旅行記』シラノ・ド・ベルジュラック
ちょっとした似非科学的なものから始まり、奇妙な世界を旅する摩訶不思議な物語。社会風刺の側面が強い。フランスの作品。
『シラノ・ド・ベルジュラック』エドモン・ロスタン
当時の名の知れた剣豪作家を主人公にした、舞台ものの活劇。ロマンスも大いに含む。フランスの作品。
『博物誌』ジュール・ルナール
率直さとシュールさの入り混じったような文学的表現。詩のような物語のような観察日記のような、不思議な気分になる文字列。フランスの作品。
『賢者の石』コリン・ウィルソン
脳がなんたら。ちょいクトゥルフみ。イギリスの作品。
『水滸伝』施耐庵
抄訳版で。内容はほとんど覚えていない。登場人物がとにかく多い。三国志なども読んでみたいけど、かなり時間かかりそう。中国の作品。
『ファウスト』ヨハン・ゲーテ
悪魔と契約した学者の物語。色んな怪物等も出てくる。「時よ止まれ」のくだりが有名。ドイツの作品。
『若きウェルテルの悩み』ヨハン・ゲーテ
若き青春の葛藤。でもそれで人生の全てを無下にしなくて良いと思う。ちょっと夏目漱石の『こころ』を思い出す。ドイツの作品。
☆エドガー・アラン・ポオ
創元推理文庫
『ポオ 詩と詩論』
『ポオ小説全集1~4』
ゴシックロマンスやゴシックホラーなど、始終妖しい雰囲気の漂う物語。美しい風景を文章に描き出した詩的な作品も豊富。アメリカの作品。
☆ハワード・フィリップス・ラヴクラフト
東京創元社
『ラヴクラフト全集1~7』
『ラヴクラフト全集 別巻上・下』
純粋な恐怖を題材にした「宇宙的恐怖(コズミック・ホラー)」を主題とした新しい世界観を確立し、今なお人々に愛される不気味な物語群。オカルト色強し。クトゥルフ。アメリカの作品。
☆ハンス・クリスチャン・アンデルセン
『即興詩人』
『絵のない絵本』
童話「人魚姫」「マッチ売りの少女」「みにくいアヒルの子」等で有名な作家の描く、暖かくも物悲しい雰囲気の漂うロマンス劇。デンマークの作品。
☆ローズマリ・サトクリフ
『ロビン・フッド物語』
『炎の戦士クーフリン/黄金の騎士フィン・マックール』
伝説の英雄達をモチーフにしたファンタジー物語。イギリスの作品。
☆フィリップ・プルマン
『ライラの冒険 黄金の羅針盤』
『ライラの冒険 神秘の短剣』
『ライラの冒険 琥珀の望遠鏡』
ファンタジーもの三部作。動物がたくさん出て来るのが好き。
☆マーク・トウェイン
『トム・ソーヤの冒険』
『ハックルベリー・フィンの冒険』
『王様と乞食』
当時の社会情勢などを風刺的に描いた物語。アメリカの作品。
☆アレクサンドル・デュマ・ペール
『ダルタニャン物語』
『モンテ・クリスト伯』
活劇や復讐劇、腹のさぐり合いなど人々の人間模様が面白い作品。結構長い。フランスの作品(『モンテ・クリスト伯』の邦訳名は『岩窟王』)。
☆ダニエル・デフォー
『ロビンソン・クルーソー』
『ロビンソン・クルーソーのさらなる冒険』
サバイバルもののパイオニア的作品。正編の方はがっつりサバイバル、続編の方はロビンソンが助かった後の生涯の冒険の数々についてみたいなお話。イギリスの作品。
☆ルイス・キャロル(チャールズ・ドドソン)
『不思議の国のアリス』
『鏡の国のアリス』
数学者が書いている作品なので、物語の諸所に数学的なモチーフがふんだんに用いられている。この数学的な美しさが、人々を長きにわたり魅了し続けているのかもしれない。イギリスの作品。
☆ホメロス
『イーリアス』
『オデュッセイア』
トロイア戦争におけるアキレウスとヘクトールの決闘を主題とする物語と、戦争後に凱旋するオデュッセウスの長きにわたる旅の長編叙事詩。古代ギリシアの作品。
☆ウィリアム・シェイクスピア
白水社
「ヘンリー六世」
「リチャード三世」
「ジョン王」
「リチャード二世」
「ヘンリー四世」
「ヘンリー五世」
「ヘンリー八世」
「タイタス・アンドロニカス」
「ロミオとジュリエット」
「ジュリアス・シーザー」
「ハムレット」
「トロイラスとクレシダ」
「オセロー」
「リア王」
「マクベス」
「アントニーとクレオパトラ」
「コリオレイナス」
「アテネのタイモン」
「間違いの喜劇」
「じゃじゃ馬ならし」
「ヴェローナの二紳士」
「恋の骨折り損」
「夏の夜の夢」
「ヴェニスの商人」
「ウィンザーの陽気な女房たち」
「空騒ぎ」
「お気に召すまま」
「十二夜」
「終わりよければ全てよし」
「尺には尺を」
「ペリクリーズ」
「シンベリン」
「冬物語」
「テンペスト」
「二人のいとこの貴公子」
舞台劇。作品数が多いので全ての詳細は覚えていないが、「夏の夜の夢」「お気に召すまま」「ペリクリーズ」辺りがお気に入りだった記憶がある。反対に「タイタス・アンドロニカス」は正直オススメ出来ない;通っていた学校に英語で書かれたシェイクスピアの主要作品の漫画があったが、基礎の設定はほぼそのままなのに世界観が滅茶苦茶すぎて笑った。イングランドの作品。
☆ハーバード・ジョージ・ウェルズ
『タイム・マシン』
『モロー博士の島』
『透明人間』
『宇宙戦争』
『恋愛とルイシャム氏』
『月世界最初の人間』
『神々の糧』
『アン・ヴェロニカの冒険』
『解放された世界』
『神のような人々』
『盗まれた細菌』
『奇妙な蘭』
『ダチョウの売買』
『ダイナモの神』
『怪鳥エピオルニス』
『蛾』
『デイヴィドソンの不思議な目』
『ウェイドの正体』
『プラトナーの話』
『マハラジャの財宝』
『海からの襲撃者』
『故エルヴシャム氏の話』
『紫色のキノコ』
『水晶の卵』
『来たるべき世界の物語』
『星』
『盗まれた身体』
『奇蹟を行う男』
『ウォルコート』
『ブリシャー氏の宝』
『世界最終戦争の夢』
『イカロスになりそこねた男』
『新加速剤』
『パイクラフトの真相』
『魔法の店』
『王様になりそこねた男』
『アリの帝国』
『塀にある扉』
戦争時代や科学の暴走、ユートピア・ディストピア思想など内容が多岐にわたる。SF作品の他、評論なども書いている。イギリスの作品。
☆A.E.ヴァン・ヴォークト
『スラン』
『非(ナル)Aの世界』(前記の漫画『成恵の世界』のタイトルはここから取ったものらしい)
『宇宙船ビーグル号の冒険』
『ロボット宇宙船』
『イシャーの武器店』
『宇宙嵐の彼方』
『宇宙製造者』
『惑星売ります』
『非(ナル)Aの傀儡』
『銀河帝国の創造』
『月のネアンデルタール人』
『目的地アルファ・ケンタウリ』
『未来世界の子供たち』
『拠点』
『地球最後の砦』
『時間と空間のかなた』
『終点:大宇宙』
『原子の帝国』
『モンスターブック』
学校で何気なく『宇宙船ビーグル号』を手に取ったのがキッカケでハマりまくったSF作家。古き良きスペースオペラ的な宇宙SF黎明期の物語。生き残るのに必死な宇宙生物や、ものすごい力を持ちながら悩み多き超人など、人間味を感じさせる登場キャラクター達が多いところが好き。カナダの作品。
☆ジュール・ヴェルヌ
『二十世紀のパリ』
『気球に乗って五週間』
『地底旅行』
『月世界旅行』
『ハテラス船長の冒険』
『グラント船長の子供たち』
『海底二万里』
『月世界へ行く』
『洋上都市』
『封鎖破り』
『八十日間世界一周』
『神秘の島』
『チャンセラー号の筏』
『マルティン・パス』
『皇帝の密使』
『黒いダイヤモンド』
『十五才の冒険船長』
『インド王妃の遺産』
『必死の逃亡者』
『蒸気の家』
『ジャンガダ』
『緑の光線』
『南十字星』
『エーゲ海燃ゆ』
『アドリア海の復讐』
『征服者ロビュール』
『十五少年漂流記』
『名を捨てた家族』
『地軸変更計画』
『カルパチアの城』
『動く人工島』
『悪魔の発明』
『氷のスフィンクス』
『ヴィルヘルム・シュトリッツの秘密』
『世界の支配者』
『サハラ砂漠の秘密』
『エクトール・セルヴァダック』
『オクス博士の幻想』
「ザカリウス親方」
「空中の悲劇」
「氷の中の冬ごもり」
「ラトン一家の冒険」
「レ=シャープ氏とミ=フラット嬢」
「二八八九年」
「永遠のアダム」
完全にSF好きになった大元。初めに読んだのは、親の本棚から勝手に引っ張り出してきた『八十日間世界一周』。出会ったのは学生の時で、子供の頃は一切読んだ事がなかった。一番好きなのは『神秘の島』。フランスの作品。
※ウェルズ、ヴォークト、ヴェルヌ作品につきまして、長編と短編の区別なく書名を並べておりますので少しややこしいかもしれません。
☆画集
『現代世界の美術18 ダリ』サルバドール・ダリ
集英社。シュルレアリスムの不思議な世界。思い出したら眺めたくなる。スペインの画家。
『現代世界の美術17 デ・キリコ』ジョルジョ・デ・キリコ
集英社。空虚なシュルレアリスム世界。謎のもの悲しさと恐怖感。イタリアの画家。
『マグリット 光と闇に隠された素顔』ルネ・マグリット
マール社。普通にあるはずの物体が、なんか普通に見えない世界。ベルギーの画家。
『エッシャーの世界』マウリッツ・エッシャー(ブルーノ・エルンスト著)
朝日新聞社。独創的すぎて、この人にしか描けないのではないかという程の綿密緻密な世界。オランダの画家。
※シュルレアリスム大好きです(もちろんその他のジャンルも)。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
皆さんも、面白そうと思った作品がありましたら是非読んでみてください。
(今回紹介させていただきました作品の中には、現代社会と照らし合わせてみて不適切と思われる内容や表現が含まれているものもあるかと思いますが、作品が描かれた当時の社会情勢などを表しているものでもありますので何卒ご理解くださいませ。)
元々あまり本を読まない人間だった自分に『ハリー・ポッターと賢者の石』を渡してくれたのは親で、その後に本をたくさん読むようになったキッカケも親の本棚を漁って面白い本に出会えたからで、そう考えると親に感謝の毎日です。
とりあえず、今回はこんなところで。
(今までリストを延々と書いていた為、こんな時間になってしまい申し訳ありません;)
今回も、ご愛読いただき誠にありがとうございます (^_^)ゞ
いつも感謝です m(_ _)m
中高生の頃より現在のような夢を元にした物語(文と絵)を書き続け、仕事をしながら合間に活動をしております。 私の夢物語を読んでくださった貴方にとって、何かの良いキッカケになれましたら幸いです。
