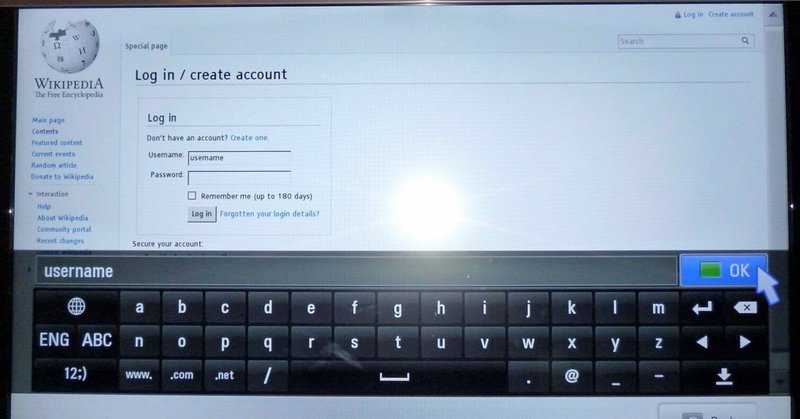2022年9月の記事一覧
Human Rights Abuses on the Net (2007年10月)
The Internet, notably the World Wide Web, is taking root as a new means of media in Japan as is the case in the rest of the world. It is good that anyone is now able to transmit information easily
もっとみる「ウォーターフォール・モデルは間違いだ!」 (2009年8月)Agile Japan2010用
シンプルで美しい方法
現在、日本におけるソフトウェア開発プロジェクトの大半は、ウォーターフォール・モデルで行われている。ウォーターフォール・モデルとは、ソフトウェア開発の工程を(1) 要求定義、(2) 設計、(3) コーディング、(4) テスト、(5) 保守のように分けて、それらを順に実施していくという手法である。
最初にきちんとした計画や設計書をつくり、それに従って実行するという方法であり
長崎県と佐賀市の取組みから何を学ぶか 「行政とADP」 (2005年6月)
地方自治体におけるIT調達改革の取組みは、それぞれの自治体によって進捗状況に大きな差があるだけでなく、その取組みの方向性もかなり異なっている。本稿では「自前設計型」の長崎県と「SI連携型」の佐賀市を取り上げ、そのIT調達改革から学ぶべきものを考えてみたい。
1. 自前設計と小分け発注の長崎県1.1. 自前設計の手法
長崎県のIT調達の特徴は、自前設計と小分け発注にある。自前設計とは、県
すでに通信と放送の融合時代は始まっている (「季刊EIT」 2006年3月)
世界で最もブロードバンドが普及している韓国では、国民のテレビ視聴時間と地上波テレビの広告収入がともに低下傾向にあるという。原因の一つは、数年前からドラマを含むテレビ番組がインターネットで再配信されるようになったからである。好きな時に見ることができるオンデマンドの番組もあるし、モバイル機器向けのテレビ放送もすでに韓国では普及している。おそらく、今後日本でも韓国のようにパソコンや携帯電話、PDAでテ
もっとみるネットバブルの崩壊から得られた教訓 第4回 「競争を勝ち抜く戦略」 (2004年)
米国商務省センサス局が調査している小売業のオンライン売上を見ると、前年同期比で20%台後半の伸びが続いています。この電子商取引市場の拡大に大きく寄与しているのは、「ピュア・プレーヤー」と呼ばれるインターネット専業の小売店ではなく、「マルチチャンネル・プレーヤー」と呼ばれる既存の小売業者になっています。
たとえば、世界最大の小売企業であるWal-Mart、百貨店のJC Penny、Sears
ネットバブルの崩壊から得られた教訓 第3回 「勝ち組みの成功要因は何なのか」 (2004年)
ネットバブル時代に多くのECサイトが目指したビジネスモデルが、薄利多売型のネット小売モデルでした。しかし、このビジネスモデルで成功したのは極めて限られています。ピュア・プレーヤーと呼ばれるネット専業の企業に限定すると、大成功したのはAmazon.comだけかもしれません。
前回に説明したように、Amazon.comのような薄利多売型のビジネスモデルでは、資金が枯渇する前に、十分な数の顧客を獲
ネットバブルの崩壊から得られた教訓 第2回 「破綻した企業と破綻した原因を考える」 (2004年)
破綻した企業はすべて、ValueAmericaのように顧客の評判が悪かったわけではありません。たとえば、ネット上で玩具を販売していたeToysは、2001年3月に破産してしまいましたが、とても評判のよい企業でした。たとえば、優良ウェブサイトを紹介した『Gomez BEST WEB 2001』という本が2000年に出版されていますが、eToysは、この本の玩具部門では第1位にランクされています。ま
もっとみるネットバブルの崩壊から得られた教訓 第1回 「ネットバブルの崩壊で何が起きたのか」 (2004年)
新興の情報系企業が数多く上場しているナスダック総合株価指数をみると、2000年3月10日に5048ポイントを記録した後、歴史的な下降局面に入り、約1年後の2001年4月初めに1600ポイント台まで下落しています。これが、いわゆるネットバブルの崩壊です。ドットコム企業の株価は暴落し、いくつもの上場企業が破産してしまいました。また、それ以上の数のネット系ベンチャーが、新規株式公開の夢を実現できないま
もっとみる