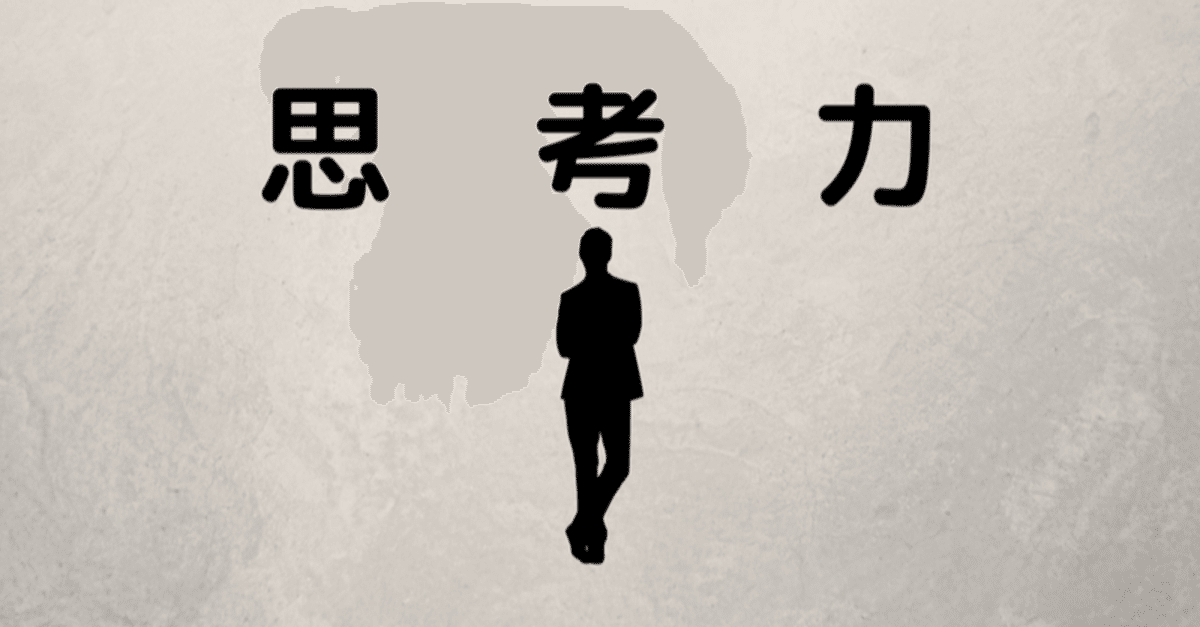
思考力の鍛え方 IQの上げ方 実践編・初級〜中級編
こんばんは、経営者のこうたです。
考える癖がつけば思考力は鍛えられるよ、というのが前回説明した内容です。
思考力とはなんぞや?
IQを上げたい!
などの疑問を持った方は、上記の記事をご参照ください。
1.前提認識
前記事でも軽く触れていますが、考える内容はなんでもいいです。
しかし最初は、普段から考えている内容だとあまり意味がありません。
例えば仕事に関してなら、自分が与えられた業務を
どのような順番で
どう効率よく
どうすれば高い成果を出せるか
業務内容にもよるとはいえ、一般的なサラリーマンはこの辺りのことを常に考えていることでしょう。
あの同僚、部下、上司はなぜ実績が伸びないのか
長所と短所は何か?
このままいくと自分の仕事はどう変化していくのか
必ずしも答え合わせを求める必要はありません。
その内容が間違っていても、普段考えないことを考えることが重要。
特に分析する思考は様々な方向に広げられますし、精度を高めて損はない分野です。
まあいざ仕事中にいつもと違うことを考えろと言っても、凝り固まった状態なのでなかなか難しいと思います。
そんな中、noteは人の思考がまとめられた有用なサイトです。
他人の意見に対して自分の意見・分析を考えるということは、論理的思考を養うのにうってつけです。
1人ディベートのようなイメージですね。
2.本を読む時にも鍛えられる
前置きが多いのは、少しでも思考のイメージをしっかりと持ってほしいからです。
本題に入る前にもう少しだけお付き合いください。
ビジネス本、自己啓発本などを読んでいる人は、どのように吸収していますか?
よく効率的な読み方として、読破後に要点をまとめてみるというものがあります。
人は200ページに及ぶ内容をしっかりと記憶することが難しく、また正しく理解するのも困難。
ゆえに自分の中で整理して書き出すことで、深い理解としっかりした記憶に繋がるというものです。
この手法、否定はしませんが個人的には非効率。
膨大な量の蓄積はいつかのために必要ですけど、活用できなければ無駄な知識と同じです。
であれば、自分ならその知識をどう活用するか、自分の状況ならどう応用すれば当て嵌められるかなど。
ここまでしなければ吸収したとは言えません。
今使えない知識をしっかりと覚える必要はありません。
必要な時に読み返せる程度に覚えておけばいいのです。
重要なのは、一見すぐに使えないと思える内容に対し、どう紐づけて思考に繋げるかを考えること。
もっとも、基礎知識の部分、いわゆる土台の理解はしっかりしたほうがいいですね。
3.noteで実戦してみよう(初級編)
さて、ここからが本題です。
分析し、自分ならどうするかを念頭に以下を読んでください。
ちなみに現代人は睡眠時間の確保が難しいことも多いため、睡眠不足を理由に改善することは省きます。
この記事は、毎回眠くなるたびに決まった行動をとることで、やがてその行動が目を覚ますことに繋がるという内容でした。
この記事を読んでいただいて、まず最初に「試してみよう」と思った人はアウトです。
思考するなら、「自分が目を覚ます時はどういう時だろう?」「眠くなった時ってどうしていたっけ?」「そもそも自分の眠くなる原因は?」です。
私が上記の記事を作成したきっかけは、何を書こうかなと考えていた時に眠かったから。
そしてどうやって眠気を覚ましていたかを考えた時、「そういえばいつもあれやってたわ」と思い至ったわけです。
眠くなる理由はなんだろう?
↓
脳の疲労
↓
原因排除の分析
↓
リセットだ!
↓
その手段は?
↓
あれ、これって……
↓
ルーティン化してたのか
細分化するとこんなにありました。
書き出して自分でもちょっと驚いています笑
これを読んだ人が活用するのだとしたら、
自分が眠くなるのはなぜ?
↓
目の疲労、薬の副作用、脳の疲労など
↓
(脳の疲労は)どうすれば改善できる?
↓
普段自分はどういう時に目が覚めていた?
↓
あれだ
↓
じゃあこれをルーティン化してみよう
ルーティン化はあくまで脳の疲労が前提なので、必ずしも効果が見込めるとは言えません。
眼精疲労ならホットアイマスクのほうがいいと思います。
薬の副作用なら試す価値はあるかもしれませんが、私なら副作用が軽減される薬を探すことから始めます。
人の思考って細分化すると複雑なことに気づきます。
自らの思考フローを書き出すのも立派な分析思考です。
3.noteで実戦してみよう(中級編)
初級編は自己分析と単独の実行だけで済む、自己完結型でした。
中級編は、自己分析に加えて、他者分析も行う内容です。
この記事は、小さな好意は簡単に与えられるから、返報性を目的に利用しようという内容でした。
まず最初に考えるのは、「小さな好意ってなんだ?」です。
上司は部下に「ありがとう」と言いましょうと書いてあるのですが、部下の立場なら、「上司にありがとうと言われたのはどういう時?」と考えてみます。
そして次に、「自分が与えられる小さな好意はなんだ?」と、同僚・部下・上司のパターンで考えます。
つまり、
上司から「ありがとう」と言われるタイミング
↓
なぜそのタイミング?(分析)
↓
同僚や他の人はどのタイミングで言われている?
↓
この働きなら「ありがとう」と言ってもらえるかも
↓
じゃあ自分が同僚や部下に小さな好意を伝えるためには?
↓
より自然に、より効果的な方法の模索
↓
小さな好意を伝えるため、もらえるために誘導しよう
必ずしもこの思考フローである必要はありません。
『言ってもらう』、『自ら実行する』、『誘導する』の3つの実行があるので、最初は1つか2つでいいと思います。
これ、重要なのは実際に実行することではありません。
もちろん試行錯誤をして思考を修正していくのも大事ではあるのですが、まずは思考をすることが先決。
実行するとしたら最低でも1日はかかりますから、そうするくらいなら他の記事を見て思考を繰り返したほうが効率的です。
ある程度したら、自分が実行できそうなものから手を出していきましょう。
上級編は次回に。
今回は分析のみでしたが、上級編は他者の意見を元に、自分の意見を0⇨1で作り出す思考法です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
