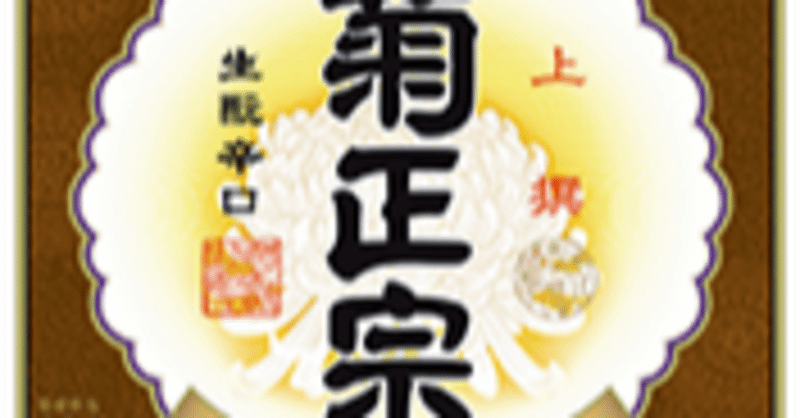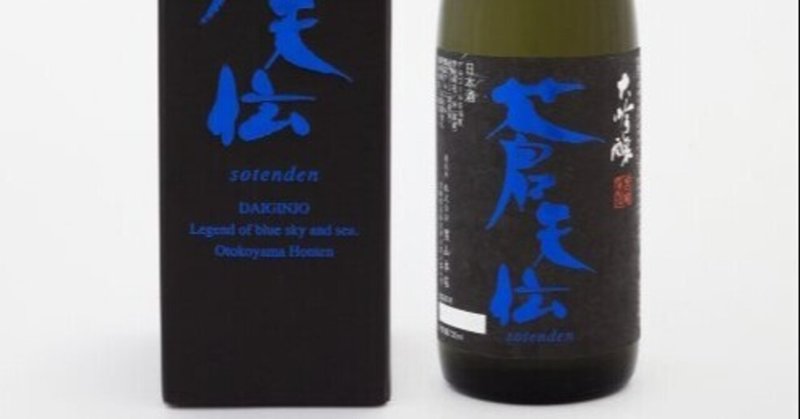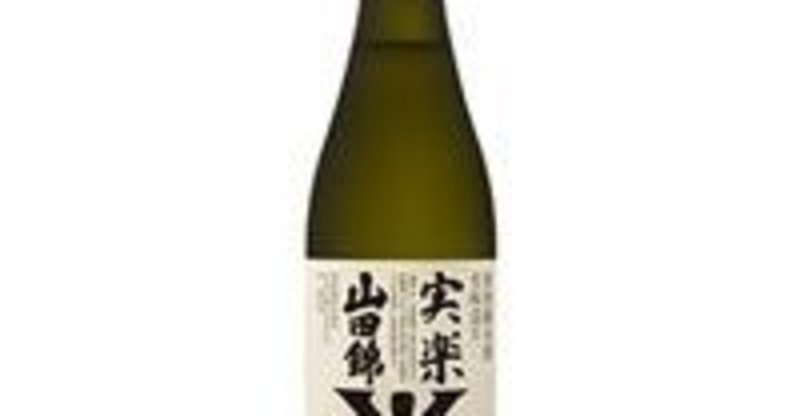#江戸時代
江戸期~昭和初期の経済成長(市場経済側の経済的な視点からの日本酒)その2 本日の紹介酒 櫻正宗 灘の生一本 純米酒 (兵庫県 灘)
※日本酒の画像は、櫻正宗㈱HPより引用
非常に厳しかった市場での酒質の競争
この頃、江戸へお酒を卸すには、上方の銘醸地である伊丹・池田・摂津富田・西宮・灘等の銘醸地の間で熾烈な酒質の競争が行われていて、現代の語の「下らない」の語源は上方から江戸へ下れない酒でありました。
仮に下れたところで仮に下れたところで、上方の酒同士での競争はもちろん、中国酒(愛知県の知多地方や三重県の四日市近辺)や関東
生酛造りで造られた日本酒の味わいとは その5 慶長の遣欧使節団とシェリー酒 本日の紹介酒 菊正宗 上撰 生酛 本醸造パック (兵庫 灘)
慶長の遣欧使節団は長期間スペインのシェリー酒の醸造所に滞在していたこの使節団は長期に渡りスペイン内のシェリーの醸造所に滞在した事が(伊達政宗の遣欧使節 松田毅一著)には出ていました。直接、日本酒造りと関係ないと言われればそれまでだし、シェリー造りでは日本酒と全く同じでは無いですが、ワインにブランデーを加える目的は、お酒の味わいをスッキリさせる事と、お酒の保存性を高める事です。
山卸を足踏みで行う
生酛造りで造られた日本酒の味わいとは その4 山卸の作業はどのように進化したのか 本日の紹介酒 蒼天伝 大吟醸 (宮城県 気仙沼市)
足で酛摺りを行うようになった機会を作った出来事 本格的に足で酛摺りを行うようになったきっかけを考える場合、可能性が一番高いのが、伊達政宗公によって行われた慶長の遣欧使節です。
何故、慶長の遣欧使節が派遣されたのかこの使節に関しては伊達家がスペインと組んで天下を取りに行ったが故に行われたのではないかという説もありますが、(実際に家康公の体調が悪い時に本当に仙台藩と江戸幕府の間で戦争に成りかけたが、
戦国期から江戸初期に日本酒造りの技術が発展した理由 本日の紹介酒は、澤の鶴 特別純米生酛 実楽山田錦 (兵庫県 灘)
応仁の乱が起こった頃の日本の人口と、関ヶ原の合戦頃の日本の人口(画像は応仁の乱wikipediaより引用)
応仁の乱の発生時(1462年)前後の人口の目安として、1450年頃の日本の総人口は約1000万人前後だと言われています。その後、関ヶ原の戦いが行われた1600年頃の日本の総人口は1500~1600万人前後と言われていて、僅か150年の間に大きな戦乱の時代が全国規模で発生しているにもかかわ