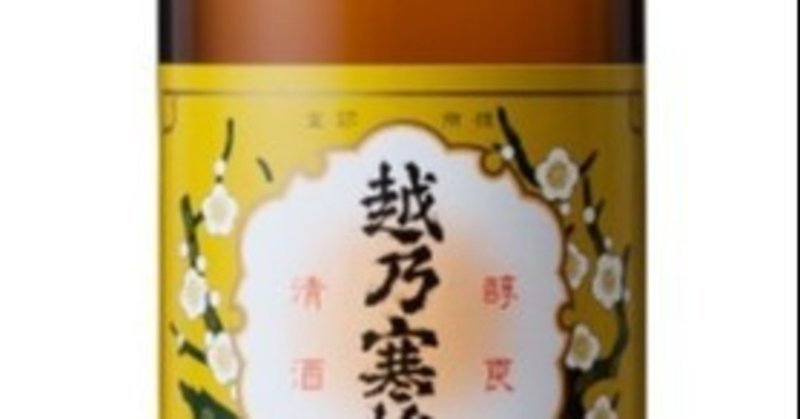- 運営しているクリエイター
#ゆたかさって何だろう
幻の越乃寒梅の別撰、想像以上に甘みを感じました。今回他の有名どころの日本酒とテイスティングの比較を出してみます。
日本酒の幻の銘酒を実際に比較テイスティングしてみました皆様も幻の銘酒と言えばって話になると思いますが、昭和40年代以降って括りにした場合に思い浮かべるお酒は何でしょうか?昭和を生きた方々ならば越乃寒梅と答えはると思いますし、その他には八海山、久保田等の新潟酒、平成ならば、一番最初に登場するのは多分、十四代では無いかなって思います。
1、特選ゴールド賀茂鶴 大吟醸 (広島県)
昭和の時代に一番最
生酛本来の味に対する疑問 その4 幕末から昭和初期に掛けての社会の変化と食 本日の紹介酒は、大七 生酛純米(福島県) このシリーズの最終回です。
幕末には黒船が来航し、この頃にコレラが流行、また、安政の大地震と言われる大地震、1854年(安政元年)に今話題の東南海地震、1855年(安政2年)には安政江戸地震等の大地震が立て続けに発生し、江戸幕府が倒れた本当の理由は、外国から持ち込まれたコレラと安政の大地震と呼ばれる大地震が立て続けに発生した事とも言われています。一方で、この頃になると各藩の財政状況もかなり悪化し、米だけでは無く各藩で特産品、
もっとみる日本酒の桶買い、桶売りに関して少し書いてみました。 本日の紹介酒は八海山 吟醸酒(新潟県)
Quoraにて、以下の質問を受けました。
「大手酒造メーカーさんの一般大衆向けの有名なお酒は、たくさん出荷しなければならないので、近隣の契約している酒造家さんからお酒を集めて調合して流通しているというのは都市伝説ですよね?」https://jp.quora.com/q/nihonshu-te-isu-tein
※上記は質問サイトQuoraの日本酒テイスティングブックのスペースです。
この件に
生酛本来の味に対する疑問 その3江戸の食の発展の側面から 本日の紹介酒は天狗舞 山廃純米酒(石川県)
読者の皆様、ファーストフードと言えば、イメージするのはマクドナルドや吉野家の牛丼、くら寿司等を想像すると思いますけど、江戸時代にもファーストフードは有りましたし、現在のような定食が出来たのも江戸で江戸の街を作るための人夫さんの為に考えられた奈良茶飯が最初だったと言われています。
※下記映像に関しては、お江戸系Youtuber堀口茉純さんのページより引用いたしました。
江戸幕府が開府したのが16
生酛本来の味に対する疑問 その2経済成長の側面から 本日の紹介酒は 櫻正宗 焼稀 生酛純米 協会1号酵母
2019年現在の日本の人口は約1億2700万人、GDPは約550兆円となっていて、国民一人当たりのGDPが約433.7万円となっていて、普通に働いて生活していれば、少々貧しくても一定のお金さえ出せば、欲しいものは買えますし、余程のことが無ければ食に困ることも、ほぼ無いと言えると思います。
※下記画像は東京の高層ビル群 じゃらんネット(https://www.jalan.net/kankou/sp