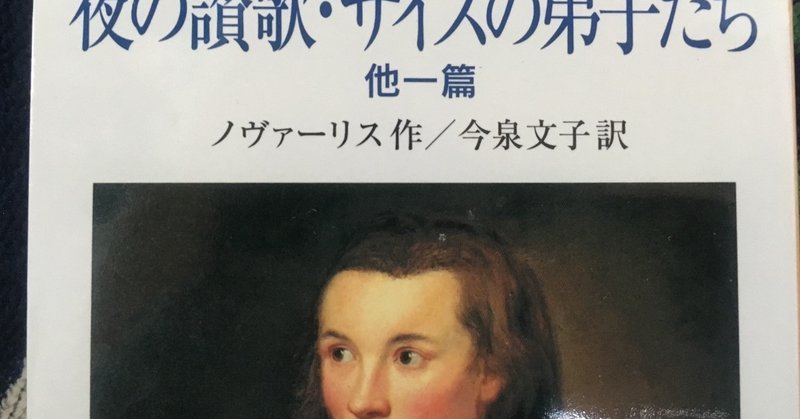
夜の讃歌・サイスの弟子たち他一篇/ノヴァーリス
モノたちの側から見て、僕たち人間はどう見えるのだろう?
「ああ、人間に」と物たちは言った、「自然の内なる音楽を理解し、外なる調和を感じとるための感官がそなわっていればいいのに!」
まあ、こう指摘するからには、「物たち」の側にはその両方ともが備わっているのだろう。だからこそ、彼らは環境において他の無機物、有機物と連携して生態系の調和を作れるのだろう。
人間とは違って……。
スティーヴン・シャヴィロの『モノたちの宇宙』という本を紹介したのは昨年12月のことだ。
その本で著者のシャヴィロは「今やぼくらはこの地球上の他のありとあらゆる生きものとどれほどぼくたちが似ていて緊密に関係しているかを知っているので、自らを他に例のない独自の存在と考えることはできなくなっている」と書いていた。
いや、あらゆる生きものが僕らに似ているだけでなく、「遍在する媒質、あるいはぼくら自身の拡張として、モノたちの宇宙は、直接、目に見え、現前しているものがどんなものだろうと、これをはるかに越えて広がっている」と言っていたりもしていて、「ある1つのモノは、どれほど広げられようと、モノの特徴や性質の目録によっては決して十全に定義しえない。なぜなら、モノはそうしたあらゆる特徴づけを越えて、それじたい自律した力を備えているからである」と、モノたちの見方は僕たちの見方にはおさまらない自律性を有していることを示唆していた。
人間の見ているものと、モノたちの見ているものは違う。
「人類」は万物の尺度ではない。ぼくらは普通、この世界をぼくら自身にあらかじめ課された概念によって把握する。この世界におけるモノたちの奇妙さ=異方性にいたるためには、つまり、ぼくらに「措定され」たり、「与えられ」たり「提示され」たりすることなくモノたちが存在する仕方に行き着くためには、この習慣を打ち破る必要がある。
というのが、シャヴィロの考えだった。
ようするに、モノたちの考えは、僕ら人間の考えをはるかに超えていたりするから、彼らが何を思い、何を考えているかなんて、僕ら人間にわかるはずもないという話だ。
モノたちの言い分を聞きとって
だとしたら、冒頭の引用中の「物たち」の人間に対する不満の声はなんだったのだろう?
人間が自分たちのこともまわりのこともわかっていないと嘆く「物たち」の不満はいったい誰が聞いたのだろう?
「人間ときたら、われわれと人間がともにひとつの全体をなすもので、どちらも他方なしには存続しえないということにあまり気づいてないのだから」
と、続く自分たち=「物」との共生関係、「物たち」との相互依存的な生態系に気づかない人間たちの鈍感さについての「物たち」の嘆きを聞きとったのは、ドイツのロマン主義詩人ノヴァーリスである。

彼の『サイスの弟子たち』という初期に書かれた小説では、さらに次のような「物たち」による人間に対する批判が続いていく。
人間はなにひとつそのまま放っておくことができず、暴君のようにわれわれを切り離し、やたら引っ掻きまわしては調和を乱すばかりだ。もし人間が、みずからいみじくも名づけたあの往古の黄金時代のように、われわれと親しく交わり、われわれの大いなる盟約に加わるなら、どんなにか幸福になれるだろうに。あの頃は、人間はわれわれを理解し、われわれも人間を理解していた」
この「物たち」による一連の嘆きは、ようは生態系の調和に配慮しようとしない人間への糾弾である。ノヴァーリスはそれを今から200年以上前の18世紀末において行っている。
『自然なきエコロジー』でティモシー・モートンが「消費主義の誕生はロマン主義の時代と一致している」といみじくも指摘しているように、ロマン主義が自然というものをその畏怖すべき崇高さを含めて、人間的な文化に対比するかのように肯定したのは、まさにヨーロッパが産業化されていく時代であった。
産業革命とそれに基づく消費社会の形成がその影響を拡大していく中で、「物たち」に人間は「暴君のようにわれわれを切り離し、やたら引っ掻きまわしては調和を乱すばかり」であると非難するように仕向けるのは、当然の反応であったといえる。しかし、同時にモートンが指摘するように、この時代の芸術家たちにとっては、それ自体、自然や「物」という観念を消費しやすいものに変えてしまうような諸刃の剣のような側面もあった。
不可解とは、理解力のなさがもたらす結果である
けれど、ノヴァーリスの作品について言えば、決して「消費しやすいものに変える」という効果があったようには思えない。
不可解とは、要するに、理解力のなさがもたらす結果にすぎない。理解力が無いと、自分がすでに持っているものしか求めない。だから、それ以上の発見にはけっしていたらないのさ。
などと言ってみせるノヴァーリスの作品からは「わかりやすくする」という意図はほとんど感じられなくて、それゆえ、理解という消費をやすやすと助長するような表現もまったくと言っていいほど見当たらない。
さらに昔に遡ると、科学的な説明のかわりに、人間と神々と動物が、共同の工匠となって作りあげる不思議な譬喩的形象に満ちたメルヒェンや詩があった。そこには、きわめて自然な仕方で世界の生成が述べられているのがうかがえる。
とノヴァーリスが1798年に書いたとき、そこには200年以上先の現在の人為的な影響があらゆる領域で地球環境を危機に晒している時代に生きる僕らにこそ、必要とされる考え方をしているよう感じられる。
先にも書いたように、『モノたちの宇宙』でシャヴィロは「科学の実験や発見の光に照らしてみても、人間中心主義はますます支持できないものになっている」と言い、「自らを他に例のない独自の存在と考えることはできなくなっている」とノヴァーリスが示したことにもつながる指摘をしている。
そう、ノヴァーリスはこんな風に言う。
岩は、まさしくわたしが話しかければ、特別の「汝」にならないでしょうか。また、わたしが物悲しい心で川波をのぞき、そのよどみない流れに百千の思いが没し去るとき、わたしは川以外のなにものでもないでしょうか。楽しみを知る物静かな心だけが植物の世界を理解し、快活な子供や野生人だけが動物を理解するでしょう。
人間は、岩にもなれば川にもなる。
これはさらに昔の古代ローマの詩人オウィディウスの『変身物語』にも通じる世界観だ。
その一大叙事詩作品の中で「どんなものも、固有の姿を持ちつづけるということはない」とオウィディウスは、かのピュタゴラスに語らせている。
「この全世界に、何ひとつ滅びるものはない」とし、「さまざまに変化し、新しい姿をとってゆくというだけのこと」であるとする、オウィディウスの世界認識は、「なのに人間ときたら、われわれと人間がともにひとつの全体をなすもので、どちらも他方なしには存続しえないということにあまり気づいてないのだから」と嘆く「物たち」の思いを感じとれる感性を持ちえている。
だからこそ、ノヴァーリスは「自然研究者と詩人は、ひとつの言語を用いることによって、つねにひとつの族であるかのようにふるまってきた」と書くことができたのであろう。
ノヴァーリスが言う「理解」とはそういう理由なのであって、安易に消費可能なわかりやすい答えとはまるで異なるものだと思う。
感じることのできる物質
円城塔は長編SF小説『エピローグ』の中で、どんな形態にも変形できる登場人物(?)のアラクネ(先の『変身物語』にも登場する女神アテナの怒りをかって蜘蛛の姿に変身させられる織物名人の女性がオリジナルだ)にこう言わせている。
わたしたちからしてみれば、あなたたちはただの自然現象のように見えます。万物と何も変わることのない、感じることのできる物質であるにすぎません。たいていのものがそうであるように、自律していると信じ込んでいる自然現象です。
見てのとおり、ノヴァーリスの「物たち」が指摘したのと同じことだ。
僕らは「感じることのできる物質」であり、大腸菌のような単細胞生物でも外界の変化を感じられるのと変わらないし、石や金属などの無機物が外界を感じていないということだって言い切れない。
僕らは自分たちが「自律していると信じ込んでいる」が、これも「物たち」が指摘してくれているとおり、「われわれと人間がともにひとつの全体をなすもので、どちらも他方なしには存続しえない」ような「自然現象」でしかない。
自然現象であることを認識することで、人間のあり方は大きく変わってくるのではないだろうか?
生まれつき眼が見えなければ、いくら色や光や遠くのものの形について説明されても、見ることは学べない。それと同じ話で、自然器官、すなわち、自己の内部に自然を生殖し、産出する道具を持たぬ者は、自然を把握するようにはならないだろう。どこにいてもあらゆるものに自然を認め、これを識別し、生来の生殖欲をもって、あらゆる物体と密接な親和関係をさまざまに結びながら、感覚を媒介としてあらゆる自然物と交じりあい、いわばそれらのなかに感入する-こうしたことがおのずとできぬ者は、自然を把握するようにはならないだろう。
進化生物学者のリン・マーギュリスが「競争ではなく、共生こそ進化の原動力」とした共生進化論の考え方がここに重なってくる。
マーギュリスは、大気学者のジェームズ・ラブロックが唱えたガイア理論の支持者でもあるが、ノヴァーリスがこの『サイスの弟子たち』という作品を通じて描く自然との共生を考える「サイスの弟子たち」はまさに、その150年以上後に提唱される、その理論を先取りしているようだ。
さらにノヴァーリスがこう考えたのは、そもそもチャールズ・ダーウィンが自然淘汰の進化論を唱えるよりも30年も前のことだ。
こうした先見性からは、ノヴァーリスが「自然研究者と詩人は、ひとつの言語を用いることによって、つねにひとつの族であるかのようにふるまってきた」と書くのも納得がいく。
美的な遭遇
「モノたちは互いに美的に遭遇しあうのであって、ただ単に認知的ないし実践的に出会うのではない」とスティーブン・シャヴィロは言っていた。
物たちが行なっている「美的な遭遇」は、ノヴァーリスが「生来の生殖欲をもって、あらゆる物体と密接な親和関係をさまざまに結びながら、感覚を媒介としてあらゆる自然物と交じりあい、いわばそれらのなかに感入する」というあり方と重なってくる。
精神の色彩がひとつに溶けあうにつれ、個々の自然物や現象も、みな、ますますひとつに溶けあい、ますます完全な、ますます人間的な姿をとって、この色彩のなかへと流れ込んでいくー印象のありようとは、感官のありように呼応するものだからだ。それゆえ、かの昔日の人びとには、万象が人間的で、なじみ深く、親しいものに思えたはずだし、かれらの眼には、それらの最も鮮やかな特性がそのまま映じたにちがいない。また、かれらの口にする言葉は、ことごとく、真の自然の息吹であり、かれらの思い描くものは、周囲の世界と一致し、その世界の忠実な表現となっていたにちがいない。それゆえ、環界の事物についてわれわれの祖先が思考したことは、当時の地上の自然状態から必然的に生みだされたものであり、その自画像であるとみなすことができる。またとりわけ、万有を観察するのに最もふさわしい道具であったかれらの思考を見ると、万有の主たる関係、すなわち当時、万有がそこに住む人びとに対してとった関係、また人びとが万有に対してとった関係が、はっきりとわかるのである。
SDGs(持続可能な開発目標)が何かと話題になる。
それはもちろんいいことだ。
けれど、どうすれば持続可能性は達成できるのだろうか?
この人新世の世が「千代に八千代に」持続可能性を維持していくためには、この200年以上前に書かれた『サイスの弟子たち』に描かれた人びとのように、日々の暮らしのなかで、もっと人間以外の物たちとの美的な遭遇を意識していかないといけないのだろう。
基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。
