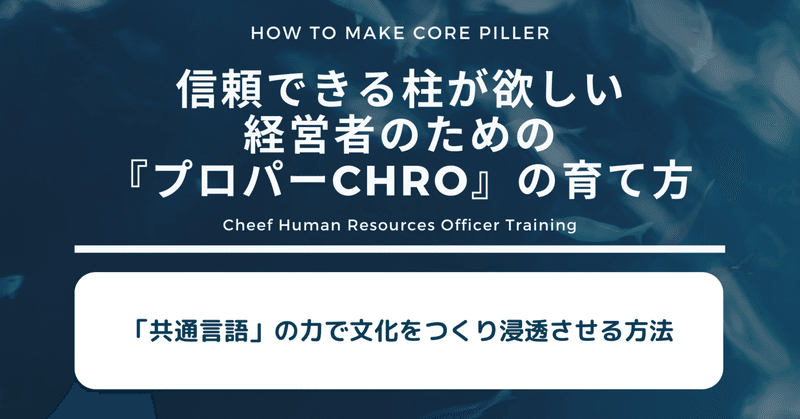
「共通言語」の力で企業風土をつくり浸透させる~信頼できる柱が欲しい経営者のための『プロパーCHRO』の育て方Vol:8~
こんにちは。株式会社シンシア・ハート代表の堀内猛志(takenoko1220)です。
このシリーズでは、「信頼できる柱が欲しい経営者のための『プロパーCHRO』の育て方」について、50名から4000名まで成長した企業で、各ステージの人事組織戦略の遂行に人事役員として奔走した自身の経験をもとに、人事トップになるために実行したことや、意識していたマインド、経営や現場とのコミュニケーションのtipsなどをお伝えしていきます。
私の経歴詳細は以下からご確認ください。
それでは、今回のアジェンダです。
今回は「共通言語」の力で文化をつくり浸透させる方法を解説します。
企業文化は戦略に勝る
ドラッカーの「企業文化は戦略に勝る(Culture eats strategy for breakfast)」という言葉はよく知られています。また、経営学者のマイケル・ポーターは著書「競争の戦略」において、「戦略とは、独自の地位、競合よりも優位なポジション、そして持続的な発展、持続的な競争優位を構築するためのフレームである」旨を述べています。
「企業とは人であり、その知識、能力、絆である」、これもドラッカーの言葉ですが、経営者の戦略を実現するのは社員であり、企業文化の醸成や変革にいかに取り組んでいくかは企業の未来を左右する重要なことです。
「組織文化」は「組織においてその構成員が共有する価値観・行動様式」を言い、それは個々の従業員の実際の具体的な行動と組織環境・組織風土にあらわれます。「企業文化」は「企業内の組織毎に存する組織文化の集合体」だと思ってください。これが「組織文化」と「企業文化」の違いです。
企業文化と企業風土の違い
文化と風土という言葉がごっちゃになって使われることがあるので整理します。企業文化は「企業が目標を達成するための価値観や規則」のことをいいます。それに対して、「企業風土とは従業員が企業に対して感じている雰囲気や人間関係」のことです。
企業文化は経営者が企業のビジョンや理念などを従業員全員に浸透させることによって、価値観や判断基準を均一化させることができます。企業文化は、「経営者が作り上げたい価値観を従業員に浸透させようとしているもの」であり、企業風土は「長年にわたり自然と根付いたもの」のことをいいます。そのため、企業文化は改革ができますが企業風土はなかなか変えることはできません。
まとめると両者には以下のような違いがあります。
企業文化は変化できが、企業風土は変えにくい
企業文化は示し合わせてできたもので企業風土は根付いたもの
企業文化はポジティブであるが企業風土はネガティブの可能性がある
以上より、企業文化を基準にして採用活用や従業員の評価、また経営時の判断することを徹底することによって、従業員の言動は、企業理念やビジョンから大きくずれることはなくなります。
従業員にとっても、企業が求めていることや人材を把握できるため満足度が上がり離職率が下がる要因にもなります。企業文化は社会や市場の変化などに合わせて改革をすることも可能です。
対して組織風土は人間でいえばくせや性格のようなもので自然と根付いたものなので、意識的に変えることはできません。人間のくせや性格も簡単に変えられるものではないのと同じです。企業のくせとは人間関係や社内でしか通用しない習慣などさまざまなものがあります。
つまり、企業は設立当初から企業文化の形成に力を入れておくことで、強い企業風土をつくることができますが、逆に、設立当初は人数が少ないからと企業文化を意識せずに、例えばゆるく、イレギュラーを認めるような言動を行っていると、企業風土は自然とゆるくなっていってしまい、変えたくてもなかなか変えられないという慢性疾患のような状態になってしまうのです。
企業文化徹底☛企業風土醸成☛企業価値向上
漢字ばかり並んで読みにくくてすみませんw
が、この連鎖が重要なので解説します。図解した方がわかりやすいと思うので以下のようにまとめました。

醸成したい企業文化は一例です。
まずは醸成したい企業文化を具体的に明文化します。ポイントはそこに解釈の要素が入る表現を極力ゼロにできるくらい具体的にすることです。
次に経営者を始め、組織長が率先垂範します。この際に、影響力が強い人材を巻き込むと尚良いです。影響力が強い人材とは「エース」「キーマン」「ムードメーカー」などのみんなから信頼が厚い人気者です。人気者がエバンジェリストとして行動を広めてくれることで、周りがその行動に自ずと引っ張られます。他には「新卒」「新人」です。権威性がないけどフレッシュな人材が行うことで、先輩に無言のプレッシャーを与えます。『後輩ができているのに先輩ができていないのは恥ずかしい』ってやつですね。
最後に、きちんと評価してRE活用することです。その場で終わっては風化します。人間は報酬によって動かされます。金銭報酬だけではなく、表彰されたり、褒められたり、非金銭的な報酬を活用することによって、さらに言動が強化されていきます。
これらを継続することで「企業風土」ができあがります。説明をしなくても、従業員が行動するうえでの良し悪しの判断基準が無意識にわかるレベルになってきます。これによってコミュニケーションコストは下がり、生産性は上がり、企業価値の向上につながるわけです。
企業文化を企業風土に変換できるのは『言葉』の力
では、企業文化をどのように浸透させると効果的でしょうか。上記のステップによって企業文化徹底☛企業風土醸成☛企業価値向上につながることは理解いただけたかと思いますが、企業文化徹底という最初のステップの難易度が高くて皆さん困りますよね。
従業員の言動を徹底するために重要なのが「言葉」を巧みに利用することです。全ての思考は「言葉」から始まるのです。
企業文化が徹底されている企業は「宗教的だ」と表現されます。日本では宗教をネガティブに考える人が多いですが、グローバルでは悪いことではありません。日本で宗教をネガティブに考えることは洗脳という要素があるからだと思いますが、「洗脳」とは「隙がないくらい合理的」であることと同義であり、本人からしたら、「目指す世界観」「大切にしている文化」「重要な価値観や言動」が心の底から納得し、合理的につながっている、ということなので、否定してくる人の方がおかしいと思うのです。
信用 < 信頼 < 信仰
右に行くほど信者の想いは強く、コミュニケーションコストを下げることができます。当然、この力を悪い方向に使ってはいけませんが、企業が目指す世界観、価値観、文化に宗教的に信仰すること自体は悪いことではありません。むしろ、経営者はこのような信仰メソッドは宗教から学ぶべきだと思います。
ちなみに、この本は宗教的な組織をつくるのに非常に学びになります。
そして、この章における本題ですが、宗教にならうと、言葉をうまく活用し、普及していることがよくわかります。キリスト教を例にとると、聖書やゴスペルがそれにあたります。
組織を拡げていけばいくほど、末端の信者が教祖に直接会う機会は減ります。また、教祖はいつか亡くなります。つまり、教祖本人じゃない人でも教祖のように信じる言葉を伝え続ける必要があるのです。その際に用いられたのが聖書やゴスペルです。教祖の考えを紡いだ聖書は、皆で読み合せることで教祖の考えをインプット⇔アウトプットすることができます。
しかし、覚えるのが苦手な人もいたでしょうし、長い文章は覚えられません。そこで考え出されたのがメロディーに乗せて言葉を伝えることです。長い文章も歌にすると自然に覚えるし、忘れかけてもリズムで思い出せますからね。
このように、普及活動に欠かせない聖書やゴスペルですが、ここで考えなければいけないのは、言葉を平易にすることです。一部の頭の良い人だけが理解できるような難しい言葉を使ってしまうと、そうじゃない人には理解ができません。よって、簡単で、口ずさみやすく、且つ、自分たちらしい言葉を選ぶことが重要になるのです。
一般的な『言葉』を企業文化に沿った『文法』に変換する
宗教の話ばかりしていると僕自身が宗教の人かと思われるので、話を企業に戻します。
文化の話をすると必ず質問をもらうのが文化の浸透方法についてです。浸透に必要なポイントをまとめると以下の通りです。
①企業文化をシンプル、且つ、具体的に明文化する
②明文化の過程で「自社らしい言葉」に変換する
③経営者、エース、新人などのキーマンが率先垂範する
④評価に紐づけて、企業文化を体現している人を評価し尊ぶ
⑤イレギュラーを出さずに徹底する
この章では、当たり前だけど忘れがちな②について解説します。
「オリジナルの言葉」を選ぶ
コミュニケーション、リーダーシップ、主体性など、これらの言葉は重要ですがグッと入ってこないのは一般化されているからでです。一般化されている言葉は軽くなりがちです。普段からどの場面でも使っていませんか?
「結局はコミュニケーションが大事ってことだね」
こんな感じで使われると言葉が軽んじられるのです。一般化されたワードは使いやすさもあってカジュアルに使われてしまいます。使いやすく頻度が高いのはいいですが、言葉が軽くなってしまうのは避けたいところです。
また、一般化された言葉は抽象度が高いので、その言葉から連想する行動の解釈も人によって違ってきます。よって、いちいち定義を確認する必要がでてきます。
「あなたの言う「コミュニケーション』はどこまでの行動を指していますか?」
大事ですけど、これを毎回するのは非常に手間ですよね。でも毎回ここからスタートしないといけないのが一般化された言葉の難点です。
一例ですが、前職ではこのように言葉をオリジナルに変えていました。
クレーム ☛ サービスリクエスト
顧客価値向上 ☛ ファンメイキング
異動制度 ☛ ネオキャリー
オリジナルだからこそ、最初に定義を伝え、キーマンが正しく使うことで、その言葉から想起するイメージが統一されます。また、オリジナルだからこそ、メンバー間で流行りやすくなります。
「サービスリクエストをもらいました」
「今の行動はまさにファンメイキングだね」
「次のネオキャリーで●●にいきたい」
人事として、新しい言葉をつくり発表した後は、サーベイ等で使いやすさ、使う頻度、使ってみてのしっくり感などを確認してみるといいと思います。
「具体的な情景が思い浮かぶ言葉」を選ぶ
人はデータをストーリーで記憶します。よって、言葉という点ではなく、その言葉から連想される具体的な情景や動きまでありありとイメージができると脳にしっかりと言葉が残ります。
前職の代表が使っていた言葉はまさにそういうものでした。
理想は高く、現実は泥臭く
給料を支払ってくれているのはお客様
悪いときは自分の責任、良いときは周りのおかげ
僕自身が新卒の時から今でも新卒研修や社員総会、または普段の月例会でも代表は必ず使っている言葉です。
新卒の時の日報を見返しても上記の言葉が多用されていて驚きます。そして、18年経った今でもよく使う言葉です。もはや刷り込まれていますね。これくらい刷り込まれる状態が「価値観まで浸透している状態」です。価値観まで浸透していると業務の中で都度起こる選択の場面で、迷いなく決定することができます。これをメンバー全員が行える組織は強いし速いですよね。
「会話で自然に使われやすい言葉」を選ぶ
オリジナリティにあふれる言葉や具体的な情景が思い浮かぶ言葉を選んでも、それが言いづらければ使われません。使われやすくするためのポイントは以下の通りです。
短くてシンプル
言いやすくて舌が回りやすい
韻を踏んでいたり、リズムで覚えやすい
関連ワードで並んでいるので、多少長くても思い出しやすい
あれもこれもと言いたいことは増え続けるのですが、聴く側は覚えていられません。前職では以下のようなものがありましたね。
明元素感:「明るく、元気に、素直に、感謝しよう!」の意
ぼんてつ番長:凡事徹底を周知する風紀委員の役割を持った人たち
ABC運動:「当たり前のことを、バカにせずに、ちゃんとやろう」の略
目標設定のSMARTとか、キャリア整理のためのSTARとか、英語の頭文字をとって覚えやすくする手はよくありますよね。また、あえて最初から略されて使うことを想定して作ることも大事です。「ぼんてつ番長」は「凡事徹底の番長」のことですが、メンバー間では「ぼんてつ」と呼ばれていました。この辺りのデザインも大事ですね。
まとめ
今回は企業文化浸透に重要な「共通言語」の力で文化をつくる方法について解説しました。
最近では社会要請的に「人的資本経営」「戦略人事」「心理的安全性」など漢字一色のものから、「1on1」「パーパス」「HRBP」みたいにアルファベットやカタカナ用語で溢れています。一般的なワードを使った方がわかりやすい場面も確かにありますが、自社の文化に浸透させる意味では、そのまま持ち込むとわかりづらいものが多いです。
今回紹介したものだけではなく、「ひらがな」を使ってみるのもいいでしょう。ひらがなは体温や感情を感じさせせてくれます。
ありがとう
おかげさま
たいせつ
テクニック的な話だけではなく、人事は翻訳家として自社のメンバーの力量に合わせて言葉を変えてみるといいでしょう。作ることよりもデリバリーや運用が大事です。是非、小さなところから実践してみてください。
より詳しい内容が知りたい、自社で戦略人事思考を持った人事責任者を採用したい、育てたいがうまくいかない、という経営者の方はご連絡をください。CHRO採用とCHRO開発を承っています。
☛takenoko1220
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
