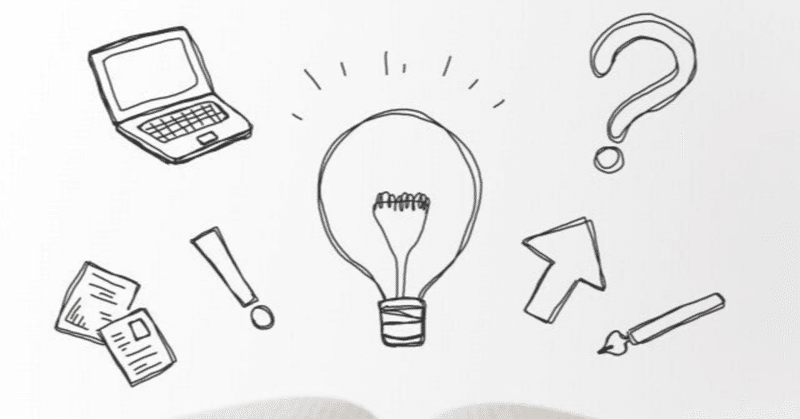
思考の整理力が、AI時代に生き延びる鍵
ChatGPTをはじめとするAI時代になると、自分の頭で独自に考えることが大事!と誰しもが思うことでしょう。
AI時代になる前から、「常に自分の頭で考えるクセを身に着けよう!」と学校でも会社でも叫ばれるようになっていましたしね。
ただね、いつも不思議に思うことは、どのように自分の頭で考えれば成長し、成果を出せるのかがいまいちよく分からないんですよね。
で、今日は僕なりの見解を思考を整理してみました。
★前提★
なんでもAIで代用できるんじゃね?という論点は、今回は横において書きますね。AIは日々進化しているので、正解めいたものは語れませんから。
1.教育に抜けているもの
僕は中学生の子供を持つ親であり、新入社員から幹部研修まで幅広く社員教育を行う企業研修の仕事もしています。
日々、様々な人と接してわかることは、子どもであっても大人であっても共通する点がたくさんあるということです。
どこでも、これからの時代は「自分の頭でしっかりと考える力を身に着けないとAIに置き換わってしまうよ」というメッセージが飛び交っています。
とはいえ、自分の頭で考えようにもなかなかアウトプットが出てこないことがよくあります。あるいはアウトプットの質が低いことがあります。
これは、大人も子どもも同じこと。
なんでかな?って考えた時にアウトプットできない人には、3つの原因がありました。
①インプットの量が少なすぎる
②インプットした情報を整理できない
③アウトプットの方法が下手
①に関しては、わかりやすく言うと、知識が乏しいのに、何か考えよう!といっても頭の中の引き出しが空っぽだとさすがにアウトプットが出てきません。
インプットが過剰になるのも考え物ですが、一定レベルでインプットは必要です。しかし、そこはネット検索やAIなどテクノロジーの力を使って補充が可能です。
いったん、②を飛ばして、③のアウトプットの方法がヘタ問題についてはどうでしょうか?
これに関しては、例えばプレゼンの方法や文書の書き方などノウハウも出回っていますし、学校から社会人まですでに教育産業として成り立つくらいに学ぶ機会があるため、あとは練習量を増やしていくだけでいいでしょう。
一方、②の整理に関してはどうでしょうか?
2.整理なくしてアウトプットなし
整理の大切さと整理をトレーニングする機会は教育の現場(学校から社会人)で、あまりないように見えます。
ただ、あくまでも私見ですが、自分の頭でしっかりと考え良質なアウトプットをするためには、「整理力」を持つ必要があると考えています。
なぜなら、インプットからアウトプットに至るまでの過程は3ステップで構成されるからです。

インプットはやみくもにせず、「どのような情報が必要なのか?」切り口を”整理”してからインプットすることで情報氾濫や頭の混乱を押さえ、効率よく質が高いインプットができます。
また、インプットした情報のうち「どの情報を選択し、どの情報を捨てるのか?」分類わけによる”整理”を行い、目的に応じた(相手のニーズに応じた)ストーリーを組み立てることで、的を外さない自分独自の考えが紡げます。
最後に、相手に分かりやすく伝えるために、簡潔かつ具体的に”整理”してアウトプットすることで、相手の心をとらえるコミュニケーションが可能となり、成果が最大化されます。
こうして考えてみると、全体的に「整理」の要素が希薄なことと、インプットした後の「整理」の工程が弱いために、選ばれた情報から”編集”して仮説へと仕立てていくことができないのではないか?
これが僕自身の仮説です。
インプットを増やし、アウトプット力を鍛えたところで、間に位置する「整理力」も鍛えないと、独自性があるアウトプットを行うのは難しい。
だからこそ、「情報を整理して自分の仮説にしたてていく思考のプロセス」を学校のテストにも、社会人教育にももっと組み込んだ方がいいと思う今日この頃です。
3.整理力の鍛え方
では、いったいどうすれば整理力は鍛えられるでしょうか?
一番王道的に思いつく方法は、以下のような思考問題に慣れるという感じでしょうか。
次の文章を読んでください。
**********************************************************************
その上で・・・
①
織り込まれている情報をいくつかの要素に分類わけしなさい。
②
分類わけした要素から、自分が伝えたいメッセージに必要な情報の選択と集中を行い、〇〇個以内に絞り込んでください。
③
最後に、絞り込まれた情報の中から、ストーリーの構成(要素の順番)を考え、〇〇文字以内で結論を導き出しなさい。
この3ステップの中に、インプットからアウトプットまでの要素が含まれています。
また、インプットからいきなりアウトプットにいくのではなく、「整理力」が求められる②のステップが入っています。
意図的に②の整理ステップを踏ませることで、インプットしたものをいきなりアウトプットする際におきる思考の混乱を押さえる効果が出ます。
このステップを何度も何度も繰り返すことで、思考の中に自分の頭で考えやすくなる習慣を身に着け、良質なアウトプットを出しやすくしていきます。
①インプット (Input)
②整理 (Seiri)
③アウトプット (Output)
これが、基本的なステップです。
②の整理はローマ字ですが、それぞれの頭文字をとって覚えやすいように僕は情報活用の「ISO」と呼んでいます。
お話している内容は当たり前すぎる内容かもわかりませんが、実際にはどれかがよく抜けているものです。
インプットはするけどアウトプットはしていない。アウトプットはしているけど事前に整理ができていないなど。
どれ一つ欠けても精度が高い仕事はできませんので、あらためて「ISO」の3点セットを意識してみてくださいね。
ちなみに、僕は書籍の執筆をするときも、企画書をつくるときも、結局、ISOの手順にのっとっています。また、整理力を重視することで、独自の見解もスピーディーにつくりやすくなりました。
というわけで、子どもの学校教育や企業の社員教育の現場を見ていて感じたことを雑記までに整理してみました。
教育に、3ステップ式”ISO”の導入を!
おしまい。
さて、今回の内容は
いかがだったでしょうか?
少しでもお役に立てば幸いです。
それでは、また会いましょう!
著者・思考の整理家® 鈴木 進介
P.S.
毎週水・日曜日に「メルマガ」でも思考整理のエッセンスを配信中です!
以下よりご登録ください↓↓↓

「LINE」でもショートコラムを毎朝7時に配信しています!
以下よりご登録ください↓↓↓

最新刊はこちらより↓
フォローしてくれたらモチベーション上がります! ◆YouTube http://www.youtube.com/user/suzukishinsueTV ◆メルマガ https://www.suzukishinsuke.com/sns/
