
伏線が縦横無尽に飛び回る結城真一郎の最新作『難問の多い料理店』より、第一話を特別先行公開!!
第一話をお読みいただく前に
2022年夏、『#真相をお話しします』の大ヒットで一躍話題となったミステリ作家、結城真一郎。現代的でキャッチ―な設定と、衝撃的な展開、リーダビリティを重視した文章で一躍話題を博した『#真相をお話しします』は、2023年の本屋大賞にもノミネートされました。
そんな結城さんの2年ぶりとなる超待望の新作『難問の多い料理店』が、来たる6月26日(水)に刊行となります。

舞台は、東京・六本木の、ある怪しげなレストラン。そこに集うのは、料理配達サービス「ビーバーイーツ」の配達員たち。彼らは、どうやら食事以外に謎の情報も運び、怪しげなレストランに持ち帰っているようです。レストランではいったい何が行われているのか、それは本文を読んでお確かめください。
今作は、結城さんにとってキャリア初となる連作短編集。収録された6つの物語に、自由自在に張り巡らされた伏線は、皆さんの予想もつかないところで回収されることでしょう。第一話で登場した人物が、後に意外な展開で再登場する…….なんてことも、あるかもしれません。
最終話を読み終えたとき、あなたはどのような感情を抱くのでしょうか。私は――、いや、このタイミングで申し上げるのは時期尚早でしょう。読了後に、皆さんと感想を語り合えることを楽しみにしております。
それでは、『難問の多い料理店』より、第一話を全文公開いたします。決してご遠慮はありません。どなたもどうかお読みください――。
『難問の多い料理店』より、第一話全文公開
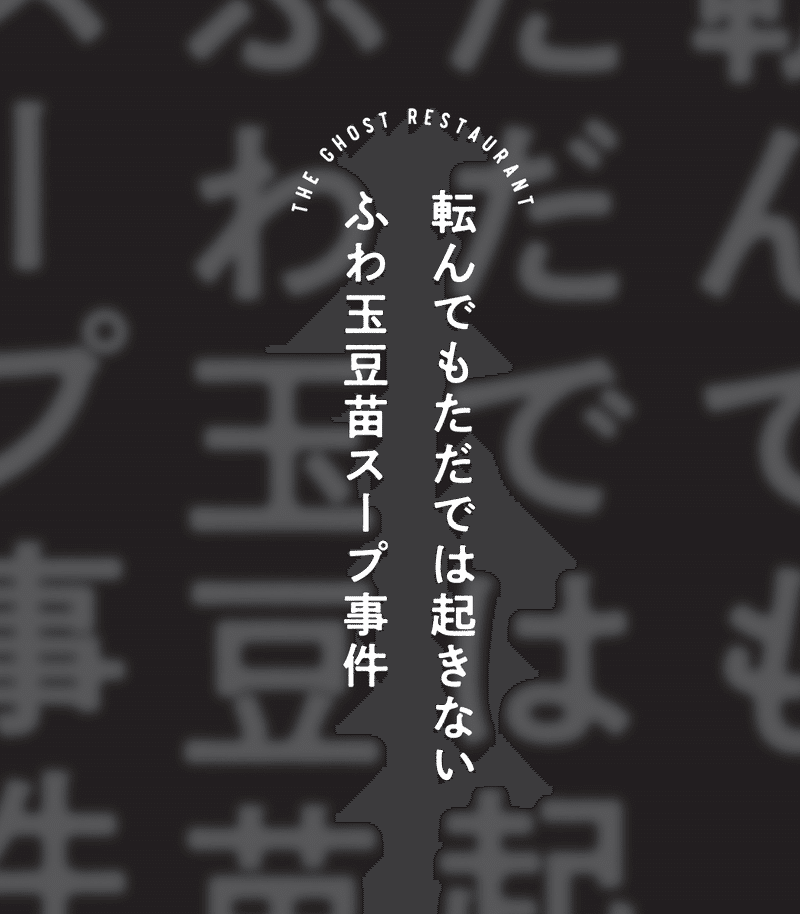
目深に被っていたキャップのつばを少し上げると、眼前のアパートを振り仰ぐ。
十二月某日、時刻は深夜零時すぎ。
二階の角部屋――二〇四号室から上がった火の手は、刻一刻と建物全体に広がろうとしていた。轟々と唸る火柱、夜空めがけて立ち昇る黒煙。時折バチバチ、ガラガラという崩落音が響き、少し離れたこの場所まで熱気が押し寄せてくる。
「ざまあみろ」
聞こえよがしに呟くと、すぐ近くで息を吞む気配がした。見ると、野次馬の一人がこちらを凝視している。寝間着にダウンジャケット、頭にはヘアカーラーをつけたまま。近所の主婦だろう。火の手に気付き、慌てて玄関から飛び出してきたのだ。
「ざまあみろ」
もう一度言い、女の視線を振り払うように歩みを進める。といっても、この場を立ち去るわけではない。燃え上がるアパートに向かって、だ。
「ちょっと、なにするつもり!?」
女の金切り声と、それをきっかけに巻き起こったどよめきを背中に聞きながら、外階段を昇っていく。踏み外さぬよう慎重に。されど見せつけるべく堂々と。カン、カン、カン、という乾いた音が小気味よい。
「危ないわよ! 戻ってらっしゃい!」
二階まで到着すると、そのまま右手に曲がり外廊下へ。これでもう観衆からは見えやしない。自分の姿も、これからすることも、何もかも。
目指すべき二○四号室は目と鼻の先だ。
再びバチバチ、ガラガラという崩落音。
熱い、目が痛い、喉が痛い、息が苦しい。
でも。
大量の煙を吸い込んだ胸は、それを遥かに上回る充足感でいっぱいだった。
1
「焼死体です」
僕がそう口にした瞬間、男の背中がピクリと反応を示した。ここまでは本当に聞いているのだろうかと不安になるほど微動だにしなかったのだが、ようやく興味のアンテナに引っ掛かってくれたようだ。
「焼け跡から、焼死体が出てきたんです」
ダメ押しのようにもう一度言いながら、そこはかとない可笑しさが込み上げてくる。まったく、なにやってんだか。もし仮に僕が探偵事務所の助手で、目の前の男がその事務所の主だとすれば、特に違和感もないのだけれど。
苦笑を嚙み殺しつつ、辺りを見回す。
向かって右手に男の後ろ姿、左手奥の壁際には縦型の巨大な業務用冷凍・冷蔵庫、正面には四口コンロ・巨大な鉄板・二槽シンク・コールドテーブルなどが並ぶ広大な調理スペース、天井には飲食店の厨房などによくあるご立派な排煙・排気ダクト。
そう、ここはレストランなのだ。それも、ちょっとばかし……いや、そうとう変わり種で、もしかするとかなりグレーな商法の。
そして僕はというと、ビーバーイーツの配達員としてこの〝店〟に頻繁に出入りする、ただのしがない大学生だ。
棚の上の金魚鉢を眺めるべく丸めていた背中を起こしながら、男は─白いコック帽に白いコック服、紺のチノパンという出で立ちのこの〝店〟のオーナーは、ゆっくりとこちらを振り返った。
「それはいささか妙だね」耳に心地よい澄み切った声で言い、そのまま歩み寄ってくると、僕の対面に腰を下ろす。
「話を続けて」
「はい」頷きつつ、視線は目の前の男に釘付けになる。
ダークブラウンの流麗なミディアムヘアーにきりっと聡明そうな眉、アンニュイな雰囲気を漂わせる切れ長の目。まっすぐ通った鼻筋しかり、シャープな顎のラインしかり、不自然なまでに完璧すぎるその造形からは、どこか人工的な匂いがしてくるほど。実はここだけの話、彼はよくできた蠟人形でして……と説明されたら「やはりか」と納得してしまうだろう。中でも異彩を放っているのはその瞳だった。無機質で無感情。すべてを見透かすようでありながら、こちらからは何の感情も窺い知ることができない。言うなれば、天然のマジックミラーだ。
そのマジックミラーが僕を見据えている。
話の続きを、と静かに促してくる。
「実は、その焼死体の身元が大問題なんです」
事の概要はこうだ。
いまから五日前、時刻は深夜零時すぎ。京王井の頭線・東松原駅から徒歩十分のところにある木造アパート『メゾン・ド・カーム』の二階の一室から火の手が上がった。
失火の原因はその部屋に住む大学生・梶原涼馬の煙草の不始末で、その日の晩、一人で晩酌を終えた彼はいつも通り寝支度を整え、床に就いたとのこと。しかし、その際ゴミ箱に放り込んだ最後の一服が完全に消えておらず、そこから炎上。ふと目を覚ましたときには、既に部屋中火の海だったという。
しばし奮闘してみたものの、自力での消火は不可能だと悟った彼はそのまま部屋を飛び出し、アパートの住民を起こして回ることにした。まずは自分と同じ二階、次いで一階と順番に。鍵のかかっていない部屋には問答無用で押し入り、締まっている部屋は住民が気付くまで外からドアを叩き続けた。その迅速な対応もあってか、幸いにもアパートの住民は全員が無事だったが、なんと焼け跡から――それも梶原涼馬の部屋から、焼死体が見つかったというのだ。
「諸見里優月という女子大生で、梶原涼馬の元交際相手とのことです」
そう告げると、予想通り、オーナーは「ふん」と鼻を鳴らした。
「確認。その日の晩、梶原涼馬は『一人で晩酌していた』と証言しているんだよね?」
「はい」
「だとしたら、その証言が虚偽――実際はその日、彼は元交際相手である諸見里優月と部屋にいた。以上では?」
たしかに、これを聞かされたときは僕もそう思った。なぁんだ、それだけの話か、といささか拍子抜けもしたくらいだ。なぜ彼女が焼死体となったのか――ただ単に逃げそびれたのか、それとも逃げられないような状況だったのか、その辺りの事情はよくわからないけれど、彼女が梶原涼馬の元交際相手だったのだとすれば、その場に居合わせたこと自体は不自然でもなんでもない。
「ところが、話はこれで終わらないんです」
「ほう」とオーナーの片眉が上がる。
「依頼人曰く、近隣住民の大勢が『アパートに入っていく女を見た』と証言しているそうで」
中でも特筆に値するのは、アパートの向かいに住む主婦の証言だろう。
その日の晩、火の手に気付いた彼女は寝間着のままダウンを着て玄関を飛び出し、家の前の道から様子を窺っていたという。住民は無事かしらという心からの気遣い半分、マイホームに飛び火したらどうしようというやや自分本位な懸念半分で。
「すると、どこからともなく女が現れ、アパートの敷地に入っていったんだとか」
危ないわよ! 戻ってらっしゃい! そう声をかけたが女は聞く耳を持たず、そのまま外階段を昇っていき、外廊下へ姿を消した。
「しかも、敷地に入っていく直前、その女はこう呟いたそうです」
ざまあみろ、と。
「なるほど」そのまま天井を仰ぎ、オーナーは瞼を閉じる。
十秒、二十秒と時が過ぎ、やがて彼は「ちなみに」と口を開いた。
「それは、いつのこと?」
「はい?」意味がわからず首を傾げる。
「時系列。女がアパートに入っていったのは、梶原涼馬が住民を救出する前なのか、それとも後なのか」
「えーっと」記憶を辿る。「前ですね」
その主婦の証言には続きがあった。
女がアパートに入ってから間もなく、二階の住民と思しき面々が順番に外階段を駆け下りてきた。そして、最後に現れたのがパンツ一丁の梶原涼馬だった、と。
そう補足すると、彼はもう一度「なるほど」と言い、やおら席を立った。
「え、もうわかったんですか?」
「あくまで推測だけど。問題は――」
それを如何に証明できるかだけ。
瞬間、ぴろりん、と調理スペースに置かれたタブレット端末が鳴る。
「あっ」と僕が目を向けたときには既に、彼は端末のほうへと向かっていた。
「注文ですか?」
「そのようだね」
「メニューは?」
「例のアレだよ」
〝例のアレ〟――すなわち、ナッツ盛り合わせ、雑煮、トムヤムクン、きな粉餅。通常では考えられない、地獄のような食べ合わせとしか言いようがないものの、だからこそ、これらのメニューをあえて注文する客には一つの共通点がある。
調理スペースに立つと、オーナーは淡々とコック帽を被り直した。
「さて、またどこかの誰かさんがお困りのようだ」
2
信号が赤に変わったのでブレーキを握り、シェアサイクルを停める。
キィーという甲高いタイヤの悲鳴は、走り始めた車の騒音に搔き消された。
それにしても、いくらなんでも寒すぎる。今年いちばんの冷え込みというのは、どうやら噓じゃないみたいだ。完全防寒のサイクルジャージを着ているとはいえ、この街特有の素っ気なさを纏った冬の冷気は、貧乏学生相手にも決して容赦してくれない。吐く息の白さと刺すような顔の痛み、感覚のない手足がそれを物語っている。
右足を路面についてバランスを取りつつ、サイクルヘルメットのあご紐を締め直す。ガサガサとジャージが擦れ、やたらと前歯の大きいコミカルなビーバーが描かれた空っぽの配達バッグが背中でゆらりと揺れた。
かじかむ手でスマホを取り出し、時刻を確認する。
夜の十一時五十分。〝店〟を出たのがつい五分ほど前のこと。新たな注文が入ったので僕の〝案件〟はいったん棚上げとなり、居座られても邪魔だとかなんとか言って追い出された形だ。いまごろ、どこぞの配達員が〝例のアレ〟を受け取るべく〝店〟に向かっていることだろう。うーん、羨ましい。けど、誰が受注できるかはアプリのアルゴリズム次第なので仕方がない。明日以降やるべき〝宿題〟も仰せつかっていることだし、今日はもう店じまい。さっさと帰って寝ることにしよう。
夜の六本木交差点は、いつもと変わらぬ騒がしさだった。
肩を組み大声を張り上げるスーツの野郎ども、足早に地下鉄の駅へと吸い込まれていく華やかな女たち、輪になって目配せを交わしつつこの後の展開を模索する男女の集団、こんな真冬なのに半袖半ズボンで巨大なリュックを背負った外国人観光客の御一行。頭上を走る首都高からは絶え間なく往来の音が轟き、右手には飛び石のようにオフィスの灯りが煌めく六本木ヒルズが聳え、眠らぬ街を静かに見下ろしている。
溢れんばかりの熱気と、渦巻く欲望と、ある種の無常観。
官能的で、享楽的で、刹那的。
東京、六本木。
その甘美な響きに漠然と惹かれていたのは事実だし、そこの空気を吸えば自分も何か特別な存在になれる気がしていたものの、いざこうして生活圏になってみると、なんてことはない普通の街だと思う。むろん、裏通りでタトゥー入りの大男が血まみれになりながら殴り合ったとか、クラブのVIPルームで鉄パイプが振り回されるような乱闘騒ぎが勃発したとか、そんな噂を耳にすることもあるけれど、こうしてビーバーイーツの配達員として走り回っている限り、それらはどこか並行世界で起こっている珍事にすぎなかった。
当たり前だ。
ありふれた自分の身に降りかかるのは、ありふれたことばかり。三日連続で道すがら黒猫を見かけたとか、改札を通るとき前の人のPASMOの残額がぴったり七百七十七円だったとか、配達の途中で東京タワーが消灯する瞬間をたまたま目にしたとか、僕が日常で出くわすイベントなんてせいぜいその程度。ドラマチックで、ファンタスティックで、手に汗握るような〝事件〟など起こるはずがないのだ。
信号が青になる。
ペダルに足を乗せると、緩慢に動き出す人波に合わせ、ゆっくりと漕ぎ出す。
そんな〝平凡な街〟の片隅に一風変わったレストランがあると知ったのは、いまから半年前――ビーバーイーツの配達員を始めて一年が経過した頃のこと。
配達員を始めた理由は気楽だから。ただそれだけだ。ぶらぶら適当に街を走り、オーダーが入ったら気分次第で受注する。特定の店舗に所属しているわけではないので上司や先輩の顔色を窺う必要もなく、好きなときに好きなだけ働けばいい。加えて、身体を動かすのは苦じゃないし、戦略的に取り組めば月に二桁万円以上稼ぐことも可能。となれば、親の反対を押し切って無理やり大学の近くで一人暮らしを始め、その代償として学費以外の援助はすべて絶たれ、明日を生きるために稼がねばならない身としては、やらない理由などなかった。
――お金を出すのは簡単だが、それじゃあお前のためにならない。
――したいのなら、自力でなんとかしろ。
ケチだなと思ったのは事実だ。たった一度きりの大学生活なのに、子どもをバイト漬けにするつもりか、と。でも、もしバイト漬けじゃなかったとしたら、これまで通り友達の家で酒浸りの副流煙まみれの麻雀漬けになるだけ。どうせ同じ漬物なら、前者のほうが歯ごたえもあって、健康にもよさそうに思えた。
そうして半年前のある晩、時を同じくしてビーバーが二十四時間対応となり、しかも深夜の配達は日中のそれより格段に報酬が高かったため、期待に胸躍らせながら夜の六本木を流していたら、折よくオーダーが入ったのだ。
『タイ料理専門店 ワットポー』――見たことも聞いたこともない店名だったけど、別に界隈の飲食店を網羅的に把握しているわけではない。もちろん二つ返事で受注し、アプリに指示された住所まで行ってみると、待ち受けていたのは何の変哲もない雑居ビル、そして奇妙な立て看板だった。
『配達員のみなさま 以下のお店は、すべてこちらの3Fまでお越しください』
そこに並んだ夥しい店名の数々――『元祖串カツ かつかわ』『カレー専門店 コリアンダー』『本格中華 珍満菜家』『餃子の飛車角』などなど。その数、優に三十を超えようか。
お目当ての『ワットポー』とやらもそこに記されていたので、不審に思いつつも指示通りエレベーターで三階へ。
扉が開き、リノリウムの廊下へ恐る恐る一歩を踏み出す。頭上の蛍光灯はチカチカと明滅を繰り返し、そのせいかやたらと薄暗い。
雰囲気的に、とても飲食店があるようには――ましてや三十店舗以上が軒を連ねているとはとうてい思えなかったけれど、エレベーターを降りてすぐの壁に『配達員の方はこちらへ↓』という張り紙を見つける。そしてその矢印が示す先には、すりガラス越しにぼんやりと灯りが漏れる一枚のドアが、たしかに存在していたのだ。
ドアノブを捻り、おっかなびっくり足を踏み入れる。
扉の先に広がっていたのは、ごく普通のレンタルキッチン――料理教室やパーティー、テイクアウト専門店などに活用される貸スタジオだった。
入ってすぐのところに申し訳程度の椅子とテーブルが置かれ、その向こうには広々とした調理スペース、左手の奥には業務用の冷凍・冷蔵庫、右手には金魚鉢が載った棚。そして、調理スペースに立ちトントントントンと何かを刻む男が一人。白いコック帽に白いコック服、紺のチノパン。他に従業員らしき人影はない。彼一人で回しているのだろう。
なるほどね、とすぐに理解した。
前に、ネットニュースか何かで読んだことがある。
ここは、いわゆる〝ゴーストレストラン〟――客席を持たず、デリバリーのみで料理を提供する飲食店なのだ。アプリ上には様々な店名があたかも別個の店であるかのように掲載されているが、実際はすべて同一の調理場で作られたもの。いままさに男が作っている料理も、数ある店名の中のどれか一軒のメニューなのだろう。そうやって出店コストや人件費を削減しつつ、各店名に「元祖」や「専門店」といった文言を冠することで、利用者の優良誤認を狙おうというわけだ。現に、僕が受けた注文にも『タイ料理専門店』と書かれていたではないか。
そんなことを考えていると、フライパンに具材を放り込んだ男がつと顔を向けてきた。
――きみ、新顔だね。
それはもう、息を吞むような美青年だった。どこが、とかではない。全部だ。顔の造形も、発する声も、その佇まいも、すべてが完璧で調和がとれているのだ。年齢はまるで見当がつかず、同世代――なんなら歳下と言われても納得がいくほどに純白の肌は透明かつ滑らかだが、そのいっぽうで、ひと回り以上歳上と言われても頷けるような、そんな落ち着きというか、そこはかとない静謐さもある。
それはさておき、〝新顔〟とはどういうことだろう。初めて来たという意味では間違っていないが、逐一配達員の顔を覚えているとでもいうのか。
――注文の品ならできてるから。
見ると、すぐ目の前のテーブルの上に白色無地のポリ袋が一つ、ちょこんと載っていた。これに違いない。というわけでいつも通り配達バッグに格納し、あざしたー、とその場を後にしようとした瞬間だった。
――あと、お願いがあるんだけど。
じゅわぁぁと湯気を上げるフライパンを放置し、男がつかつかと歩み寄ってくると、なんとも香ばしいニンニクの香りが漂ってくる。この時間に嗅ぐこの匂いは、ほとんど犯罪的と言っていい。
――これを、いまから言う住所までついでに届けて欲しいんだよね。
差し出されたのは、ごく普通のUSBメモリだった。当然ながら首を傾げていると、男は続けて信じられないことを口にしてみせる。
――報酬は、即金で一万円。
――あ、もちろん受領証をもらってここに戻ってきたら、だけど。
なんだそれは! そんな美味しい話があっていいのか!
ただでさえ噓みたいな見てくれの男が持ち掛けてきた、これまた噓みたいな儲け話。
――どうだい? やってくれるかな?
多分に胡散臭すぎたけれど、正直言ってかなり魅力的だった。
なんてったって、こちらは貧乏学生――明日を生き延びるために必死こいてギグワークに明け暮れる身なのだ。そこへ急に、飛んで火にいる福沢諭吉お一人様ときた。
――ちなみに、この話は絶対口外しないように。
――もし口外したら……
命はないと思って。
それだけ言うと踵を返し、男はネグレクトしていたフライパンの元へ帰っていく。
そんなバカな、と内心笑ってしまったが、顔には出さないし、出せなかった。こちらを見据える二つの瞳があまりに冷たく、ただの〝虚空〟と化していたから。
とはいえ、こんな美味しい話を誰かに教えるわけがない。
それは、僕の退屈な日常に紛れ込んできた初めての〝事件〟だった。
以来、僕はこの〝店〟にどっぷり浸かるようになった。
オープンと同時に周辺をチャリで流し、なるべくこの〝店〟絡みの案件を受注できるようにする。ビーバーに注文が入った際、それを提供する飲食店の近くにいる配達員へ優先的にオファーがなされるからだ。
〝店〟が開いているのは夜の十時から翌朝五時までの七時間。テイクアウト専門店としては前代未聞すぎる営業スタイルだが、とにかくその時間になったら周辺をうろうろし、オーダーが入り次第すかさず受注する。その足で〝店〟に駆け付け、商品を受け取る。すると、かなりの頻度で〝追加ミッション〟が課される。これをどこどこまで届けて欲しい。どこどこまで行って物を受け取ってきて欲しい。その〝お使い〟をこなすだけで即払い一万円。はっきり言ってうはうはだ。こんな景気のいいことをしていて商売が成り立つのかとむしろ不安になる。というか、そもそも僕は何を運ばされているんだ? もしや、ヤクや何かの運び屋として利用されているんじゃ――なんて一瞬疑ってみたこともあったが、この疑問も〝店〟の仕組みを知る中で解決した。
その仕組みというのが、次の通りだ。
基本的には通常のテイクアウト専門店と同様、注文が入ったらすぐにそれを作り、配達員が客先に届ける。ただ、それだけ。
変わっているのは、特定の商品群をオーダーすることが〝店〟に対する〝ある依頼〟の意思表示となること。「サバの味噌煮、ガパオライス、しらす丼」で〝人探し〟、「梅水晶、ワッフル、キーマカレー」で〝浮気調査〟というように、いくつかの〝隠しコマンド〟が用意されているのだ。中でも一番アツいのが「ナッツ盛り合わせ、雑煮、トムヤムクン、きな粉餅」という地獄の組み合わせだった。
これらの四品が意味するのは〝謎解き〟――要するに、探偵業務の依頼というわけだ。このオーダーが入ると、受注した配達員には「その場で相談内容を聴取してくる」という〝追加ミッション〟が課される。報酬は即払い三万円。〝お使い〟よりも難度は高く手間もかかるので、まあ妥当な額だろう。そうして根掘り葉掘り聞き終えたら、すぐさま〝店〟へとんぼ返りし、内容を報告する。と、あら不思議。オーナーが鮮やかに解決へと導いてしまうのだ。めでたし、めでたし。
とはいえ、その日の聴取事項だけで万事解決するのは稀なので、追加で〝宿題〟が出ることもある。その場合、同じ配達員がそれを引き受け、いわば専任としてその案件に携わり続けるのが通例だ。もちろんこの〝宿題〟だってきちんと報酬が出るし、その額は〝お使い〟の数倍以上。フレキシブルな働き方が売りのギグワーカーを長時間拘束することになるため、多少なりとも色を付けてくれているのだろう。
こうなってくると、わざと〝宿題〟を課されるために前段の相談内容聴取を杜撰にするやつも出てきそうだが、少なくとも僕はそんなことしようとは思わない。そんな危ない橋は渡れっこない。というのも、顔見知りになった常連配達員の一人からこんな噂を耳にしたからだ。
――ここだけの話、前にそれをやったやつがいてね。
――あるときから、ぱったり姿を消したんだ。
――消したというか、消されたのかも。
もちろん、転居などにより縄張りが変わっただけかもしれない。どこかの企業に就職して配達員を辞めた可能性もある。というか、普通に考えればそういった理由によるものだろう。が、もしそうじゃなかったら? あの日のオーナーの〝洞のような目〟を思い出すにつけ、あながちありえない話でもない気がしてならなかった。
それはさておき、過去に一度だけ「どうしてこんな回りくどいことを?」とオーナー本人に尋ねたことがあるのだが、
――外注できる部分は外注する。コストダウン。当たり前でしょ。
とのこと。
配達員に〝お使い〟やら〝宿題〟やら毎度ウン万円も払うことがコストダウンに繫がるのかはよくわからないが、そのぶん多くの案件をこなせればトータルではプラスという判断なのだろう。ビーバーイーツならぬ、ビーバーディテクティブ。ついに探偵業務の一端をもギグワーカーが担う時代が来たかと思うと、なかなか趣深いものがある。オーナー曰く「俺は〝探偵〟じゃなく、あくまでただの〝シェフ〟だ」とのことだけど、それを真に受けるほど僕もバカじゃない。
ちなみに、偶然にも例のメニューを頼んでしまった客がいたらどうするのか。これについては明確な回答が一つある。そんなやつはいない。以上。なぜって、四品とも見かけ上は異なる飲食店の商品だし、それぞれ単品で二万五千円――つまり、この四つを同時に注文すると料金は十万円になるため、これによって発動する〝隠しコマンド〟を知らなければ、酔狂な億万長者でもない限り、まかり間違ってもオーダーするはずがないのだ。
ついでに言えば、数ある配達サービスの中で「一回の注文で複数のレストランから注文することができる」のはビーバーだけなので、事実上、ビーバーでしかこの依頼はできないことになる。その意味でも限りなくニッチで、アンビリーバブルな隙間産業と言えるだろう。
いずれにせよ、これこそが〝店〟の真の姿であり、僕が何度も秘密裏に遂行してきた例の〝お使い〟は、依頼者に報告資料を届けたり、追加資料を貰いに行ったり、そうした真っ当な目的があってのものだったわけだ。
〝ゴーストレストラン兼探偵屋〟――多角経営、ここに極まれり。
3
再び赤信号に捕まり、シェアサイクルを停める。
それにしても、と僕は配達バッグを担ぎ直す。
今回の案件は、なかなかに骨があると言わざるを得なかった。
オーダーが入ったのは今夜十時すぎ、〝店〟の開店とほぼ同時だった。
いつも通り受注し、注文主の元へ。配達先は、六本木の外れに佇む高級マンション『クレセント六本木』一〇一一号室。六本木通りを溜池山王方面へひた走り、大通りから一本入ると突如現れる比較的閑静な住宅街の一角に、お目当ての物件は建っていた。
――お待ちしていました。梶原です。
玄関に現れたのは、物柔らかな紳士然とした男だった。
歳の頃は、およそ四十から五十といったところ。長身瘦軀で容姿端麗。いまは上下とも緩いスウェット姿だが、それすら「オフモードのIT系カリスマ社長」みたいで様になっている。こざっぱりした短髪に縁なし眼鏡、その奥の鋭い双眸と、これでスーツなんか着た日にはどう見てもインテリヤクザだが、言葉遣いや所作は丁寧かつ洗練されており、第一印象はすこぶる良かった。
あの、これ、と形ばかりに注文の品々が入ったポリ袋を差し出す。
それを一瞥した梶原さんは、「ああ」と苦笑いを浮かべた。
――基本、夜は炭水化物を取らないようにしているんですけど。
これを注文するのがルールなので仕方ありません――と続いたわけではないが、そういう意味だろう。それなら別に無理して食べなくてもとは思ったけれど、たしかに捨ててしまうのは忍びない。食品ロスへのささやかな配慮、小市民にもできるSDGsだ。
――どうぞ、大したおもてなしはできませんが。
そう促され、配達バッグを小脇に抱えたまま玄関扉をくぐる。事情を知らない人が見たら「え、最近のビーバーは家に上がり込んで配膳・食事の介助までしてくれるようになったのか?」となりかねない場面だが、幸いマンションの内廊下に人影はなかった。
通されたのは、ごく普通の1LDKだった。白い天井に、白い壁、白い床。整然と並んだダークブラウンの家具たち。統一感があり、シックで落ち着いた雰囲気だ。物の少なさからして、おそらく一人暮らしだろう。そのうえ、どこからともなく良い香りがする。ハーブというかスパイスというか、とにかくそんな感じの。なんにせよ、暮らし向きは悪くなさそうだ。
――風の噂で、なにやら面白い店があると耳にしまして。
ダイニングテーブルの椅子を引きながら、梶原さんはぎこちない笑みを寄越す。
たしかに、人伝に聞く以外でこの〝店〟の存在を知る方法はない。どこにも広告など出ていないのだから当然だ。しかし、存在を知ったからといって「じゃ、物は試しに」くらいのお茶目なノリで注文できるものでもない。四品で計十万円――いわゆる〝着手金〟だが、それを惜しまぬほどの問題を抱えているのは確実だろう。
事実、向かい合う形でダイニングテーブルに着くと、梶原さんはこう口を切った。
――相談というのは、息子の件なんです。
差し出される二枚の写真――構図はどちらも同じだった。眼鏡の少年を挟むようにして立つ小奇麗な男女。場所は校門の前で、背後では桜が咲き乱れ、三人のすぐ脇にはそれぞれ「入学式」と書かれた大きな立て看板が立っている。僕から見て右の写真が小学校、左が中学校のものだ。
写真の男はもちろんスーツ姿の梶原さんなわけだが……これはどう見てもインテリヤクザです、本当にありがとうございました。いっぽう、女性のほうはベージュのジャケットに同じくベージュのワイドパンツを合わせた、クールで知的な洋風美人。うん、お似合いだ。お似合いすぎて、ちょっと嫌味な感じもする。
写真の少年は、見るからに利発そうだった。顔の輪郭がへこむほどに度が強めの黒縁眼鏡しかり、その奥の意志の強そうな瞳しかり、ニヒルに歪んだ口元しかり、迷いなく伸びた背筋しかり。シャッターが切られる一瞬とはいえ、この年頃でこんな佇まいを見せられる男子はそう多くない気がする。さらさらの黒髪は耳が隠れるくらいに長いし、全体的に色白で、線も細く、ぱっと見だと女の子と勘違いしてしまいそうだ。
――手元にあるのは、この二枚だけなんです。
思いがけない言葉に、えっ、と写真から顔をあげる。
――実は、六年ほど前に離婚していまして。
そう言って、肩をすくめてみせる梶原さん。なるほど、だからいまはここで一人暮らしをしているわけか。たぶん、僕が「ご家族は今夜どこに?」と疑問に思うことを見越して先回りしてくれたのだろう。離婚事由については、あえて訊くまい。もし必要なら勝手に話してくれるはず……と思っていたら、早速その話題になる。
――恥ずかしながら、リストラにあいましてね。
そうして食い扶持を失った彼は自暴自棄になり、酒やギャンブルに溺れるようになってしまったらしい。愛想を尽かした妻は息子を連れて出て行き、まもなく送られてきた離婚届─それに判を押し、当時住んでいた横浜の賃貸マンションを引き払い、いまはここ六本木で一人住まいなのだという。
――すみません、余計な話でした。
いえいえと頭を下げながら、あらためて室内を見回してみる。やはり暮らし向きは悪くない。それに、腐ってもここは東京・六本木。やや辺境に位置しているとはいえ、家賃だってそれなりだろう。一度そこまで落ちぶれたのに、よく持ち直したものだ。
そうやって思いを巡らせる僕をよそに、梶原さんの話はいよいよ核心へと迫っていく。
――親権は妻にあり、めったに会うことはないんですが。
先日、ひょんなことから知ったのだという。
息子の――梶原涼馬の下宿先のアパートが全焼したと。
そこから語られた経緯は、僕がオーナーに報告した通り。
ひとしきり説明を終えた梶原さんは、なにやら声を潜めると、探るような上目遣いを寄越した。
――いちおう、現時点ではただの失火となっていますが。
おそらく警察は他のセンも─もしかしたら殺人の可能性すら疑っているかもしれない。なぜって、失火させた張本人の元交際相手が遺体となって焼け跡から出てきたのだ。むしろ、事件性を疑うのが当然だろう。例えば……そう、痴情のもつれとか。僕の貧弱な想像力では、それくらいが限界だけど。
とはいえ、例の〝アパートへ突入した女〟という謎もある。これがもし事実なら――というか、それだけ目撃者がいるのなら事実なのだろうが、そうだとしたら、奇妙奇天烈な自殺というセンも否定できまい。動機は見当もつかないけれど、でなければなぜ、自ら燃え盛る炎の中に飛び込むような真似をする必要があるというのだ。
――ですから、ぜひとも突き止めていただきたいんです。
これは不幸な事故なのか、はたまたなんらかの事件なのか。
――警察よりも先に。
そう言って再度上目遣いを寄越す梶原さんだったが、その瞳の奥に、一瞬だけ粘着質な光が宿ったのを僕は見逃さなかった。
――そうすれば、なんらかの対策を打てるかもしれないから。
なんらかの対策─仮に息子が犯罪行為に手を染めていたとしたら、なんらかの隠蔽工作を施すつもりなのだろうか。先の妖しげな光をそのように解釈してしまうのは、さすがに捻くれすぎだろうか。
――お願いします、愛する息子のために。
わからない。というか、それは僕が考えるべきことじゃない。
なんせ、僕はただの〝運び屋〟だ。こんな夜中に大盛りはよした方がいいのではと思っても、言われた通り、客の元へ牛丼を運ぶしかないのだ。そこに僕の価値判断が介在する余地はないし、させる必要もない。思考停止という名のどこか窮屈な自由。でも、それはそれで意外と居心地が良かったりする。
とにもかくにも、僕は明日、仰せつかった〝宿題〟へ取り組むことになる。
例の主婦とやらから、当時の話をあらためて聴取するのだ。日給五万円――ただの〝お使い〟が霞んで見えるくらいに実入りがいいので、気合が入らないわけがない。
溢れんばかりの熱気と、渦巻く欲望と、ある種の無常観。
官能的で、享楽的で、刹那的。
東京、六本木。
その片隅で、怪しげな〝裏稼業〟に勤しむ特別な自分。
信号が青になる。
めいっぱいペダルを漕ぎ、高揚感と優越感――そして、もしかすると一抹の背徳感に背中を押されながら、僕は暗闇の中を明日に向かって駆けていく。
4
「なんというか、迷いはない感じだったわ」
そう言うと、目崎さん――『メゾン・ド・カーム』の対面に住み、謎の女に関する証言をした例の主婦は、ずずず、と湯飲みの茶を啜った。濃いめの化粧とぐるんぐるんにカールした髪が年齢を感じさせない――いや、訂正しよう。それらがやや年齢不相応な、どこにでもいる話し好きの気のいいおばちゃんだ。
一夜明けた昼下がり、時刻は午後一時三十分を回ったところ。
オーナーの指示通り、僕はせっせと〝宿題〟に勤しんでいる。
「いくら呼びかけても、まったく聞く耳を持ってくれなかったし」
インターフォンに出た彼女は最初こそ不審そうだったが、僕が素性を――「先日の火事で亡くなった女性の友人なんです。実は、妙な噂を耳にしまして……ええ、そうです、その件です。でも、にわかには信じられなくて……だから、現場に居た方から直接お話を伺えないかなと思い」と説明すると、必死さが伝わったのか、快く家に上げてくれた。罰当たりすぎる噓だが、ぎりぎり方便の範囲か。
目崎さんが語る話に、これまでの情報との齟齬はいっさいなかった。
火事の晩、彼女は寝間着のまま玄関を飛び出した。そこへ不意に姿を見せた女は、しばし燃え上がるアパートを見上げていたが、やがて「ざまあみろ」と呟くとそのまま外階段を昇り火の海に姿を消した。うん、どれも既に知っている。
「でも、ありえないわよねぇ。燃えている現場に自分から飛び込むなんて。そんなのただの自殺行為じゃない」
住民を助けようって感じでもなかったし、とみかんの皮を剝きながら独り言ちる彼女をよそに、いまいちど事故現場についても思い返してみる。
目崎さんのお宅を訪ねる前に─というか、目崎さんのお宅の目の前なので当たり前だが、もちろん現場はこの目で確認している。
そこら一帯は、良く言えば〝昔ながらの下町情緒溢れる〟、悪く言えば〝ゴミゴミとした狭苦しい〟、ごくありふれた住宅街だった。死んでも空き地だけは作らんという決意表明のごとく密集した民家、軽自動車がやっとすれ違える程度の細い路地、無秩序に頭上で入り乱れる電線。周囲に飛び火しなかったのは不幸中の幸いだ。
火事のあった『メゾン・ド・カーム』は、思った以上にひどい有様だった。
木造の二階建てで、各階とも四部屋ずつという実にこぢんまりした佇まいながら、全体の七割ほどが焼け落ちていると、やはり見るに堪えないほど凄惨だ。辛うじていまだ建物としての体は為しているものの、二階――特に出火元となった角部屋の二○四号室を中心に、黒焦げとなった壁はただれたように崩れ落ち、屋根は抜け、そうして筒抜けとなった建屋内からはなんの残骸とも知れぬ廃材が無秩序に顔を覗かせている。
ここで、諸見里優月は命を落とした。それも、自ら火の海に飛び込む形で。
自分の意思だったとはいえ、さぞや苦しかったことだろう。
両手を合わせ二十秒ほどの黙禱を捧げるが、その間も疑問は付きまとっていた。どういう意味だったんだ? きみは、なにに対してそう思ったんだ?
ざまあみろ、ざまあみろ――
「聞き間違いということはないですか?」
堪らずそう尋ねてみると、目崎さんは「え?」と怪訝そうに眉を寄せた。
「『ざまあみろ』と聞こえたけど、本当は別の言葉だったとか」
うーん、と皮を剝く手が止まり、すぐに逆質問を寄越される。
「すぐには思いつかないけど、例えば?」
おっしゃるとおりだ。僕がラッパーなら咄嗟に韻を踏んだ別の言葉も出ただろうが、あいにくヒップホップは友達ではない。
「マスクのせいで声はくぐもっていたけど、聞き間違いではないはずよ」
「マスク……ですか」まあ、特に不自然ということもない。
とはいえ外見にまつわる話になったので、その点についても掘り下げてみる。
「ちなみにその日の晩、彼女はどのような服装だったんでしょうか?」
「服装? うーん、割とうろ覚えだけど……」
レディースっぽい緩めのワイドパンツにオーバーサイズのロングパーカー、白のスニーカー、そして目深にキャップを被っていたという。いちおう新情報ではあるが、特徴がなさすぎてなにかに繫がるものでもなさそうだ。
まずい。突破口がない。
そう焦りを感じ始めた瞬間、ふと、オーナーの妙な依頼を思い出した。
――その主婦に会ったら、こう確認して欲しいんだ。
――パンツ一丁で現れたのはこの男で間違いないか、と。
彼が差し出してきたのは、僕が梶原さんから貰った二枚の写真のうちの一枚――中学の入学式に撮影された家族写真だった。もちろん現物ではなく梶原さんが事前にコピーしていたものだが、それにしても不可解だ。なんせ、七年ちかく前の写真なのだから。
調べたところ、梶原涼馬はネットリテラシーが低いのか、それとも自己顕示欲が強いのか、フェイスブックやらインスタやらですぐに本人アカウントを特定できたし、そこには最近の写真がしこたま掲載されてもいた。相変わらずフェミニンな感じで、ファッションもユニセックスな感じで、無造作ヘアーもかなりイケてて、大学デビュー……かどうかは定かでないが、眼鏡からコンタクトに変わった目元はさらに涼やかで、全体的に流行りの韓流アイドルみたいで、要するに何が言いたいかというと、めちゃめちゃモテそうだから気に食わなかった。
そんな僕の勝手すぎる妬み嫉みはさておき、それらじゃダメなんですかと訊くと、オーナーは「うん」と頷いた。
――SNSのではなく、貰った写真で確認するんだ。
たしかに梶原涼馬は童顔だし、中学の入学式の写真でも問題なく同一人物だと認識はできるものの、だからといってなぜ?
とはいえ、指示通り「すみません、もう一点だけ」と例の入学式の写真を差し出す。
「パンツ一丁の男は、この彼で間違いないですか?」
「えーっと、どれどれ」すぐさま手に取り、眉間に皺を寄せながら眺めていた目崎さんだったが、やがて「ええ」と頷いた。
「眼鏡のせいで一瞬わからなかったけど、この彼で間違いないわ」
「なるほど、そうですか」
ダメだ。収穫なし。
ついに音を上げ、そろそろお暇しようと決めかけたときだった。
「あ、そういえば、いま思い出したんだけど――」
なにやら中空に視線を泳がせる目崎さん――やがて僕の視線に気付くと、いや、大した話じゃないんだけどね、と断ったうえで次のように語ってみせた。
曰く、二階からパンツ一丁で駆け下りてきた梶原涼馬は、そのまま一階の住民を起こして回ると、最後は道へ出てきて力尽きたように膝から崩れ落ちたという。大変なことになってしまった、大変なことをしてしまったと、うわ言のように口走りながら。
しかし、次の瞬間。
「道の先に目を向けると、『あかね』って呟いたの」
視線を追って見てみると、二十メートルほど離れたところに立っていたのは、彼と同じくらいの年恰好をした派手な女だった。彼女は燃え上がるアパートを見やりながら、ただただ呆然と立ち尽くしていたのだとか。
「写真を見たら、ふと思い出して」
注目に値する新情報だ。
脳内メモに「あかね」と書きつける。
顔見知りか、もしかすると、現交際相手かもしれない。
「すみません、急に押しかけてしまって」
頭を下げ、土産にみかんを二つ貰って、目崎さんの家を後にする。
最後の最後に、ようやく収穫らしきものを手にできた。むろん、二つのみかんのことではない。〝脳内メモ:あかね〟─次に頼るべきは、たぶんこれだろう。
5
「絶対〝復讐〟のためだよ」
あかねこと芹沢朱音は、西日に目を細めながらそう吐き捨てた。
「復讐?」思いがけない言葉に首を傾げると、彼女は「そう」と頷いた。
「あの子、涼馬のこと逆恨みして、ストーカーみたいになってたから」
「え?」とんだ新事実ではないか。
「だから、火事になったのを見て思いついたんだよ。ここに飛び込んで死んだら、涼馬は自分のことを一生忘れないって。どれだけ忘れたくとも、忘れようとしても、絶対に――」
さらに一夜明けた夕刻、時刻は午後四時をちょっとすぎたところ。
いま僕がいるのは、京王線・明大前駅からすぐの明央大学和泉キャンパス――その一角にあるテニスコートだ。
昨日、目崎さんから仕入れた情報をもとに、例によって梶原涼馬のインスタを巡回してみると、すぐにお目当ての人物は見つかった。
芹沢朱音。ご丁寧にもタグ付のうえ、三か月記念とか言ってツーショットが掲載されていたからだ。そのまま芹沢朱音のアカウントにも飛んでみたところ、二人は同じ大学の同じテニスサークル『タイブレイク』に所属する同級生だということがわかった。その『タイブレイク』とやらも公式HPがあり、曰く、月水金はキャンパス内のテニスコートで練習をしているとのことだったので、こうして突撃取材を敢行したわけだ。
コートに到着してすぐ、後輩らしき男子学生に「芹沢朱音さんと話がしたい」と伝えると、訝しみながらも彼女を呼び出してくれた。
――え、なに? まず誰?
やって来たのは、上下ジャージ姿のどこにでもいる派手な女子学生だった。肩口ほどの髪は鮮やかな金色に染め上げられているが、根元はやや黒くなっている。これから運動をしようという人間とは思えないほどに化粧はばっちり決まっており、流行りの太眉、アイライン強めの大きな目、ぷるんと艶やかなリップと、絵に描いたような量産型JDだ。
最初は警戒心丸出しの彼女だったが、梶原涼馬の家から焼死体が見つかった件について依頼を受けて調査をしている旨を告げたところ、やや興味を示してくれた。
――え、もしや探偵みたいな感じ?
――こんな、どこにでもいる大学生みたいな人が?
余計なお世話だ。
――てか、その依頼者ってまさか涼馬のお母さん?
――悪いけど、もしそうなら協力はできないから。
聞き捨てならない台詞だった。なにか折り合いでも悪いのだろうか。とはいえ、母親からの依頼ではないし、協力してもらえないのは純粋に困るので、正直に「お父さんからです」と答える。守秘義務違反という文言が脳裏をよぎったが、別にそういう類いの契約を交わした覚えはないし、正直知ったこっちゃない。
――ああ、お父さんね。なら、いいよ。
――離婚しても、やっぱり息子想いなんだね。
優しくて素敵なお父さんだわ、と一人勝手に頷く彼女だったが、その説明には多分に頷ける部分もあった。別の女に乗り換えた元彼への〝復讐〟――これなら、例の「ざまあみろ」発言も割と筋が通りそうだ。
人知れずほくそ笑む僕をよそに、彼女は立て板に水のごとく喋り続ける。
「たしかに私は涼馬に彼女がいるって知っててアプローチしてたし、まあ、そういう意味では略奪みたいなもんだけどさ、でも、自由恋愛なわけじゃん? さすがにストーカー化するのはお門違いだし、ヤバいでしょ」
自由とやりたい放題を履き違えた典型的なアホ学生とは思ったが、自分も人のこと言えたもんか怪しいので黙っておく。
「ストーカーというと、具体的にどんなふうに?」
そう水を向けると、よくぞ訊いてくれたと言わんばかりに彼女は捲し立て始めた。
「大学の正門で待ち伏せしてたり、一晩中アパートの呼び鈴を鳴らしたり、郵便受けに脅迫状まがいの手紙を放り込んだり。最初は涼馬だけだったんだけど、最近は私も同じような目に遭ってて、正直なにかされるんじゃないかってビビってたんだよね。前に一度、最寄り駅で待ち伏せされて、『お前を殺して私も死ぬ』って言われたし――」
「なるほど」思った以上に事態は切迫していたようだ。
余談だけどさ、と彼女の話は続く。
「お酒を飲むと、もう全然ダメなんだって。まったく手が付けられないっていうか。さっきの『お前を殺して私も』のときだって、明らかに酔ってる感じで。付き合ってた頃からそうだったらしいんだけど、情緒不安定になって、泣いたり喚いたりして、もう大変なんだって。まあ、お酒に強いわけじゃないからすぐに寝ちゃって、勝手におとなしくなるらしいんだけど」
彼女になんら他意はないのだろうが、ここで登場した〝お酒〟というキーワードは、実は割と重要だった。というのも昨夜、目崎さんから得た情報を伝えるべく〝店〟を訪れた際、オーナーからこんな話を聞かされたからだ。
――死亡した諸見里優月について、とある筋に調べてもらったんだ。
曰く、彼女の死因は一酸化炭素中毒によるもので、それ以外─火災による火傷・裂傷などを除き、不自然な外傷はなかったとのこと。
――倒れていたのはバストイレ兼用の浴室らしいが、ここで一つ重要な情報がある。
――火事の瞬間、おそらく彼女は下着しか身に着けていなかったようなんだ。
これに関しては皮膚に残留していた繊維などから、まず間違いないとのこと。だとしたら当然の疑問として「服はいずこ?」となるのだが、浴室前の廊下にそれらしき衣服の残骸が見つかっているらしい。
――さらに、どうやら彼女は酩酊状態だったとみられている。
血中アルコール濃度から推察するに、こちらもほぼ確実だという。飲みすぎて、吐き気を催しトイレに駆け込んだ――というのは、いちおう筋書きとして納得できる。が、はたしてその際に服を脱ぐだろうか? お気に入りだから汚したくなかったとか? でも、だからってさすがに脱がないよな。
どれも聞き捨てならない情報ではあるが、いったいぜんたい、その〝とある筋〟とは何者なんだ? こんな情報、警察しか持っていないはず――と疑問に思ったので素直にそう尋ねてみると、
――世の中にギグワーカーは自分だけだとでも?
とのこと。
なるほど、そういうことを専門にしている〝手足〟が他にもいるわけか。話の腰を折ってすみませんでした。
――さらに、もう一つ。
――その日の夕方、彼女のスマホに公衆電話から着信があったそうで。
しかも、それは『メゾン・ド・カーム』から徒歩五十メートルほどの距離にある公衆電話だと既に特定済みとのこと。着信があった時刻、その公衆電話を何者かが利用していたという目撃証言は出てきていないらしいが――
――梶原涼馬が、彼女を呼び出した可能性は高い。
同感だ。というか、事情を知る者なら誰もがそう思うだろう。
彼女が東松原駅へやって来たのが、その日の午後九時二十二分。駅周辺の複数の防犯カメラがその姿を捉えていたという。
――ちなみに、そのときの彼女の服装は目崎女史の情報と一致している。
緩めのワイドパンツにオーバーサイズのロングパーカー、白のスニーカー、目深に被ったキャップ、そしてマスク。
――チェックメイトまで、あと一手ってところか。
オーナーは金魚鉢から顔をあげ、こちらを振り返った。
――ってなわけで芹沢朱音の件、よろしく頼むよ。
「ちなみにその日、芹沢さんは彼氏さんのお宅を訪ねたんですよね?」
よろしく頼まれているので、いよいよ本題へと切り込むことにする。
あの晩、芹沢朱音が現場に現れたのは偶然か、はたまた必然か――一瞬逡巡するようなそぶりをみせたものの、黙秘や虚偽報告は不利に働くと思い直したのだろう、彼女は「そうだね」と首を縦に振った。
「謝ろうと思ったから」
「謝る?」
「その日、大学でちょっと喧嘩してさ」
続けて語られたのは、次のような内容だった。
曰く、学食で雑談していた二人はひょんなことから口論へと発展したという。
「きっかけは、私が『もっとちゃんとした格好で大学来てくんない?』って言ったこと」
「はあ」痴話げんかの火種は、いつだってこんなものだ。
「前までは割と気を遣ってくれてたんだけど、最近は結構手抜きでさ。髪なんてぼさぼさだし、コンタクトじゃなくて眼鏡だし、服装もジャージとかスウェットだし」
それをきっかけに始まった軽い言い争いは、徐々にヒートアップしていく。
「その勢いに任せていろいろ言っちゃったんだよね。布団の上では絶対にスナック菓子を食べないとか、ワックスとかコンタクトを付けたままでは絶対寝ないとか、そういうところは異常なほど神経質なくせして、大学来るときの見てくれには無頓着なのかよ――こんなのが彼氏だと思われるの正直恥ずかしいんですけど、とか、あの女と禍根を残すような別れ方したせいでこっちも迷惑してるんですけど、とか、さっさとあんなボロアパート引っ越したらどうなのとか、そういう余計なことまで。思ってたこと全部」
「まあ、ありがちなやつですね」
ありがちだが、それにしてもよく喋る子だ。たぶん、喧嘩の際はこの何倍もの一斉掃射になるのだろう。うん、自分なら無理だ。三分と耐えられない。
「アパートの件はさ、お母さんが厳しいんだって。甘やかすのはよくないとかで、仕送りの金額的にもあれくらいの部屋にしか住めないんだって。しかもそれだけじゃなくて、彼女は作るなとか、学生の本分は学業だとか、とにかく口うるさいの。それもあって、あの女のこと警察に言いたくないんだって。母親にバレるといろいろ面倒だから。バカみたいでしょ。いや、わかるよ? わかるんだけど、ちょっと厳しすぎるというか、いまはそんな時代じゃないっていうか。家にはその前に一回だけ行ったことあったんだけど、隣の生活音とかめっちゃ聞こえるんだよ? 普通にそんなのムリでしょ」
なにが普通にムリなのかは、僕も大人だ、人知れず察することにしよう。
ただ、彼女が梶原涼馬の母親を敵視する理由はわかった気がした。がみがみと口うるさく子どもに干渉する、いわゆる教育ママ――その煽りを少なからず彼女自身も食らっていて、その顔色を窺っている(ように見える)彼の姿勢にも不満があるのだ。
とはいえ、彼の母親の気持ちもわからないではない。離婚し、女手一つ――かどうかは知らないが、いずれにせよ手塩にかけて育ててきた愛息なのだ。そりゃまあ、厳しくもなるだろう。
それでいったら、我が家だって同じだ。一人暮らしをしたいと言ったとき猛反発されたのは、詰まるところそういう理由なのだ。お金を出すのは簡単だが、それじゃあお前のためにならない。したいのなら、自力でなんとかしろ。別に意地悪で言っているわけじゃないし、そのことを子どもはきちんと理解もしている。〝親の心子知らず〟と言うが、この歳になるとより正確には〝親の心わかっちゃいるが子素直になれず〟なのだ。
だからこそ、その点を部外者に突かれるのは梶原涼馬としても我慢ならなかったのだろう。お前に口出しされる筋合いはない、外野は黙ってろ。同じ状況になったら、僕だってこんなふうに声を荒らげてしまうはずだ。
「で、夜になっても全然ラインが返ってこなくてさ。未読無視、ずっと。だからちょっと不安になったんだよね。言い過ぎたかな、とか、まさか浮気してないよね、とか」
「なるほど、だからアパートに」
「迷ったんだけど、ぎりぎり終電もあったから」
その瞬間、コートのほうから「あかねー、次だよ次」と呼ぶ声がして、その場はお開きになった。
「まあ、なにかわかったら教えてよ。探偵さん」
ひらひらと手を振り、仲間の元へ駆けていく芹沢朱音。言っておくが、僕は〝探偵〟じゃなく〝運び屋〟だ――と、どこかで聞いたことのある台詞を胸の内で呟きつつ、彼女の背中を見送る。
多少なりとも、彼らにまつわる諸々の事情は透けて見えてきた。
日中に交際相手と喧嘩になり、ある種の浮気心が芽生えて元交際相手を呼び出したというのは、ありえない話でもない。そうして逢瀬を果たし、梶原涼馬の家を後にした諸見里優月は、何らかの理由――忘れ物をしたとか、名残惜しくなったとか、とにかく何かしらの理由で現場に舞い戻り、燃え上がる二〇四号室を目撃する。そして、妖しく円舞する炎を前にふと思いついてしまうのだ。
――ここに飛び込んで死んだら、涼馬は自分のことを一生忘れないって。
――どれだけ忘れたくとも、忘れようとしても、絶対に。
いちおう、筋は通る。いくつか不可解な点は残るものの、想定される筋書きとしてはもっとも合理的な気もする。いや、さらに言えば彼女自身が放火したというセンもありえるだろう。久方ぶりに意中の梶原涼馬から呼び出され、これ幸いと〝常軌を逸した心中計画〟を決意した、とか? 問題は、それを如何に証明できるかだが――
「――お疲れ。これで全部揃ったね」
その日の夜、このときの顚末を報告するや否や、オーナーは表情一つ変えずにそう言ってのけたのだ。
「え? マジですか?」
「うん、マジ」
呆然とする僕をよそに、オーナーは「てなわけで」とあくまで飄々としている。
「商品ラインナップにも追加しておかないと」
いよいよ〝最後のステップ〟――依頼主への報告だ。
実は、このときのために、初回の往訪時に〝合言葉〟を決めることになっている。特になんでもいいのだが、梶原さんは「合言葉って言われてもねえ」と苦慮していたので、僕から「座右の銘などは?」と促してみたところ、
――〝転んでもただでは起きない〟とかかな?
とのこと。
そうしていま、夥しい店名の中の一つ――『汁物 まこと』という店の商品ラインナップに、その〝合言葉〟を冠したメニューが追加されようとしている。たぶん「転んでもただでは起きないコンソメスープ」とか「転んでもただでは起きないけんちん汁」とか、そんな類いの何かが。そして、その料金がそのまま本件の〝成功報酬〟となるわけだ。どれだけ高額であろうとも、それを注文しないと依頼主は解答を知ることができないので、アコギな商売であることこのうえない。
汁物まこと、つまり、真相を知る者だ。
「値段は、五十万ってところかな」
耳を疑い、目を見開く。過去最高額ではないか。
「そんな値段で……はたして注文しますかね?」
堪らずそう尋ねると、オーナーは「ああ」と当たり前のように頷いた。
「大丈夫。いくらだって、彼は知りたがるはずだよ」
「え、それはいったいどういう……」
しばしの沈黙。
聞こえてくるのは、ぐあんぐあんと唸る換気扇の音だけ。
やがてコック帽を被り直すと、オーナーは飄々とこう言った。
「それじゃあ、試食会を始めようか」
6
信号が赤に変わったのでブレーキを握り、シェアサイクルを停める。
キィーという甲高いタイヤの悲鳴は、走り始めた車の騒音に搔き消された。
右足を路面についてバランスを取りつつ、サイクルヘルメットのあご紐を締め直す。ガサガサとジャージが擦れ、〝例のアレ〟を積んだ配達バッグが背中で小さく揺れた。
あの日、ラインナップに追加された『転んでもただでは起きないふわ玉豆苗スープ』はすぐにオーダーされ、そのままラインナップから静かに姿を消した。そんなふざけた商品が一瞬とはいえメニューに並んでいたことを知る者は、この世にほとんどいない。
結局、それを梶原さんの元へ届けたのは、僕ではない他の誰かさんだった。残念だけど、誰が受注できるかはアプリのアルゴリズム次第なので仕方がない。
報告資料に目を通した梶原さんは、なにを思ったのだろう。
その後、彼らの身にはなにが起きたのだろう。
寒さに身を震わせながら、いま一度、僕はあの日の顚末を思い返す。
「それじゃあ、試食会を始めようか」
僕の対面に腰を下ろしたオーナーは、続けてこう断言してみせた。
「結論から言うと、なにもかも梶原涼馬の自作自演だ」
目を瞠りつつ、心のどこかで「やはりな」と頷く自分もいた。うっすらと、その可能性は頭の片隅にあったのだ。とはいえ、いくらなんでも異常すぎてありえないか――とも思っていたし、それを裏付ける肝心かなめの証拠がない。
「彼のやったことは、おそらく以下の通り」
公衆電話から諸見里優月に電話をかけ、アパートに呼び出す。理由はなんでもいい。久しぶりに会いたいでも、話したいことがあるでも。いずれにせよ、彼女に断る理由などなかったはずだ。
「そうして部屋に上がり、しこたま酒を酌み交わす」
すると、どうなるか。
お酒に強いわけじゃない彼女はすぐに寝てしまい、勝手におとなしくなるはずだ。
「その彼女を浴室まで運び、服を脱がせる」
そしてそれを着ると、梶原涼馬は自らの部屋に火を放ってから外へ出たのだ。
ここで思い出すべきは、彼はフェミニンな感じで、普段から服装もユニセックスなものばかりということ。当然、女物の服でも問題なく着ることができたはず。ましてや、その日の彼女の服装は緩めのワイドパンツにオーバーサイズのロングパーカーなのだ。中肉中背の一般男性なら、彼に限らず誰でも着こなせただろう。
「やがて火が燃え広がったタイミングを見計らい、彼は現場へ舞い戻った」
それが、目崎さんを含む近隣住民が目撃した〝謎の女〟――その正体は、女装した梶原涼馬だったわけだ。
「『ざまあみろ』と呟いたのは〝復讐〟だと誤認させるため」
その際、声でバレる可能性は小さいと踏んだのだろう。そもそも火事で騒然としている現場なうえ、マスクで声がくぐもるから。いずれにせよ、この証言が出てくれば〝女〟の正体は梶原涼馬に悪意を持っている者――つまり、焼死体として見つかった諸見里優月に間違いないとなるはず。その策略に、全員が見事嵌まっていたわけだ。
「自室へと舞い戻った彼は即座に服を脱ぎ捨て、再び外へ出た。浴室に彼女を放置したまま」
これなら浴室前に脱ぎ捨てられていた衣服にも、彼がパンツ一丁で飛び出してきたことにも説明がつけられる。また、そもそも論として後者については誰も違和感を覚えるはずがなかった。冬場とはいえ、暖房などをつけていれば布団を被ってパンイチで寝ることはありえるし、なにより、自室が燃えているのだ――飛び起きた後、服なんて着ている暇はなかったはずだと、誰もが勝手に納得するだろう。
「そうして住民全員を避難させれば、今回の状況ができあがる」
すなわち、火災現場に自ら入っていった〝謎の女〟が焼死体となって発見されるというものだ。なるほど。すべての状況に説明がつくし、もはやそうであるとしか思えなかったが、問題は「如何にしてそれを証明できるか」ということ。
すると、オーナーは「その点に関してだが」と顎を引いた。
「そもそもおかしいと思ったのは、女が現場に入っていったタイミング」
証言によると、女がアパートに入ってから間もなく、二階の住民と思しき面々が順番に外階段を駆け下りてきた。そして、最後に現れたのがパンツ一丁の梶原涼馬だったとのこと。つまり、彼が外階段を降りてくる前だ。
「おかしくないか?」
そう問われても、首を傾げるしかない。
察しが悪いなとでも言いたげに鼻を鳴らすと、オーナーは続けてこう明言した。
「だとしたら、梶原涼馬と出くわすだろ?」
あっ、と声を上げてしまう。
その通りだ、完全に見落としていた――と思ったら、オーナーはさらにその先を行っていた。
「が、これに関してはギリギリ言い逃れが可能」
なぜなら、アパートの住民を起こして回る際、彼は鍵のかかっていない部屋には問答無用で押し入っているから。だとしたらその隙にその部屋の前を通過し、彼と出くわすことなく二○四号室まで辿り着いた可能性も、かなり苦しいがゼロとは言い切れない。また、さらに厳密には、彼が寝ている間に浴室へ忍び込むこともできた可能性はある。むろん、彼が玄関を施錠していなければ、という仮定の話ではあるが。
「とはいえ、この話を聞いた時点で、おや、とは思った」
しかし、とその瞳に鋭い光がよぎる。
「それ以上に、彼の証言にはおかしい点があるんだ」
しばし試すような沈黙が流れた後、オーナーは静かに結論を口にしてみせた。
「あの日の晩、梶原涼馬は寝ていない」
えっ、と意表を突かれ、そのまま言葉を失う。
どういうことだ? たしか、梶原さんの話では「その日の晩、一人で晩酌を終えた彼はいつも通り寝支度を整え、床に就いた」とのことだったが――
「だとしたら、彼は眼鏡をしていたはずだろ?」
「へ、眼鏡?」
「だって、起きてからしばらくは自力で消火すべく奮闘していたんだから。ぼやけた視界のまま、そんなことができるだろうか?」
瞬間、脳裏をよぎる「写真」の中の彼─顔の輪郭がへこむほどに度の強い、牛乳瓶の底のような黒縁眼鏡。命の懸かっている場面とはいえ――いや、むしろそういう場面だからこそ、身の安全のためにも眼鏡は必須なはず。
それと同時に、次々と脳裏に甦ってくる台詞があった。
――眼鏡のせいで一瞬わからなかったけど、この彼で間違いないわ。
そう言って頷いてみせた目崎さん。
――ワックスとかコンタクトを付けたままでは絶対寝ないとか、そういうところは異常なほど神経質なくせして、大学来るときの見てくれには無頓着なのかよ。
そう言って頰を膨らませていた芹沢朱音。
僕がすべてを察したと気付いたのだろう、オーナーは「その通り」と頷いた。
「いつも通り床に就いたなら、彼はコンタクトを外していたはず。しかし、道に出てきた彼は眼鏡をしていなかった」
眼鏡をしていたか、とダイレクトに尋ねられたら、ピンポイントすぎて思い出せないかもしれない。だから、あえて俯瞰的に――眼鏡をしている時代の写真を見せることで、目崎さんの〝そこはかとない違和感〟を喚起することにしたのだという。
「『何かがなかった』という証言を引き出すのは、思っている以上に大変なんだ」
だからこそ、SNSにあがっている最近の――裸眼の写真ではなく、七年ちかく前の家族写真を見せるよう指示を出したのだ。
なるほど、完璧だ。筋は通っている。
が、ここであえて反論を試みる。なぜって、彼が単に裸眼だったという可能性があるからだ。別に彼の肩を持ちたいわけじゃないし、眼鏡のせいで顔の輪郭がへこむほどに目の悪い人間がはたして裸眼のまま動き回れるだろうか、という疑問はあるものの、ここは指摘しておかねばならないだろう。
「いや、裸眼なはずがない」
しかし、これをあっさりと否定するオーナー。
「だって、彼は呼びかけたじゃないか」
なにに?
薄闇の中、二十メートルほど離れた位置にいる女に「あかね」と、だ。
「その視力で、判別できるはずがないんだよ」
たしかに、おっしゃるとおりだ。
「よって、普段通り床に就いたという彼の証言は、十中八九虚偽と考えて間違いない」
では、なぜそのような噓をつく必要があったのか?
ここまできたら、答えは火を見るより明らかだった。
ふうっとため息をつき、椅子の背に身体を預ける。
瞬間、なぜだか笑いが込み上げてきた。
何者なんだ、この男は。どうしてこんな男が、これほどまでにニッチで隙間産業的なことに従事しているというのだ。
それと同時に、依頼主である梶原さんの顔が脳裏に浮かんでくる。
――ですから、ぜひとも突き止めていただきたいんです。
――お願いします、愛する息子のために。
この事実を知ったとき、彼は何を思うのだろう。なんてバカなことをと涙するのか。それとも、愛する息子のために「なんらかの対策」を打つべく奔走するのか。
「あんな良い親父さんなのに……」堪らずそう呟いた瞬間だった。
「は?」小首を傾げると、オーナーはテーブルに身を乗り出してくる。
「なにか誤解しているようだな」
僕を見据えていたのは、例の〝洞のような目〟だった。
「依頼主の梶原という男についても、例のとある筋に調べてもらったんだ。はっきり言って、碌なもんじゃないぞ」
その後、彼の口から語られたのは、耳を疑うような新事実だった。
曰く、彼がリストラにあった理由は会社の金を着服していたことがバレたこと――しかし大事になるのを嫌った会社上層部はこれを刑事事件とせず、彼を懲戒解雇することで事を収めることにしたという。
「それ以来、やつは本性を現したそうだ」
酒やギャンブルに明け暮れ、夫婦が息子のために貯めてきた貯金に手を付け、それを窘めてきた妻には手を出すようになり─そうして、離婚届を突きつけられた。
しかし、別れた後も彼はたびたび元妻のところへと押し掛けた。俺が悪かった、よりを戻そうと迫り続け、ついに元妻は「これっきりにして」と札束を突き出してしまう。
「それが、運の尽きだったわけだ」
それに味をしめた彼は、その後も折に触れては金を無心した。あるときは「これで最後だから」としおらしく、あるときは「もし渡さなければ」と脅迫まがいに。平穏な暮らしを壊されたくない彼女は、こんなのいけないと頭ではわかっていながら、その都度金を渡してしまった。そうして彼は、元妻に寄生虫のごとくとりついたのだ。
「それに、どうやらそうとう黒いことにも手を出しているみたいだぞ。例えば、大麻の栽培・密売とか─その甲斐あって、ずいぶんといい部屋に住んでいなかったか?」
その瞬間、鼻腔の奥であの日の記憶が燻る。部屋に通されるなり、どこからともなく漂ってきた良い香り。ハーブというかスパイスというか、とにかくそんな感じの。あれはもしかして――
絶句するしかない僕だったが、オーナーはそこへさらなる追い打ちをかけてくる。
「おそらく、今回のこの件も強請のネタにするんだろう」
は? と全身が強張った。
「だから、さっき言ったんだ。いくらだって、彼は知りたがるはずだよって」
愕然として、目の前が真っ暗になる。
残念ながら、涼馬は人を殺した。ここに、確たる証拠もある。で、どうする? もし黙っていて欲しければ――そうやって、元妻に迫ろうというのか。
「〝転んでもただでは起きない〟ってわけだ」
そんなことにこれを利用するなんて、それでも実の親か?
「そもそも手元に二枚しか写真が残っていない時点で、円満な夫婦関係の解消じゃないことまでは容易に想像がつく」
そのうえ、と頰杖をつくオーナー。
「どうして、警察より先に真相を知る必要があるんだ」
「あっ」ぐらりと視界が揺れる。
「警察の出した結論に納得がいかないというのなら、依頼の趣旨としてまだわかる。でも、あの時点では表向きただの失火だとされていたんだろ? 問題ないじゃないか、それで。さらに言えば、仮に警察より先に真相へ辿り着いたとしても、火事から五日が経過したあの時点で打てる〝なんらかの対策〟なんてありゃしない」
よって、とオーナーは椅子の背に倒れ込んだ。
「別の目的があると睨んだわけだ」
もはや返す言葉もなかった。
「まあ、父親も父親なら、息子もたいがいだがな。〝転んでもただでは起きない〟どころか、目的のために〝わざと盛大に転んでみせる〟んだから」
言いながら、オーナーが目を向けたのは棚の上の金魚鉢だった。特に意味はないのだろうが、その瞬間、僕の脳裏には一つのイメージが浮かんでくる。
金魚鉢の水を替えようと運んでいた彼は、蹴躓いて盛大にすっ転び、その金魚鉢を壊してしまう。当然、金魚も死ぬ。それを見た人は「よそ見なんてしてるから」と𠮟責もするだろうが、たぶんそれ以上に「怪我はないか」と心配するだろう。でも、駆け付けた人々は気付かないのだ。彼の真の目的が金魚を殺すことだったとは。その真意を隠蔽するために〝わざと盛大に転んでみせた〟とは。
つまるところ、彼がやったのはそういうことなのだ。
真相が明るみに出なければ、おそらく彼が問われる罪は失火罪のみ。死者が出ているとはいえ、自分から火の海に飛び込む人間が出てくるなんてことはとうてい予見不可能なので、おそらく過失致死にはならないだろう。殺人を隠蔽するためなら、失火罪に問われるのもやむなし。木を隠すなら森の中どころか、その森ごと自分で植樹したのだ。
「それに、もしかしたら家を燃やすこと自体にも意味があったのかもな」
思い出したのは、芹沢朱音のしかめ面だった。
――勢いに任せていろいろ言っちゃったんだよね。
――さっさとあんなボロアパート引っ越したらどうなのとか。
――アパートの件はさ、お母さんが厳しいんだって。
――仕送りの金額的にもあれくらいの部屋にしか住めないんだって。
もしかして、一石二鳥だとすら思っていたのだろうか。ストーカー行為を繰り返す元交際相手を厄介払いしたうえ、いまの家が燃えてなくなれば新居に移ることができると、そう期待していたのだろうか。だとしたら、あまりにふざけている。それなら配達員でもなんでもして、必死こいて引っ越し費用をためるのが筋ではないか。自分がそうだっただけに、その考えの甘さには反吐が出る思いだった。
「とはいえ、これがすべて真実だと確定したわけではない」
状況を見るに、梶原涼馬の自作自演というセンが限りなく濃厚なだけで、諸見里優月が自分の意思で飛び込んだ可能性も完全には否定されてはいない。
「ただ、客の要望には応えた。これで決着だ」
決着……決着?
はたしてそうなのだろうか。むしろ、何一つとして決着などついていないのではないか。この〝謎〟を解いてしまったがゆえに――というか、単に一つの〝解答例〟を示しただけだが、そうしてしまったがゆえに、さらなる悲劇の連鎖が生まれかねないのだとしたら、はたしてそれは決着と言えるのだろうか。
「おい、勘違いするなよ」
黙りを決め込む僕に、オーナーはぴしゃりと釘を刺す。
やはり、この男は鋭い。人の仕草─それも〝動〟だけでなく〝静〟の仕草からも、相手の胸中に渦巻く様々な思いを読み解いてしまうのだから。
「うちは、ただのレストランなんだ。であれば、すべきことは一つ」
客の空きっ腹を満たしてやる。
「ただ、それだけだ」
なに無責任なこと言っているんだ、と憤慨しかけたが、なるほどそういうことか、と少しして納得がいった。
――俺は〝探偵〟じゃなく、あくまでただの〝シェフ〟だ。
あれは、そういう意味だったのか。
なんらかの欲に飢えた人々の、その空きっ腹を満たしてやる。目撃証言や現場の状況など、客観的事実という名の〝素材の味〟を活かしつつ、客の〝好み〟に合わせて調理・味付けをする。それこそが、この〝店〟の――一風変わった〝ゴーストレストラン〟の存在意義であり、価値なのだ。調理の過程でどれほどの添加物や化学調味料、劇薬、毒物の類いが食事に混入しようと、それが客の望みであるのなら――それで腹が膨れるのなら、その後いくら身体に支障をきたそうが、それでいいのだ。
いや、それでいいのか?
わからない。というか、たぶんそれは僕が考えるべきことじゃない。
オーナーがただの〝シェフ〟であるのと同様に、僕はただの〝運び屋〟だ。その食事がいかに健康を害する可能性のあるものだったとしても、言われた通り、仰せのままに、客の元へ運ぶしかないのだ。それがギグワーカーのあるべき姿であり、矜持なのだ。
信号が青になる。
背中の配達バッグには、今日もまた誰かが頼んだ〝例のアレ〟が入っている。これを欲する誰かさんは、いったいなにに飢えているのだろう。どんな〝味〟を望んでいるのだろう。その腹は満たされるべきなのか、それとも飢え死にさせるべきなのか。
わからないし、わかる必要もない。
だって、僕はただの〝運び屋〟なのだから。
そう言い聞かせながら、溢れんばかりの熱気と、渦巻く欲望と、ある種の無常観にまみれた街の片隅で、今宵もまたペダルを漕ぎ続ける。高揚感と優越感─そして、以前よりも少しばかり増した背徳感と一抹の疑念を胸に、ただひたすら黙々と。
(了)
終わりに
「転んでもただでは起きないふわ玉豆苗スープ事件」、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。謎に包まれたオーナーの元には、この事件以外にも様々な謎が持ち込まれます。謎を解くための情報を運ぶのは、シングルマザー、アマチュアお笑い芸人、冷え切った家庭で過ごす男性など様々。彼らによってもたらされた情報のみで、客の腹を確実に満たすオーナーは、いったい何者なのか……。
今作を含む6つの事件が収録された『難問の多い料理店』は6月26日(水)の発売です。既に予約販売が始まっておりますので、確実にご購入されたいという方は、書店店頭や各ECサイトでご予約をお勧めいたします。各ECサイトへのリンクは、以下のページからご覧になれます。
また、雑誌「小説すばる」7月号には、『難問の多い料理店』には未掲載のシリーズ最新短編「今度こそ許すまじ春野菜といんげん豆の冷製スープ事件」が掲載されます。どうやら、この事件は『難問の多い料理店』で持ち込まれる6つの謎とは、少々毛色が違うようで......。
気になる方は、ぜひ「小説すばる」も併せてご購入ください。
『難問の多い料理店』は、6編通して皆様に極上の謎を配達します。どうぞ、首を長くしてお待ちください。

◉書誌情報
『難問の多い料理店』
著者:結城真一郎
2024年6月26日発売/1,870円(税込)
352ページ/四六判仮フランス装
装画:ハチナナ 装丁:川谷康久
ISBN:978-4-08-771870-6
◉収録作
転んでもただでは起きないふわ玉豆苗スープ事件(『本格王2023』選出作)
おしどり夫婦のガリバタチキンスープ事件
ままならぬ世のオニオントマトスープ事件
異常値レベルの具だくさんユッケジャンスープ事件
悪霊退散手羽元サムゲタンスープ事件(『本格王2024』選出作)
知らぬが仏のワンタンコチュジャンスープ事件
◉著者略歴
結城真一郎(ゆうき・しんいちろう)
1991年、神奈川県生まれ。東京大学法学部卒業。2018年『名もなき星の哀歌』で第5回新潮ミステリー大賞を受賞してデビュー。2021年「#拡散希望」で日本推理作家協会賞(短編部門)を受賞。「#拡散希望」を収録した『#真相をお話しします』で、2023年本屋大賞ノミネート。その他の著書に『プロジェクト・インソムニア』『救国ゲーム』がある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
