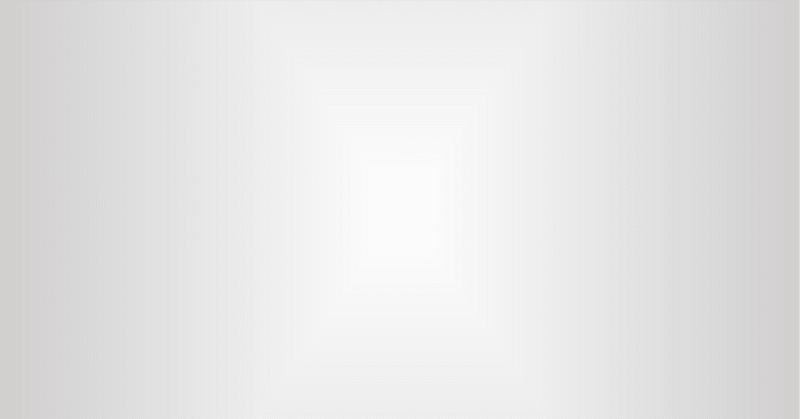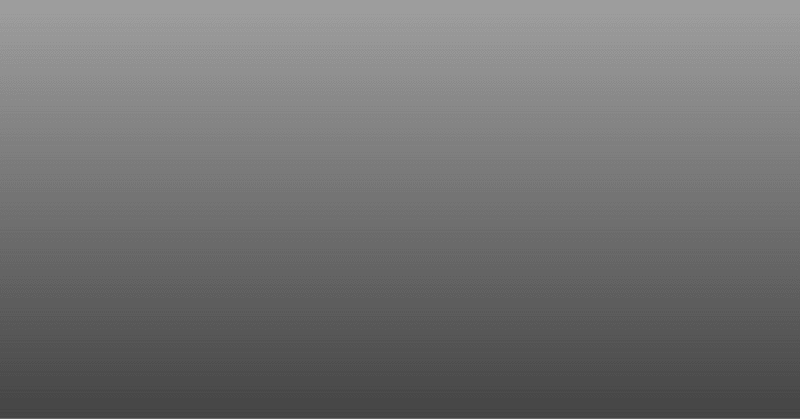#芸術
音の奥にある「言葉」を語る──アンドレアス・シュタイアー『Schubert:Piano Sonatas No.19 & 20』【名盤への招待状】第16回
標題や詩といった言葉をもたない音楽にたいしても、その音の奥になにかそれに近いもの、言葉にならなかった言葉のようなものを見出し聴き取ろうと耳を傾け、それを実体化しようとするのもひとつの演奏の在り方である。とりわけシューベルトのような、まず詩があってそこから音楽が生まれる歌曲という分野を創作の中心に据えていた作曲家の器楽作品には、そのようなアプローチで迫ることでしか立ち現れない世界があるように思える
もっとみるあたたかく、優しい光──レオン・フライシャー、シュトゥットガルト室内管弦楽団 ほか『モーツァルト:ピアノ協奏曲 第7番、第12番、第23番』【名盤への招待状】第15回
ピアニストで指揮者のレオン・フライシャーの最後の来日公演を聴いたのは、大学三年の晩秋のことだった。二〇一五年一一月二〇日、すみだトリフォニーホール大ホールでの新日本フィルとの共演である。そのときは、すでに高齢であったとはいえ、これが彼の生演奏を聴く最初で最後になってしまうとは、思っていなかったのだけれど……。
苦しんでいた時期だったことも、その、苦悩や傷も含めて生のすべてが人間的な優しさやいた
「こちら」と「あちら」の狭間から響く声──ジェシー・ノーマン、クルト・マズア指揮ゲヴァントハウス管弦楽団『R.シュトラウス:4つの最後の歌』【名盤への招待状】第14回
気晴らしや耳のさみしさを埋めるためばかりではでなく、なにかもっと根源的な渇きを潤すためにも音楽を聴いているのだとしたら、その渇きとはつまり厭世観のことであると言っていい。音楽を痛切に求める心性の根本には、つねにこの世界にたいする嫌気や失望があるはずだろう。こうした暗く重たい想念からは、現実とはべつの時間の流れのなかに身を置くことでしか解放されない。
だから、ある意味、あらゆる音楽の背景にはそう
鮮烈な感性が示す伝統の大きさ──エカテリーナ・デルジャヴィナ『J.S.バッハ:フランス組曲』【名盤への招待状】第13回
芸術表現に触れるということは、他者の話に耳を傾けること──それも、実際の話し言葉では伝え得ない複雑にして痛切な話に耳を傾けることである。だから、話を聴いたあとでその内容や語り口にさまざまな感想を抱くことは自由だが、話を聴く前から話者に対して「自分はこういう話が聴きたい」と求めるのは、本来的に慎まなければならない態度である。
そのことを踏まえた上で、個々の内容というより芸術体験そのものに望まれる
モデラートの呼吸──アントワン・タメスティ&マルクス・ハドゥラ ほか『Schubert: Arpeggione & Lieder』【名盤への招待状】第12回
楽譜の冒頭にModerato(モデラート)と記されているとき、演奏者はそれを、「中庸の速さで演奏するように」という指示として受け取る。あるいは、Allegro moderato(アレグロ・モデラート)などのように、それがほかの速度表記と併せて書かれている場合には、前に置かれた言葉の指示する速さの程度が控え目であることを意味していると捉える。
この文章に目を通してくださっている方々は音楽に詳しい
濁りのない、清冽な音──アルテュール・グリュミオー『J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ(全曲)』【名盤への招待状】第9回
濁りのない、清冽な音を浴びたいとき、アルテュール・グリュミオーの『J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ(全曲)』をかける。ソナタ第1番ト短調の冒頭の和音が響いた瞬間から、耳の奥にこびりついたさまざまなものが洗い流されてゆく。淀んだ空気さえも凛とさせてしまう澄みきった音は、宿命的な響きをもつト短調の悲しみをたった独りで引き受けるような高潔さに満ちている。繊細だが内向的ではなく、
もっとみる右にも左にも傾かない──エディット・ピヒト=アクセンフェルト『バッハ:トッカータ集』【名盤への招待状】第7回
白か黒か、右か左かが極端に明確で、自身の主義主張に反する価値観を激しく罵倒する言葉が氾濫している。両者の対立はますます深まり、さらにこのところは、右と左、両者の中でも対立が生まれ、日々深刻化しているように見える。
強い表現は時には必要だ。しかし、何かが起こる度にころりと変わってしまう潮流や、ナイーブに右往左往する人々、自らの「正義」のためには倫理的に堕落することさえ躊躇わない人々を眺めていると
閉ざされた世界の歪さと孤絶──アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ『ショパン・リサイタル』 【名盤への招待状】第2回
芸術家の定義は様々だが、何か過剰なものを抱えてしまった人間のことであると言うこともできよう。彼ら彼女らは、人間なり時代なりの抱える問題を、その鋭敏な感性ゆえに肥大化させた状態で抱えてしまっている人物であり、その重みから自らを解放させるためにも、芸術作品というかたちにそれを昇華させている。
だから、そのようにして生まれた芸術自体もまた、当然にどこか過剰さを秘めているはずである。そしてそれゆえにこ