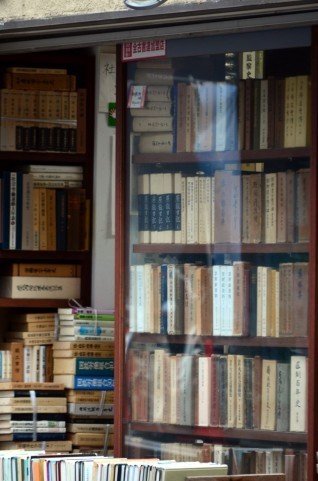
聖書や日本書紀、平家物語などを読みながら、「日本」について外国人に説明するにはどうしたらいいかとか、農村部の論理と都会人の論理がどう違うかと言ったことについてのヒントを考えていま…
- 運営しているクリエイター
#ナス
「紙」マルチによるニンジン栽培のテスト。地代は原価+手間賃で決まる価格とは別の原理で成り立っている件など
アダム・スミスは国富論の中で、賃銀と利潤は価格の原因だが地代は結果だとしています。
「地代」について、制度や政策と言うことを離れて考えてみると、確かに「労働」によって実現される価値とは違う性格を持っていることは確かです。
価格や価値と「労働」の関係ですが、アダム・スミスは「労働価値説」、つまり、労働があらゆる価値の源泉だとしています。
たとえば、僕が大根を育てて、1本100円である飲食店に卸









