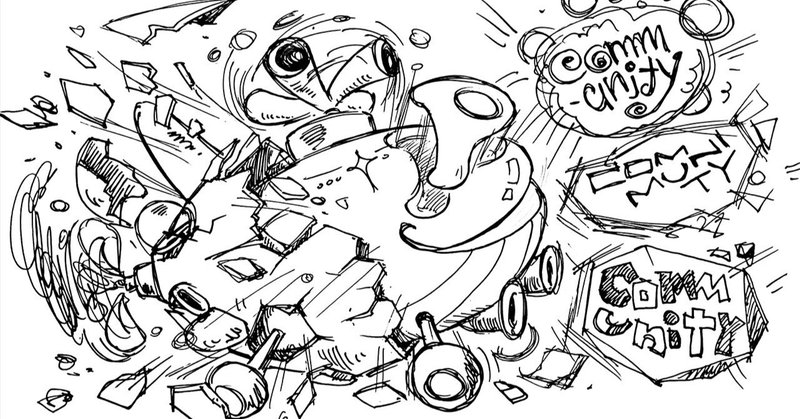
コミュニティとの共創は自己変化の原動力『ピートラ』Vol.72
イノベ乗組員のましもんです。
ピープルで、商品企画を約20年やってきました。
今は、2つの新事業チームのリーダーとして、ピープルのパーパス「子どもの好奇心がはじける瞬間をつくりたい」の実現のために考え、実行し、模索し続けています。
最近ずっと、子どもとの共創「子どもPeople」について書いてきましたが、
私の共創デビューは、SNSユーザーコミュニティとの共創が始まり。
2016年11月から、7年以上になります。
関わったメンバーは500人は超え、今現在も、育休コミュニティ100名以上と新規事業をとずっと進行し続けています。
また、それ以外にも発達障害コミニュティとの共創、社会人コミュニティとの共創も実施したことがあり、ピープルで一番コミュニティ経験値は高いです。(ゼロからの立ち上げもあれば、既存コミュニティとの共創も含む)
なぜ、私がコミュニティとの共創を続けるのか?
ピープルでは、自分自身の好奇心が向かう仕事を選び、優先して時間を使うことを推奨されています。
コミュニティの共創も、最初のきっかけですら会社に命令されたわけでもなく、自分自身の好奇心ではじめ、ワクワク心が動くから続けています。今や、「コミュニティとの共創」は私の仕事の好奇心の源といけるかもしれません。
自分が長年、企画者としてコミュニテイとの共創に魅了され続けている理由をエピソードと共に綴ってみます。
自社の「当たり前」を壊す
私自身、他の会社で働いた経験がありません。だから、「ピープル」の当たり前を疑う機会は、社外の人と触れ合う時。
コミュニティと共創する場合、今まで慣れでやってきたことも言語化することができたり、当たり前と思っていたことも強みや弱みとして認識できたり。
自社を伝え、客観的な視点で捉え直すことができる。しかも、コミュニティだとその視点は多様!
且つ、一緒に何かを生み出す!というハードな目的があることで、「当たり前」への疑問が露出しやすくなったり、思いもよらなかった自社の強みも見つかります!

ピープルにとっては、普段合言葉になっていたり、社風として根付いていることも、入れ替わりの激しいコミュニティメンバーと共創する上では、言語化して伝える必要がありました。様々な失敗からピープルの社風をもとにつくった行動指針(ピープルにとってはごく当たり前の価値観)。今では、このバリューを体験できただけで価値!と言ってもらえるものに!
https://note.com/people_pr/n/nd1cb390e254b
自分の「当たり前」を壊す
ピープルは、約50人の会社で、社員の入れ替わりも少ないです。そのため、長年付き合っているともはや家族のような環境ができて、なんとなく各人に求められる個性や役割が固定化しがち。
でも、人が入れ替わるコミュニティだと、集まった人によって場の雰囲気が変わり、その中での自分の役割を探すと、今までにない新しい自分を発見できることも多々。コミュニティメンバーの好奇心に引っ張られて、自分にとっては新しい世界の扉を叩けたり!自分だけでなく、コミュニティとの共創の中で社員の新しい個性が発見できることも!
また、人によって捉え方や考えは違うという前提で、過去の結果にとらわれず、目の前の客観的事実から状況を捉えたり判断すること、自分の価値観を疑ってみる、常に更新することを、意識的に心がけるようにもなりました。

具体的な課題を提示するよりも、目的だけ伝えて自由度が高い方がモチベーションがあがるのでは?とコミュニティOGに言われ、そんな丸投げで大丈夫かな、、と半信半疑で実行したところ、満足度がアップしました。もちろん、具体的な課題の方が良い場合もあるのですが、毎回そうではない!コミュニティや人は生き物なので状況によって変化する!毎回違うことを楽しみながら、ベストな関係性を築いていきたいです。
アイデアの「仮説」を壊す
最後は、イノベーションに一番大事なこと。
アイデアの仮説を常に疑い、トライ&エラーし続けることが、コミュニティとの共創でスピードアップ&強化されます!
ピープルは、子どもの観察が商品開発の軸で、子どもの反応によって常にアイデアをやり直すことがロングセラー商品を作れる秘訣。
ただ、それを大人(出費してくれる人)にどう伝えるか?
子ども観察の結果を、大人に共感してもらう伝え方を模索する必要があります。
そのために、その時代に子育てする親を知る、子育て環境を常に観察し続けることも重要です。その上で、コミュニティとの共創によって出てくるアイデア以上に、率直な疑問、反対意見はとても貴重。
子ども達の好奇心も環境には影響されるものなので、社外の子育て世代の人と共創できることで、新しい子ども観察の視点やアイデアも生まれてくるはずです。
つい最近の私の驚きを紹介。
5年前までは、認知が低かった「非認知能力」という言葉、コミュニティ内でよく聞くようになって、調査したら、なんと!子育て世帯で9割以上の認知率!
コミュニティ内でのつながりで、非認知能力コーチとお話しする機会が持てたり、非認知能力視点での子ども観察アイデア会を持つこともできて、私の子ども観察視点が広がりました。
強制的に変化し続けられるワクワク
私にとって、
コミュニティと共創することの最大のメリットは、「変化」に敏感でいられ、「変化」を強制的に自分に取り入れられること。
この経験は、仕事に限らず、私生活にも影響し豊かな視点を得られるきっかけ、新たな自分に変化できるきっかけにもなっていて、もはやライフワークです!
いろんな共創活動を続けてきたことによって、
今、コミュニティ同士の交流が生まれたり、コミュニティをきっかけにプロボノや副業でピープルに参加してくれる人が出てきたり、、
そして、いよいよ2025年にはコミュニティとの共創の新規事業リリースも目指しており、より広い共創の輪が広がっています!
これからも、強みを再発見しつつ、新たな自分に変化することを楽しみながら、コミュニティとの共創をしていきます!
関わっていただいている皆さん、これから関わってくださる皆さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
