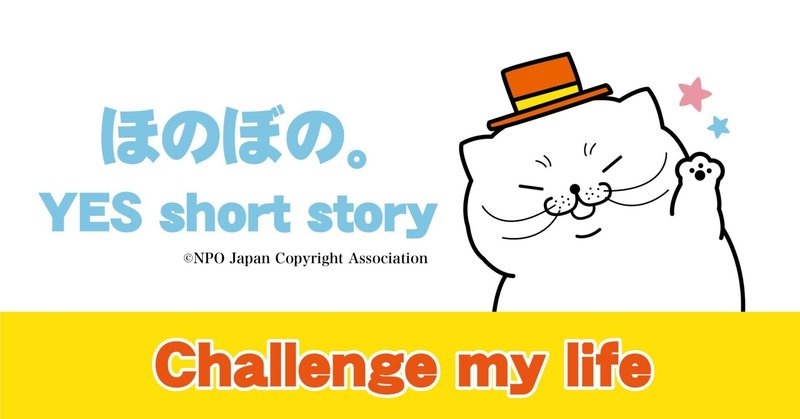
280.生きている事だけが、しあわせなのさ!Only being alive is happy!
みなさん、coucouさんです。ごきげんよう!
本年の4月1日で9か月目の270日連続投稿記念。作品数299作品目。あと4か月でようやく1年です。(前回の2日前、早いけれど、間違えて投稿してしまいました…。)
本日は2作品。金曜日、土曜日、日曜日にお読みくださいね。
そこで、もう一度、再チャレンジ!
そう、coucouさんのスローガン「challenge my life」だからもう一作品まとめました。

1.遠い、遠い、昔。
遠い、遠い昔の出来事だった気がする…。
coucouさんの人生はこのときに決まったんだ!
真っ暗闇の大きな部屋の中。
まわりからは苦しそうなうめき声、
突然、奇声をあげる声、
大きな声の寝言、
いびき。
目を開けると小さな裸電球がひとつ。
昼間でも薄暗い部屋だが、昼間は蛍光灯の明かりがつく。
廊下を人が歩く音、
裸電球に人影が常に反射する部屋、
すきま風の音、くしゃみや、咳の音、
移動するベットのタイヤの音、
人のざわめき、
悲しむ人たち、泣いている人たち、嬉しそうに笑顔の人たち。
coucouさんは共同部屋12のベットの窓側にいた。
朝になると、ガシャガシャと音を立てて看護師さんがワゴンを運ぶ。
それには、大嫌いな薬や注射器が音で合図をする。
まず最初に、聴診器を当てられながら、熱を測り、血液検査のための針を刺す。そして、味のない朝食が運ばれる。
食べれない日が続けば罰として栄養剤などの点滴が与えられる。
それが嫌でゴミ箱に食事を捨てたら怒られる…。
昼間になると、車の騒音、信号機の音、子どもたちの騒ぎ声が聞こえる。
きっと、野球をしているのだろう。
おーい、おーいと掛け声とバットの音が聞こえる。
当時の建物は木造3階建て、2階、3階の音も良く聞こえる。
共同部屋なのですべての話し声が音のように耳に入る。
coucouさんの世界は幅1200×長さ1800という小さな世界。そこからは決してはみ出してはいけないし、出歩いてはならないという先生の教えがありそれを守らないと注射を打たれると脅かされた…。
これは、coucouさんの小学校2年から4年生の後半の約3年間の忘れられない物語だ。
小学2年生になったばかりのとき、トイレが真っ赤に染まった。
水洗トイレではなかったので慌ててバケツに水を入れて流した。
次の日は普通と変わらないため気にしていなかったが、段々と色が濃くなりバケツで流してもきれいにならない。
慌てたcoucouさんは先生に相談したら、
すぐさま両親に連絡を入れて、病院に行かされた。
そこで尿検査、血液検査で腎臓病だと聞かされた。
確かに、毎日疲れやすいし、だらけていて授業中に先生に叱られ、いつもバケツを両手に持たされて立たされていた。(今思えば苛めか体罰に近い…)
そして、そのまま入院することになった。
coucouさんはピクニック気分で楽しかったが、父や母は暗い表情をしていたことを覚えている。
そもそも、腎臓病はcoucouさんの家系では多く、父の祖父、曾祖父、兄弟と代々続いていた伝統のようで、父はそのためにこの世を去っていった家族の姿をそのときに想い出していた。

2."サイレントディジーズ"(静かな病気)
coucouさんの歪んだ性格はこのときに埋め込まれたのかもしれない。
日本での患者数が約1,300万人と推定され、世界の死亡原因の12位に位置している慢性腎臓病(CKD)
腎臓つて、腰の辺りに2つあるそら豆のような形をした握りこぶし大の臓器のことをいう。この小さな臓器には、毛細血管が毛糸玉のように丸まった「糸球体」という器官で、心臓から送り出される血液の老廃物や塩分を濾過し、尿として体外へ排出する重要な役割を担っている。
(※CKDとは、なんらかの腎障害が3カ月以上続く状態を指す)。
放っておくと腎機能がどんどん低下してしまい、最終的には末期腎不全となり、人工的に老廃物を取り除く人工透析療法が必要となるケースもあるという。
※国際腎臓学会(ISN)は、世界の腎臓病の有病者数は8億5,000万人に上るという推計値を発表した。有病者数を比較すると、糖尿病(4億2,200万人)の2倍で、がん(4,200万人)やHIV/AIDS(3,670万人)の20倍以上に相当する。
腎臓病はこれまで、健康問題としてクローズアップされることが少なく、過小評価されてきた傾向がある。しかし、腎臓病いまや世界中で「隠れた流行病」とも言える状態になっている。
腎臓病は進行すると、腎不全、透析療法、血管疾患、感染症を引き起こし、入院治療を要することの多い疾患だ。

3.「こころのひと葉」のベアマンなんていない、「幸せの王子」も神さまもいない世界。
coucouさんの父親はとても驚いていた…。
「死ぬかもしれない…」、父は当時のことをそう振り返り語った。
coucouさんは当時、脳天気な明るい子どもだったので、まるで修学旅行気分だった。それに自分だけのベッドをえらく気に入っていたんだ。
でも、全身のむくみはなかなか退かない。
血尿も減らない…。
ぶくぶくに太りはじめた。
すると、利尿剤が与えられる。
つまり、腎臓が働いてくれないんだ。
やがて、利尿剤も効かなくなる。
そして、尿毒症を恐れ、さらに安静状態を保つためトイレにも歩いてはならないと命令される。
動悸や息切れ、めまいや立ちくらみ、全身倦怠感などの症状のためどちらにしろ動けなくなる。全身のかゆみ、かき壊すと炎症を起こし水ぶくれになる。まるで身体中に蚤を飼っているかのように辛い。
すると、次々と薬を処方される。
毎日は注射と点滴の薬漬けの拷問。
そんな生活が2年続いたら、病院内での栄養失調となる。それは食べ物を受け付けられなくなるからだ。一切の塩分を取ってはならない。食べ物はすべて砂糖と酢で味付けしたものばかり、無理して食べると吐いてしまう…。
すると、栄養剤の点滴という罰を与えられる。
両腕、両手、両足首が穴だらけとなる。もう、刺した場所の内出血だらけで、刺す場所がない。
目はうつろ、廃人のように、身体はビアフラの子どもたちのようにお腹だけ膨れ、あとは骨と皮だらけ。
父や母は見舞いに来るたびにcoucouさんが変わり果てていく姿に驚きを隠せない。でも、coucouさんはとてもいい子にしていた…。だって、これ以上父や母に迷惑をかけたくなかったからね。
だからお医者さんの言うことを信じて、言うとおりに我慢し続けた…。
でも、3年目が近づいたとき、coucouさんはもう、身動きができなくなっていた…。搔き壊した後に黴菌が入り、両手、両足の爪裏が鎖はじめ膿が出るようになった。慌てた医師たちはcoucouさんの両手、両足の爪をすべて剥ぎ取り膿みを取り出す手術をした。
もう、完全に動けない…。
もう、終わりかもしれない…。
coucouさんはこのままこの世からいなくなることが最後の親孝行、恩返しになるのではないか、そう思うようになった。
それは、もう心配と、お金の負担をかけたくなかったからだ。
それに、両親の疲れ果てた姿は子どもでもわかっていた…。
そう、膨大な入院費だったから…。
まだ、小学3年生。
もう一度、みんなに会いたい、
みんなと学校に行って遊びたい、
先生に怒られて立たされて笑われてもいい、
何よりも、家に帰りたい…。
父や母のところに戻りたい…。
本当は、元気になって父や母を安心させるためにこのアウシュビッツの収容所でも我慢し続けてきた…。
本当はただの実験材料でも、それでも治るなら。
coucouさんには「心のひと葉」のような絵を描いてくれるベアマンなんていない。「幸せの王子」のようにネズミさんが助けに来てくれない。それにこの世には神さまなどいない。
人が死ぬなんてことはわからないけれど、
この共同部屋の12ベッドのわずかな生き残り。
みんな突然、退院の挨拶もなく消え去っていった。
それが死ぬことなのだろうか。
coucouさんは死ぬという意味がわからないけれど、
この世から消え去るということは小学生でも理解していた。

4.寂しくなんてない!
病院に入院したばかりのときは担任の先生や同級生たちがよく見舞いに来てくれた。でも6か月、12か月を過ぎると誰も来ない…。
もう、忘れ去られたのかも。
毎日会うのは看護師さんと医師の先生。
掃除のおばさん、同室の12人の老若男女。
当時はみな同じ部屋、こども部屋なんてない。
もちろん、アウシュビッツ収容所なのでプライバシーもない。
カーテンすらない中でベッドの下で尿瓶、便瓶ですべて処理する。
着替えだって恥ずかしいなんていえない。
すべては丸見え。
もう、お風呂もシャワーも2年近く入れない。
身体は薬と汚れた匂い。
看護師さんがいくら身体を拭いてくれても皮が剝けるような垢だらけ。
今考えるととても不衛生だ。
まさに牢獄の日々だった。
でも、寂しくなくなった…。
なんと一人は気が楽なんだ、と思うようになった。
もう、愛されたいなんて贅沢な言葉はない。
とにかく、何がなんでも生きること、病気を治すことの優等生にならねば、この収容所から脱出するのは不可能だから。
coucouさんは父が大量にくれた紙と鉛筆、そして本を読みあさった。
それは、coucouさんにとっての自由な時間だからだ。
頭の中で想像する、考えることができる。
どんな所でも想像することで出かけることができる。
もちろん幽体離脱もだ。
目をつぶれば思いのまま、
家にだって何度も帰ることができた。
だからねこの想像力、創造力、空想、妄想に随分と救われてきた。
だって、自分だけの自由な世界だからね。
しかし、やがて、薬漬けの中でその大切な想像力を奪われはじめたんだ…。
そう、これで終わりなんだね…。

5.逃走・脱獄
3年を過ぎ、coucouさんは身動きできずに諦め切っていた…。
そんなとき、父が血相を変えて病院に来てcoucouさんをおんぶして、オートバイに乗せ逃走を計った。
coucouさんの大切な絵や本を風呂敷に包み、歩けない私を背中に乗せて家に向った…。
coucouさんにしてみれば青天の霹靂だ、
何がなんだかわからないままの脱走だ。
後に父は医師や看護師と何度も話し合いをしたのだという。
「このまま治る見込みがないのなら家に連れて帰る」と。
医師たちは猛烈に反対した。
父はさらに問い詰めた、
「生きれるのか?死ぬのか?はっきりして欲しい、どんどんと悪くなっている…。この姿を見てくれ、はっきりと宣告して欲しい…。息子は人体実験なのか?それに答えられないのならこのまま退院させる…」
医師たちは、父の問に答えることはできず、
「…もうこの病院では引き取りませんよ!どうするのですか?」といった。
父は、
「答えられないのなら引き取ります、この私が必ず治して見せる…」といって病院を飛び出したのだった。
coucouさんは事情もわからず、
オートバイの後ろから夜空の星を眺めていた…。
ああ~本物の夜空と星だ~
時間はまるでスローモーションのように流れていた。世の中のすべてが止まっているように見えた…。
何よりも下界の空気がおいしい。

6.治療
後に父から聞いた話だが、父は当時米軍で働いており英語も話せた。
そこで米国の軍医から食事療法で治せると聞いてた。
また、当時の病院での薬物治療、食事療法に疑問を持っていた。
さらに医師たちの的確な助言はなくあくまでも決められた処方に従った素人同然だということを知った。
それはあまりにも米国との治療方法の違いを学んだからだった。
父は米国の医学書を読みあさり自分なりの研究を仕事の合間にし続けていたようだ。
そこでどう治療方法が違うのかというと、当時の日本の治療方法は「一切の塩分を与えない」「利尿剤治療などでの脱水症状」「栄養不足による栄養失調」など、今ではあり得ない、という結果だったからだ。
現在では塩分を一日当たり6グラムと糖尿病患者と同じ制限をしているが、問題は「個人差」があるところまでの分析はなく、あくまでもマニアルにある治療方法に沿っていることだ。あれから数十年、いや半世紀過ぎているのにも関わらず薬物治療以外での大きな変化がない。
人間の身体から水分を減らしたら死ぬしかない。
それと同時に、塩分を取れなければこれもまた死ぬしかない。
水と塩はいのちと直結していることを父は理解していたようだ。
coucouさんが退院した翌日のお昼ご飯はラーメンだった。
忘れもしないあのおいしさ。
お汁は一切飲んではいけないが麵についた汁はかまわない。
信じられないことだが3年目のはじめての塩分の摂取から、父の治療が始まった。
さらにカリウムも取らせはじめた。
病院では考えられない食事だった。
一切の果物も禁止されていたが、
寒い冬に西瓜を食べさせてくれた。
カリウムが一番少ない果物だ。
しかし、真冬にあるわけがないが、これは米軍から調達した西瓜の缶詰だった。
coucouさんは脱出後の食べ物に次々と感動していた。
また、日本ではまだ市販されていないコカ・コーラ、チョコレート、ピーナッツクリームやドーナツなども食べた。
アウシュビッツの収容所の地獄からいつのまにか天国に来たようだった。
当時の読み物は英語の漫画雑誌「スパイダーマン」「スーパーマン」「ポパイ」や「ウォルトディズニー」作品がcoucouさんには言葉の意味はわからないがそこから、わずかな「希望のひかり」を感じるようになった。
それから一年、自宅療養生活の中で体重も増え、身体も自由に動かせるようになり、外を歩くようになった。ただ、退院後も毎日尿検査は続く。
こうして、coucouさんは社会に出所することになった。
だが、この出来事は生涯忘れられない最低の想い出が、人生最高の想い出に変わるなんて思い描けるまでにさらに数十年を要した。
※参考文献が後半にあります。お時間があればお読みください。又は保存していただければ何かのお役に立つかもしれません。


coucouさんです。みなさん、ごきげんよう!
話の長いのは得意のcoucouさん、
能力的にどうしても短くまとめることのできない未熟者、
お許しくださいね。
でも、ここまでおつきあいしたくれた、
みんなにはとても感謝申し上げます。
おそらく文字数だけでいえば10,000文字を超えているかもね。
昨年末、coucouさんは血尿とともに緊急手術入院。クリスマス、年末、正月がすべて消え去り、まるで浦島太郎のような新年を迎えた。
(入院中のnote記事のほとんどは入院直前までに必死に作ったもの、あとは自動的にお願いしたものでした)
coucouさんはあの忘れられない子どもの頃を鮮明に想い出したが、今度もダメかと内心感じていた。
567のため一切の家族も兄弟も一切の面会はできず、両手、両足は針だらけ、身体は管だらけ、あのときの拷問よりもつらい日々。
ああ~まだまだやり足らないものばかり、
こうして人はあっけなくこの世を去るのだろうか?
術後の痛み止めも効かない。
眠れない、痛い…。
スマホもパソコンも操作できない。
何よりもこの状況を家族にも連絡できない…。
coucouさんは永遠に病から離れることができない運命なのか?
またまた落ち込んだ。
4年前に手術したばかりの転移再発だったからだ。
でも、coucouさんには薬漬けの中でも想像力がわずかに残されていた。
そのおかげで、この世を去った父と母と話ができた。
弟とも対話ができた。
おそらく届いただろう。
父は笑顔で「大丈夫だよ…」という。
そして、
「生きていることが一番の幸せだよ!」
「生きれるって素晴らしいこと」
「生きているだけで人に役立てる!」
「それ以外の幸せなんていらないよ」
「それ以外に何を求めるんだい!」
「そう、何も心配ない…」
という、いつもの口癖が、声が聞こえた…。
coucouさんは恩返しに、父や母を救うことができなかったけれど、その分を生き続けることなんだね。coucouさんが生き続けている限り、父や母も一緒に記憶の中に、いつまでも生き続けていることになるのだから。
それに、coucouさんがこの世を去るときは、
父や母にもう一度会えるときだと楽しみにしている。
まだ、会いに行くには早いんだね。
もしかすると、365日で終了と考えている、coucouさんはこのnote記事とともにこの世を去るまで、かき続けているかもしれない。
そう、生きているだけで人の役に立つのなら。
みんな~
ここまで読んでくれて、
ありがとう~
とても、とても感謝しています!
では、またね!

※腎臓病 参考文献(付録)
※一般社団法人日本腎臓学会ホームページより参考引用
1.浮腫(むくみ)
浮腫(むくみ)とは、腎臓から水分を十分排泄できなくなり、体内に余分な水分がたまっている状態をさします。腎臓の病気によるむくみは左右対称的であり、むくんでいる部分を指で10秒以上強く押えますと、指の跡がへこんだまま残ります。通常、体重が2~3kg増えますと、重力の関係で、足首のくるぶし付近からむくみ始めます。さらに体重が5kg以上増えますと、むくみは全身にひろがります。肺や心臓に水がたまり、複数の利尿薬でむくみのコントロールができない場合は、透析治療が必要となります。
代表的な腎臓の病気として、たくさんのタンパクが尿に漏れて血液中のアルブミンが低下するネフローゼ症候群や、腎臓の働きが正常の30%未満まで低下した慢性腎不全が挙げられます。
しかし、むくみは腎臓以外の原因、例えば心臓や甲状腺の働きが低下した場合や、足の静脈瘤やリンパの流れが悪い場合などでもみられます。そのため、むくみの原因を解明し、原因に応じて対処することが大切となります。
2.尿量
腎臓は血液中の老廃物をろ過し、尿として体の外に排出する役割を担っています。健常成人の尿量はおおよそ1.0 L~1.5 L/日 です。しかし、何らかの原因で尿量が減少し、1日の尿量が400mL以下になることを乏尿、100mL以下になることを無尿といいます。逆に尿量が増加し、2500mL以上となることを多尿といいます。脱水や心不全により腎血流が低下したり、腫瘍や結石のために尿管や膀胱が閉塞したりすると、尿量は低下します。腎臓の機能が低下すると、尿の濃縮力が低下して多尿となり、夜間頻尿になることが多いですが、さらに腎機能低下が進行すると、尿量が低下します。その他、主な多尿の原因としては、糖尿病、尿崩症、心因性多尿、ミネラルの異常(高カルシウム血症、低カリウム血症)などが挙げられます。尿量の異常が続く場合は、何らかの腎臓の病気が隠れている可能性もありますので、早めにかかりつけ医への受診をお奨めします。
3.夜間尿
夜間に何度もトイレに行く原因としては、膀胱の萎縮や前立腺肥大、膀胱炎などに伴う排尿障害のほか、眠りが浅く日中同様に尿意を感じる睡眠障害を起こしやすいこともあります。夜間睡眠時無呼吸で高血圧をきたした場合や心不全、糖尿病などで夜間尿量が増えることもあります。お薬や寝る前の水分の摂りすぎが原因の場合もあります。また、腎機能が低下した方や高齢の方は、尿の濃縮機能が低下するために夜間多尿となります。また、腎臓の機能が低下すると、摂取したナトリウムを日中に排泄しきれず、夜間に血圧を高くしてナトリウムを排泄しようとすることも夜間多尿の原因となります。
4.頻尿
尿の回数が増えることで、1日8〜10回以上、夜間2回以上トイレに起きる状態をいいます。頻尿には、尿量の増加(1日2L以上)によるもの(多尿)と、尿量が増えずに、回数が増える(狭い意味での頻尿)があります。両者は、1回の排尿の際の尿量で判断ができます。多尿の原因には、糖尿病、尿崩症などがあります。狭い意味での頻尿の原因として、もっとも多いのは、高齢男性に見られる前立腺肥大です。他にも、膀胱炎などによる膀胱粘膜への刺激、過活動膀胱などもあります。治療は、原因となる病気を診断し、その病気の治療をすることになります。
5.だるさ
だるさは末期の腎不全でよく認められる症状の一つです。腎不全により尿毒症物質が蓄積したことにより起こる尿毒症症状の一つとしてだるさが認められることがあります。そのほか、腎不全による貧血が進行したとき、また体液が過剰になったことにより心不全が悪化したとき、電解質異常など、さまざまな要因によりだるさが生じます。腎機能が高度に低下し、だるさが出現する場合には、末期腎不全の症状である場合が多く、透析などの腎代替療法を検討する時期であることが多いです。
6.貧血
腎臓は尿を排泄するだけではなく、ホルモンを分泌する働きもしています。その一つとして、赤血球を作る働きを促進する「エリスロポエチン」というホルモンを分泌しています。腎臓の機能が低下すると腎臓がエリスロポエチンを十分に分泌させることができなくなり、赤血球の産生能力が低下します。このようにしておこる貧血を「腎性貧血」と言います。
腎性貧血になると、一般の貧血と同様に動悸や息切れ、めまいや立ちくらみ、全身倦怠感などの症状が現れますが、貧血は徐々に進行するため、気がつかないこともあります。貧血の有無については、定期検査で行われる血液検査のヘモグロビン濃度で知ることができます。慢性腎臓病で、特にヘモグロビン濃度が11.0 g/dL 未満の方は腎性貧血の可能性がありますので、主治医の指示に従って、適切な治療を受けることが大切です。ヘモグロビン合成ための材料として鉄が必要ですので、鉄欠乏を認める場合には、鉄剤の投与が必要になります。鉄が充足しているにも関わらず貧血を認める場合は、赤血球造血刺激因子製剤(ESA)やHIF-PH阻害薬による治療が必要となります。治療の目標は、ヘモグロビン濃度11~13g/dLです。
7.かゆみ
あなたがかゆみを感じる時、もし皮膚に発疹があったら皮膚科にかかり、皮膚に発疹がないなら内科に相談してください。皮膚疾患でかゆくなることは多いですが、腎臓や肝臓の病気の時もかゆくなります。
腎臓は体の中や血液の老廃物を尿へ捨てる臓器ですので、腎臓が悪くなると老廃物が血中や皮膚にたまってしまいます。それら老廃物は皮膚の中にあるかゆみ受容体のミュー・ペプチド受容体を刺激し、その電気信号が脳へ伝わってかゆみを感じます。この現象は腎機能が高度の低下した透析患者で多く見られ、半数は強いかゆみを感じます。
腎臓が悪くなると皮膚が乾燥しますが、これもかゆみの原因となります。腎臓の働きが悪くてかゆい方は、まめにお風呂に入ったり、皮膚に湿気を与えるぬり薬を塗ったりすることがかゆみ対策になります。皮膚の防御作用をこわさないために、お風呂で皮膚をこすりすぎないことも大切です。
8.心血管合併症(CVD)
慢性腎臓病(CKD)という概念が提唱され、特に世に知れ渡るようになったのは、CKDが特に心血管疾患(CVD)と関わりが強いからです。CKD患者さんの死亡原因としてもっとも多いのがこのCVDです。腎機能の低下とともに、CVDの発症率およびCVDによる死亡率が高くなっていくことが知られています。このように腎機能の低下は大きな問題ですが、尿蛋白の存在もCVDに関わる重要な因子として知られています。たとえ同じ腎機能であっても、尿蛋白があるCKD患者さんではCVDによる死亡率が約2倍になることが報告されており、また軽視されがちな微量な蛋白尿の存在であったとしても、死亡やCVDの発症に強く関係することも知られています。これらのことから、CVDの観点からみてもCKDを早期に発見することは重要であり、腎機能だけでなく、尿検査異常にも注意を払うことが必要であると考えられます。
9.骨ミネラル代謝異常
CKD-MBDとは、もともとは透析患者で考案された疾患概念ですが、慢性腎臓病(CKD)の患者さんにも認められ、カルシウムやリン、PTH(副甲状腺ホルモン)などの検査値の異常を示すとともに、骨がもろくなり、血管などの骨以外のところに石灰化をきたすという、3つの特徴的な症状を示すことから名付けられています。これが進行すると骨折や心血管イベントをきたしやすくない、死亡することもあります。たとえば、透析患者さんは心血管イベントを高率に起こしますが、その原因の一つとして血管や心臓の弁が骨のように石灰化し、かたくなることがあげられています。このような異所性石灰化のある患者さんでは、検査値異常や骨がもろくなりやすいことがわかっています。骨の健康にとって不可欠なビタミンDは、腎臓にある尿細管という部位で1α水酸化酵素の働きによって活性化され、活性型ビタミンDと呼ばれるホルモンとなって腸管でカルシウムやリンの吸収を促します。しかし、CKD患者さんや透析患者さんはビタミンDを活性化できなくなり、活性化ビタミンDが低下し、骨折をきたしやすくなります。活性化ビタミンDが低下するため、CKD患者や透析患者では、骨を溶かして血清カルシウム濃度を上げる作用のある副甲状腺ホルモン(PTH)が上昇しますが、PTH値が高いと骨折を起こしやすいこともわかっています。また、CKD-MBDの治療として、リン吸着薬や活性型ビタミンD製剤あるいはカルシミメティックスとよばれるPTHを下げる薬剤が使われます。これらによって検査値異常を改善するのみならず、骨折や心不全をはじめとする心血管イベントを抑制できることがわかっており、最終的には死亡抑制につながると考えられています。
※腎臓病の治療方法(食事療法)
※慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版, 日本腎臓学会より引用
たんぱく質を抑えて腎臓の負担を減らす。
―なぜ、たんぱく質を制限するの?―
お食事からたんぱく質を摂ると体内では老廃物が作られます。その老廃物の処理をしているのが腎臓です。そのため、老廃物が作られるほど腎臓の負担になっていくのです。たんぱく質を減らすことは、腎臓の負担を減らしてあげることに繋がります。
―減らせば減らすほど良い?-
たんぱく質はとても重要な栄養素ですので、必要以上に減らしてしまうと栄養不足を招きます。そうすると、せっかく食事療法を行っても腎機能を悪化させてしまうことがあります。大切な役割のある栄養素を減らすわけですから、減らした分のエネルギーを「脂質」と「糖質」で補うことが大切です。たんぱく質以外からしっかりとエネルギーを摂ることで、腎機能の低下を防ぎ、栄養不足を防ぎます。手軽にエネルギー補給ができる「治療用特殊食品」を利用するのも良いでしょう。
塩分制限
―高血圧予防のためだけではない?腎臓病の塩分制限―
「高血圧」と「塩分の摂り過ぎ」についてはよく知られています。では、腎臓病の場合はどうでしょうか。
通常、食事から摂った余分な塩分は、尿と一緒に身体の外へ出て行きます。その働きをしているのが腎臓ですので、腎機能が低下すると、余分な塩分と尿の排泄がうまくできなくなり、身体の血液量が増え身体に溜まります。そうすると、本来排泄されるはずのものが溜まっていきますので体は浮腫み(体液量が増え)、高血圧を引き起こします。さらに進行すると心臓の負担になったり呼吸が苦しくなったりと、様々な症状が出てきます。腎臓病での塩分制限は、身体の水分(体液)を調整するために大切です。
少なすぎてもダメ!塩分制限
塩分制限の目標は、1日3g以上6g未満です。
味噌汁を1日1回に減らしたり、麺類の汁を残すなど日常生活ですぐに始められる「できること」から始めましょう。継続する事が大切です。
カリウム制限
1番初めの項目に記載してありますが、カリウムはステージ3bの方で2000mg以下、ステージ4以降では1500㎎以下に制限をします。
たんぱく質制限
たんぱく質源となる食品にはカリウムが多く含まれています。その為、きちんとたんぱく質制限が出来ていれば同時にカリウムを減らすことができるのです。
野菜は1日300g
たんぱく質制限をきっちり行っていても、野菜や果物を食べ過ぎるとカリウムは身体に溜まっていきます。緑黄色野菜100g 淡色野菜200gを目安にしましょう。調理の際に、切った野菜を水にさらしたり茹でこぼすことでカリウムを減らすことが出来ます。
※coucouさんの電子書籍のご案内「~とどかない言葉~「悲しみよ、こんにちは。」好評発売中!下記URLにて検索してください。
人生を楽しく明るく!幸せになるための物語。 書 https://www.amazon.co.jp/s?i=digital-text&rh=p_27%3ACou+cou&s=relevancerank&text=Cou+cou&ref=dp_byline_sr_ebooks_1

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
