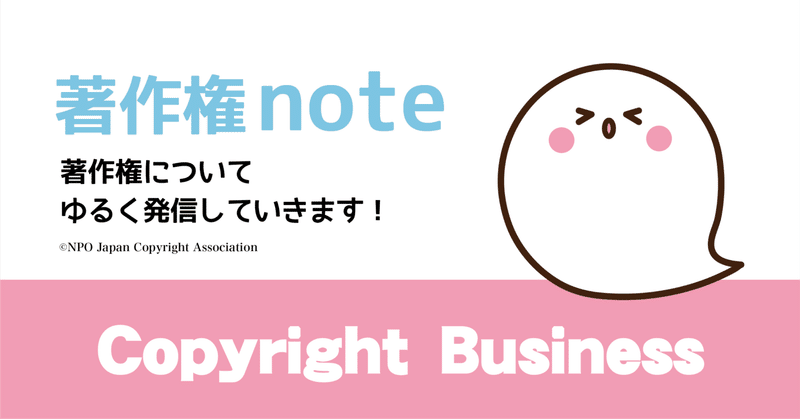
78.note記事のみんなのための、知って得する知的財産権!
1.気をつけよう!その他身近な著作権侵害例 ③「写真無断使用で1200万円賠償命賠償命令」
2004年7月14日、東京地裁は出版社2社に写真無断使用で1240万円の支払いを命じた。
これは雑誌にプライベート写真などを無断で掲載され、プライバシー権や名誉を傷つけられたとして、「モーニング娘」のメンバーや優香さん、佐藤江梨子さんらの女性歌手やタレント28人が、出版社2社に計8700円の損害賠償を求めていた。
出版社は発行元である「サン出版」(東京都新宿区)と「コアマガジン」(豊島区)の2社。東京地裁の市川巳裁判長は、「通学中の姿を撮影た写真を掲載したり、在籍している高校名を公表することは、プライバシー権の侵害にあたる」とした。
問題となったのは、サン出版の「トップスピード」のコアマガジンの「ブブカスペシャル7」。
判決は、グラビア写真並み大きさで掲載された一部の写真について、著名人の氏名や肖像から生じる経済的利益を独占使用できる「パブリシティ権」も侵害したと認定したが、被告か違法と認識していなかったため賠償を賠償を認めなかった。
また、よくいわれている、「『追っかけ』や『カメラ小僧』の撮影した写真を買い受けて雑誌に掲載することが、追っかけ活動の横行を助長させている」とも指摘した。

2.著作権と関連する権利「知的財産権」って何だろう
その1・特許権って何だろう
発明は、特許法によって、特許権として一定期間保護されます。
発明には技術的なアイデアが含まれていればよく、つまようじから宇宙開発まで、あらゆるものが特許の対象となります。
この特許権を取得すると、発明した物や技術などを独占的に生産・使用ができ、第三者が無断でその物を生産したり、技術をまねすれば、権利者は、侵害者を訴えることができます。
ただし、特許を受けるには次の要件を満たしているかを判断されます。
①「自然法則を利用した技術的思想の創作であること」
計算方法や、たんなる発見は対象になりません。
②「産業上利用できること」
病気の治療方法などは対象になりません。
③「新規性があること」
出願前に日本国内で公知であったものや、国内または外国の刊行物に載っていたものは新規性がないとされます。
④「進歩性があること」
公知の技術では容易に発明できないことです。
⑤「公序良俗などの不特許事由に該当しないこと」
このようなことを実体審査し、審査官が審査をおこない、出願内容に関する要件を備えているかを判断します。

その2・実用新案権って何だろう
ライフサイクルの短い物品というのは流行に左右されるもので、すぐに模倣した製品などが出回ることが多いので、これらに関するアイデアや技術は、早期に権利として保護する必要があります。
このようなアイデアや技術を保護するために、実体審査なしで権利が与えられる実用新案制度があります。
特許だと早くても出願から二〜三年後に権利となるのに対し、実用新案権は、出願から半年くらいで登録され、権利として認められます。
実用新案権の対象となる考案は「物品の形状、構造又はその組み合わせに係るもの」(実用新案法三条)に限られ、製造方法や、その他の方法に関するものは除かれています。登録の要件は、特許の場合とほぼ同じです。
実用新案権の効力は、権利期間が六年間と短い以外は特許と同じですが、実用新案権は実体審査されず登録される権利であることから、特許庁が作成する「技術評価書」を提出して警告したあとでなければ、権利の侵害を防ぐことの措置をとれません(同二十九条の二)。
技術評価書は、誰でも特許庁に請求して作成してもらえます。

その3・意匠権って何だろう
商品のデザインのことを意匠といいますが、デザインである意匠は、意匠法によって意匠権として保護されます。
意匠法では、意匠を「物品の形状もしくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの」(意匠法二条)と定義しています。
物品とは、うどんやせんべいなどの食品や、自動車などの形のある工業製品などで、単独で商取り引きされるもので、意匠は、物品と一体不可欠の関係といわれています。
したがって、似たようなデザインでも物品が違えば別意匠になります。
意匠権の効力は、登録した意匠の実施を専有する権利で、特許権とまったく同じ効力を持ちます。
しかし、似たようなデザインが物品が違うことによって類似品が多くなっては困ります。
そこで、デザインを少し変えただけの意匠による侵害を防ぐため、意匠権者は登録した意匠に類似する意匠を登録できる「類似意匠制度」があります。
また、登録して防御手段はとるが、当面は意匠を公表したくない人もいます。そのため、登録後三年間を限度として、その意匠の内容を公報に掲載しないという秘密意匠制度があります。
さて、意匠登録を受けるための要件があります。
それは、
①工業上利用できること
②出願時に新規性があること
③公知の意匠から容易に創作できないこと
④同一または類似のものが先に出願されていないこと
⑤公序良俗違反など不登録事由に該当しないこと
⑥願書、添付図面が規定通り作成されていること
⑦一意匠に対して一出願となっていること、という要件があります。

その4・商標権って何だろう
消費者は、商品名やマークなどの商標(ブランド)によって商品を区別します。そのため、商標は企業にとって重要な財産ともいえるものです。
商標は、商標法によって商標権として保護され、商標は、他社の商品と区別するためにつけられる「文字」「図形」「記号」、またはそれらの組み合わせです。(商標法二条)
商標権は、指定商品について登録商標を独占的に使用する権利ですが、指定商品または類似する商品にしか権利が及びません。
そこで、商標は類似の商標をつくられたり、類似の商品で使われやすいため、通常の商標登録のほかに、連合商標登録という制度があります(同七条)。
商標登録の中に「連合商標登録制度」というものがあり、この制度は、自己の登録商標に類似する商標を登録したり、類似の商品やサービスについて商標を登録することができます。
また、著名な商標を、他の分野の商品やサービスであっても、使用できないようにする「防護標章登録」の制度があります(同六十四条)。
それでは、商標登録をうけるための要件とは、何でしょうか。
①自己の業務に係るものについて使用すること。
②他人のものと識別できる特徴を有している。
③登録を禁止している不登録事由に該当しない。
④商標および指定商品が、ともに同一または類似のものが先に出願されていないものであること。
⑤商標登録出願書および商標を表示した書面が、法律に規定する要件を満たしていること。
⑥ひとつの商標に対してひとつの出願であること、などが要件となっています。

5・サービスマークって何だろう?
サービスマークは運送業者や旅行業者、クリーニング業者などのサービス(役務)を、他の業者のサービスと区別するために用いられる、デザインした字体や図形マークのことをいいます。
今まで商標法では、商品の商標のみを保護していましたが、近年におけるサービス取り引きは大きく変化、発展し、1992年4月1日より、サービスマーク(役務商標)を保護することにしたのです。
サービスマークの登録要件は商標登録と同じです。

6・不正競争防止法って何だろう?
不正競争防止法は、特許等の工業所有権(実用新案権・商標権・意匠権)や著作権を補完的にカバーする法律です。
ここにもうひとつの知的財産権といわれる意味があります。
不正競争防止法は、事業活動における不正な競争行為を規制している法律です。1993年に全面改正され、不正競争の類型が新たに追加されるとともに、違反者に対する制裁が大幅に強化されました。
不正競争防止法では、特許権などの有無にかかわらず、不正競争を目的とする商品やブランドの模倣行為などが違反とされます。
これは不正行為があった場合、模倣された者(被害者)は、違反者に対し、その違反行為の差し止め、損害賠償、信用の回復措置を請求でき、刑事告訴することもできます。
これは特許等の工業所有権の場合は、出願しなければ権利を取得することはできませんが、不正競争防止法と著作権、著作隣接権などは一切の登録、出願は必要はありません。
それでは、不正競争行為とはどんな行為のことをいうのでしょうか。
①広く知れわたっている他人の商品表示(商号、商標、容器、包装など)とそっくりのものを、同業種または類似の業務をおこなう者が、自己の商品に使用して他人の商品と混同させる行為。
②業種、業務内容にかかわらず、他人の著明なブランドのもつ宣伝効果や信用にただ乗りする行為。
③本物そっくりな商品(デッドコピー商品)を本物の商品が最初に発売された日から三年以内に販売する行為。
④他社の製造技術屋顧客リストなどの営業秘密を詐欺や窃盗など不正な手段で入手して使用する行為。
⑤商品もしくは役務に、商品の原産地や品質、内容、製造方法、用途、数量などを虚偽に表示する行為。
⑥競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を述べたり、うわさを流したりする行為。

特非)著作権協会です。
みなさま、こんにちは!
今回は著作権だけでなく、著作権を含めた全体知的財産権のお話となりました。これら無形の財産権は私たちには関係ない、と思っていても何かしらに関係していることがわかりますね。
日々の生活や仕事に欠かせないものだからです。
ただ、「著作権」とその他の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)と比べた場合の大きな違いが2つあります。
「著作権」は一切の出願はいりません、必要ありません。
「著作権」の場合は創作した時点で自動的に権利が発生するのに対して、「知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)」は出願しなければ権利になりません。
これが1つ目の大きな違い。
2つ目の大きな違いは、「著作権」の場合は万国共通の「世界法」であり、すべての加盟国では出願しなくとも権利は保護されます。
しかし、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の場合はその国ごとの「国内法」であり、日本で出願して権利を手にしたとしても他国でも取らなければならないことです。
そう、すべての国々で出願しなければなりません。
困ったことに出願登録されたものは誰もが自由に閲覧できるため、大切なアイデアが世界中に無料で公開していることになります。
近年、出願することで公開されてしまうため、あえて出願しない企業や個人の方々も増えてきているようです。コカ・コーラやケンタッキー・フライドチキンなども製法がわかってしまう恐れがあるために出願をしないという戦略を取っているといいます。
それが困るのであれば世界中で出願しなければなりません。
大手企業なら世界進出などを念頭に入れて多額の費用をかけれますが、個人や小さな会社では資金的に不可能のため、「国内だけの国内法」にとどまっている状態です。
実際には「独占権を取得する」といううたい文句ですが、完全なる知的財産権というものは存在してはいません。
そのために、特許等の知的財産権だけでなく「著作権」があり「不正競争防止法」等で補完しあっているというのが現状だと考えられるでしょう。
まだまだ深い、著作権、特許等の知的財産権を知る必要があるのかもしれませんね。
ここまでの長い説明、おつきあい、ありがとうございます。
次回も、どうかよろしくお願い致します。
※特非)著作権協会おすすめ電子書籍のご案内「~著作権110番~「著作権事件簿」全17巻好評発売中!下記URLにて検索してください。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
